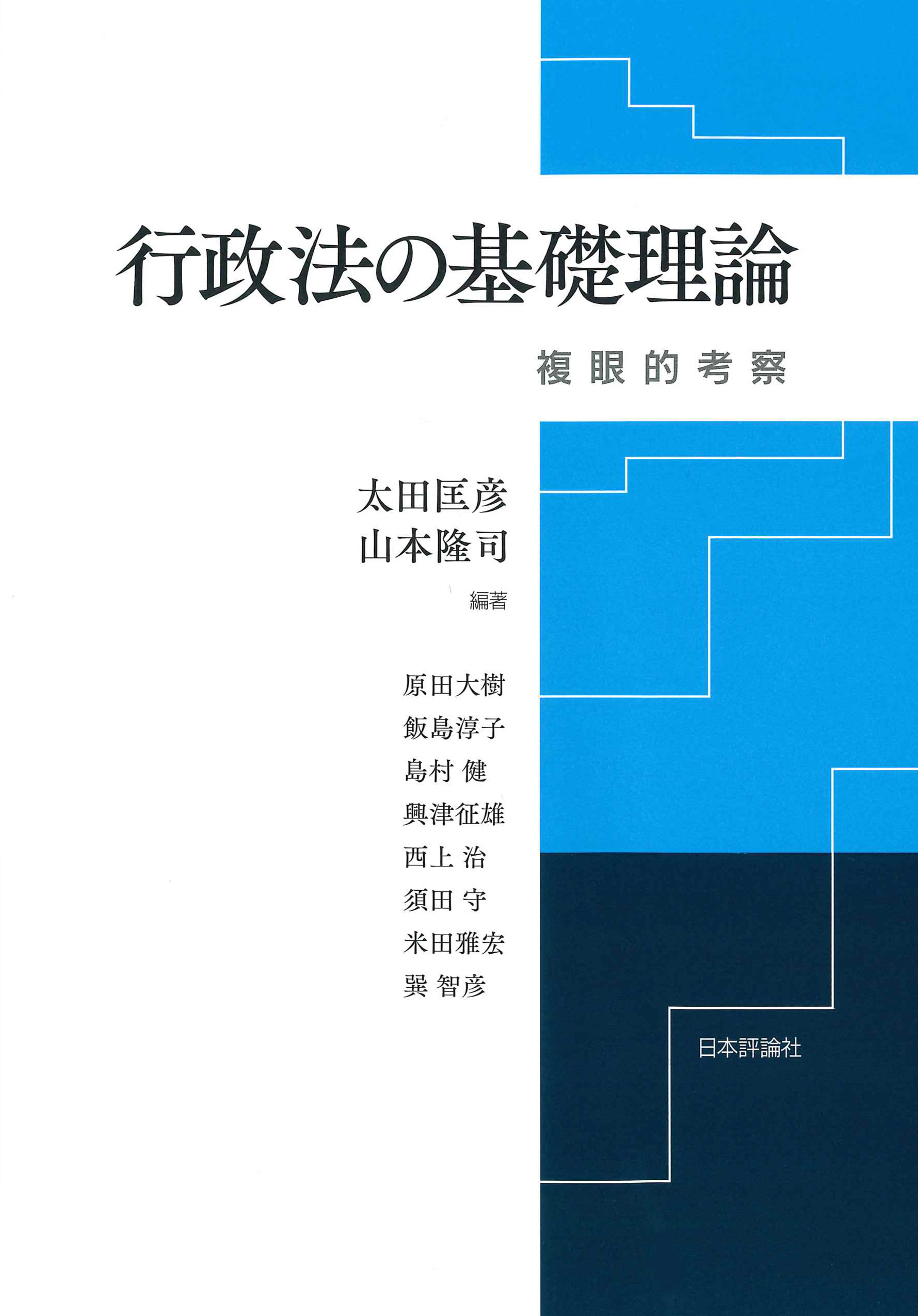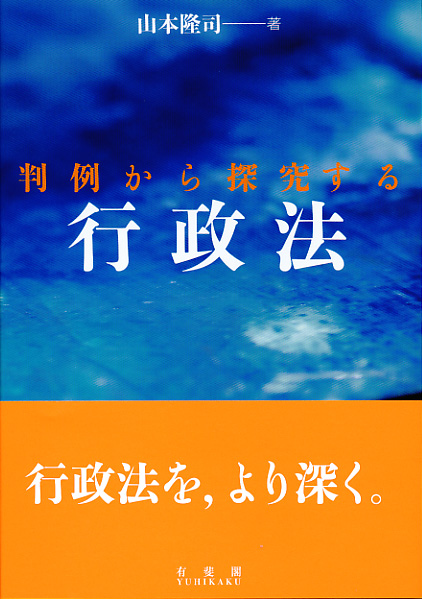本書は、法律時報92巻8号 (2020年8月) から同94巻5号 (2022年5月) にわたって、「行政法の基礎理論」のタイトルの下で連載された論攷をまとめたものである。執筆者はいずれも日本の行政法学を担っている第1線の研究者である。
行政法ないし行政法学は、変転する社会状況・政策的要請に即応する必要から多種多様に展開する行政活動・行政組織を、一定の視角から法を用いて整序し規律することで、見通しを利かせて透明性を高め、個人の自由・権利を保障するとともに、民主政の下での行政を可能にすることを試みる法分野ということができるだろう。このような多種多様な組織と活動を対象とする法領域であることから、対象の展開を批判的に検討するためにも、自らが憲法原理に基礎づけられたものであるためにも、あるいは自らに関する理解可能性 (見通しの良さ) を確保するためにも、行政法は一定の基礎理論を必要とする。同時に、行政法が有する議論のうち、とりわけ基礎理論と呼びうるものは、学問と実務の積み重なりの下で形成されてきたものであり、それがいかなるもので、またその根拠は奈辺にあるのか、何故基礎理論と性格付けうるのか等に関して、省察を必要とするものでもある。本書に収められている各論攷の執筆者は、このような意味での行政法の基礎理論に関わる問題を自由に設定し、研究会で報告を行い、その報告を巡って参加者間で行われた議論を踏まえて執筆した。したがって、それぞれの論攷が取り上げているテーマは、各論者が自身の学問的関心に基づいて設定したものである。しかしながら、同時に、テーマの設定にあたっては、どのような理論的問題が存在し、それにいかに立ち向かうべきか、またそれがいかなる意味で基礎理論と言いうるのかが意識されている。
本書に収められた各論攷は、上記の趣旨を踏まえ、現在の日本において行政と行政法実務が直面している問題、さらにその奥にある問題に鋭利な分析を加えている。各論者が社会に向き合いながら自己の関心に基づいて問題を設定し法を用いて考察する各論攷から、読者は行政法の多様さを実感できるであろう。同時に、各論者が自由に問題を設定したとしても、社会の中の実践を法学の観点から考えることは各論者に共通しているのであって、鋭敏な読者は、各論攷の中に伏流する共通の関心・視角を見いだすこともできる。本書は既にそのような読者に恵まれており、本書の書評である木庭顕「行政法学はデモクラシーの変化にどう応えていくべきか」自治研究99巻7号 (2023年) 143-153頁も読むことで、自由な論文集に伏流する共通の関心を見いだす読書・解釈の醍醐味に触れることができる。
この紹介を執筆した私は、編者として、各論者が自由に問題を設定し議論を展開できる連載とすることに意を払ってきたつもりである。この論文集が、行政法学の多様さと豊穣を示し、今の社会と行政法実務の奥にある問題への接近の手掛かりとなるものとなったことに感謝している。
(紹介文執筆者: 法学政治学研究科・法学部 教授 太田 匡彦 / 2023)
本の目次
I 契機
II 現状
III 将来
IV 展望
2 地方自治と行政法 再論……飯島淳子
1 問題意識──なぜ「基礎理論」か
2 社会システムのなかの立法の諸相
3 「自由と財産」を行使する責務の規範的基礎付け
4 ヒトの活動を公共的活動に媒介する規範
5 PDCAサイクルの法理論
6 結語──なぜ「地方自治と行政法」か
3 地方行政組織の構成原理に関する一考察
――公選制行政委員会の終焉に寄せて……島村 健
1 公選制地方行政委員会の成立と消滅
2 地方行政委員会の構成原理
3 公選制地方行政委員会の構想とその終焉
4 公選制地方行政委員会とは何であったか
4 正統性の構造分析
――行政国家の正統性を手がかりに……興津征雄
1 はじめに
2 正統性とは何か
3 意思説の限界
4 利益説の可能性
5 おわりに
5 法律上の特別の根拠なき機関訴訟の基礎づけ……西上 治
1 本稿の課題
2 私的な権利・利益の保護・救済への偏重
3 その他の課題
6 私人の情報提供と行政判断……須田 守
1 私人による情報提供
2 情報提供の実効性
3 行政判断の法的把握
4 協力する私人
7 情報秩序としての行政過程の法問題……山本隆司
1 情報秩序としての行政過程
2 行政手続
3 行政上の行為形式・執行の制度
4 結 語
8 「法規範が利益を一定の態様で保護する」という思考が行政法において意味するもの……太田匡彦
I 課題の設定
II 原告適格、「自己の法律上の利益に関係のない違法」
III 公権力の行使に起因する国家賠償責任における利益を保護する規範の特定・構成
IV 再構成
9 危険管理責任の再定位――義務違反構成の試み……米田雅宏
1 はじめに──本稿の目的
2 危険管理責任のパースペクティブ
3 危険回避義務と安全配慮義務
4 義務違反構成による責任規範の具体化
5 おわりに──国賠違法の認識フレームの組み替え
10 長等が地方公共団体に対して負う損害賠償責任
――法人のガバナンスの横断的分析の端緒として……巽 智彦
1 法人のガバナンスと損害賠償責任
2 地方公共団体の長等の責任の実体法上の構造
3 責任の性質ないし法律構成
4 責任の成立要件──任務懈怠責任を素材に
5 おわりに
関連情報
https://www.nippyo.co.jp/shop/magazines/backnumber/1.html
書評:
木庭顕 (東京大学名誉教授) 評「行政法学はデモクラシーの変化にどう応えていくべきか」 (『自治研究』第99巻7月号 2023年6月28日)
https://www.daiichihoki.co.jp/store/upload/pdf/jichikenkyu2023_07.pdf



 書籍検索
書籍検索