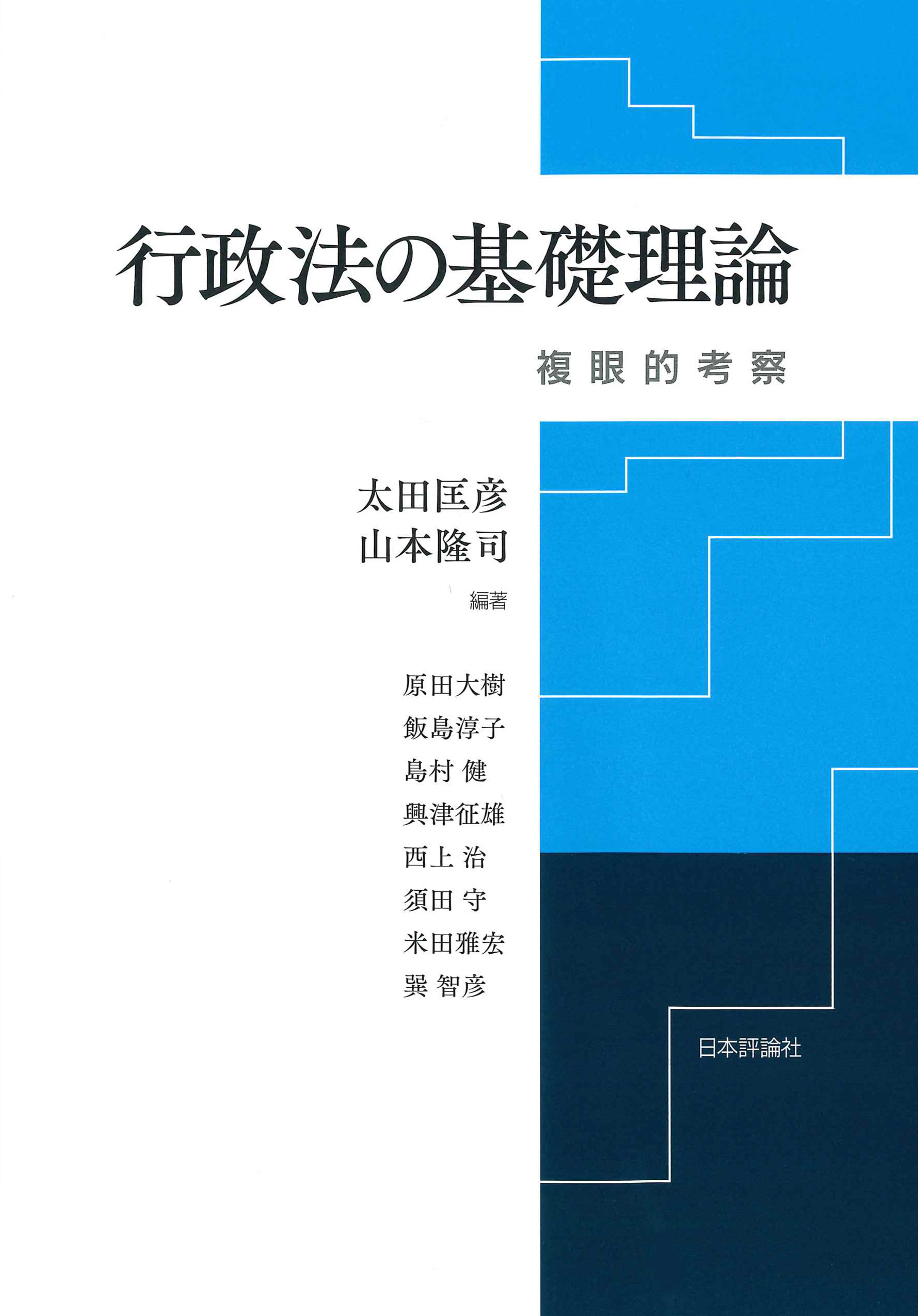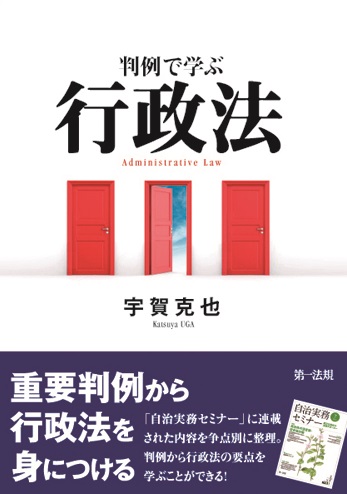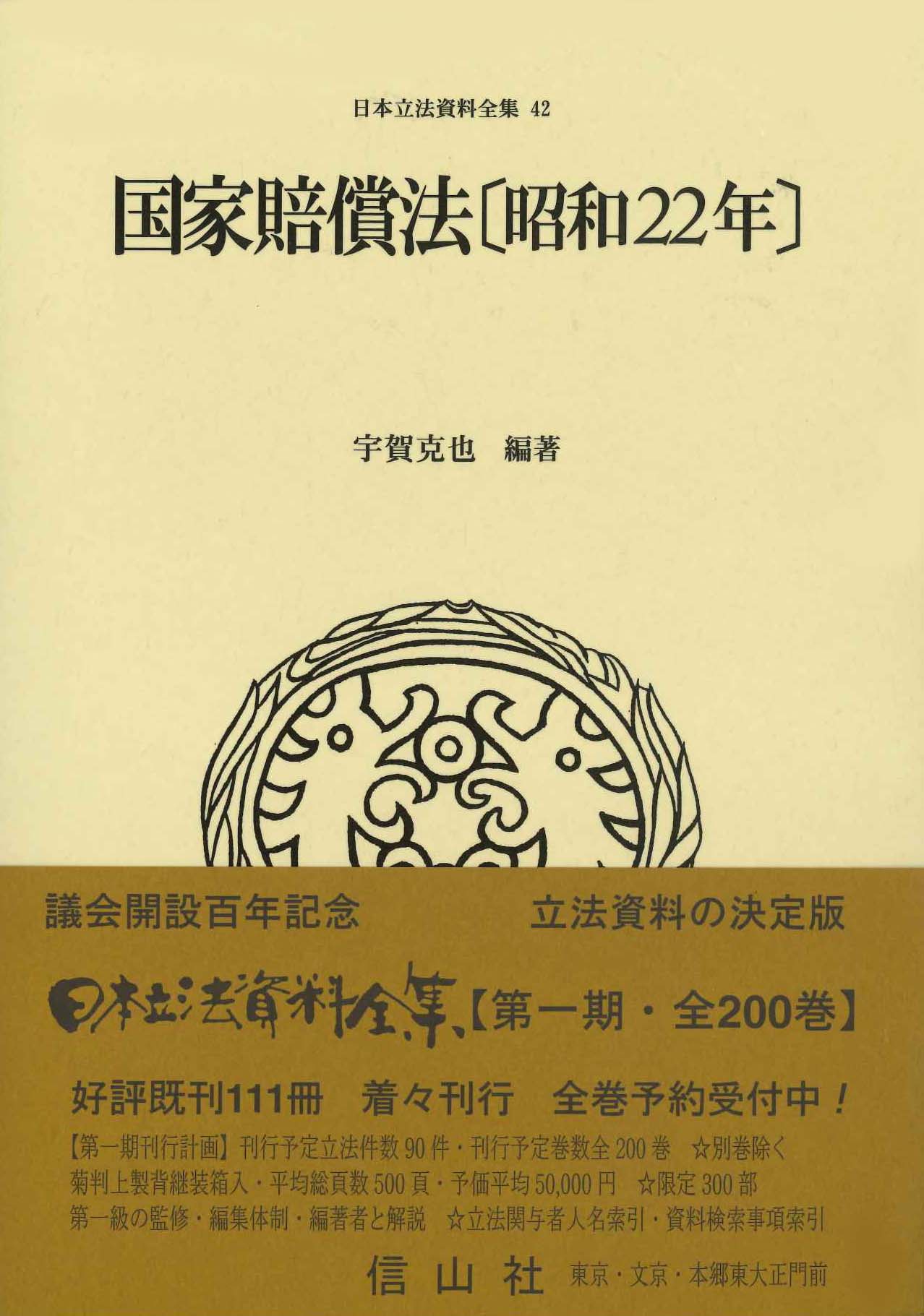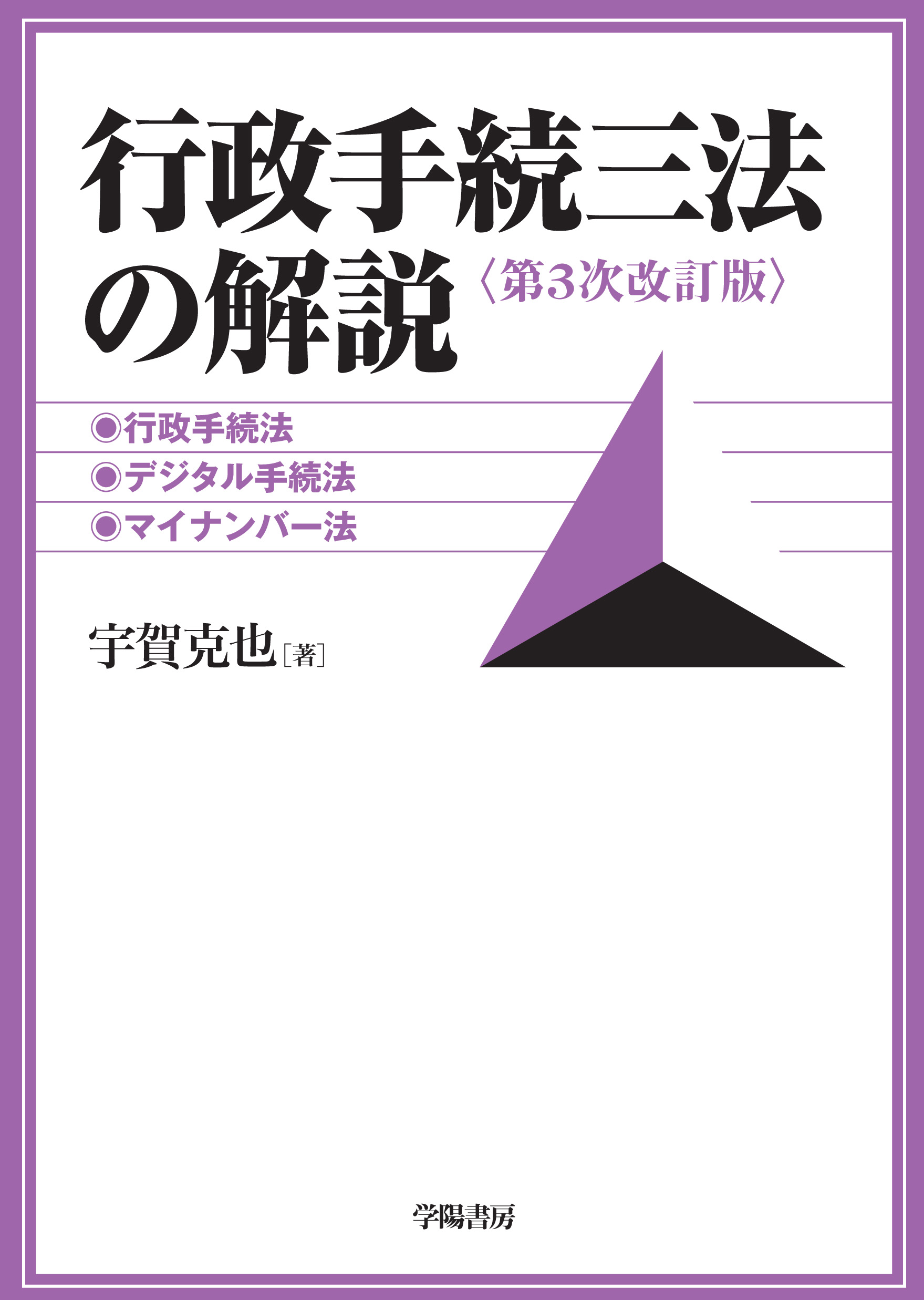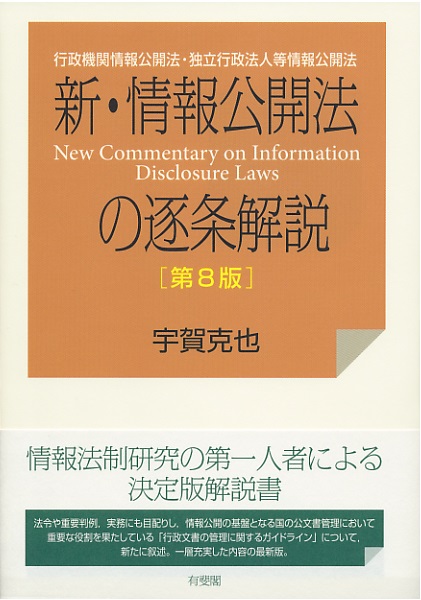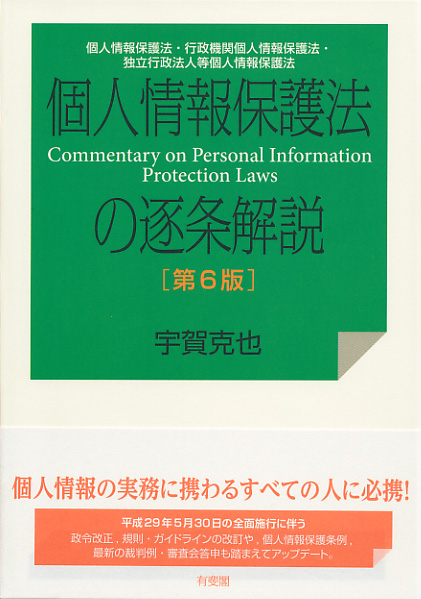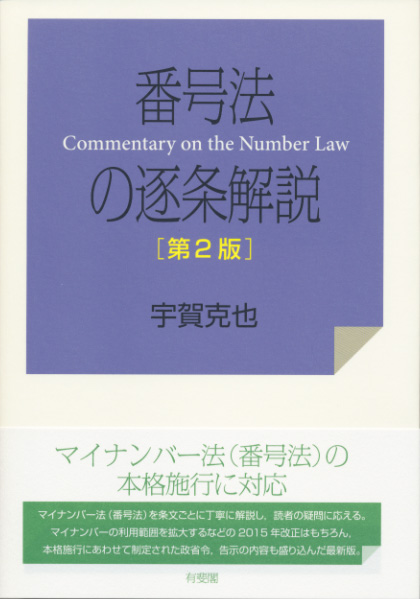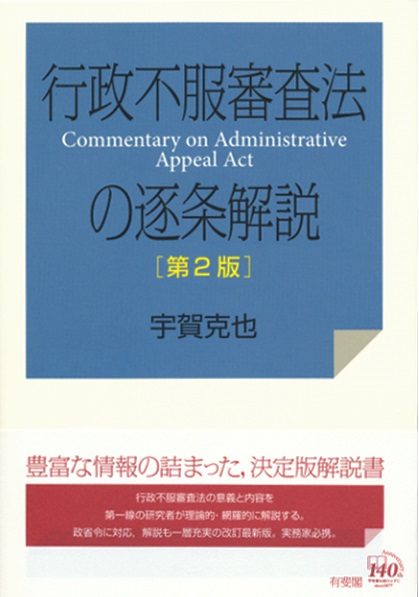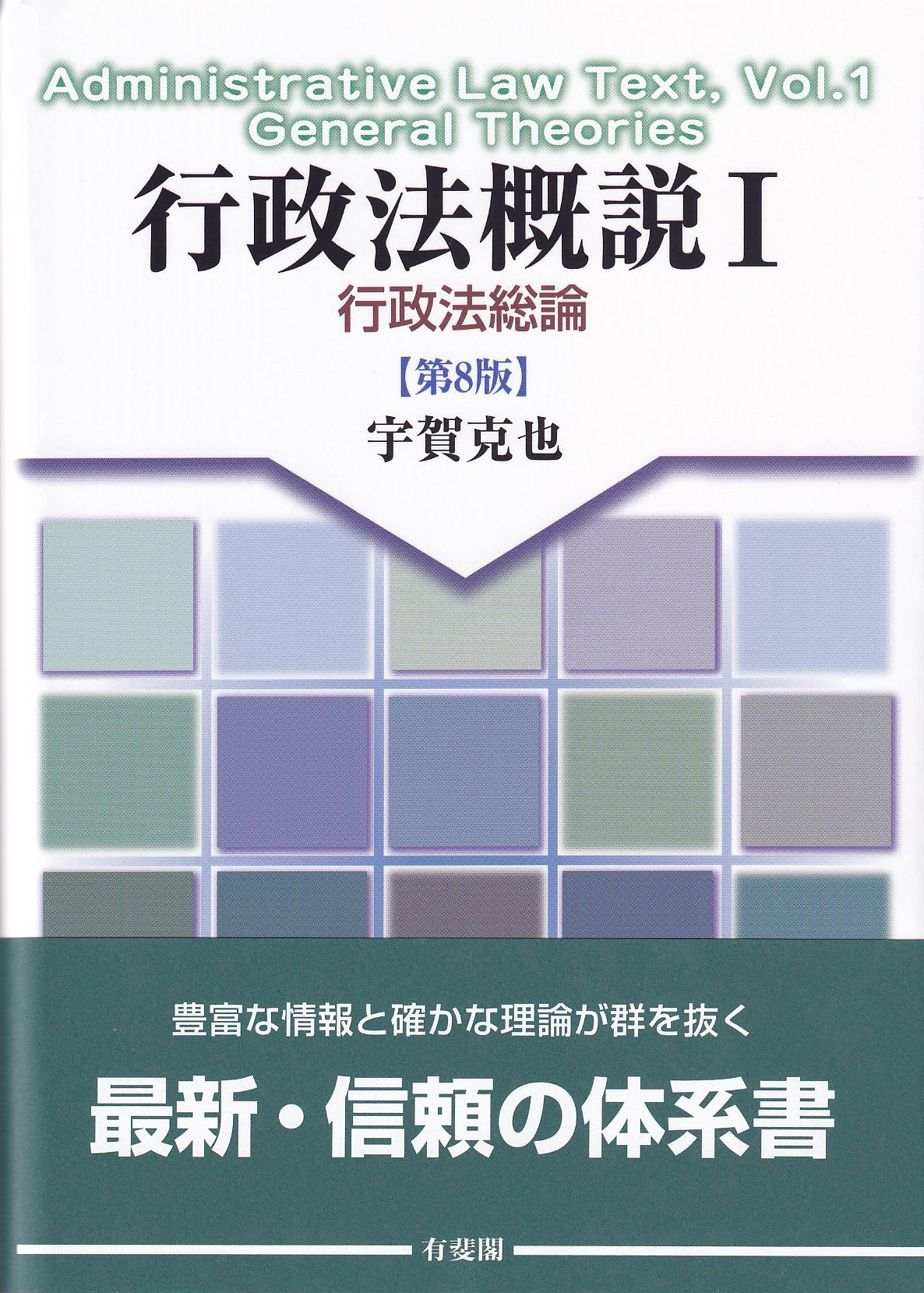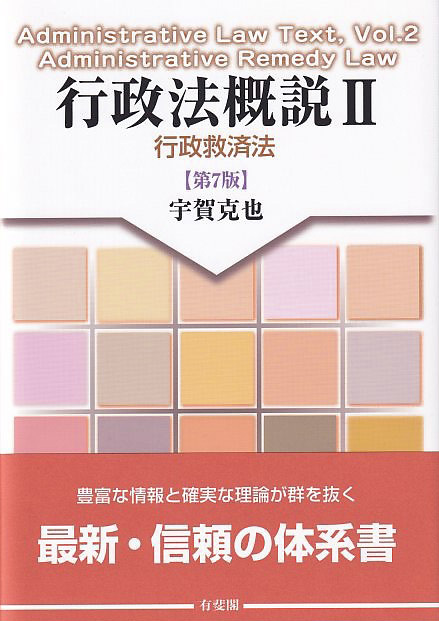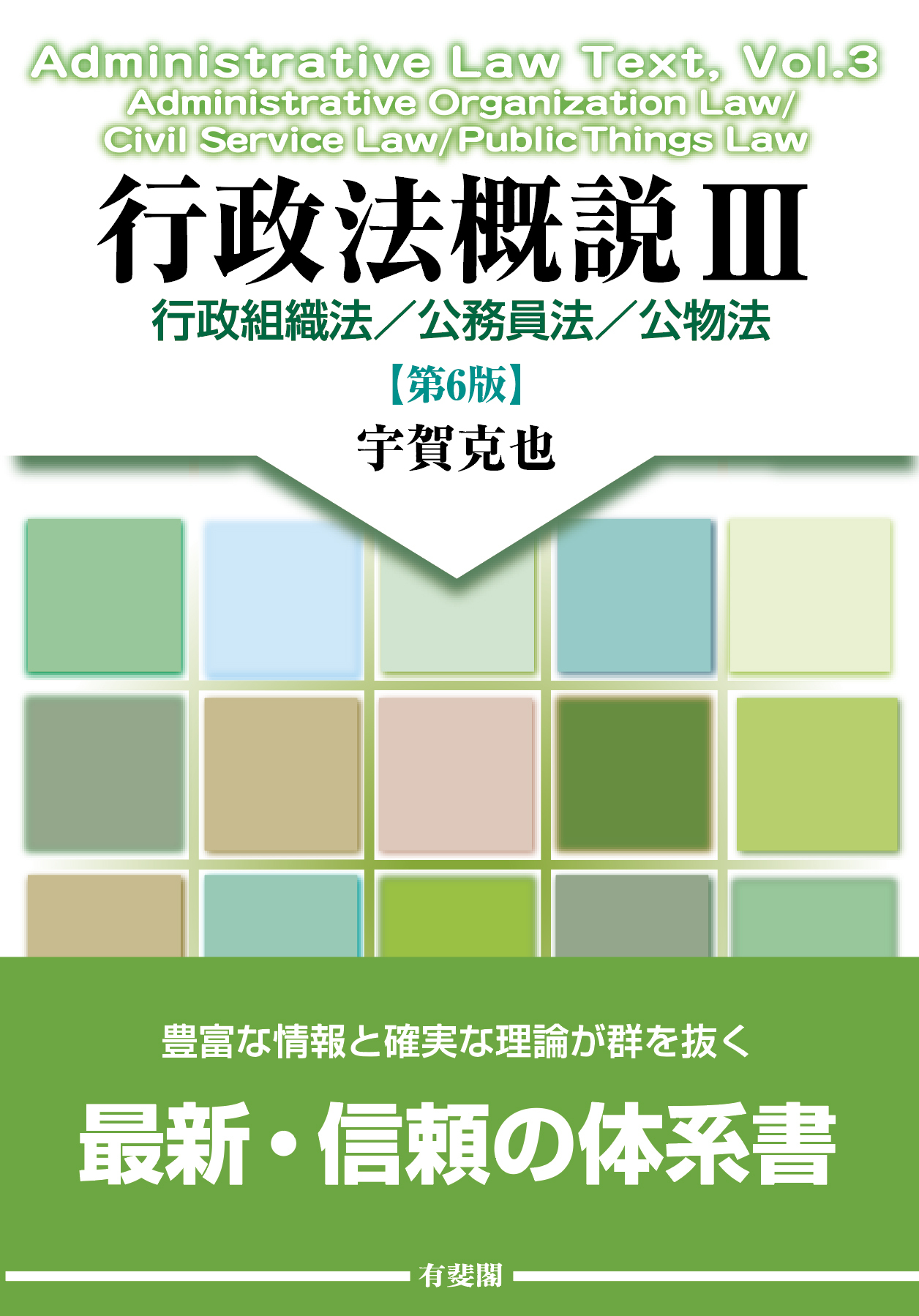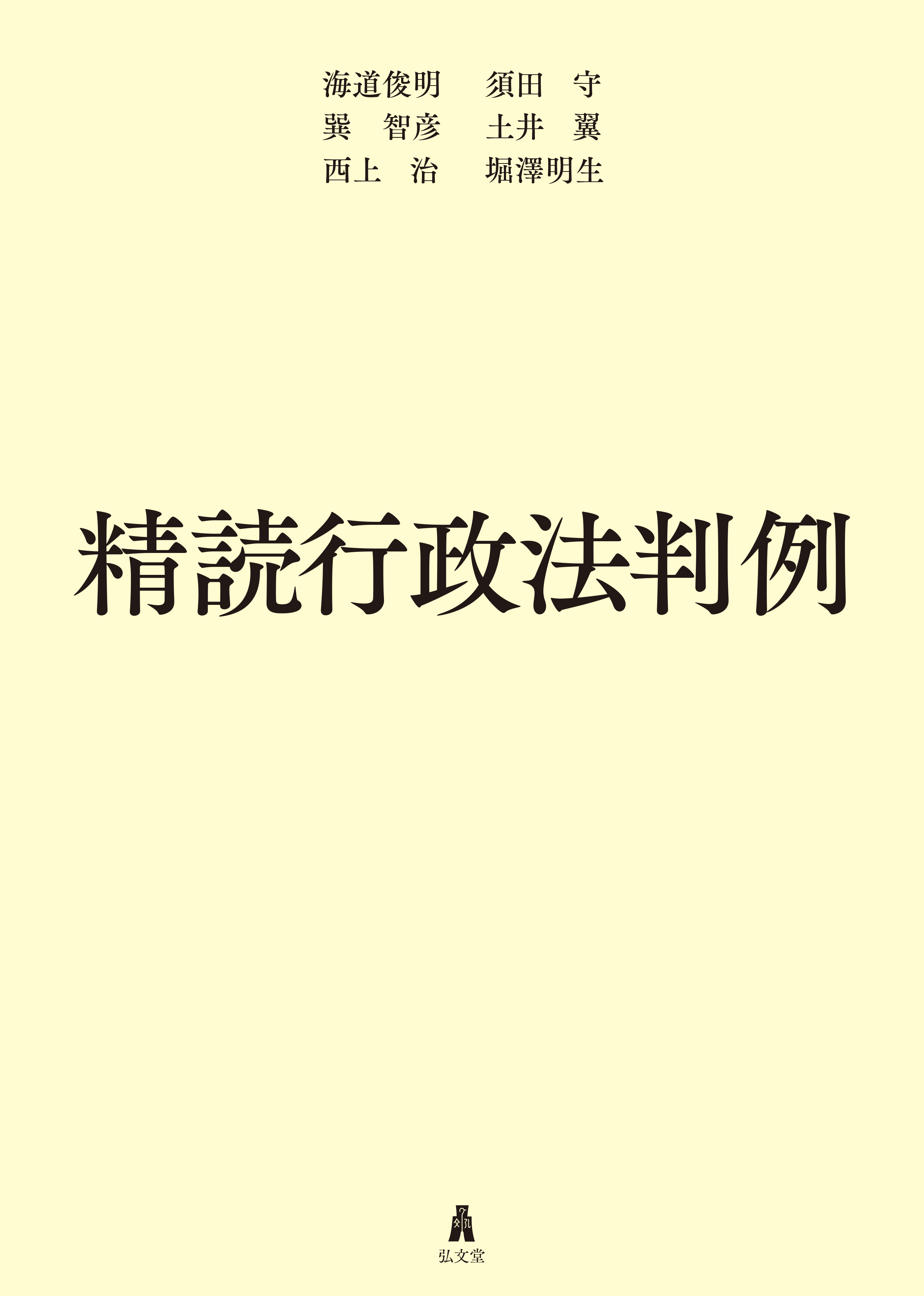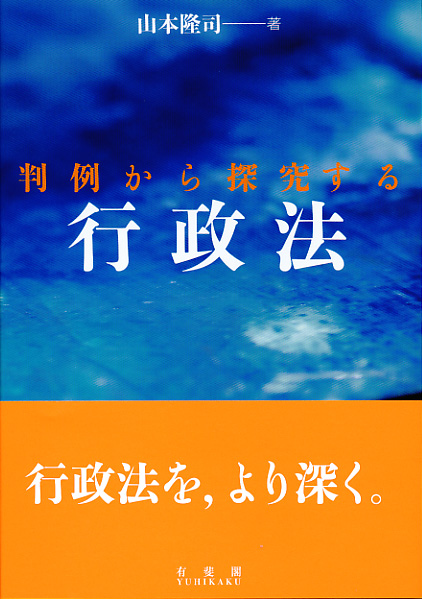
書籍名
判例から探究する行政法
判型など
654ページ、A5判、並製
言語
日本語
発行年月日
2012年12月5日
ISBN コード
978-4-641-13112-5
出版社
有斐閣
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
日本では世紀転換期に、行政手続法、行政機関情報公開法の制定など、行政統制の基礎となる法制度が整備され、さらに2004年には、司法制度改革の一環として行政事件訴訟法が大きく改正された。こうした立法の動きに呼応するかのように、行訴法改正が議論され始めた頃から6、7年の間に、最高裁判所は、行政法理論の発展および再考を促す判決を多く下した。私は、こうした最高裁の判例に顕れている、あるいは隠されている問題提起を丁寧に掬い上げて、学説と裁判実務の双方に反省と考究の素材を明確に提示し分析することが、今度は学説の側が引き受けるべき課題であると考えた。そして、「法学教室」誌に論攷を連載し、それを基に30の最高裁判決を標題として取り上げる単行書の形にまとめたのが、本書である。
本書の狙いを章ごとに要約すると、以下の通りである。
国や地方公共団体という行政主体と私人との関係を、公法・私法という概念により把握する考え方は、行政法学上克服されて久しい。しかし、公法私法二元論に代えて、行政主体が私人に対する関係において有する基本的な権限または義務を根拠付ける法原則、および、行政主体に対する関係において (も) 意義をもつ私人の基本的な法的地位を明らかにする作業は、未だ十分には行われていない。こうした作業を試みたのが、I・II章およびIII章[11]である。
III章の残りおよびV章は、行政行為ないし行政処分を、権力性の強弱という視点から捉えずに、次のように分析する方法を打ち出している。すなわち、行政機関および裁判所が私人とのコミュニケーションを経て実体法 (上の法的地位) に関する判断を行い、確定して実現する手続法関係の一形態として、行政行為・行政処分を理解し、他の法関係との共通性・相違点・接続関係を分析する方法である。錯綜の相を見せる「処分性」に関する近時の最高裁判決を一貫した論理により説明したV章は、こうした方法の成果である。
IV章の「行政裁量の裁判統制」論は、三権分立の基本に関わる。最高裁が近時、明確に行政裁量統制手法の中心に据えている「判断過程の統制」の理論的基礎は、別稿 (判例時報1933号) で説いたため、本書は、最高裁判例において判断過程統制が定着したことの分析にとどめている。本書公刊後、再び理論的に判断過程統制を総括し整理する論攷を発表した (行政法研究14号)。
VI・VII章は、行政法における私人の権利利益をテーマとする。同章では、行政機関の権限と私人の権利利益とを単純に対向させるのではなく、諸種の利益の表出・集合・衡量により公益が実現される行政過程を想定し、こうした過程の各局面で私人にどのような法的地位を認めるべきかを分析する方法をとっている。こうした法的地位と、より現実的・具体的な訴えの利益、および法的地位の侵害に対する国家賠償請求権との関係を、明確にする作業も行った。最後の[29][30]では、行政主体と協働して私的主体が行った行政活動により他の私人が損害を被った場合に、いかなる法的根拠により誰が賠償責任を負うかという、近時注目されている問題について、協働の形態の類型化に基づく答えを試みている。
(紹介文執筆者: 法学政治学研究科・法学部 教授 山本 隆司 / 2016)
本の目次
[1]法律による行政の原理と公課
[2]公共用物の管理と占有
[3]住民の公証
[4]「公法と私法」― 国・地方公共団体の金銭債権・金銭債務の消滅時効
[5]信義則
II 私人の法的地位および行政組織の多元性
[6]公の施設の利用者に関する平等取扱い
[7]外国籍公務員と民主的正統化
[8]地方公共団体と関連団体との「距離」
III 行政の法形式と手続
[9]金銭債権に係る行政行為と国家賠償
[10]違法性の承継と「公定力」― 判断枠組
[11]行政契約 ― 公害防止協定
IV 行政裁量の裁判統制
[12]判断過程統制の構造
[13]行政計画における諸利益のウェートづけ
[14]行政過程と行政訴訟手続との関係
[15]行政契約における経済性と政策的要素のウェートづけ
[16]小括判断過程統制の諸相
V 行政訴訟(1) -- 処分性
[17]権力性 ― 形式的根拠と実質的根拠
[18]規律性(1) ― 「法的効果」の拡張?
[19]規律性(2) ― 最終決定性による拡張
[20]小括 -- 処分性の判断枠組
[21]具体性(1) ― 行政計画の場合
[22]具体性(2) ― 条例の場合
VI 行政訴訟(2) ― 原告適格・訴えの利益
[23]原告適格(1) ― 判断枠組
[24]原告適格(2) ― 個別利益保護性
[25]取消訴訟における訴えの利益
[26]当事者訴訟における訴えの利益
VII 国家賠償
[27]国家賠償法上の違法性(1) ― 判断枠組
[28]国家賠償法上の違法性(2) ― 権限不行使の違法
[29]私人の行為による国家賠償(1) ― 責任の根拠
[30]私人の行為による国家賠償(2) ― 責任の階梯
関連情報
書評 (村田法律事務所ホームページ 2019年11月6日)
http://www.murata-law.tokyo.jp/cms/topics/654
興津征雄 (神戸大学准教授) 評 (『書斎の窓』 2013年6月号)
http://www.yuhikaku.co.jp/review/detail/456



 書籍検索
書籍検索


 eBook
eBook