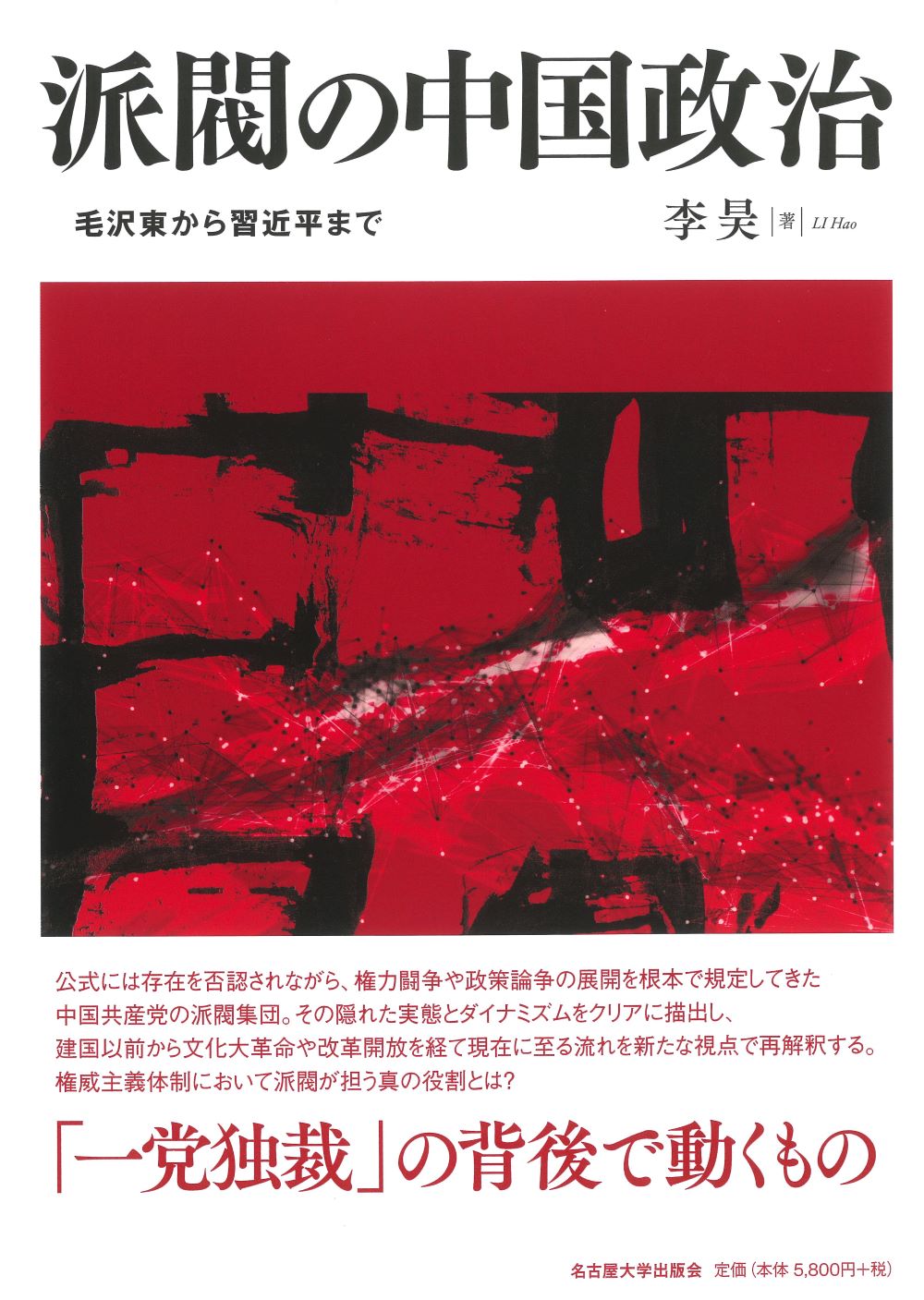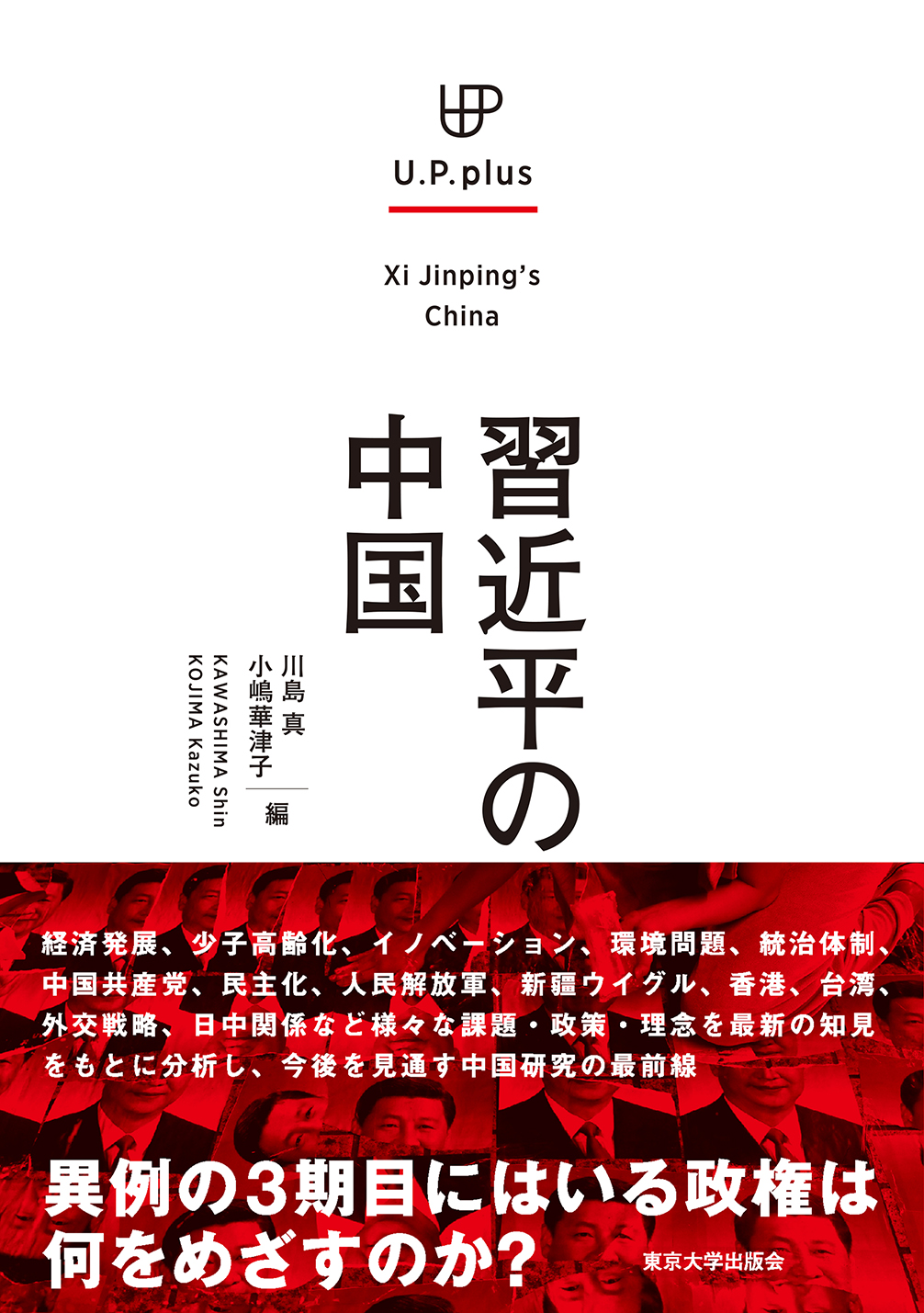本書は派閥という視点から、中国政治のメカニズムを解明することを目指した。派閥が政治エリートに権力基盤を提供し、中国共産党内の政治闘争の単位となってきたことを明らかにし、また、派閥の活動が党内に政策的多様性をもたらして、共産党体制そのものの強靭性を高めたことを指摘する。本書は、これまでジャーナリスティックに言及されることが多かった派閥という概念を、比較政治学の知見を援用しながら再定義し、比較歴史分析の手法を用いて、中国共産党の代表的な派閥を取り上げて詳細に実証分析を行った。
本書の特徴は、理論的な分析を重視した点である。派閥の形成、成長、衰退の過程に着目し、そのライフサイクルと政治闘争の連動の分析に重点を置いている。既存の研究の多くは、派閥を静的なアクターとして分析し、個々の政治問題に対する派閥の影響力をはかることに重点を置いている。本書は、派閥の盛衰それ自体が重要な政治現象であると考える。派閥が成長することで、政治的影響力が拡大され、派閥間の対立が一層激しくなる。そうした動的な派閥と政治闘争の連動を分析し、派閥の活動のメカニズムに対して明快な説明を与えている点が、本書の学術的価値である。また、派閥内部の政治と派閥間の合従連衡の双方から分析を加えている点も本書の重要な貢献である。従来、派閥に関する研究は、派閥間の協力や闘争に着目しがちであった。本書は、派閥内部の政治にも焦点を当て、本人―代理人関係を手がかりとして、派閥内部の協力と対立を分析した。派閥の領袖と追従者が本人―代理人関係を構築し、政策実現や昇進などにおいて互いにメリットを享受できる場合、協力が維持されるが、意見の相違や感情のもつれなどの要因によって、代理人問題に由来する対立が発生することも多い。派閥内の対立が解消されずに激化した場合、派閥の分裂が生じやすい。派閥の分裂は往々にして大きな政治変動を引き起こすが、本書ではそのメカニズムを理論的に説明した。
同時に、本書を通じて、現代中国政治史の理解を深めることもできる。1921年の中国共産党成立から今日に至るまでの百年にわたる期間を分析しており、中国共産党におけるエリート政治の全体像を掴み、時代による変化を理解することができる。本書は個々の事例研究においても、充実した分析を行っている。最新の史料を用いて、中国共産党の派閥をめぐる政治闘争について、独自の歴史解釈を含む詳細な実証分析を行った。各事例分析はそれぞれ独立して優れた政治史分析ともなっている。2022秋の党大会までを含む習近平政権期も議論を展開しており、時事分析としても有用である。
このように、本書は比較政治学における研究対象としての中国の有用性を示したと同時に、中国を専門としない読者にとっても読みやすく、理論を通じて中国を理解できる著作になっている。
(紹介文執筆者: 法学政治学研究科・法学部 准教授 李 昊 / 2024)
本の目次
―― 派閥研究の理論枠組み
1 派閥の研究課題
2 派閥とは何か
3 派閥のダイナミクス
4 派閥と権威主義体制の強靭性
第1章 中国における派閥の歴史と特徴
―― 北洋軍閥・中国国民党・中国共産党
1 近代中国の派閥
2 中国共産党の派閥の歴史と特徴
第2章 毛沢東の派閥操作術
―― 革命戦略と留ソ派・周恩来・劉少奇
1 中共の成立とソヴィエト革命 —— 毛沢東の台頭
2 長征 —— 革命戦略をめぐる対立
3 延安時期以後 —— 毛沢東の指導権確立
小 括
第3章 「林彪集団」と文化大革命
―― 毛沢東独裁の完成と江青
1 廬山会議と文化大革命の発動 ——「林彪集団」の登場と台頭
2 第9回党大会前後 —— 文化大革命をめぐる対立
3 九一三事件 ——「林彪集団」の崩壊
小 括
第4章 余秋里の石油閥と「洋躍進」
―― 華国鋒の経済発展戦略の挫折
1 大慶油田開発から文化大革命まで —— 石油閥の形成と台頭
2 「洋躍進」—— 経済発展戦略をめぐる対立
3 渤海2号事件以後 —— 石油閥の退潮
小 括
第5章 陳雲・経済保守派と改革・開放
――「改革・開放の総設計師」鄧小平再考
1 改革・開放の開始 —— 経済保守派の出現と台頭
2 六四天安門事件への道のり —— 改革・開放をめぐる論争
3 鄧小平の南方談話 —— 経済保守派の消滅
小 括
第6章 江沢民の上海閥と社会主義の変容
―― 政治の制度化と胡錦濤・習近平
1 江沢民政権期 —— 上海閥の形成と台頭
2 胡錦濤政権期 ——「中国の特色ある社会主義」をめぐる対立
3 習近平政権期 —— 上海閥の衰退
小 括
終 章 中国共産党と派閥
―― レーニン主義と比較の視点
1 中共における派閥の役割と変容
2 比較の中の派閥
注
あとがき
参考文献
図表一覧
索 引
関連情報
内藤寛子 評 (アジア経済研究所地域研究センター) 評 (『アジア経済』66巻1号 2025年3月15日)
https://doi.org/10.24765/ajiakeizai.66.1_65
国分良成 (慶應義塾大学・防衛大学校名誉教授) 評 (『現代中国』第98号 2024年)
https://genchugakkai.com/cms/wp-content/uploads/2025/03/20250303.pdf
菱田雅晴 評 (『中国21』第61号 2024年10月)
https://leo.aichi-u.ac.jp/~genchu/china21/2024_10.html
阿南友亮 (東北大学教授) 評 (『中国研究月報』第917号 2024年7月)
https://www.institute-of-chinese-affairs.com/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%9C%88%E5%A0%B1
石井知章 (明治大学教授) 評 (『図書新聞』第3625号 2024年2月3日号)
https://toshoshimbun.com/product__detail?item=1706663237515x548651536913793000
藤野彰 (北海道大学名誉教授) 評 (『公明新聞』 2023年12月4日)
関智英 (津田塾大学准教授) 評 (『週刊読書人』第3513号 2023年11月3日号)
本よみうり堂:遠藤乾 (国際政治学者・東京大教授) 評「縁故・恩の絆 政争100年史」 (『読売新聞』 2023年10月6日)
https://www.yomiuri.co.jp/culture/book/reviews/20231002-OYT8T50049/
関連記事:
「中国で何が起きているのか」(17) 李昊・東京大学大学院准教授 (日本記者クラブ – jnpc 2024年8月6日)
https://www.jnpc.or.jp/archive/conferences/36803/report
なぜ中国共産党は習近平の暴走を止めないのか…中国が「世界の嫌われ者」に転落した根本原因 (プレジデントオンライン 2022年10月21日)
https://news.infoseek.co.jp/article/president_62811/
メディア出演:
NIKKEIで深読み 中国経済の真相: #11 習近平氏は本気で台湾を攻めるつもりか、李昊さんが読む中国共産党の未来 (ラジオNIKKEI 2024年10月31日)
https://www.radionikkei.jp/podcast/episode.html?p=cn_shinsou&e=9296fe6e-96aa-11ef-847d-a3fe531d23cf
セミナー:
現代中国研究センターセミナー「中国政治を読み解く----派閥の視点から」 (慶應義塾大学東アジア研究所 2023年12月18日)
https://cccs.kieas.keio.ac.jp/activity/000553.html
神戸大学国際文化学研究推進インスティテュート(Promis)共催セミナー
連続研究会「平和と共生の政治学ー国家中心主義を超えてー」
第4回:中国共産党の派閥と江沢民・胡錦濤・習近平 (神戸大学国際文化学研究科 、国際関係・比較政治論コース 2022年7月1日)
http://promis.cla.kobe-u.ac.jp/promis-wp/wp-content/uploads/2022/06/20220701.pdf



 書籍検索
書籍検索