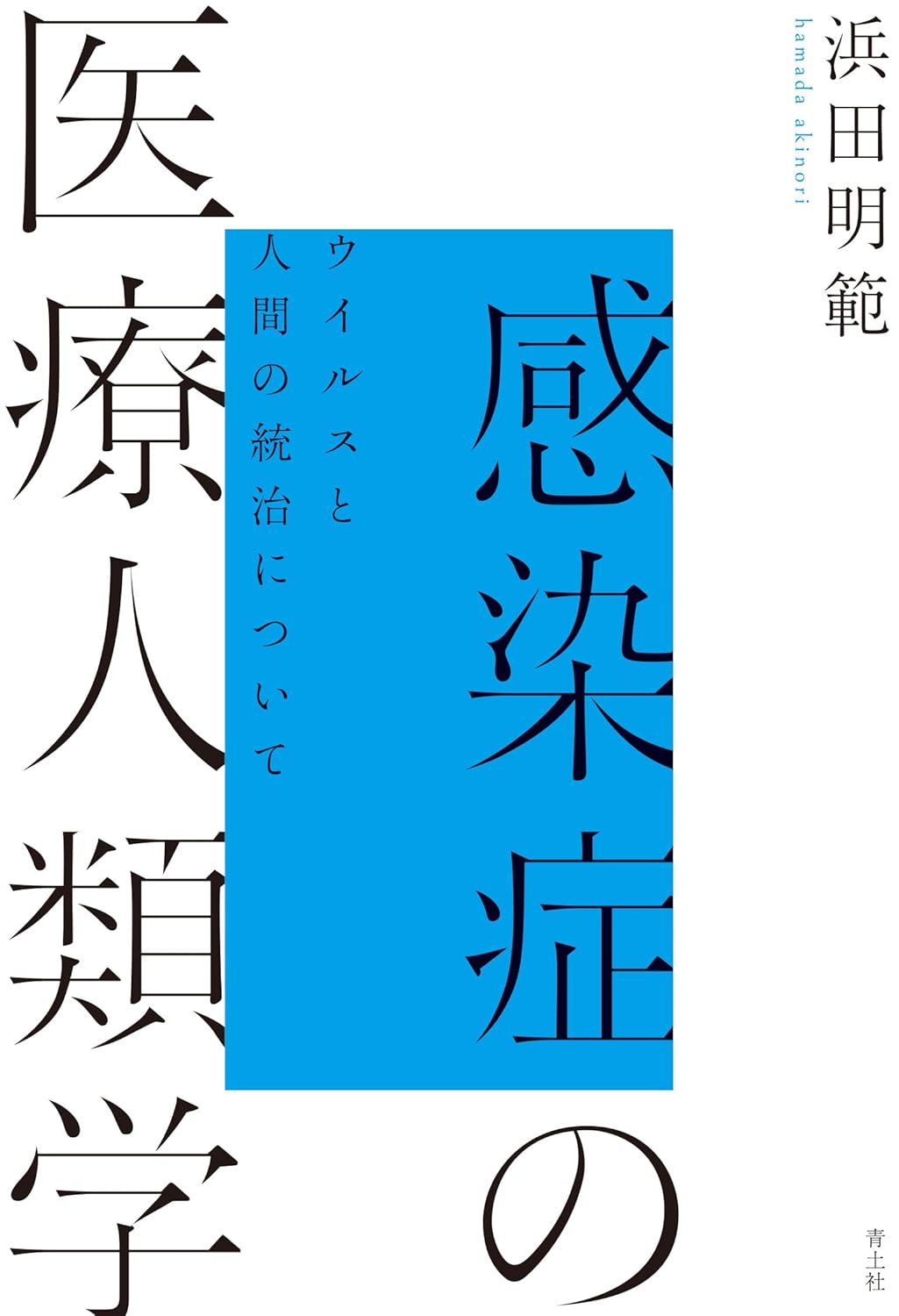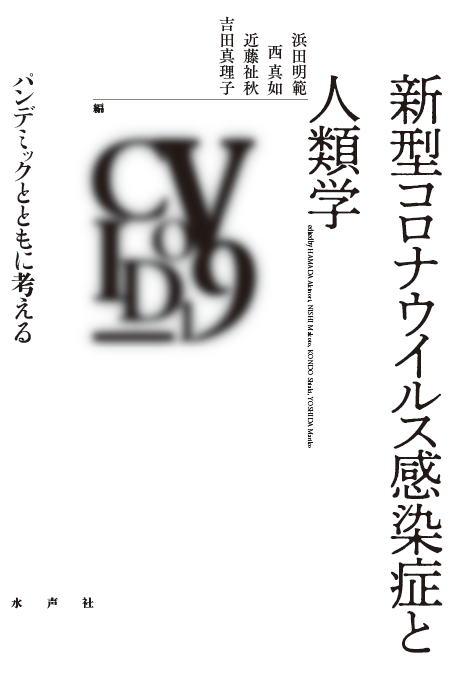1970年代後半に文化人類学の下位分野として確立した医療人類学は、長らく、歴史学、社会学、哲学などと歩調を併せながら、いかに生物医療や公衆衛生を批判するのかに力を注いできた。そこでは、医師や科学者の視点からだけでなく、患者や普通の人の視点から病気について検討する意義が強調されてきた。他方で、文化人類学においては、2000年代以降、自然や科学技術については自然科学に任せ、それらに対する文化的意味づけのみを検討する人文学の態度に対する厳しい内省が行われてきた。現在の世界の状況に目を向ければ、自然と文化、科学技術と政治の絡み合いこそが探究すべき課題であることは明らかだからだ。いわゆる「存在論的転回」と呼ばれるこの潮流と正面から向きあうのであれば、医療人類学も、単純に生物医療や公衆衛生を批判して済ませるわけにはいかなくなる。
本書はこのような問題意識に基づいて、次世代の医療人類学を構想しようと試みたものである。第1部「パラ医療批判の人類学に向けて」では、これまでの感染症の人類学の蓄積と筆者が2005年より続けてきたガーナ南部の医療状況についての現地調査に基づいて上記の問題意識の重要性を展開している。とりわけ感染症に関する医療人類学的研究においては、単純に生物医療や公衆衛生の権力性を批判するだけではなく、どの生物医療やどの公衆衛生が行われるべきなのかについても検討されてきている。そこで目指されていたのは、生物医療や公衆衛生をひとまとめにぶった切る「医療批判」ではなく、生物医療や公衆衛生のとなりで、より良き生を探究するという目的をそれらと共有したうえで、同時代を生きる者としての責任を引き受けた「パラ医療批判」とでも呼ばれる態度である。この「パラ医療批判」に形を与えるために、第1部ではガーナ南部の医療状況についての研究成果も収録している。第2章ではよりミクロな視点から結核対策について検討し、第3章ではメゾレベルから河川盲目症対策やワクチン接種のあり方について検討している。
第2部「このパンデミックを生きる」は、2020年以降の新型コロナウイルス感染症の流行について、日本の経験に基づいて時系列に沿って議論を展開している。当初目指していたのは、他者を理解するという文化人類学の伝統にのっとって日本の公衆衛生専門家たちの思考と振舞いを理解することであり、同時代を生きる者としての責任を引き受けて、感染症の流行を減速させるための言葉をいかに紡ぐことができるのかということだった。第2部の後半はより理論的な関心に基づいて、ウイルスを通して人間存在について考える思考の端緒を収録している。この方向性については、本書の執筆後も継続して研究を続けている。
本書を通じて、多くの人に新しい医療人類学の動向に触れていただき、ともに道を進んでいく人が現れることを切に願っている。
(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 准教授 浜田 明範 / 2024)
本の目次
第1部 パラ医療批判の人類学に向けて
第1章 感染症と人類学
第2章 干渉を描くこと――環境改編としての政策・適応・書き物
第3章 化学的環境のリズム――薬剤を時空間に配置することについて
第2部 このパンデミックを生きる
第2部のための端書
第4章 患者の責任とペイシャンティズム
第5章 感染者数とは何か――COVID-19 の実行と患者たちの生成
第6章 医薬化する希望――不在のワクチンが見えづらくするものについて
第7章 ウィズコロナの始まりと終わり――パンデミックにおける身体、統治、速度
第8章 テレストリアルたちのパンデミック
終 章 テレストリアル的介入の行方
おわりに パラコロナを生きる
あとがき
参照文献一覧
索引
関連情報
市野川容孝 評<本の棚> (『教養学部報』第657号 2024年10月1日)
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/about/booklet-gazette/bulletin/657/open/657-2-02.html



 書籍検索
書籍検索