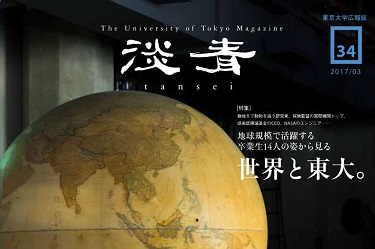スペシャル対談 「世界と大学。」 | 広報誌「淡青」34号より

特集テーマについて識者が語り合う本誌恒例の巻頭対談。
今回は、担当理事として東大の国際化に取り組む羽田正先生が、このテーマでいま話したい人として真っ先に名前を挙げた、オックスフォード大学の苅谷剛彦先生をお迎えしました。
大学が国際社会で果たすべき役割、世界のなかでの東大の立ち位置、目指すべき国際化の姿、はたまた東大や東大生への注文について、地球儀を手元に置きながら語っていただきました。

――課題が山積する国際社会で大学はどういう役割を果たすべきか。日本は、東大は、世界でどんな立ち位置にいるのか。その辺りから始めていただけますか。
羽田 では私から。世界的な課題というのはそう簡単に解決するはずはない、と私は思っています。唯一の解というものはなく、様々な解があって、その様々な解にアプローチするための知を提供する場として機能しているのが大学です。グローバル化が進み、国家の力だけでは世界の秩序を維持できない中、大学は世界の諸問題の解決に資する知を生み出し、世界の公共性に奉仕するために存在します。東大憲章にも記されたこの考え方が非常に重要です。日本には日本語による知の体系があり、そこから生まれる独自の見方、問題へのアプローチに特徴的なものがある。日本にある東京大学はこれを活かして世界の知に貢献すべきだと思っています。苅谷先生はいかがでしょうか。
ユニバーサルな分野と
地域性を背負う分野の違い
苅谷 便宜的に文・理に分けてみましょう。理系の分野では、論文を英語で書くのが普通です。英語以外にも数式、化学式とユニバーサルな言語があって、対象もユニバーサルですから、どこで研究しようと問題ありません。一方、文系の学問の多くは歴史と文化と地域性を背負っています。非西洋圏で、ローカルな言語で学問的蓄積を社会や文化に対して行えているという意味では、日本は世界でトップです。その知の体系は日本語で表現し蓄積してきたもの。歴史や文化の独自性と同時に、それを学問として残してきたことが強みとしてあります。この20~30年で西欧中心の見方にも反省が加わり、西欧は世界の中心ではないという見方が浸透してきました。そこで新しい発想を打ち出せるとしたら、極の一つは日本です。当然、東京大学の役割は非常に重要です。
羽田 その通りですね。日本は日本語で世界の細部に到るまで考え、理解できる知の体系を持っています。英語やフランス語など別の言語の知も貪欲に取り込みましたから、複雑で高度な知の体系になっているはずです。でも、残念ながら関心をもつ外国人は多くない。その知を他言語に移し替えることもあまり行われていない。それが問題です。
苅谷 自動翻訳の技術が劇的に発展したら話は別ですが、なかなかそうはいかないとすると、精密な表現が可能なローカル言語を持つことは強みです。ローカル言語のまま閉じるのでなく、文系も外に発信しようとはよく言われます。このとき、発信の本質を間違うと、読まれるものになりません。日本語で書いたものを他言語に移すだけでは見てもらえない。読まないと一つの理論が組み立てられないとか、その発想を使えば+αが生じるとか、独自の価値が加わらないといけない。研究が海外でも価値を持つにはどうすべきかという発想を持つべきです。
文系でも、経済学、心理学、社会学の一部など、サイエンスに近い分野は言語に依存しません。世界標準の手法を日本語で行えばよいわけですが、これはユニバーサルな手法に日本のデータを載せるということ。日本の知の体系のアピールにはなかなかなりません。ずれが見つかったとしてもそれだけでは他国の人を引きつける価値にはなりにくい。歴史、文化、発想のほうで勝負したい。ただ、やりすぎると日本は特別だという日本論に陥りがち。一瞬の驚きで終わってしまいます。
羽田 たとえば、新渡戸稲造は英語で日本の武士道について書き、英語圏の人々に大きなインパクトを与えました。西洋の騎士道にあたるものが非西洋のはずの日本にもあると言って、西洋だけが特別だという見方を批判したのです。でも、もとにある西洋対非西洋という世界観の枠組みそのものの変更を迫るには至っていないと思います。
苅谷 英語の達者な日本人が西洋の知識をもとに日本人の精神を紹介したわけですね。文化の交わりのなかでこの段階は必ず通過するはずですが、日本がグローバル社会でどんな役割を果たすかを考えたい今の段階では、これでは足りません。
羽田 西洋中心の考え方ではおかしいというときに、ではどういう見方がよいのかを提案したわけではないですよね。いまなすべきは、西洋も知悉した上で、世界で起こっていることを理解できる新しい枠組みを提案することです。
苅谷 新渡戸の時代、英語で書くことは英語圏の人が読むことを前提としましたが、今はむしろそれ以外の人が読むことを意味する。そういう時代に日本の発想で何を説明できるかを考えないといけませんね。
羽田 大学の話に戻しますと、日本語での教育をきちんとやると同時に、日本語の知の体系をどのように英語にして教え、理解させるかという点も重要です。東大がこれをうまくできれば、他大にはないアドバンテージになります。
苅谷 実は、私がオックスフォードの授業でやっているのはまさにそのためです。私の強みは圧倒的に日本語が読めること。英語の文献を使って日本のことを教える際、元の日本の現象や日本語文献との間にどんなずれがあるか、そのずれにどんな意味があるかは、重要なテーマとなります。そこを考えれば日本からの発想で何かが生まれることになる。日本の大学は英語の授業を増やそうとしていますが、単純に教員を外国人に置き換えたらいいわけではないですね。たとえば、母国語でも一種の異文化として接するようなセンスが必要です。
羽田 その通りです。なかなかこの話は通じないことがあります。心強いですね。
誰も気づかないテーマなら
ゆっくり丁寧に研究できる
苅谷 海外で英語を使って日本を研究する人と、日本で日本語を使って研究する人とでは、互いに気づかないテーマがあります。国際標準のスキームにデータをあてはめて日本を語ろうとすれば、いかにいいデータを得るか、より進んだ統計手法を使えるかという速さの競争になります。でも、他の人が気づかないテーマを見つけると、ゆっくり丁寧に進めることができます。そうしないと英語ネイティブと同じ土俵では戦いにくいですしね。
――東大の長所ということではいかがでしょうか。
苅谷 たとえば、書庫に潜り込み、目当ての文献の近くの本をめくって初めて見つかるものがあります。これはデータベースでは探せない。充実した書庫がないと無理です。その意味で東大は日本についてはもとより西洋の知識や理論を日本語で体系化してきた知的資源の宝庫です。露天掘りのように、手に触れる形で知が埋まっている。ただ、残念ながら相当な日本語力がないと掘り出せない。国際的に通用する知にどう加工するかというプロデュースの問題があるわけです。
羽田 自分の本を翻訳する際、このままだと日本人以外には通じないな、と感じることがあります。翻訳を前提に書くのと、翻訳を前提にせずに書くのとでは、書き方が変わりますね。
苅谷 英語で書く場合でも論文と本では書くスキルが違うことも重要な点です。研究を正しく伝える論文と、一つの世界が映し出される本の差は、分野を問わずあります。英語論文の書き方と同様に、英語に翻訳される本のノウハウはある程度教えられるはず。そのプロデュース力が加われば、日本語で書かれた知の有効性はもっと強くなると思います。
羽田 実は今、翻訳されることを初めから意識しながら新しい本を書いています。日本語で書くと無意識のうちに日本語話者だけを対象にしてしまいます。それは誰かに言われないと気づかないことが多いと思います。
苅谷 知的共同体たる大学が優秀なエディターを雇って進めるべきことかもしれませんね。
――東大の順位がよく話題になる世界大学ランキングについてはいかがですか。
学生と教員が全員外国人なら
最も優れた大学になるのか
羽田 たとえばTimes Higher Education(THE)のランキングでは留学生と外国人教員が多いほど点数が高くなります。東大の評価が低い部分ですね。先日、THEの人と話した際、「学生と教員が全員外国人なのが一番いい大学か? 」と質問したら、さすがに詰まっていました。ランキングは完全なものではありません。彼らはビジネスとしてランキングを作っています。それは自由にやればよい。ただ日本の政治家やマスメディアはそれを無条件に信奉しないでほしいと思います。
 苅谷 外貨を稼ぐ産業としての高等教育は英語圏の強みですね。先日、初めてオックスフォードがTHEで1 位になりました。いままで誰も何も言わなかったのに、今回は学長が全教員宛のメールに書いていましたよ(笑)。そういえば、日本政府が指定国立大学制度を進めていますね。ランキングを意識しているのかもしれませんが、英語圏でない日本が高等教育で外貨を稼ぐのは無理筋です。順位より日本の知がつくってきたコンテンツのほうが国際貢献できるはずです。
苅谷 外貨を稼ぐ産業としての高等教育は英語圏の強みですね。先日、初めてオックスフォードがTHEで1 位になりました。いままで誰も何も言わなかったのに、今回は学長が全教員宛のメールに書いていましたよ(笑)。そういえば、日本政府が指定国立大学制度を進めていますね。ランキングを意識しているのかもしれませんが、英語圏でない日本が高等教育で外貨を稼ぐのは無理筋です。順位より日本の知がつくってきたコンテンツのほうが国際貢献できるはずです。羽田 国際担当の理事・副学長としては、東大の外国人留学生は30%程度がよいと思っています。10%だと少なすぎますが、30%いれば一つのマスとして存在できる。30%だと大学ランキングでは上位にいけませんけどね(笑)。
苅谷 私のいるカレッジでは地域研究の研究者が多いんです。中東研究でも中国研究でもあえてイギリスで行うのは、イギリスの歴史的な背景があるから。日本にも特徴的な背景があります。日本でこそ学べる重要な見方があることを知れば、外国の研究者が集まります。「日本を研究する」でなくてもいい。「日本を通して○○を研究する」人を増やせばいいと思います。
――最後に東大生や東大にメッセージをお願いします。
苅谷 東大に入ったということは宝の山に入り込んだということ。何か一つ人と違う強みを持つとその宝が生きてきます。そして、チャンスに恵まれた場にいるという自覚と責任を持つべきです。そうすると、いかに自分がそれを無駄遣いしているかがわかるでしょう。この宝の山をフルに活用してほしいと思います。
羽田 国際化が外国人と普通につきあえるようになることだとすると、教員の多くはすでにこれを実現しています。大学の執行部としては、教員同士の協力を束ねて大学同士の関係に高め、教育・研究を共同で進められるようにしたいです。交換留学、体験活動プログラム、サマープログラムなど、学生に国際的な体験をしてもらう様々な仕組みづくりを進めています。オックスフォード大学にもそのよきパートナーであってほしいと思っています。
苅谷 互いにとって意味のある連携相手でありたいですね。
Masashi Haneda
1953年生まれ。東京大学東洋文化研究所教授、同所長、東京大学副学長、国際本部長を経て、2016年より理事・副学長(国際担当)。専門分野は世界史。主な著書に『新しい世界史へ』(岩波書店)、『冒険商人シャルダン』(講談社)、『東インド会社とアジアの海』(講談社)、『イスラーム世界の創造』(東京大学出版会)など。趣味はテニス、歌舞伎鑑賞。
Takehiko Kariya
1955年生まれ。放送教育開発センター助教授、東京大学教育学研究科教授を経て、2008年よりオックスフォード大学社会学部・ニッサン日本研究所教授。専門は日本社会論、社会学。主な著書に『イギリスの大学・ニッポンの大学』(中公新書ラクレ)、『教育と平等』(中公新書)『教育の世紀』(ちくま学芸文庫)、『学力と階層』(朝日文庫)など。趣味はウォーキングとスイミング。
はみだしトーク1
羽田 日本の知が世界の知の構造を大きく変えた例はまだないと思いますが、私はグローバルヒストリーでそれを試みています。欧米と違う日本独特の世界観と歴史観で世界の歴史の新しい描き方を提示したい。そう簡単にはいきませんが。
苅谷 80~90年代、日本的経営システムの長所は国外から注目されました。影響力があったのは確かで、今もトヨタの生産方式は世界に通用します。その強さの秘密の一端は教育にあるということで、日本の教育も注目されました。日本の追いつき型近代という今の私の研究テーマのなかで教育政策は宝の山です。様々なイデオロギーが入り込んでいる。海外の研究者も日本にいる研究者も気づきにくいことです。
羽田 日本語の「近代」をそのまま「modernity」に翻訳しても話が成り立たないという難しさがありますね。
はみだしトーク2
羽田 本当に国際的な大学とは、国際担当理事がいない大学、international divisionのような部署がない大学だろうと思うんです。オックスフォードには国際本部なんてありませんよね?
苅谷 いかに国際化を進めるかという部署だとすると、それはないです。
羽田 日本人とその他を分けている限り、国際的ではありません。でも、日本の大学の事務体制はそのように分かれています。
苅谷 ヨーロッパのほかの古い大学がTHEでランクの低いなか、オックスフォードやケンブリッジは英語圏の強みで何とか国際性が認められています。アメリカの大学は留学生は多いがドメスティックで、自国のためという姿勢が基本です。
羽田 アメリカで国際化と言っても英語以外の言語は考えないでしょう。「国際的」と「international」の意味も違いますね。
はみだしトーク3
苅谷 私にとって最初の海外体験は、留学前の語学研究で行った夏のカリフォルニアです。もうあらゆることが楽しかった。その後の留学はノースウェスタン大学でした。
羽田 シカゴですね。
苅谷 博士課程を始めるというのに全然英語が通じず、苦労しました。オーラルなんてとんでもない話で。日本人は読めて書けるというけど、それもダメでした。
羽田 私は最初がソ連。留学はイラン革命の余波でパリでした。冬に着いたら、寒いのに暖房がない部屋。器具を買いに行ったら何度言っても売ってくれず。小切手か現金かを聞かれていたと後で知りましたが、小切手なんて語は初耳で(笑)。
苅谷 日本で学ぶ語学では、そういうローカルな表現までは習いませんから。
羽田 ヨーロッパの冬はきついですよね。
苅谷 シカゴの冬もきついです(笑)。
 向ヶ岡ファカルティハウス(アブルボア)
向ヶ岡ファカルティハウス(アブルボア)
今回の対談場所は弥生キャンパスにあるAbreuvoir(フランス語で「動物たちの水飲み場」の意)。アーティスティックな雰囲気のレストラン、木をふんだんに使ったバー、14部屋の宿泊施設、会議室を備えたファカルティハウスです。http://www.abreuvoir.co.jp

ファルク地球儀レプリカ
江戸時代の輸入地球儀で現存する最古のものが長崎県の松浦史料博物館にあります。1700年にオランダのファルクが製作 し、平戸藩主・松浦静山が伝えてきたもの。北海道がなくオーストラリア辺りが不正確なのは製作が伊能忠敬やクックの登場前だから。銅版画家でもある製作者 による美しい球体が大航海時代の息吹を現代に伝えます。
渡辺教具製作所 blue-terra.jp
写真:貝塚 純一
※本記事は広報誌「淡青」34号の記事から抜粋して掲載しています。PDF版は淡青ページをご覧ください。