寄稿/元国連職員の准教授が解説する「国連と東大。」|広報誌「淡青」34号より

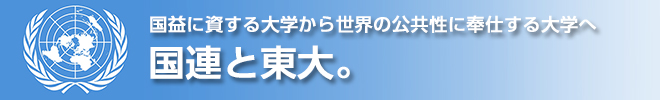
2014年、エマ・ワトソンUN Women親善大使(当時24歳)が国連で行ったスピーチが話題を呼びました。『ハリーポッター』や『美女と野獣』で知られるワトソンは、ジェンダー平等をめぐり、「悪が勝利するには簡単で、善良な男女が何もしないだけでいい」との言葉を引用し、「私でなければ―誰が? 今でなければ―いつ?」(UNIC訳)と述べ、全ての人に行動を呼びかけたのです。
二度の大戦後、平和の誓いの下に創設された国連は、2015年、創設70周年を迎えました。加盟後60年間、日本は、安全保障理事会非常任理事国に加盟国最多の11回選出され、30年に渡り第2位の拠出国であり続けています。東大との繋がりは特に深く、日本人初の国連職員である明石康元国連事務次長、高須幸雄国連管理局長をはじめ8人の歴代事務次長のうち6人が東大出身である他、天野之弥国際原子力機関事務局長等、多くの国連幹部・職員を輩出し、外交官や市民社会の立場からも卒業生による多くの貢献がなされてきました。また、事務総長であったコフィ・アナンや潘基文が来校し学生と交流した他、国連訪問や講義を含む教育活動、最先端の研究成果の提供、学生による活動など、東大と国連を結ぶ様々な活動が続けられています。
2017年、元ポルトガル首相で前国連難民高等弁務官のアントニオ・グテーレス新事務総長が就任し、「世界中で多くの人々が、恐怖に駆られた決定を下している。(中略)こうした人々の不安を理解し(中略)相互に対する恐怖を相互に対する信頼に変えられるよう、力を合わせることです」と述べました(UNIC訳)。また、2030年までの国連の開発をめぐる優先目標「持続可能な開発目標(SDGs)」では、「誰一人取り残さない」ことが中心に据えられました。最も周辺化された人々にこそ目を向けることに世界中が同意したのです。今も、難民や避難民、女性、子供、移民、障害者、高齢者、先住民、そしてLGBTなどをめぐり、多くの国で深刻な状況が続いているからです。
47歳で第2代事務総長となり、和平ミッション中に飛行機事故で亡くなったダグ・ハマーショルドが残した「国連は、人を天国に誘うためではなく、人を地獄から救うために創設された」という言葉に、国連は立ち返りました。その上で、新事務総長が「恐怖」に注目したように、従来の軍事や金を中心とする見方から、人々の心のウェルビーイングに目を向け、それを指標とする社会を作り上げる必要があります。UNESCO憲章が「戦争は人の心の中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」と謳った理念に、人類は追いつかねばなりません。
実現を担うのは、強い者と徒党を組むよりも苦しい状況にある者に手を差し伸べ、インフラや身体などの形あるものと共に感情や背景事情に目を配り、自らの文化も異なる文化も共に尊ぶことができる人たちです。東大に戻り、開講した国連に関するクラスに、そのような学生が沢山いることを頼もしく思っています。
 井筒 節 Takashi Izutsu
井筒 節 Takashi Izutsu教養教育高度化機構 国際連携部門
特任准教授
東京大学医学系研究科博士課程修了(PhD)。国立精神保健研究所を経て2006年に国連人口基金へ。2009年より国連事務局精神保健・障害チーフとして精神的ウェルビーイングと障害をSDGsに加えるべく尽力。2015年より現職。ディズニー・ミュージカル『リトルマーメイド』『アラジン』の翻訳も担当。
「国連アカデミック・インパクト」への参加
国連アカデミック・インパクトは、国連と世界の高等教育機関を結ぶパートナーシップ。SDGsなどの国連の活動をめぐり、世界各国の高等教育機関同士の連携、教育機関と国連との連携を促すことを目的としています。東大は2016年2月に参加し、「国連憲章の原則を推進、実現する」「性別、人種、宗教、民族を問わず、全ての人に教育の機会を提供する」ほか、10の原則を支持し促進させる取り組みを始めています。
全学自由ゼミ「国連と文化」
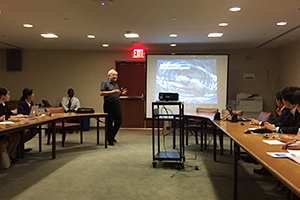 2016年8月に行われた、心の交流や文化・芸術を通して国連を捉えてもらうためのプログラム。レポート審査を経てニューヨークの国連本部を訪問した学生たちは、事務局、ユニセフ、国連開発計画(UNDP)、人道問題調整事務所などで働く国連職員から世界の現状と国連の活動の実際を学ぶ一方、現地の文化・芸術に触れる活動を展開。帰国後は国連への提言をまとめ、国連職員の皆さんに配布する予定です。
2016年8月に行われた、心の交流や文化・芸術を通して国連を捉えてもらうためのプログラム。レポート審査を経てニューヨークの国連本部を訪問した学生たちは、事務局、ユニセフ、国連開発計画(UNDP)、人道問題調整事務所などで働く国連職員から世界の現状と国連の活動の実際を学ぶ一方、現地の文化・芸術に触れる活動を展開。帰国後は国連への提言をまとめ、国連職員の皆さんに配布する予定です。
全学自由ゼミ「国連とインクルージョン」
2016年9月からのセメスターで行われた授業。SDGsの最大テーマ「誰一人取り残さない」(Leaving no one behind)を念頭に、マイノリティの中でも取り残されがちな精神障害・知的障害をめぐるインクルージョンについて、オムニバス講義とグループディスカッションを行いました。関連する国際機関のほか、日本HIV陽性者ネットワーク、精神障害者当事者会などからも講師をお迎えしました。
国連と東大を結ぶ学生団体UNiTe
「国連と文化」に参加した学生が国連本部で受けた刺激をもとに立ち上げた団体です。SDGsの広報を通じて国連と東大を結びつけることがモットー。2016年12月には駒場図書館で「東大×国連」と題した展示を行い、アフリカの蚊帳や、職員がかぶる帽子など、国連活動の現場で使われた各種現物が注目を集めました。



国際会議のシミュレーションを行う模擬国連駒場研究会
 国連の会議を模した活動を行うのが模擬国連。各参加者が一国の大使として政策を提案し議論するもので、60カ国以上で行われています。駒場を舞台にする模擬国連駒場研究会は2017年で10期目を迎えたサークル。2016年10月には国際連携部門と共に「国際機関合同アウトリーチ・ミッション講演会」を開催。9機関の人事担当を招き、国連で働くことの実際を学生が学べる貴重な機会を提供しました。
国連の会議を模した活動を行うのが模擬国連。各参加者が一国の大使として政策を提案し議論するもので、60カ国以上で行われています。駒場を舞台にする模擬国連駒場研究会は2017年で10期目を迎えたサークル。2016年10月には国際連携部門と共に「国際機関合同アウトリーチ・ミッション講演会」を開催。9機関の人事担当を招き、国連で働くことの実際を学生が学べる貴重な機会を提供しました。
国連は、6つの主要機関と、その下に位置する様々な機関、連携関係を持つ専門機関などから構成され、そこで働く職員も様々です。国連関連機関で働く約 3.2万人の専門職以上の職員のうち、日本人は790人で全体の2.5%(2013年現在・国連資料CEB/2014/HLCM/HR/21)。国別の拠出額は2位で拠出人数は7位です。出身大学別の数字は不明ですが、「ICUや上智大学と共に東大出身者が多い」(井筒先生談)とのこと。明石さんを筆頭に、これまで多くの東大出身者が国連を支えてきました。そしてこれからも。
※本記事は広報誌「淡青」34号の記事から抜粋して掲載しています。PDF版は淡青ページをご覧ください。







