研究コミュニケーションコンテスト3MTを開催 工学系研究科のマクシミリアン・ベルテットさんが優勝

開催日:2022年7月29日
博士課程の学生が3分以内で研究内容を説明することに挑む、国際的な研究コミュニケーションコンテスト「Three Minutes Thesis (3MT)」。参加者は、一枚のスライドだけを使って、自分の研究を専門家でない聴衆に向けて分かりやすく説明しなくてはなりません。
今年で4回目となる東京大学3MTは、7月29日にオンラインで開催されました。予選と準備を経て、16名のファイナリストが録画した動画のテーマは、砂漠の緑化から持続可能な食消費、そして都市遺産の管理やリモートワークプレイスのコミュニケーションまで、多岐にわたりました。

審査員を務めたのは、昨年優勝した新領域創成科学研究科のダイアン・バレンズエラ・グバタンガさん、神戸大学戦略企画室のユアン・マッカイ特命准教授、そして医科学研究所の石井健教授の3名です。
審査員は各自、ビデオを視聴し、その後オンライン会議を開き最終審査を行いました。優勝に輝いたのは、工学系研究科のマクシミリアン・ベルテットさんの "Sailing satellites, pushed by the air and the sun "(「帆走する衛星 空気と太陽に押されて」)と題したプレゼンテーションです。審査員のマッカイ特命准教授は、「彼のプレゼンテーションをとても楽しませてもらいました。非常に複雑なものをシンプルにすることに成功していました。マックスは彼の考えを凝縮し、それを視聴者が簡単に理解できるようにまとめていました。私たちが共感できるような彼ならではの味わいや、実例を交えながら、良いストーリーを作り上げました」と評価しました。
準優勝に選ばれたのは、理学系研究科のミカ・ハヤシさんのプレゼンテーション "Deciphering our DNA through the lens of AI" (「AIを通して私たちのDNAを解読する」)です。「ミカさんは、分かり易い例を挙げて、研究内容を明解に説明しました。ストーリーもよく練られたものでした」と審査員のグバタンガさんは話しました。
UTokyoアカウントを持つ学生や教職員は2週間にわたって、ピープルズチョイス賞に投票することができました。集計の結果、断トツで一位に選ばれたのは、工学系研究科のキュンジン・キムさんのプレゼンテーション "Estimating the response of damage concentrated floor without sensor" (「損傷が集中している床の応答をセンサーを使わずに推測する」)です。「問題を明確かつシンプルに表現することに優れていて、発表の仕方も非常にフレンドリーで魅力的でした」とマッカイ先生は述べました。
審査員は、今年の応募作品は選ぶのが難しかったと話し、プロフェッショナルでとても魅力的なプレゼンテーションを行ったすべての参加者に祝辞を述べました。「皆さん本当にうまく自分たちの研究を説明してくれました。皆さんの情熱も伝わってきました。このような能力があれば、将来はとても優秀な研究者になれると思います」とグバタンガさんは話しました。マッカイ先生は、「全てとても良いストーリーでした。問題点、プロセス、将来性、そして影響などをうまく表現していました。本当に見事でした」と述べました。
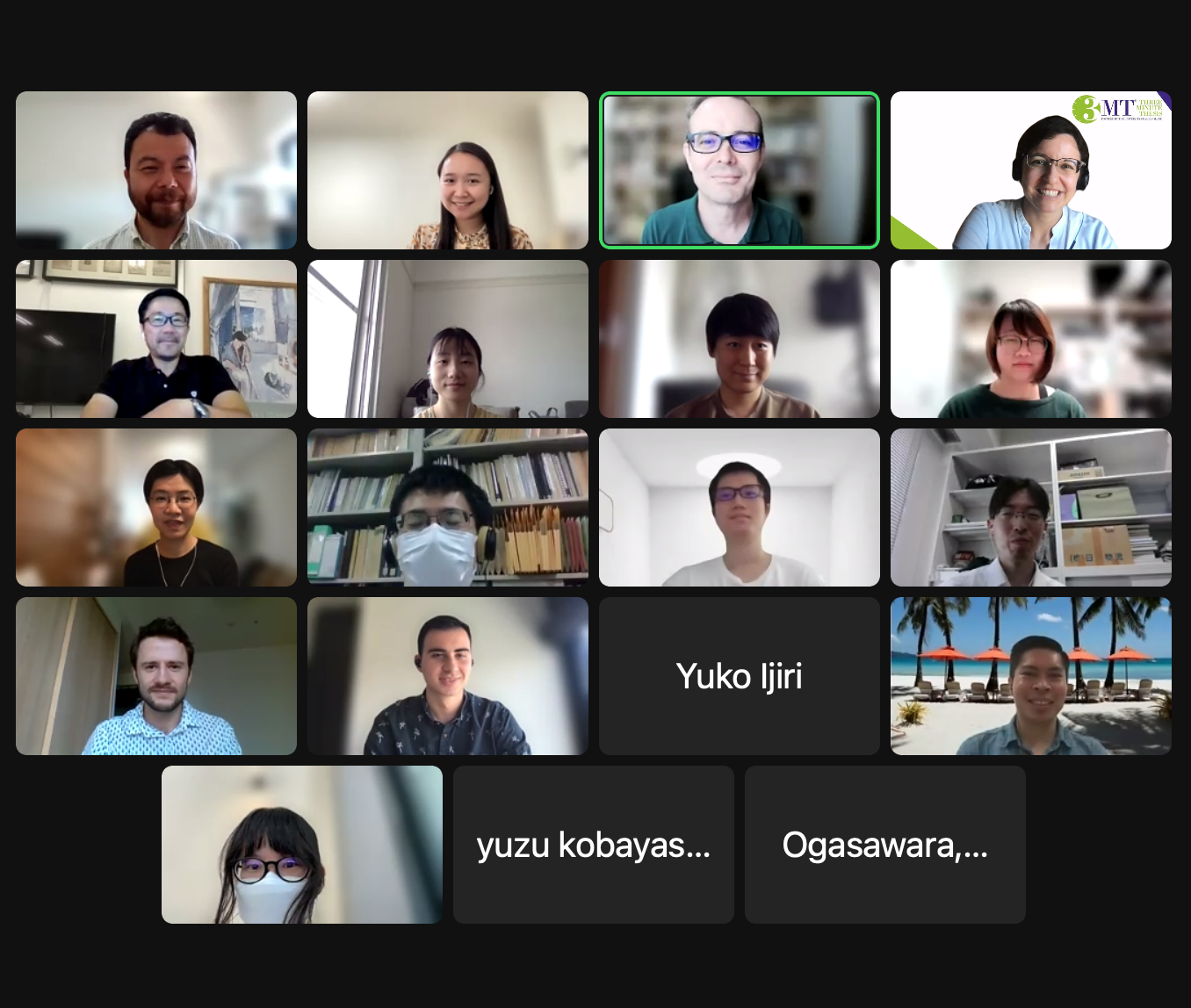
3MTは研究費を獲得するチャンスですが、それ以外のメリットもあります。マッカイ先生は、このコンテストに参加してサイエンスコミュニケーションを学ぶことは「誰かに何かを説明するときに、役立ちます。自分が何をしているのかを説明しようとするときに、自分の考えを理解する助けになります。自分の知識を共有し、他の人もそれを活用できるようにすることは大切ですが、それは研究者自身にとっても同様に重要です。また、観客を意識するということは、一生役に立つスキルといえます」と説明しました。
今年の東大の3MTは終了しましたが、優勝したマクシミリアン・ベルテットさんは、9月26日にオンラインで開催されるクイーンズランド大学主催の2022年アジア太平洋3MTセミファイナルに、東大代表として出場します。
受賞者たちのプレゼンテーション動画を含む、全ての最終応募作品は、東大のYouTubeチャンネルで視聴できます。
3MT®は、オーストラリアのクイーンズランド大学(UQ)が開発した学術研究コミュニケーションコンテストです。2008年に初めて開催され、現在では世界85カ国以上、900以上の大学で開催されています。
入賞者からのコメント
3MTに参加した感想は?今後の参加者にアドバイスは?入賞したマックス、ミカ、そしてキュンジンの3人に3MTについて話を聞きました。
マクシミリアン・ベルテット(優勝)

東大の3MTに参加して良かったことは?
私は、3MT参加準備のためのコミュニケーション・ワークショップの段階から参加しました。技術を学び、フレームワークを持つ良い機会でした。これまでパブリックスピーキングに関しては、経験したり、人づてに聞いたりして学んできました。今回のワークショップでは、正式な基礎を学び、それまで自分が考えていた概念を再構築し、点と点をつなげることができました。また、他の大学院の研究者と出会い、彼らが何に取り組んでいるのか知ることができたのも良かったです。目からウロコだったのは、研究内容を凝縮して専門家でない聴衆に伝える、ということに苦労しているのは自分だけではないということ。動画の作成はとても面白く、かつチャレンジングでした。最終的なアウトプットは、私が初めに考えていたものとは全く違うものになりました。
今回の経験を将来どのように生かしていこうと考えていますか?
二つあると思います。一つは参加するプロセス。そしてもう一つは、アウトプットです。先ほど話したことと似ていますが、プロセスについていえば、今回の経験を通して、サイエンスコミュニケーションやパブリックスピーキングに関して、自分の考えを構築するためのコンセプトを得ることができました。また会議やイベントを準備する際、そして友人と会話をするときに、彼らを疎外しないような話し方をするための方法を学びました。二つ目は、優勝し、3MTのコミュニティの一員になり、東大を代表する ―― 責任をもち、自分の研究の域を超えて考え、そして大学の国際化を促進するためにどう活用できるかを考える ―― ということを大変光栄に思います。また、自分自身の内気な性格を克服し、他の人にも試してみることを働きかける挑戦でもあります。受賞は終着点ではなく、むしろスタート地点です。
3MTへの参加を考えている学生へのアドバイスはありますか?
おそらく、準備万端だと思える時はこないということです。延期したり、何かしらの言い訳を見つけることはいつだってできます。来年ならとか、そんな時間はないとか。いつまでも延期し続けることもできます。なぜ待ち続けるのでしょうか。今やりましょう。自分を他人と比較して、他の人のほうがスキルがあるとか、自分は劣ってるなどと感じることはありますが、特にパブリックスピーキングの分野においては、個性が問われることが多いので、他人と比較する必要はありません。自分に自信をもってください。あなたの個性やあなただからこそ貢献できることがあります。挑戦してみてください。
ミカ・ハヤシ(準優勝)

東大の3MTに参加して良かったことは?
新しいことに挑戦するとてもよい機会でした。私はあまりそういうことをしないので。普段は大学に来て、研究室で仕事をするという毎日で、他の人とのやりとりといえば、研究室の人たちや共同研究者や、メールなどを通じて友人とつながるということがほとんどです。特に楽しかったのは、3MT参加準備のためのワークショップです。普段は研究室の新メンバーくらいしか新しい出会いがないので、学内の様々な人々と出会うことができたのはとても良かったです。
今回の経験を将来どのように生かしていこうと考えていますか?
プレゼンテーションスキルは確実に向上しました。特に、予備知識のない人に何かを説明しなければならないときのスキルが向上したと思います。私が行っている研究の骨子や基礎についての考えを深めていく助けになったと思います。そしてもちろん、学術のキャリアにおいても、プレゼンテーションを行うときに役に立つことでしょう。しかしそれだけでなく、私が考えていることや意見を友人に伝えるといった日常生活でも役に立つのではと思います。普段の会話もスムーズになるかもしれませんね。
今後参加するかもしれない学生へのアドバイスは?
少しでも興味があれば、参加すべきだと思います。時間的なコミットメントが必要で、実際長い時間と多大な努力が必要でした。しかし、もし何も受賞しなかったとしても、自分の研究やコミュニケーションスキルについて多くのことを学べます。また、他の人と知り合うとてもいい機会でもあります。とにかく、挑戦してみてください。
キュンジン・キム(ピープルズチョイス賞)
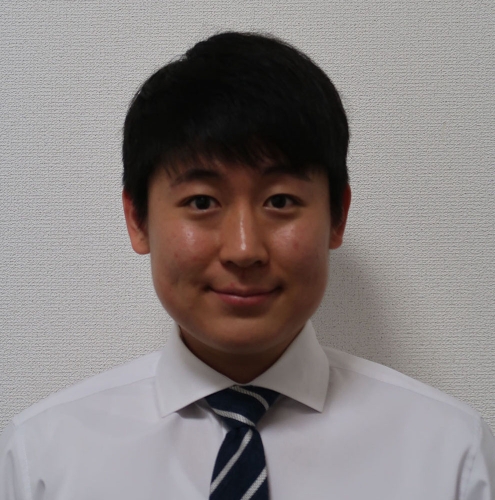
東大の3MTに参加して良かったことは?
準備するなかで一番良かったことは、自分の研究のコンセプトや重要な部分に気づくことができたということです。また、専門用語は使えないので、専門家ではない人たちのことをもっと理解しようと思うようになりました。3MTに向けて準備をすることで、言葉を慎重に選び、また自分がどのように何をやっているのかということを、より深く考えることができるようになりました。
今回の経験を将来どのように生かしていこうと考えていますか?
他のさまざまな経験に役立つと思います。というのも、(前述したように)専門家以外の人に説明することは、私と同じ分野の専門家に説明するよりもはるかに難しいからです。なので、このコンテストとプレゼンテーションを経験したことは、今後さまざまなプレゼンテーションを行う上で役に立つと思います。また、ジェスチャーなど今回学んだことは大変興味深く、プレゼンテーションにのめり込むことができました。3MTに挑戦したことは、私の人生で最も大きな経験の一つだったと思います。自分が研究する科学の特定分野が、どのように世界の人々の役に立つのかといったことについて考えることは、本当に楽しかったです。
今後参加するかもしれない学生へのアドバイスは?
まず応募することが大切だと思います。一次選考を通過できてもできなくても、とにかく挑戦してみてください。
*この記事は、2022年8月10日にUTokyo FOCUS 英語版に掲載されたものです。
UTokyo 3MT 2022 contestants and their presentations






