石井健教授 東京大学基金研究者インタビュー 次のパンデミックで100日以内に安全な国産ワクチンを「デザイン」する若手人材を育成したい

次のパンデミックで100日以内に安全な国産ワクチンを「デザイン」する若手人材を育成したい
石井 健 教授
東京大学・医科学研究所・ワクチン科学分野・教授
同研究所・国際ワクチンデザインセンター・センター長
平成5年横浜市立大学医学部卒業。3年半の臨床経験を経て米国FDA・CBERにて7年間ワクチンの基礎研究、臨床試験審査を務める。平成15年帰国しJST・ERATO審良自然免疫プロジェクトのグループリーダー、大阪大学・微生物病研究所・准教授を経て、平成22年より平成30年まで医薬基盤健康栄養研究所アジュバント開発プロジェクトリーダー、ワクチンアジュバント研究センター長、平成22年より現在まで大阪大学・免疫学フロンテイア研究センター教授。平成27年―29年まで日本医療研究開発機構(AMED)に戦略推進部長として出向、平成29-31年科学技術顧問を務める。平成31年より現職
私が所属している東京大学医科学研究所は、白金キャンパス(港区白金台)に本拠を構えています。医科学研究所の母体は、“感染症の撲滅”に心血を注いだ微生物学者・北里柴三郎博士が明治25年に設立した「大日本私立衛生会附属伝染病研究所」です。医科学研究所は国立大学附置研究所として唯一の附属病院を有しており、世界トップレベルの研究成果に基づく臨床試験、先端医療を進めています。さらには、医学・生物学系の「国際共同利用・共同研究拠点」として国内で唯一の認定を受け、世界的な枠組みでの基礎・臨床研究を加速させています。今から10年ほど前、医科学研究所の組織内に設置されたのが「国際粘膜ワクチン開発研究センター」で、私は2019年に東京大学からお声かけをいただき、同センター長に就任。そして、同センターのリニュアルを進めていた矢先、新型コロナウイルスによる世界的なパンデミックが発生しました。
ご存じのとおり、アメリカ、イギリス、中国、ロシアの4カ国が歴史上例を見ないスピードで新型コロナのワクチン開発に成功し、我が国はその輸入に頼るという残念な構図となったわけです。結果、国内では「なぜ日本にはできなかったのか」といった不満・不安の声が高まりました。また一方、新型コロナウイルスのパンデミックは、人類がいまだに感染症を克服できていないという事実とワクチンの研究開発の重要性を明らかにしました。私たちはそれらへの反省を込めて、病原体を調べ、免疫学の基礎研究を進めるだけではなく、ポストコロナ時代のワクチン開発はいかにあるべきかをしっかりと考え、障壁となっている諸問題の解決に取り組むべく、本年2022年4月1日、「国際ワクチンデザイン・センター」として「国際粘膜ワクチン開発研究センター」の名称および組織の変更を行い、新たな活動を開始しました。
そもそも日本がワクチン開発をうまく進められなかった理由は、研究力や技術力が他国に比して劣っていたわけではありません。たとえ話になりますが、今やワクチン開発は、多様かつ多数の最先端技術を集積させた新型ロケットをつくるような取り組みです。それと同じように、ワクチンをつくるために必要となるさまざまな情報、多様な分野の専門人材、それらを集め、まとめ、組み合わせ、デザインし、世に送り出すための仕組み・ネットワークが十分に確立できていなかったことが原因だと考えます。「国際ワクチンデザイン・センター」は、それら諸問題を克服するための拠点として、また未来の“ワクチンデザイナー”人材を育成していく孵化装置としての活動を推進していきます。

もう一つは、時間をかけて順番に行うべき試験を、“平行”かつ“同時”に実施したこと。ワクチンでもほかの薬剤でも、一番大事なポイントは絶対に安全であることです。今回は、臨床試験、生産体制の整備、配送、保管条件の確定など、安全なワクチン開発に必須とされる試験のすべてを“同時・平行”で進めていった。いっさいのスキップをせず、です。そして、それができたのは先述した4カ国だけでした。これら各国の政府は、新型コロナ以前から、たとえば生物兵器によるバイオテロによって自国にパンデミックが起こるような事態を避けるため、ワクチンの開発が国防上極めて重要になると考え、膨大な予算投下も含めて入念な準備をしていました。結果、4カ国が今回のワクチンの開発に成功し、ワクチンの販売という外交においても非常に強い立場をとることができたのです。
はからずも新型コロナウイルスのパンデミックは、ワクチンの研究開発と供給が国民の健康を守るだけではなく、国防や経済にもかかわる重要な国家戦略であることを再認識させてくれました。2021年6月に開催された先進国首脳会議(G7)に参加した各国は、次のパンデミックでは“100日以内”にワクチンを開発するという目標に合意。当時の菅義偉総理もサインしています。世界の研究者たちは、この目標に対して「非常に難しい」と口を揃えます。しかし、「この目標は、世界の研究者が協働して目指すべき“北極星”」であるとも。
日本でワクチンの研究開発に携わる私たちも、ここに歩調を合わねばなりません。「国際ワクチンデザイン・センター」では、抗体医薬を代表とするタンパク製剤研究の第一人者である津本浩平教授、マラリア免疫学で世界に認知されているCevayir Coban(ジェヴァイア チョバン)教授、ウイルス学で活躍している佐藤佳教授に加え、メタゲノムを駆使したワクチン免疫の植松智特任教授、パスツール研究所の感染疫学のAnavaj Sakuntabhai客員教授、代謝免疫学の反町典子客員教授らが参画し、ワクチンデザイナー育成の準備が整ってきました。それに加え、ワクチン開発のための研究開発拠点群「東京フラッグシップキャンパス(東京大学新世代感染症センター)」を率いる河岡義裕先生、基礎免疫学の世界的に著名な高柳宏先生(東京大学)、人工知能AI研究の第一人者といわれる松尾豊先生(東京大学)、ウェアラブルセンシング技術で画期的なデバイスを開発している染谷隆夫先生(東京大学)などなど、学際を越えたトップレベルの研究者、最先端のテクノロジーとネットワークしながら、自国のためだけではなく、世界中から求められ、認められる日本らしい“安全・安心”なワクチン開発の“最適解”を追求していきます。

私は横浜市立大学医学部を卒業後、臨床医になりました。3年半ほど、大学病院や市立病院などに勤務しましたが、ほとんどが救命救急センター(ER)や、集中治療室(ICU)での仕事です。当時は、1日36時間働いているような感覚でしたね(笑)。患者さんの心臓や呼吸器などの機能を回復させ、命を救うことが使命なわけですが、残念ながら亡くなってしまう方々の多くは感染症が原因でした。その仕事を続けているうちに、より多くの命を救うためには、感染症や免疫の研究をすべきなのでは?と思うようになり、大学院に戻ることにしたのです。
そして、大学院の制度を活用して、私はアメリカ合衆国の政府機関FDA(アメリカ食品医薬品局=Food and Drug Administration)に留学する道を選択。マラリアに対するDNAワクチンの研究からスタートし、2年後にはFDAの職員となって、ワクチンの審査業務に携わることになりました。以降5年間ほど、膨大な提出資料と格闘しながらワクチンの安全性をチェックする審査業務に従事したのですが、当時はこの仕事にまったく満足していませんでした。その後、やはり感染症や免疫に関する研究をしたいという思いが募り、日本に帰国して免疫学の第一人者である審良静男先生(大阪大学)に師事しました。振り返ると20年以上ワクチンの研究開発にかかわってきましたが、FDA勤務時代の審査業務によって、英語能力の向上と“ワクチンの安全性”を見極める目を養えたことが、今の私の大きな武器になっています。
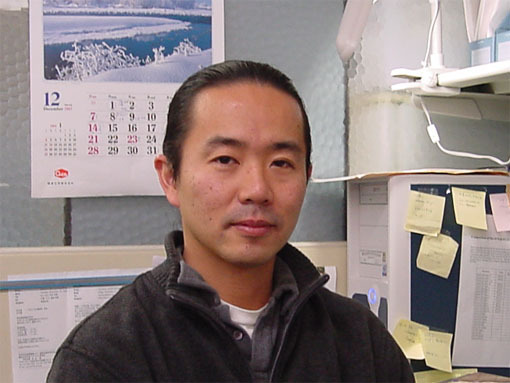
阪大時代の石井先生
私の専門は、ワクチンを構成する3つの要素のうちの一つ「アジュヴァント」(アジュバントとも)の研究です。3要素について、わかりやすく説明します。[1]生体に免疫反応を起こさせる「抗原」、[2]体内の免疫応答が起こる場所へとコントロールする「デリバリーシステム」、[3]ワクチンの有効成分の作用を補助、増強する「アジュヴァント」です。私は“ワクチンの調味料”と呼んでいますが、ワクチンの安全性を大きく左右するのが「アジュヴァント」です。
ワクチンは高い安全性が求められる予防的医薬品になります。自動車にたとえれば、利用者の命を守るシートベルト、エアバッグのようなものでしょうか。事故にあってから後悔しても遅いのと同様、ワクチンも感染して重症化してから後悔しても遅い、という意味でよく似た意味合いでたとえさせてもらっています。余談になりますが、ある大手自動車メーカーの安全管理担当の方とお話をした際、膨大な部品・要素で構成される自動車とワクチンの一番大切なポイントは安全性であるという点、そこに必要なのは想定しないリスクを想定できる“想像力”であるという点で合意し、お互い大いに盛り上がりました。
さて、先に説明したワクチンの3要素にはそれぞれ多様なパターンがあるため、病原体の種類によってその組み合わせは天文学的な数にのぼります。私たちは、これら3要素をモジュール化することで、効率的にワクチンを設計する技術の開発を目指します。ただ、病原体に対するワクチンの有効性は、個々人によって異なる可能性もあります。感染患者やワクチン被験者のサンプル情報をデータベース化し、プロファイリング技術、AI解析技術などを駆使しながら、一人ひとりに合ったワクチンをデザインすることが究極の目標です。
(略:全文は、「東京大学基金」ウェブサイトの研究者インタビューをご覧ください。)
取材・文:菊池 徳行(株式会ハイキックス)






