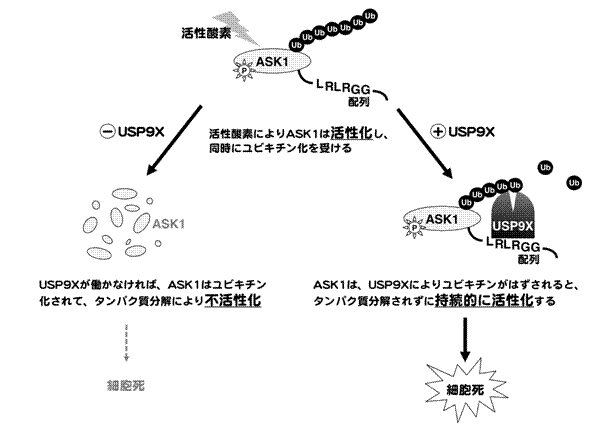活性酸素が引き起こす細胞死を促進する新たな仕組みを解明-脱ユビキチン化によるリン酸化酵素の活性化持続時間の制御機構-研究成果

活性酸素が引き起こす細胞死を促進する新たな仕組みを解明-脱ユビキチン化によるリン酸化酵素の活性化持続時間の制御機構- |
活性酸素が引き起こす細胞死を促進する新たな仕組みを解明
-脱ユビキチン化によるリン酸化酵素の活性化持続時間の制御機構-
概 要:
活性酸素は、細胞内の様々なタンパク質の中で特にASK1リン酸化酵素を活性化することで、様々な疾患の原因である細胞死を誘導します。今回、ASK1の活性化時間を持続させ、活性酸素による細胞死を促進する新たなタンパク質として、USP9Xという脱ユビキチン化酵素を発見しました。
内 容:
東京大学大学院薬学系研究科の一條秀憲教授らの研究グループは、活性酸素によって引き起こされる細胞死が、より強く誘導される細胞内の情報伝達の仕組みを解明しました。細胞内の情報伝達経路に関わる様々なタンパク質の中で、活性酸素はASK1リン酸化酵素を活性化して細胞死を誘導することを、当グループは以前より見出していました。そのASK1と活性酸素依存的に結合する分子を探索した結果、USP9Xという脱ユビキチン化酵素を発見しました。
タンパク質の機能は、その分子を構成するアミノ酸がユビキチン化などの修飾を受けることで、様々に調節されます。ASK1は活性酸素刺激によって一旦活性化した後、ユビキチン化され、タンパク質分解酵素複合体であるプロテアソーム依存的に分解されることで、不活性化することが分かりました。このUSP9Xは、活性酸素刺激によってユビキチン化されたASK1から、ユビキチンを切り出し、ASK1をプロテアソームによる分解から回避させ、ASK1の活性化時間を持続させる機能を持っており、このUSP9Xを欠損した細胞では、活性酸素による細胞死が起こりにくくなることが明らかとなりました。これらの発見は、心筋梗塞や脳梗塞といった虚血性の疾患など、活性酸素が誘導する細胞死によって引き起こされる様々な疾患の原因の解明や、USP9X阻害剤などを用いた治療法の開発に繋がるものと期待されます。
さらに、USP9XとASK1との結合には、ASK1の分子内に存在する特徴的なアミノ酸配列(LRLRGG配列)が必要で、この配列はUSP9Xの基質であるユビキチンの分子内に存在するものと同じでした。ユビキチンの分子内の特別なアミノ酸配列が、ユビキチン以外の情報伝達分子のタンパク質分解機構に使われることを示したのは、これが初めてであり、タンパク質分解による細胞内情報伝達機構の調節の仕組みやこれに関連する様々な疾患の病因の解明にも、今後大きく役立つと思われます。
発表雑誌:
米国科学雑誌「Molecular Cell(モレキュラー セル)」
(出版日:2009年12月11日)
“Ubiquitin-like Sequence in ASK1 Plays Critical Roles in the Recognition and Stabilization by USP9X and Oxidative Stress-Induced Cell Death”
Hiroaki Nagai, Takuya Noguchi, Kengo Homma, Kazumi Katagiri, Kohsuke Takeda, Atsushi Matsuzawa, and Hidenori Ichijo
注意事項:
解禁日時: 日本時間 2009年12月11日午前2時(アメリカ東部時間 2009年12月10日正午)
問い合わせ先:
一條秀憲 教授
〒113-0033 文京区本郷7-3-1
東京大学 大学院薬学系研究科 生命薬学専攻 細胞情報学教室
用語解説:
ASK1(Apoptosis signal-regulating kinase 1):活性酸素、TNFなどの炎症性サイトカイン、細菌毒素、カルシウム、小胞体ストレスなどの様々なストレス刺激によって活性化されるストレス応答性リン酸化酵素である。ASK1の活性化によって、細胞死や細胞分化、炎症・免疫反応などが誘導される。
USP9X(Ubiquitin specific peptidase 9, X-linked):脱ユビキチン化酵素の一つで、鎖状のポリユビキチンから共有結合を切断してユビキチンを切り出す働きを持つタンパク質分解酵素である。細胞分裂や小胞膜輸送などの様々な細胞機能への関与が報告されているが、ストレス刺激に対する応答や細胞内情報伝達における生理機能はこれまで良く分かっていなかった。
ユビキチン: 76個のアミノ酸からなる比較的小さなタンパク質で、他のタンパク質の修飾に用いられ、タンパク質分解やDNA修復、小胞膜輸送、シグナル伝達など多様な生理機能に関わる。特にユビキチンが共有結合によって鎖状に連なったポリユビキチンは、タンパク質分解酵素複合体であるプロテアソームによって認識され、分解されるべきタンパク質の目印となることが分かっている。
参考図: