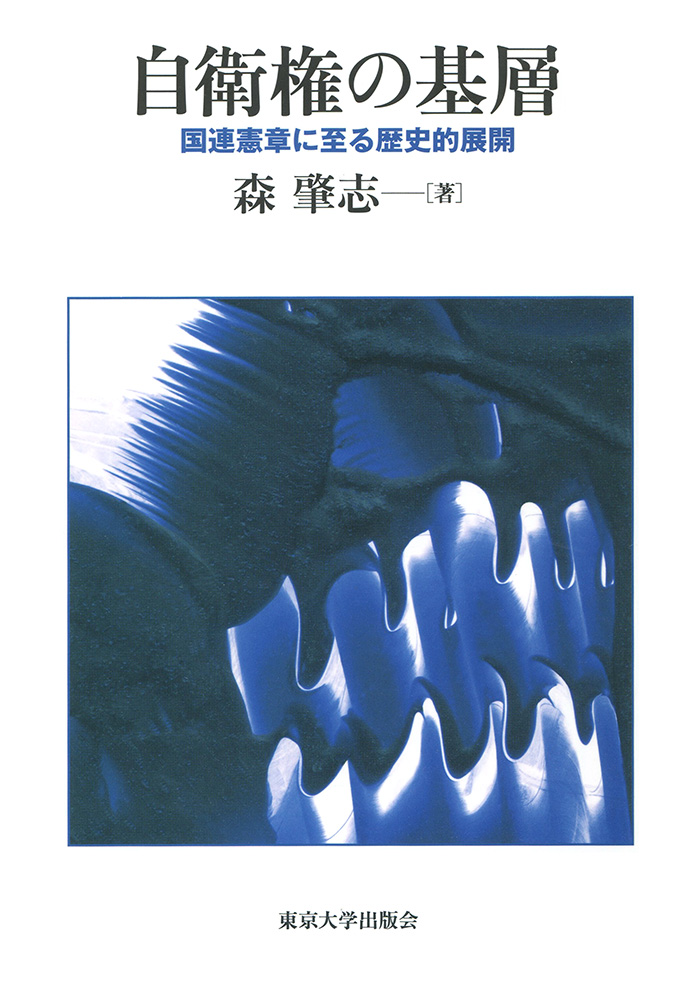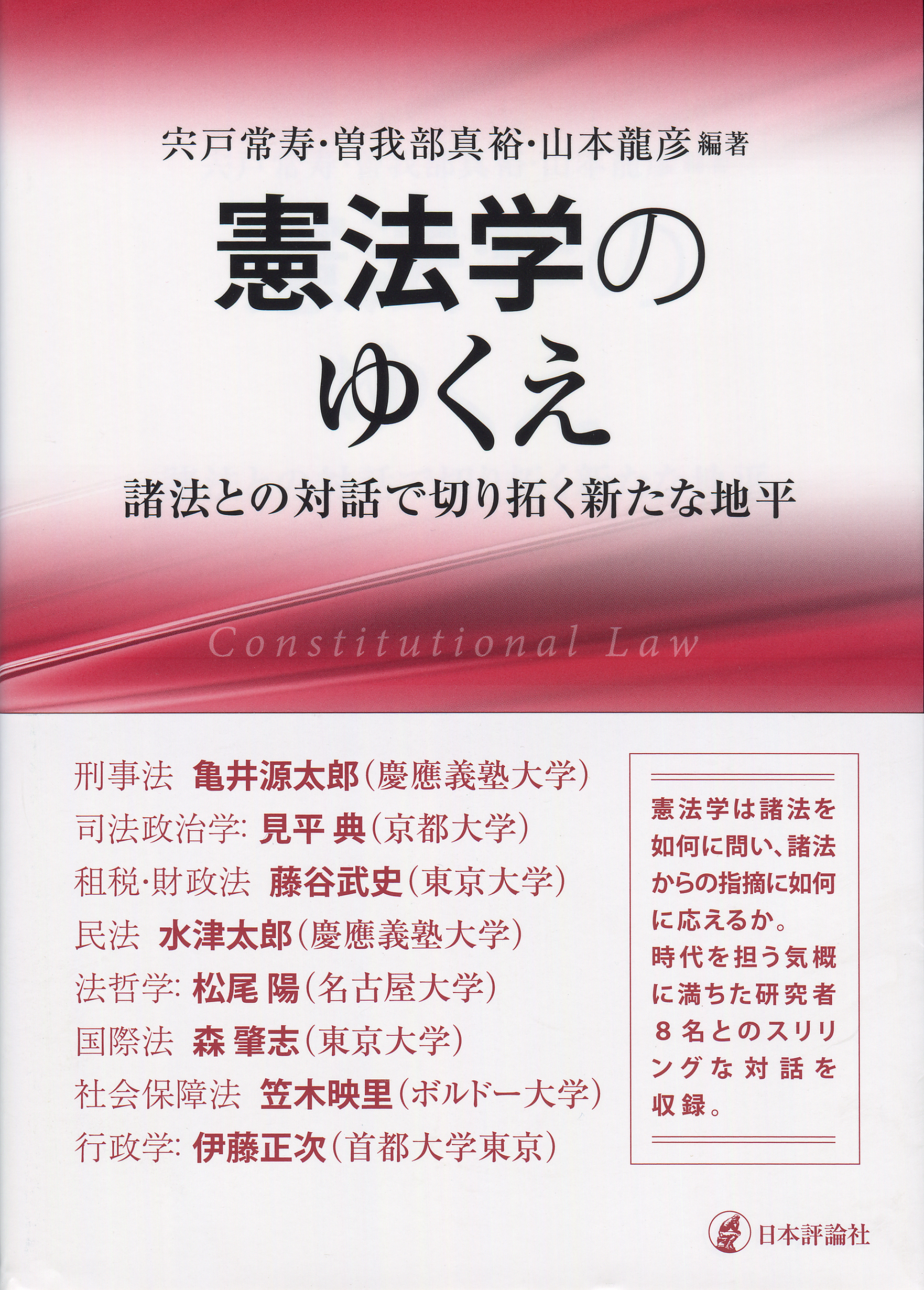本書は、現代国際法上の自衛権に関する議論の「混乱」を解きほぐし、その現在を論ずる基盤を得るために、19世紀中葉から国際連合憲章制定までの、自衛権概念の歴史的展開を明らかにしようとしたものです。
*
国際法上「個別的および集団的自衛権 (国際連合憲章第51条)」が何を意味するか、というのは、国際法における武力行使の法的規制に関するもっとも重要な問題の一つとされるが、いまだ十分解明されているわけではない。そもそも自衛権とはなにか、について、混乱が見られるのである。
本研究の結果、国連憲章制定以前の自衛権およびその国連憲章への受容については、以下のように理解できることが明らかになった。
まず第一に、こうした自衛権には、第1次世界大戦以前を起源とするものと、戦間期を起源とするものとがあり、前者は、私人による自国に対する侵害があり、領域国あるいは旗国による抑止が期待できない場合に、相手国領域に侵入しあるいは公海上で、自らに対する侵害を排除すること、すなわち領域侵害あるいは公海自由の侵害を正当化する根拠として理解され、後者は、国際連盟規約以降の戦争違法化の進展を背景として、侵略戦争あるいは侵略行為の禁止に対する例外として、それらに対する抵抗としての防衛戦争あるいは武力行使を正当化する根拠として理解されることが明らかとなった。前者を治安措置型自衛権、後者を防衛戦争型自衛権と名付けたが、両者は、いつを起源とするかという、時期についてだけではなく、正当化対象および問題となる文脈をまったく異にしている。さらに、両者は戦間期において並存していたのである。
こうした自衛権概念の中で、国連憲章制定過程において明確に意識されていたのは、防衛戦争型自衛権であった。一方、こうした両者の区別は、国連憲章の起草過程において、不明確となったが、治安措置型自衛権の許容性が米国国務省内の検討において認められていたことは注目すべきである。
第二に、一般に国連憲章制定時にはじめて登場した概念とされる集団的自衛権について、その先駆と言うべきものが、戦間期においてすでに生み出されていたことが明らかとなった。これは、防衛戦争型自衛権に包摂されるものだが、そこで注目されるのは、個別的自衛権と集団的自衛権の先駆とでは発動条件が異なり、後者の方が限定されていたことである。これは、戦間期において個別的自衛権の発動条件と位置づけられた侵略概念が不明確であることに鑑み、その集団性によって戦争を拡大する危険性の高い集団的自衛権の行使について、一定の制限を課そうとするものであった。
集団的自衛権に対するこうした位置づけは、国連憲章の制定過程においても変化していない。集団的自衛権と個別的自衛権との発動要件の区別は、国連憲章において明示的には規定されていないが、その準備作業においてその区別を見出すことができる。憲章の起草者たちがこの点について意図していたのは、集団的自衛権の発動要件を制限することであり、個別的自衛権の行使を武力攻撃の発生の場合のみに限定することではなかったと考えられるのである。
このように、国連憲章制定以前における自衛権概念は、起源を異にし、また機能および発動要件を異にする、3つの概念の集合体として成り立っており、それはあたかも地層をなしているように理解できる。こうした概念は、国連憲章起草過程の中にも見出されるのであり、憲章規定の下部に存在し、基層をなしているのである。
*
自衛権の行使に関しては、しばしば立場の違いが前面に出て議論自体が成り立たなくなる傾向があります。そうした違いを超えて議論するための共通の基盤を探ることが必要なのであり、本書がそのための一助となれば幸いです。
(紹介文執筆者: 法学政治学研究科・法学部 教授 森 肇志 / 2017)
本の目次
第1部 伝統的議論の呪縛と自衛権をめぐる混乱
第1章 伝統的議論枠組
第2章 自衛権をめぐる「混乱」の深み
第2部 2つの自衛権概念
第3章 第一次世界大戦以前の自衛権概念
第4章 戦間期に確立した自衛権概念
第3部 国際連合憲章制定時点における自衛権概念
第5章 2つの自衛権概念の関係
第6章 国際連合憲章起草過程における自衛権
結論
関連情報
『Origins of the Right of Self-Defence in International Law: From the Caroline Incident to the United Nations Charter』がBrill社より発売 (2018年2月12日)
https://brill.com/abstract/title/35792?rskey=JvNXc9&result=1
受賞:
平成21年11月 第42回安達峰一郎記念賞 (安達峰一郎記念財団)
http://m-adachi.or.jp/scholarship01.html
著者インタビュー:
東大大学院教授・森肇志さん 時代の正体〈81〉国民に委ねられた選択 (神奈川県新聞『カナロコ』 2015年4月12日)
https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-58476.html
著者関連記事:
新安保法制と国際法上の集団的自衛権 (『国際問題』No.648 2016年1・2月)
https://www2.jiia.or.jp/kokusaimondai_archive/2010/2016-01_002.pdf?noprint
(集団的自衛権を考える(中)) 適切な政治判断 課題に 森肇志 東京大学教授 (『日本経済新聞』 2014年5月22日)
https://www.nikkei.com/article/DGKDZO71552360R20C14A5KE8000/
書評:
浅田正彦 評 (『Japanese Yearbook of International Law』Vol. 54 2011年)
http://www.ilajapan.org/jyil/components/archive/vol54/tableofcases_JYIL54.pdf
川岸伸 評 (『国際安全保障』37巻4号p.112-116 2010年)
https://doi.org/10.57292/kokusaianzenhosho.37.4_112
春名展生 評 (『史學雜誌』119巻4号p.523-528 2010年)
https://doi.org/10.24471/shigaku.119.4_523
松田竹男 評 (『国際法外交雑誌』第109巻1号 2010年5月)
http://www.jsil.jp/journal_page/jrnl/109.pdf



 書籍検索
書籍検索