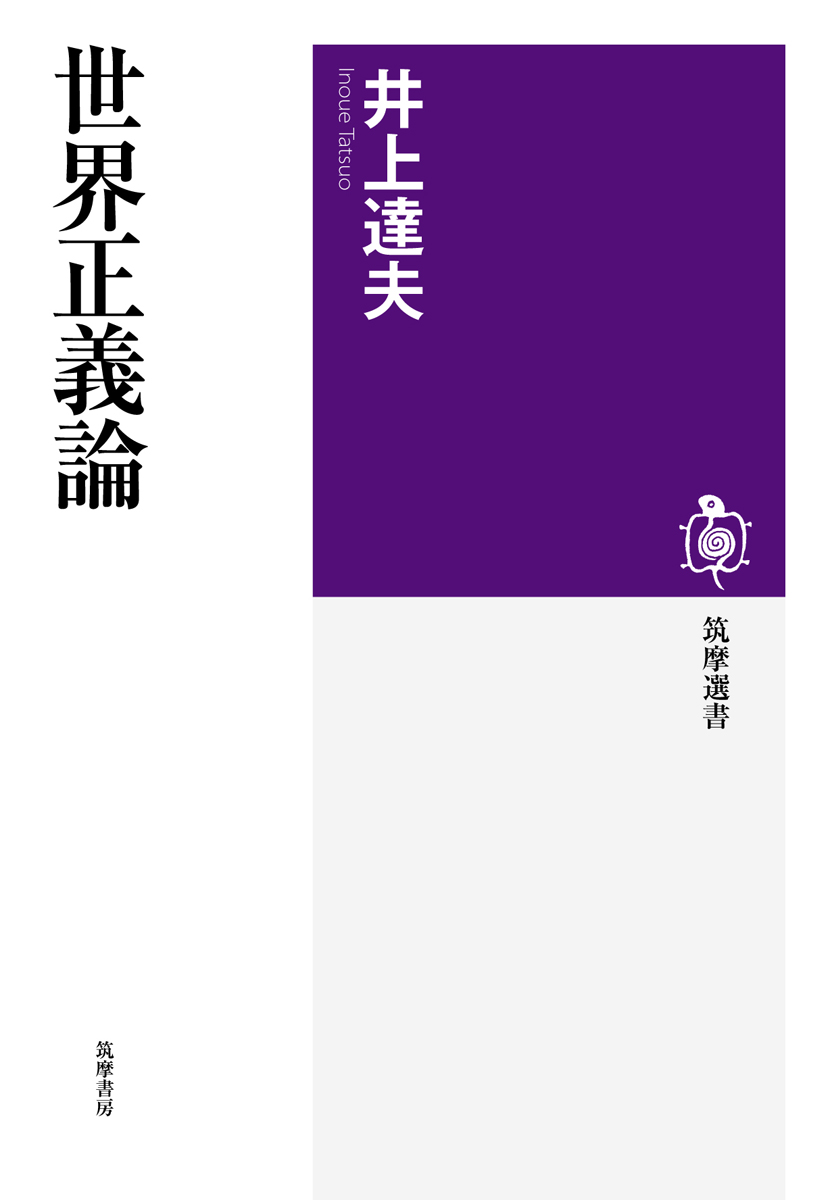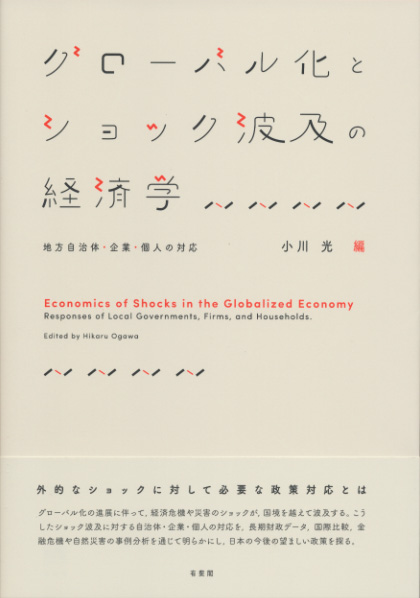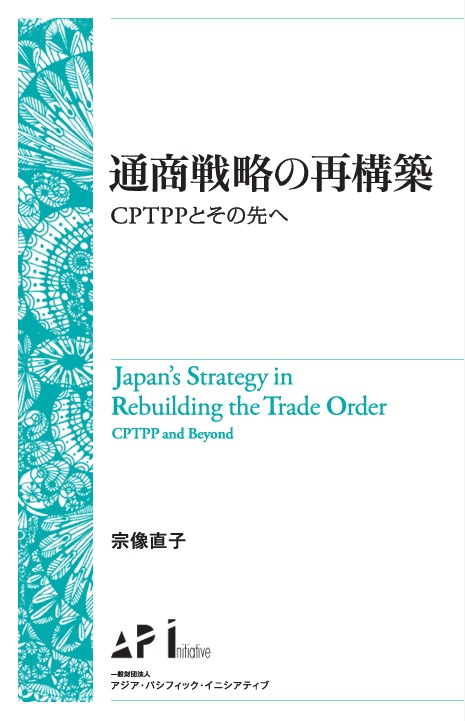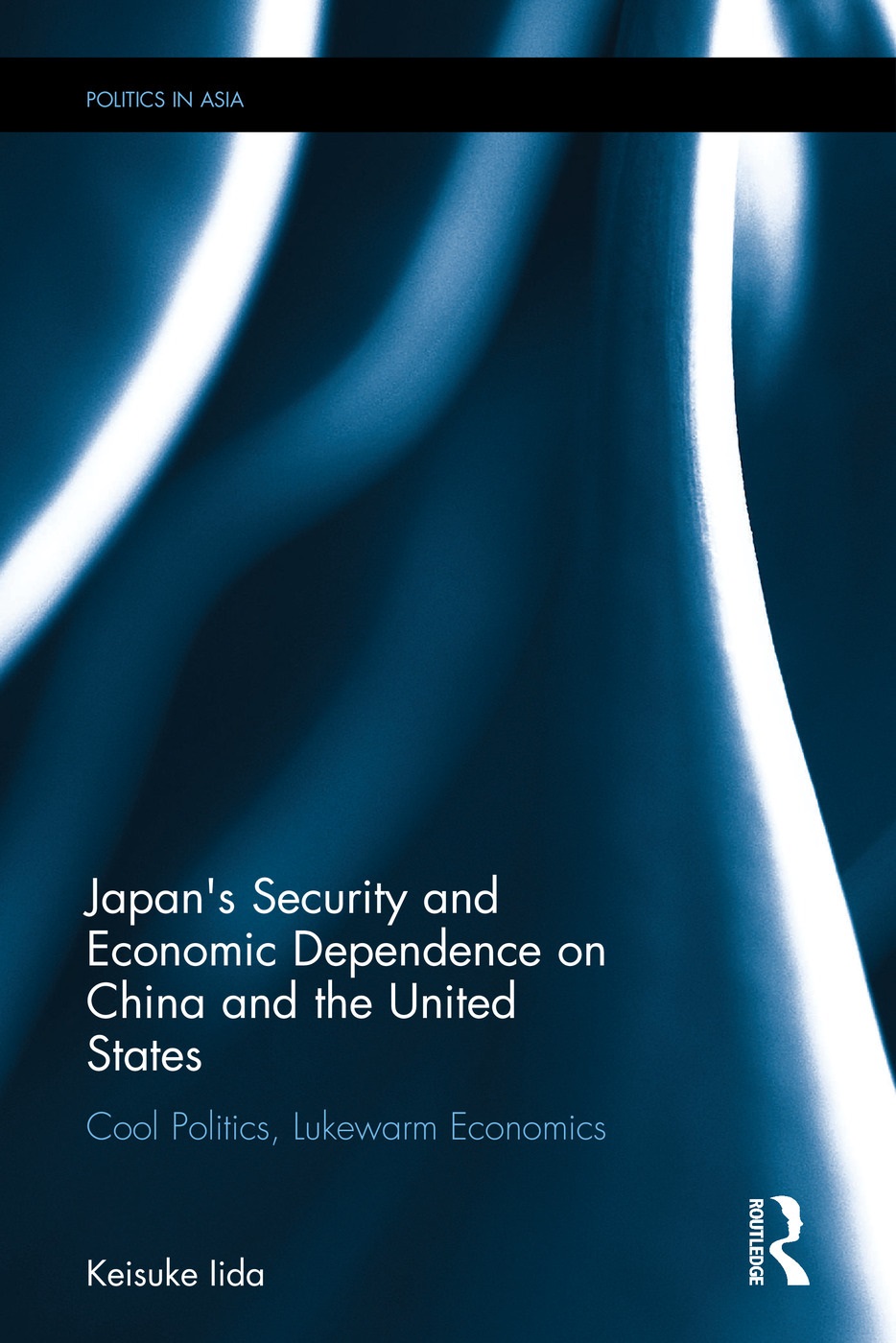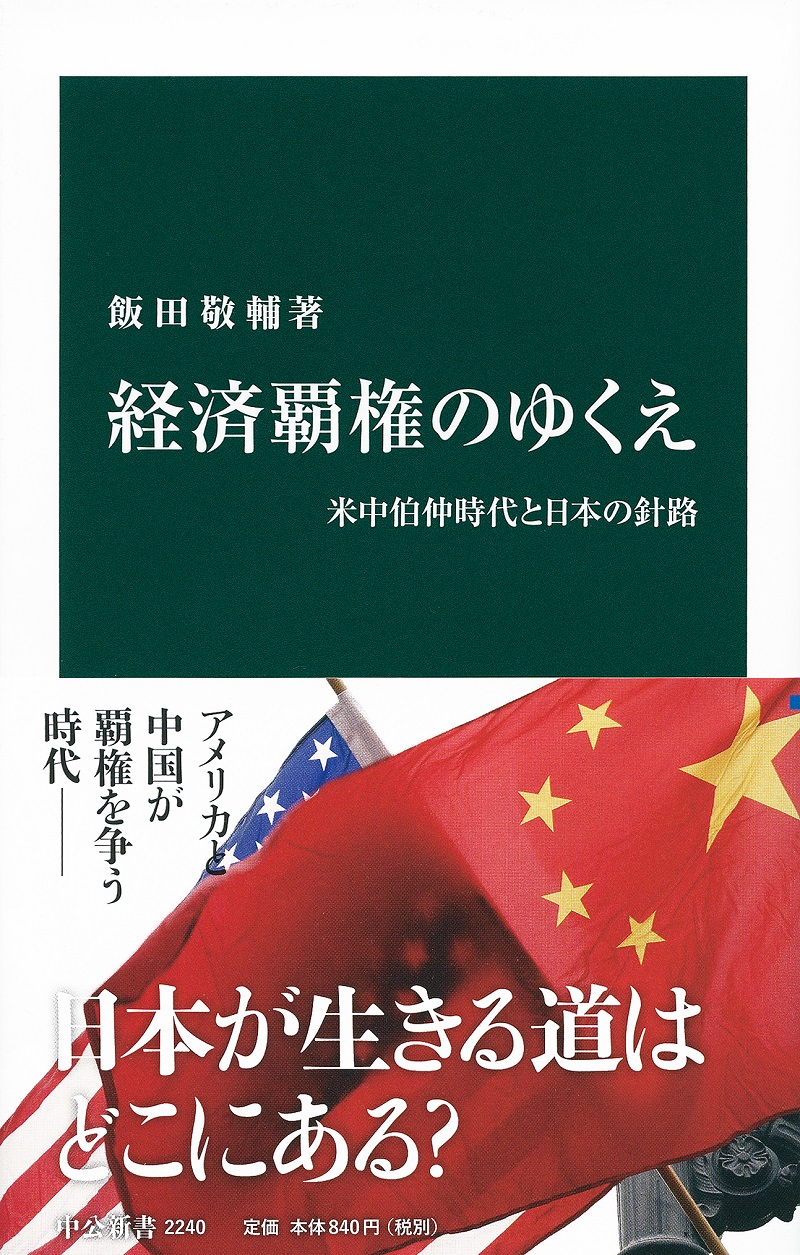
書籍名
経済覇権のゆくえ 米中伯仲時代と日本の針路
判型など
288ページ、新書判
言語
日本語
発行年月日
2013年11月25日
ISBN コード
978-4-12-102240-0
出版社
中央公論新社
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
本書は「覇権安定論」といわれる国際政治経済理論を、リーマンショック (2008年) 以降の展開を中心に再検討した論考である。もともとは本学法学部のホームカミングデーで講演した内容の要約を法学部のニュースレターに掲載したところ、これがある編集者の目にとまり、新書というある程度まとまった形で公刊された。
覇権安定論とは一言でいえば、覇権 (圧倒的に強大な国の経済力) が凋落すると国際経済秩序が不安定化するというもので、もっとわかりやすく言えば、米国経済が衰退すれば、いずれ世界大恐慌のような混乱が再来することを予測する理論である。これまでに幾多の論文や書籍が書かれ、学界では一定のコンセンサスがあると思っていたが、執筆してみると、意外と知られていないことが多いことに気付かされた。本書の結論としては、米国経済の長期的凋落は本物であること、その影響としては、国際貿易秩序がいよいよ二国間あるいは地域的な協定に傾きつつあること、金融では金融・通貨危機の頻度が上がっていること、しかし銀行監督の分野では (理論に反して) 規制が強化されていること、などであった。また理論の予測する、既存の経済秩序に対する新興国の挑戦としては、いまだBRICS諸国による軽微なものにとどまっていることを明らかにした。
理論書としては上記の内容だけで十分なのであるが、やはり世間の関心はもっぱら中国の台頭にあり、この点についても触れざるを得なかった。リーマンショックの直後、米国やその他の先進国の経済が停滞する中で、中国だけは順調な経済成長を遂げたことから、いずれ米国経済規模を中国が追い抜くのではないかという予測がなされた。本書でも、中国が順調に成長を続ければ2030年ごろには追い付いても不思議でないというような予測めいたことを書いたが、昨今の中国経済の減速を考えると、これはもっと遅れる気配である。社会科学では予測はいかに難しいかがわかる。
さて、本書の中に書かれていることで、すでに再考を迫られている点がある。覇権安定論の予測のなかで有名なものの一つに、覇権が衰退すると世界経済が閉鎖的な方向に向かうという説がある。本書はいろいろなデータを検討した上で、目下のところそのような兆候は見受けられないと結論付けた。しかし、2016年11月の米国大統領選挙では保護主義・排外主義を唱えてきたトランプ候補が当選した。同候補が選挙期間中に唱えていたことがどの程度実行に移されるのか、本稿執筆時点では明らかではないが、公約の半分が実行されただけでも、米国経済はかなり閉鎖的な方向に向かうことは間違いない。覇権安定論が予測していたことはあながち間違ってはいなかったことになる。この辺も社会科学理論の検証の難しさを示しているといえよう。
(紹介文執筆者: 法学政治学研究科・法学部 教授 飯田 敬輔 / 2016)
本の目次
第1章 覇権衰退は混乱をもたらすか
第2章 戦後国際経済秩序の誕生
第3章 通商体制の変遷
第4章 通貨・金融体制の変遷
第5章 世界金融・経済危機
第6章 中国の台頭と「共同覇権」
第7章 米中は逆転するのか
関連情報
Seeking to unravel the unknowns facing the world today (東京大学公共政策大学院ホームページ 2020年7月)
https://www.pp.u-tokyo.ac.jp/grasppers-voice/prof-keisuke-iida/
書評:
田所昌幸 (国際大学国際関係学研究科 特任教授) 評「覇権安全論は有効か?」 (『レヴァイアサン』56号、149-151頁 2015年4月15日)
https://www.bokutaku.net/leviathan/leviathan_56.html
岡本全勝 評「政治の役割:国際経済秩序」 (岡本全勝ホームページ 2013年11月30日)
https://zenshow.net/2013/11/



 書籍検索
書籍検索


 eBook
eBook