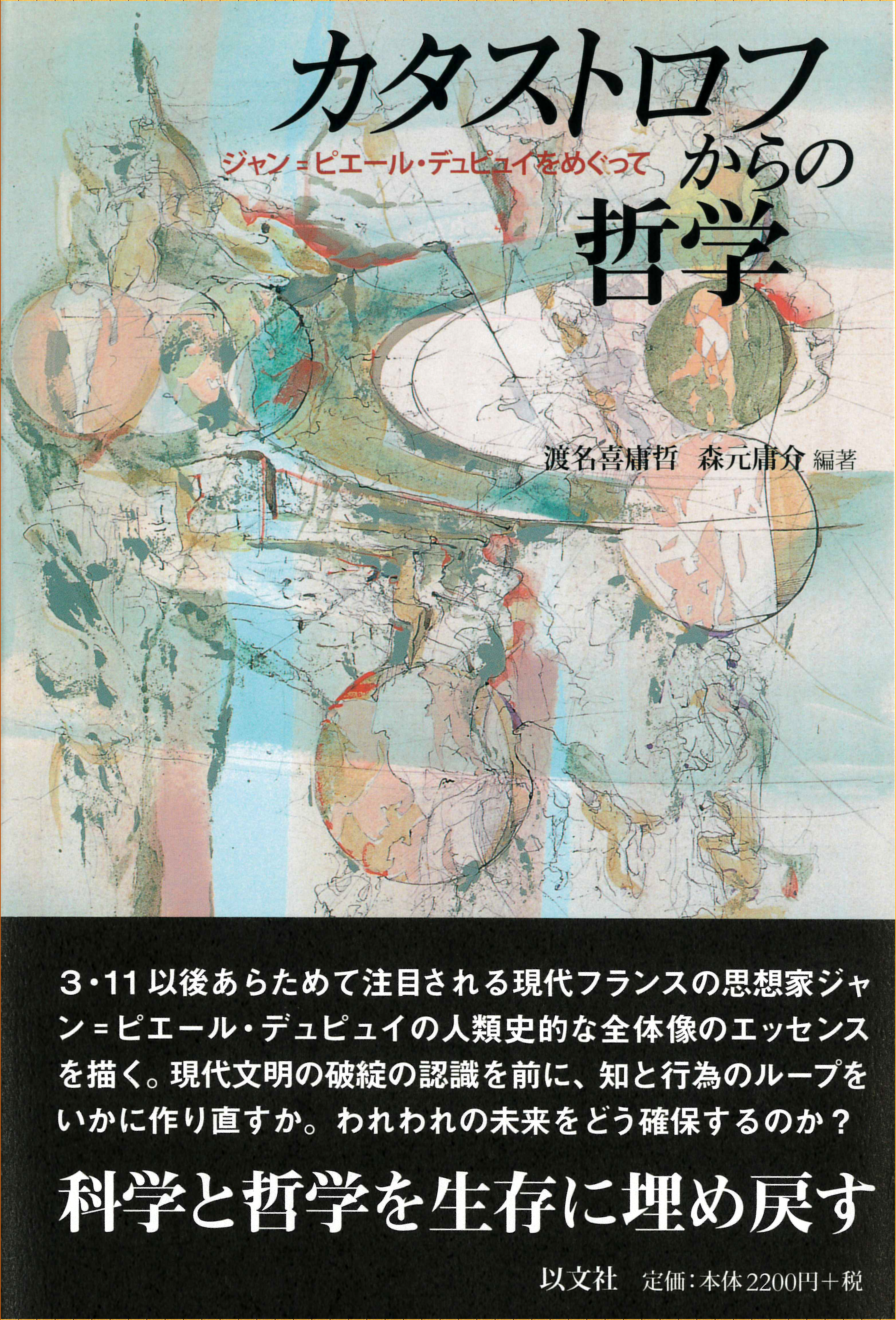
書籍名
カタストロフからの哲学 ジャン=ピエール・デュピュイをめぐって
判型など
200ページ、四六判、上製カバー装
言語
日本語
発行年月日
2015年10月23日
ISBN コード
9784753103270
出版社
以文社
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
ジャン=ピエール・デュピュイは、キリスト教を有力な背景とした人間学 (イヴァン・イリッチ、ルネ・ジラール) とシステム論 (ハインツ・フォン・フェルスター) に同時に依拠しつつ、近年はとりわけ破局 (カタストロフ) という観点から、大規模災害、金融危機、そして核の脅威などを幅広く論じる異色の哲学者である。日本での紹介は1980年代にさかのぼるが、その仕事が改めて注目を集めたのは2011年の東日本大震災、またそれに起因していまだ収束を見通せない福島原発事故をきっかけとしてのことである。2004年に上梓された破局についての一般的考察『ありえないことが現実になるとき』、またそれにもとづくふたつのケース・スタディというべき『ツナミの小形而上学』(2005年)、『チェルノブイリ』(2006年) といったかれの著作を、わたくしたちはわたくしたち自身が経験した災厄の事後に、いわば成就してしまった不幸の予言として読むことになった。
そのような経緯を踏まえつつ、デュピュイの破局論の理論的構成を改めて検証することを主旨とした論文集が本書である。
遠からぬ破局が避けがたいものとして予見されながら、人類はしかし必要なアクションを起こせずにいる。そのことは現在のグローバルな環境危機への政治的対応が端的に示すとおりであるが、これはいったいなぜなのか。デュピュイによれば、それは、わたしたちが破局の到来を「知っている」にもかかわらず、自分たちが「知っている」そのことを結局のところ「信じる」ことができずにいるからだ。では、「知」を「信」と接合し、「アクション」へ差し向けるために何が必要か。時間モデルの逆転であるとデュピュイはいう。すなわち、過去から未来へ向かう常識的な「歴史的な時間」のモデルに代えて、未来―この場合はとりもなおさず破局の事後の未来―をすでに到来したものとして基点に据え、固定されたこの未来をそれでも / だからこそ回避するためのアクションを (未来にとっての過去である) 現在から起動すること―実践のために設定されるこうした新しい時間モデルをデュピュイ自身は「投企の時間」と呼ぶ。
とくに哲学者デヴィッド・ルイスに依拠しつつ、「反実仮想」的な推論形式を方法的な核として構築されたこのようなモデルは一見して逆説的である。だが、自分で自分の靴紐を引っ張り上げるかのような本質的に逆説的、不合理な企て (「自己超越」) によってこそ、人間は自身の未来を切り開いてきたのだともデュピュイは確言する。破局によって未来は閉ざされていると考えることこそが未来を開く条件となる―しかし、本当にそんなことが成り立つのだろうか。本書の著者たちはそのような率直な疑問を共通の出発点として、哲学と科学論、またキリスト教思想からデュピュイの思想へのアプローチを試みた。それは「信じる」ために改めて「知ろうとする」試みであったといえるかもしれない。
(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 准教授 森元 庸介 / 2020)
本の目次
1 J=P・デュピュイとカタストロフ論的転回 (渡名喜庸哲)
1 「さまざまなカタストロフの時代」
2 リスク論からカタストロフ論へ
3 運命論的カタストロフ論から賢明なカタストロフ論へ
2 デュピュイの科学哲学と破局論―― システム論から出発して (中村大介)
序論
1 デュピュイとシステム論
2 破局論の時間性
3 破局論―― <事情に疎い者> の形而上学
結論
補遺――デュピュイ (及び自己組織化) とエピステモロジーの関係についてのノート
3 救済の反エコノミー (森元庸介)
あとがき
ジャン=ピエール・デュピュイの著作一覧
関連情報
“今“を生き抜くための102冊 by SEALDs (SEALDs 2016年3月30日)
https://www.sealds.com/#sealds102
新刊紹介 (REPRE vol.26 2016年2月28日)
https://repre.org/repre/vol26/books/02/09.php
シンポジウム:
「ジャン=ピエール・デュピュイの思想圏― カタストロフ、科学技術、エコノミー ―」 (慶應義塾大学日吉キャンパス 2014年12月13日)
https://www.jactfl.or.jp/?p=1122



 書籍検索
書籍検索


