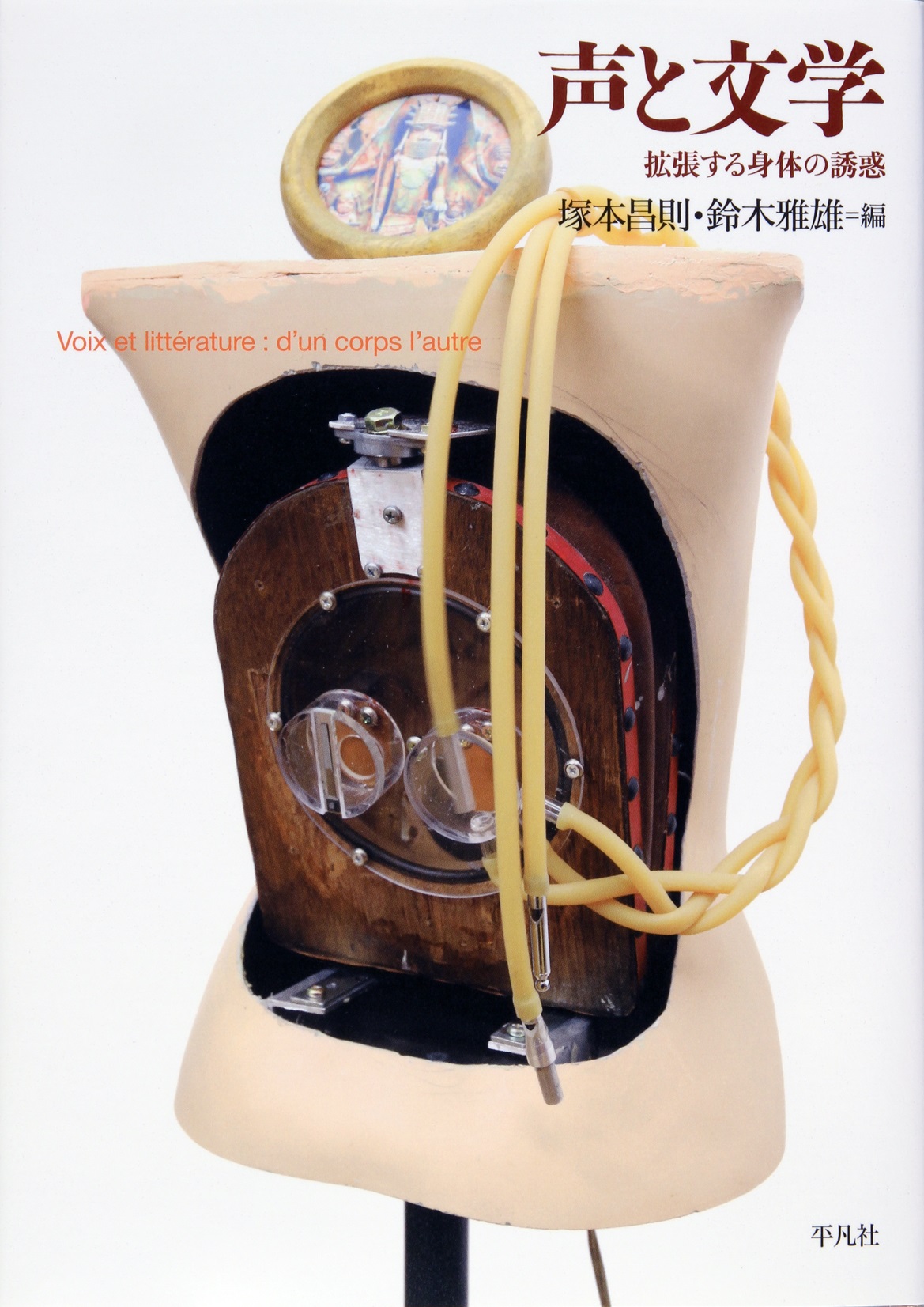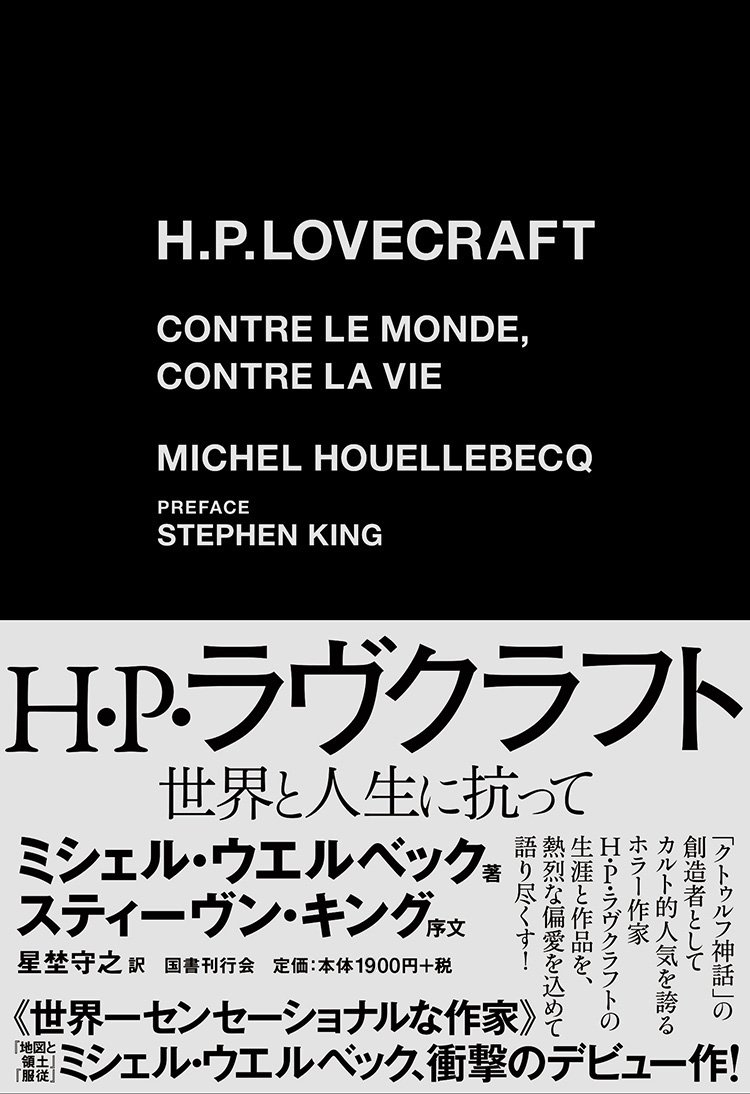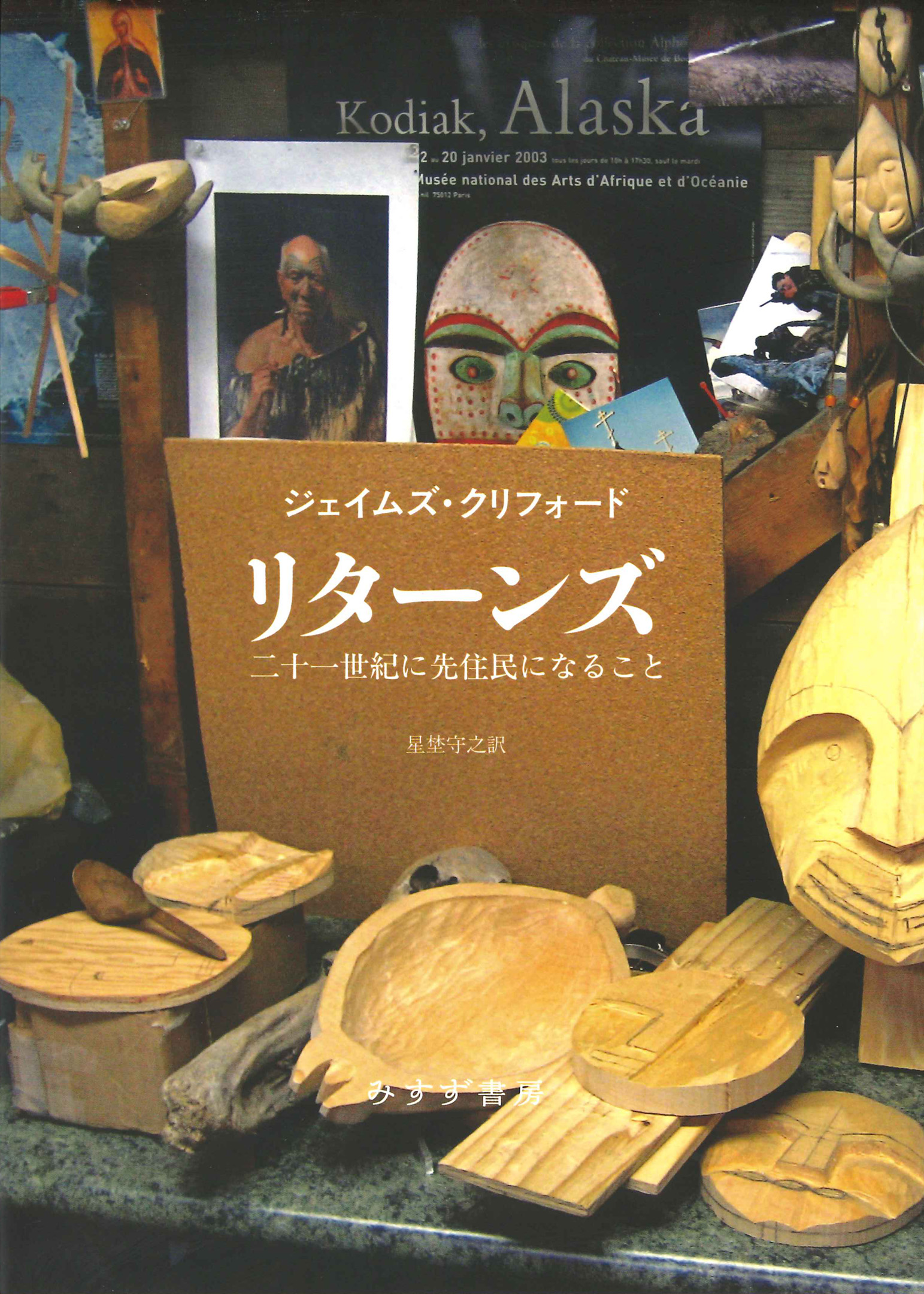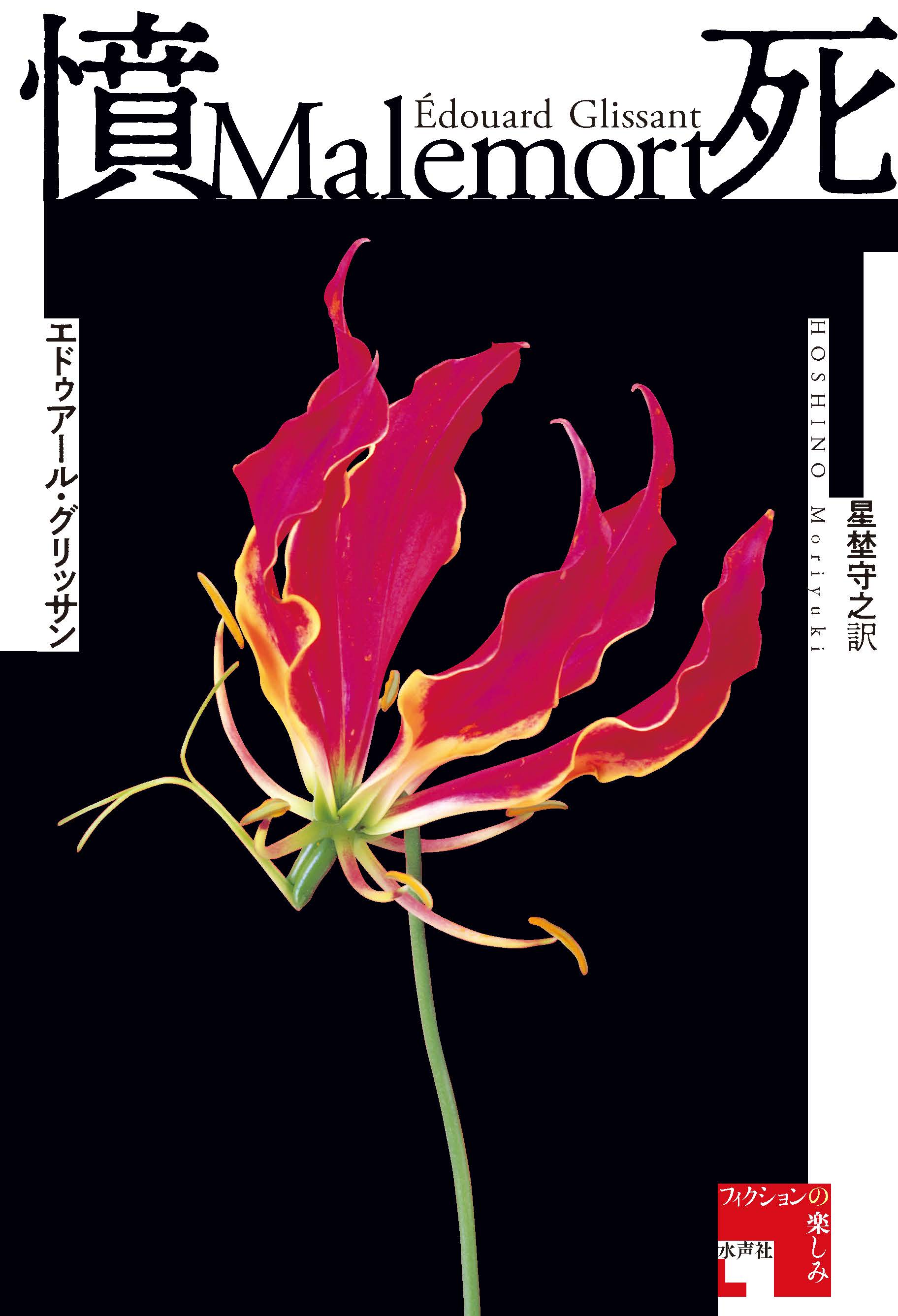書籍名
シュルレアリスムと抒情による蜂起 アンドレ・ブルトン没後50年記念イベント全記録
言語
日本語
発行年月日
2017年7月
ISBN コード
9784990915735
出版社
エディション・イレーヌ
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
本書は、パリのシュルレアリスム運動の最後のメンバーの一人であったアニー・ル・ブラン氏が2016年の9月に来日した折におこなった講演の邦訳を中心に、関連イベントの記録と、シュルレアリスム運動の主導者だったアンドレ・ブルトンの関連テクストの邦訳を加えて編集されたものです。私自身は9月21日にアンスティチュ・フランセ東京でおこなわれた講演「若き見者よ、次に語るのは貴方だ―アンドレ・ブルトン、近くから、遠くから」の通訳を務め、本書では同講演のテクストの邦訳を担当しています。
シュルレアリスム、あるいはシュールレアリスムと表記されることもありますが、皆さんはこの言葉から何を連想するでしょうか。美術が好きであれば、サルバドール・ダリやルネ・マグリットの不思議な絵画作品を思い起こすかもしれませんし、「シュールな」といった一般的な言い方が頭に浮かぶかもしれません。たしかに、ダリやマグリットは実際にパリのシュルレアリスム運動とかかわりながら作品を作っていた時期がありますし、「シュルレアリスム」という語は「超現実主義」と訳すこともできますので、現実離れした事態を「シュール」と形容するのはそれなりに元々の意味と関連がありそうです。もう少し歴史的に事実関係を確認しておくなら、フランスの詩人アンドレ・ブルトンを中心として、1920年代にパリで誕生し、夢、詩、イメージ、偶然といったキーワードを梃にして日々の「現実」を根本的に問い直そうとする考えを共有した人々の運動、ならびにその考え方そのもの、という具合になるでしょうか。アンドレ・ブルトンが1924年に著した『シュルレアリスム宣言』は岩波文庫で読むことができますので、こちらもぜひお読みになるとよいと思います。
ただ、意外に知られていないのが、1920年代にスタートしたこのシュルレアリスム運動が、実際の運動体として1970年頃まで存在し続け、一定の影響力を保っていたという事実です。そして、本年 (2019年) には77歳になるアニー・ル・ブラン氏は、この運動に参加し、1966年に亡くなったアンドレ・ブルトンと親しく接することのできた最後の世代の一人です。ところで、シュルレアリスム運動が「日々の現実を問い直す」という風に言いましたが、1920年代から今日にかけて、私たちが直面している現実の姿は大きく変化してきています。アンドレ・ブルトンが20歳の当時は、ヨーロッパは第一次世界大戦の戦火の中にありました。また、ソヴィエト連邦が登場したのもこの時代です。しかし私たちが直面している世界の現実は、それとは大きく異なっています。アニー・ル・ブラン氏も、彼女がシュルレアリスムから受け取ってきた思想を武器に、そんな現代世界の現実―「フクシマ以降」の現実も含めて―と対峙しつつ若い世代に語りかけています。
(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 教授 星埜 守之 / 2019)
本の目次
I アニー・ル・ブラン来日公演記録
01 かつてあったこと、それはこれからも起こるだろう
―シュルレアリスムと抒情による蜂起 (塚原 史 訳)
02 若き見者よ、次に語るのは貴方だ
―アンドレ・ブルトン、近くから、遠くから (星埜守之 訳)
II 参考文献―アンドレ・ブルトンの重要テクスト
01 「物事を見抜く若き見者よ、次に語るのはあなただ」(アンドレ・ブルトン、前之園望 訳)
02 三部会 (アンドレ・ブルトン、前之園望 訳)
03 線と糸との物語―アンドレ・ブルトンの三部会 (前之園望)
III 「アンドレ・ブルトン没後50周年記念展」
IV 五十年後の夏―アニー・ル・ブラン来日記 (松本完治)
後跋
関連情報
「ダダ・シュルレアリスムとアナーキズム」~アニー・ル・ブラン来日講演を読み解く (LIBRAIRIE6/シス書店 2017年7月15日)
http://www.editions-irene.com/news/170702.html



 書籍検索
書籍検索