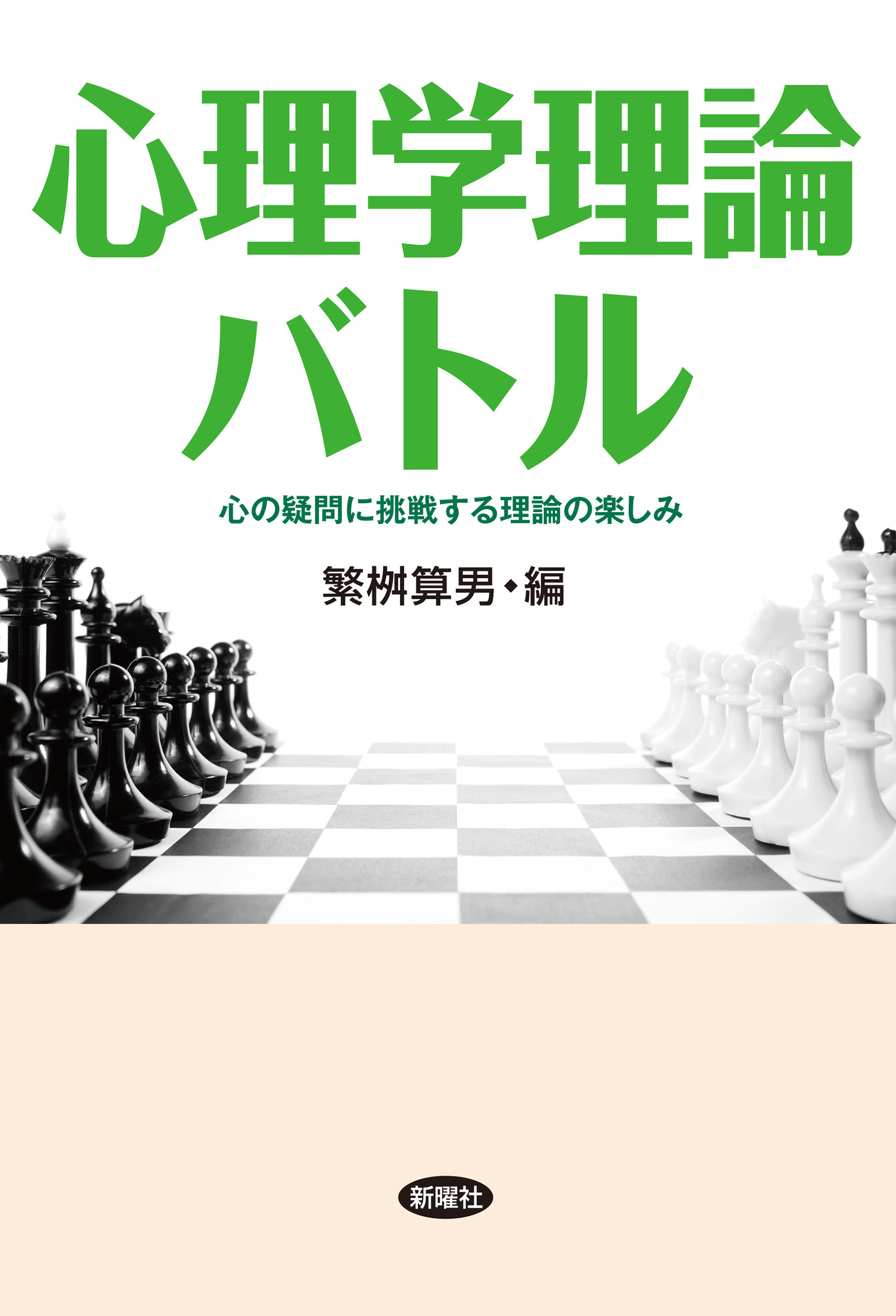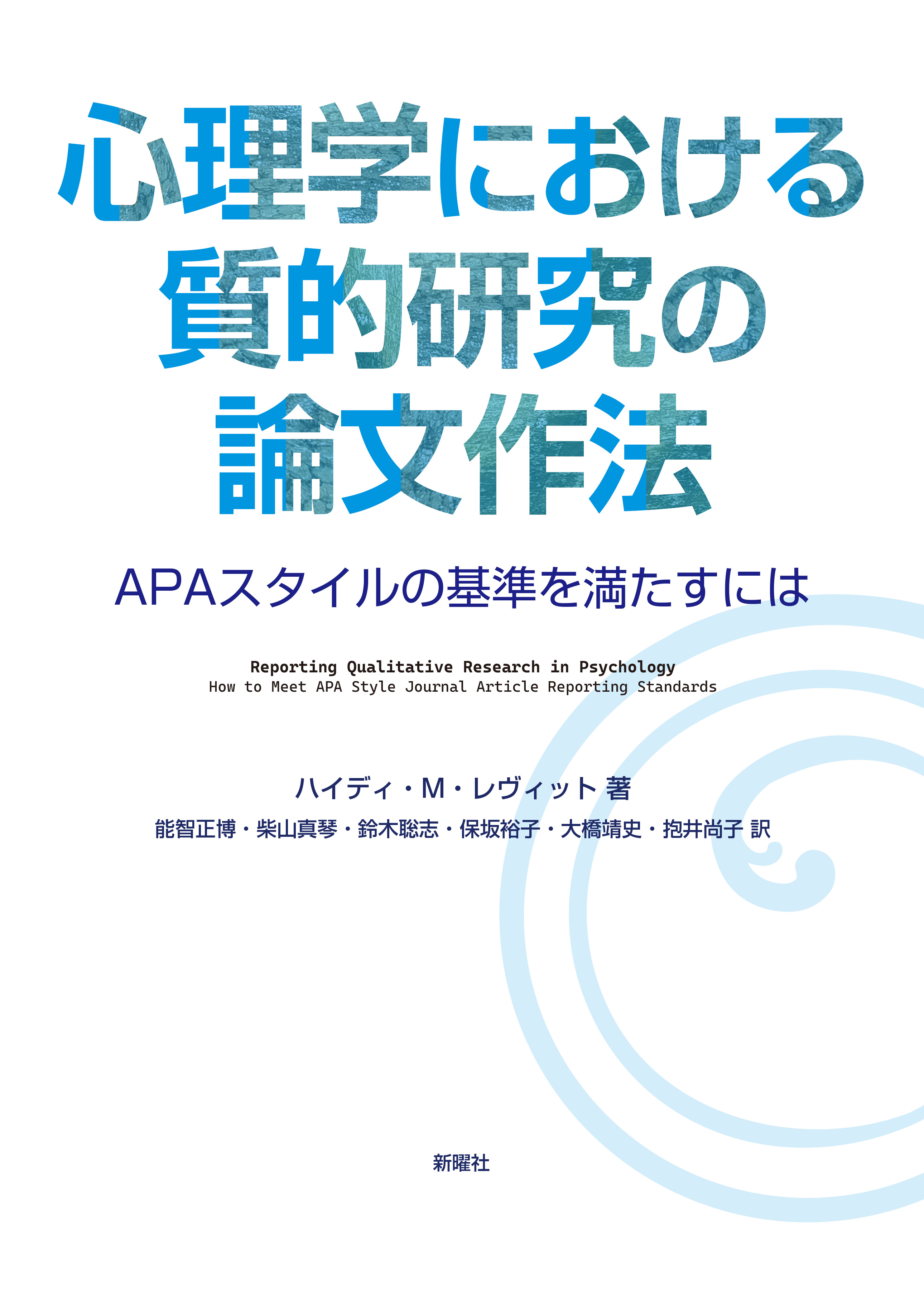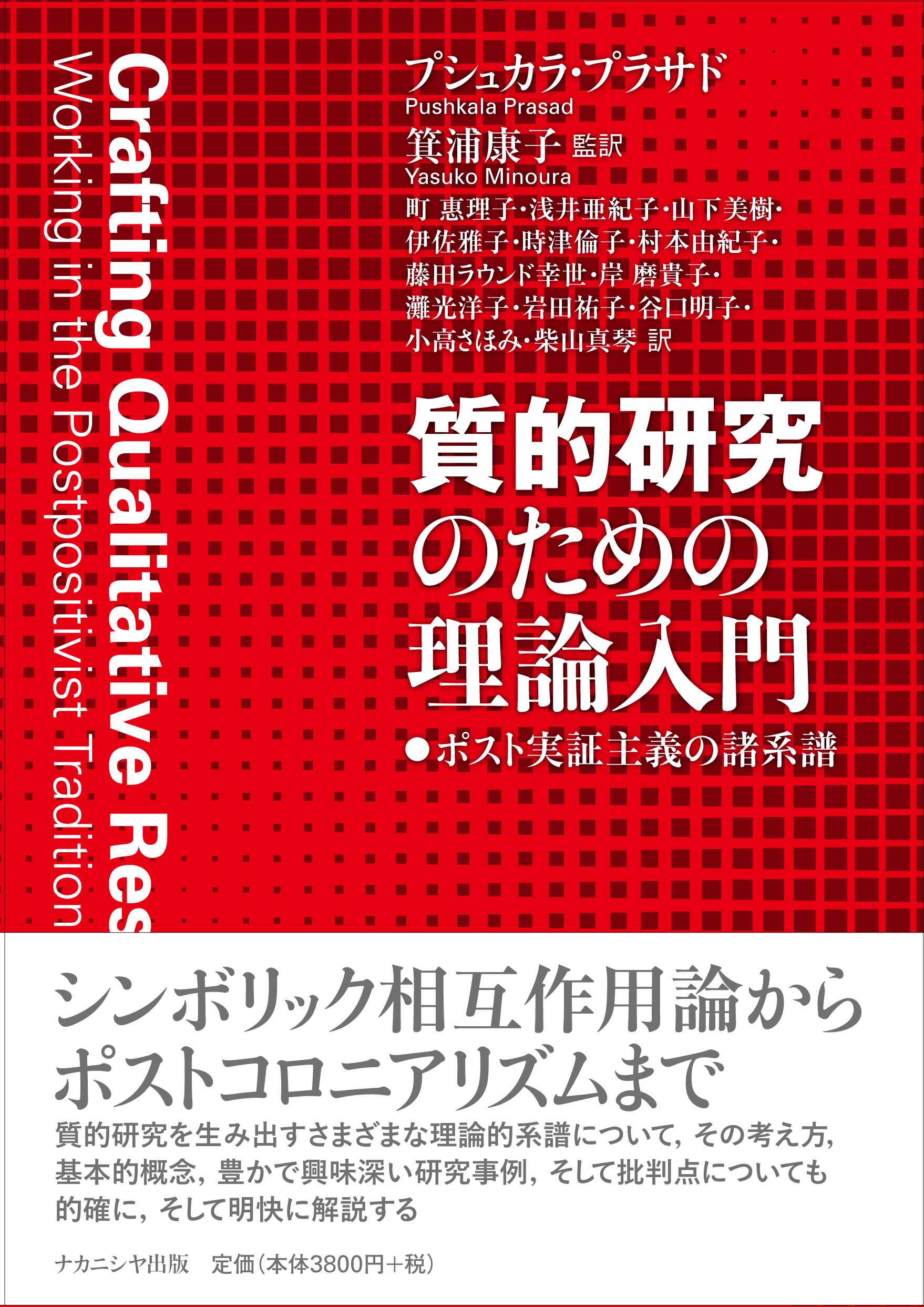
書籍名
質的研究のための理論入門 ポスト実証主義の諸系譜
判型など
376ページ、A5判
言語
日本語
発行年月日
2018年1月30日
ISBN コード
9784779512230
出版社
ナカニシヤ出版
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
本書は、2005年に刊行されたPushkala Prasad著『Crafting Qualitative Research: Working in the Postpositivist Traditions』の全訳です。原題にあるcraftという語は、その含意を日本語で短く表現することは難しいため、邦題には直接生かされていませんが、職人が手仕事で何かを創りあげることを表す動詞です。この原題には、数字に還元できない質的データを丹念に読み解き、洗練された研究として練り上げていくための道筋を示す、という著者の姿勢が込められていることがうかがえます。
人文社会科学系の多くの学問において、質的研究は重要な研究方法論です。その背景には、実験や調査といった定量的な方法論の基盤となる実証主義とは一線を画した認識論の枠組み、「ポスト実証主義」があります。それはすなわち、研究対象たる世界を、自分とは切り離された (客観的に把握しうる) 外界として捉えるのではなく、社会的に構築されたものとして捉える考え方です。
このポスト実証主義の認識論には多彩な伝統や系譜があります。質的研究を志す研究者は、自らが拠って立つ理論的視座を明確に認識し、その視座に根差したやり方でデータを読み解いていくことが求められます。しかし、質的研究に関する従来のテキストは、どのようにして研究を実施するかという「手法」に特化したものが大半で、その研究の基盤となる思想や哲学を幅広く扱った文献はなかなか見当たりませんでした。
本書の独自性は大きく2点あります。その一つ目は、13におよぶポスト実証主義の多彩な学派・伝統を広く網羅していることです。扱われる研究者も極めて数多く、ブルーマー (シンボリック相互作用論)、ディルタイ、ガダマー (解釈学)、ゴフマン (ドラマツルギー)、ガーフィンケル (エスノメソドロジー)、ソシュール、パース (記号論・構造主義)、フランクフルト学派、ハーバーマス (批判理論)、ギデンズ、ブルデュー (構造化と実践)、リオタール、ボードリヤール (ポストモダニズム)、フーコー、デリダ (ポスト構造主義) など、枚挙にいとまがありません。
そしてもう一つの大きな特徴は、これらの諸理論をそれぞれの専門家が分担して解説するのではなく、一人の著者がすべてを見渡して描き切っていることです。ほとんどの章で、その学派の中心的概念、その哲学的背景、考え方をめぐる論争、興味深い研究事例 (著者の主たる研究領域を反映し、経営・組織系の事例がほとんどです)、将来展望などが満遍なく語られます。さらには、いくつかの章を束ねるかたちで、同じ系譜に属する各学派の相互関係を一望できるコンセプト・マップも示されています。本書を貫く著者の一貫した書きぶりは、読者がそれぞれの考え方を比較したり、その系譜を体系的に理解したりするうえで、大きな助けになっています。
翻訳を担当したのは、監訳者の箕浦康子先生 (心理人類学) 以下、教育学・心理学・人類学・社会言語学・コミュニケーション論等々、人文社会科学の多方面の研究者によるチームで、私自身もそのひとりです。互いの訳文を何度も突き合わせ、原書の統一感を損なわないよう努めました。ページをめくるにつれて、読者は著者の博識に感服するとともに、やがて自らも、質的研究の多彩な理論的視座を広い視野から眺める眼を、身につけることができるはずです。人文社会科学の幅広い学問領域で、質的研究を志す多くの方々に、本書を手に取っていただければ幸いです。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 村本 由紀子 / 2021)
本の目次
01 技(わざ)としての質的研究:ポスト実証主義の諸系譜と研究スタイル(町惠理子[訳])
1 質的研究をおこなう場合のジレンマ
2 技としての質的研究:研究の諸系譜とスタイル
3 本書について
I 解釈的アプローチの系譜
02 シンボリック相互作用論:自己と意味を求めて(浅井亜紀子[訳])
1 シンボリック相互作用論への哲学的影響
2 シンボリック相互作用論の中心概念
3 シンボリック相互作用論学派の研究例
4 シンボリック相互作用論における論争と新たな方向性
03 解釈学:テクストの解釈(山下美樹[訳])
1 解釈学の哲学
2 解釈学派の中心概念
3 解釈学派の研究例
04 ドラマツルギーとドラマティズム:劇場・舞台としての社会生活(伊佐雅子[訳])
1 ドラマツルギーの哲学的先駆者たち
2 アーヴィング・ゴフマンとドラマツルギー
3 ドラマツルギー学派の研究例
4 ケネス・バークとドラマティズムの哲学
5 ドラマティズム学派の中心概念
6 ドラマティズム学派の研究例
05 エスノメソドロジー:日常生活の成り立ち(時津倫子[訳])
1 エスノメソドロジーの理論と哲学
2 エスノメソドロジーの中心概念
3 エスノメソドロジー学派の研究例
4 エスノメソドロジーの貢献と限界
06 エスノグラフィー:ネイティブの文化的理解(村本由紀子[訳])
1 エスノグラフィーにおける人類学の遺産
2 古典的エスノグラフィーの中心概念
3 非正統的なエスノグラフィー諸派
4 エスノグラフィーの研究例
5 エスノグラフィーの系譜における論争と新たな方向性
II 深層構造に着目する系譜
07 記号論と構造主義:社会的現実の文法(藤田ラウンド幸世[訳])
1 記号論の哲学
2 記号論と構造主義における中心概念
3 記号論的アプローチの研究例
4 構造主義の最近の動向と発展
III 批判的アプローチの系譜
08 史的唯物論:階級,闘争,そして支配(岸磨貴子[訳])
1 カール・マルクスの哲学
2 史的唯物論の中心概念
3 史的唯物論に基づいた研究例
4 史的唯物論における批判と論争
09 批判理論:ヘゲモニー,知の生産,コミュニケーション行為(灘光洋子[訳])
1 批判理論の哲学
2 批判理論の中心概念
3 批判理論学派の研究例
4 批判理論についての論争と新たな方向性
10 フェミニズム:中心的社会原則としてのジェンダー(岩田祐子[訳])
1 フェミニスト理論と哲学
2 フェミニスト学派の中心概念
3 フェミニスト学派の研究例
4 フェミニスト学派における論争と新たな方向性
11 構造化と実践の理論:権力という枠組のなかでの二元論を超えて(谷口明子[訳])
1 アンソニー・ギデンズと構造化理論
2 ギデンズの構造化理論の中心概念
3 構造化学派の研究例
4 ブルデューの社会理解と社会研究
5 ブルデューの実践の理論における中心概念
6 ブルデューの実践の理論を用いた研究例
IV 「ポスト」がつく諸学派の系譜
12 ポストモダニズム:イメージおよび「真なるもの」との戯れ(小高さほみ[訳])
1 リオタールとポストモダンの知
2 ボードリヤールとポスト近代社会
3 ポストモダン学派の研究例
4 ポストモダン学派における批判と論争
13 ポスト構造主義:言説,監視,脱構築(時津倫子[訳])
1 脱構築の哲学
2 脱構築における中心概念
3 フーコーの知の考古学と知の系譜学
4 フーコーのポスト構造主義の中心概念
5 ポスト構造主義の研究例
6 ポスト構造主義への批判
14 ポストコロニアリズム:帝国主義を読み解き,抵抗する(町惠理子[訳])
1 ポストコロニアリズム伝統の出現
2 ポストコロニアル学派の中心概念
3 ポストコロニアル学派の研究例
15 結論:伝統,即興,質のコントロール(柴山真琴[訳])
1 質的研究における伝統と即興
2 研究の質のコントロール:個々人の主体性
3 研究の質のコントロール:ゲートキーパー
4 質的研究をつくる喜び
参照文献
監訳者あとがき



 書籍検索
書籍検索