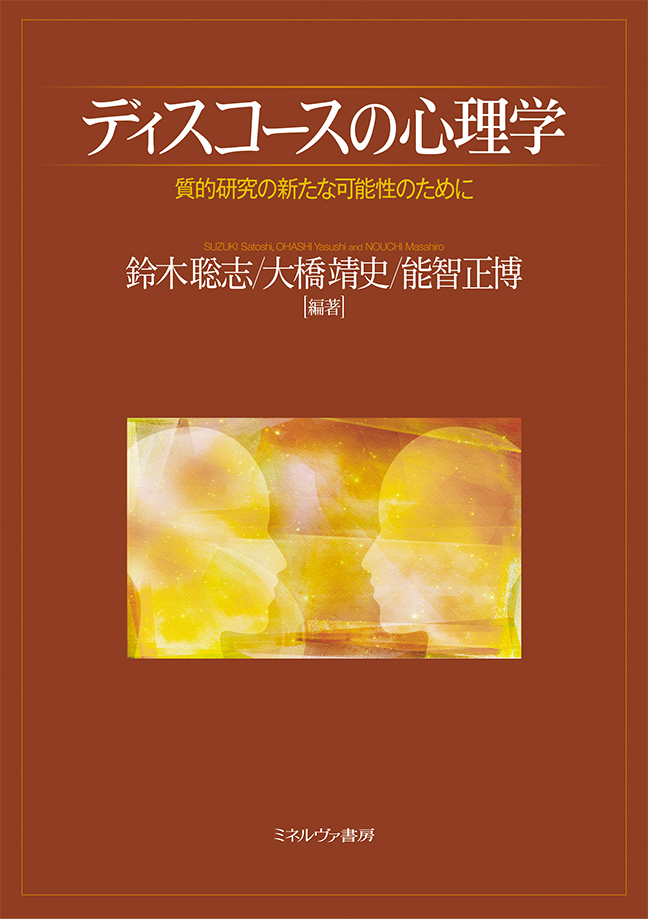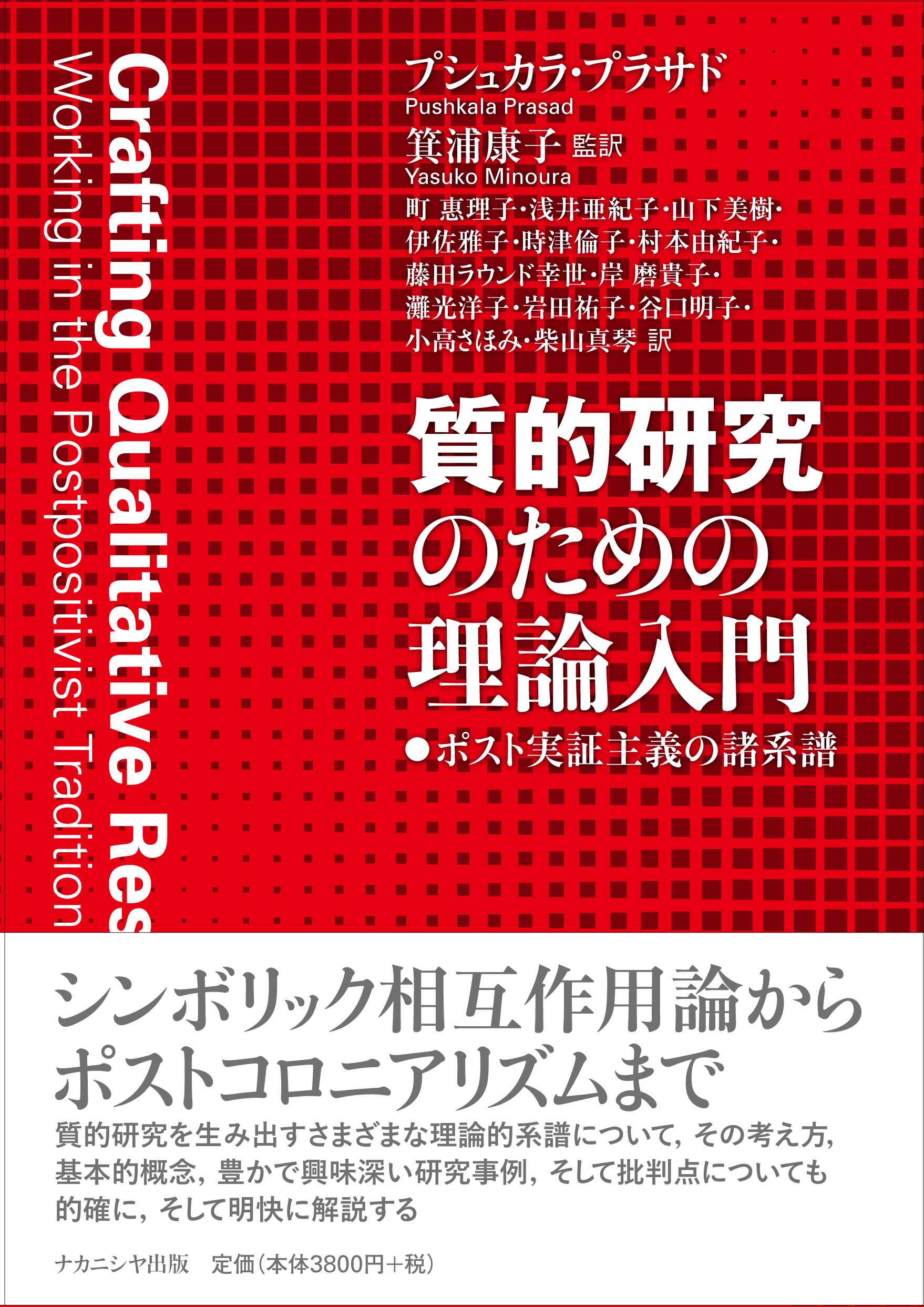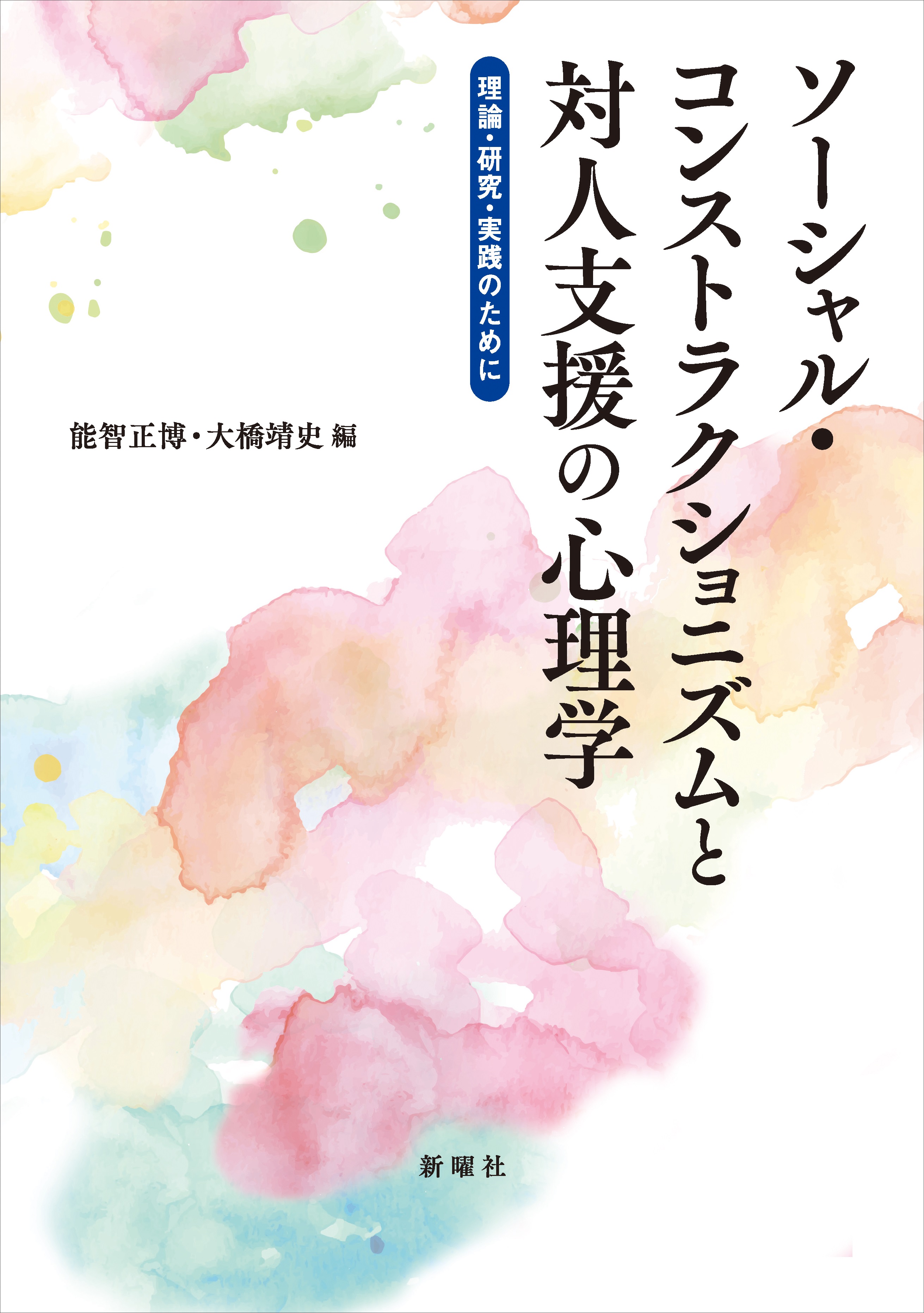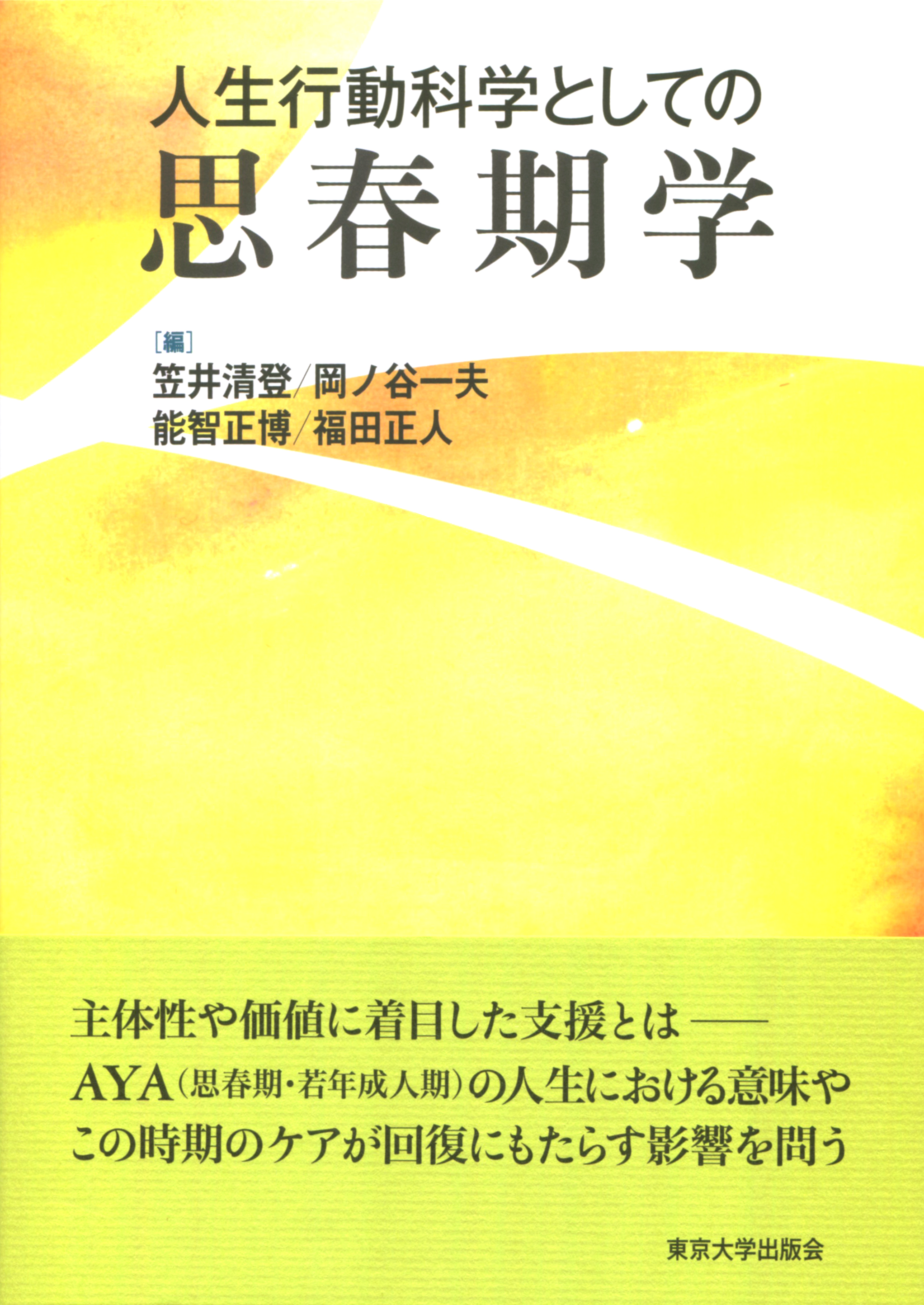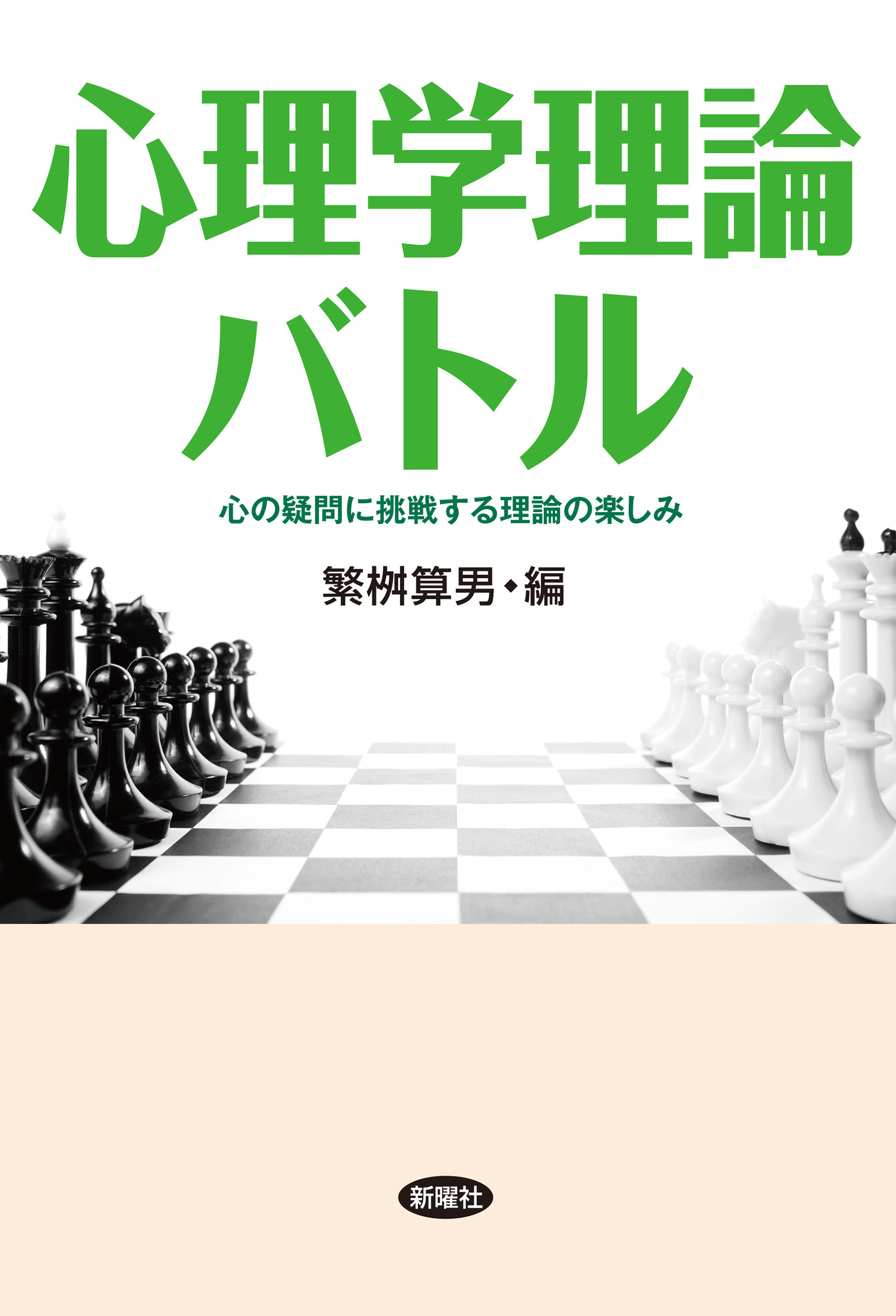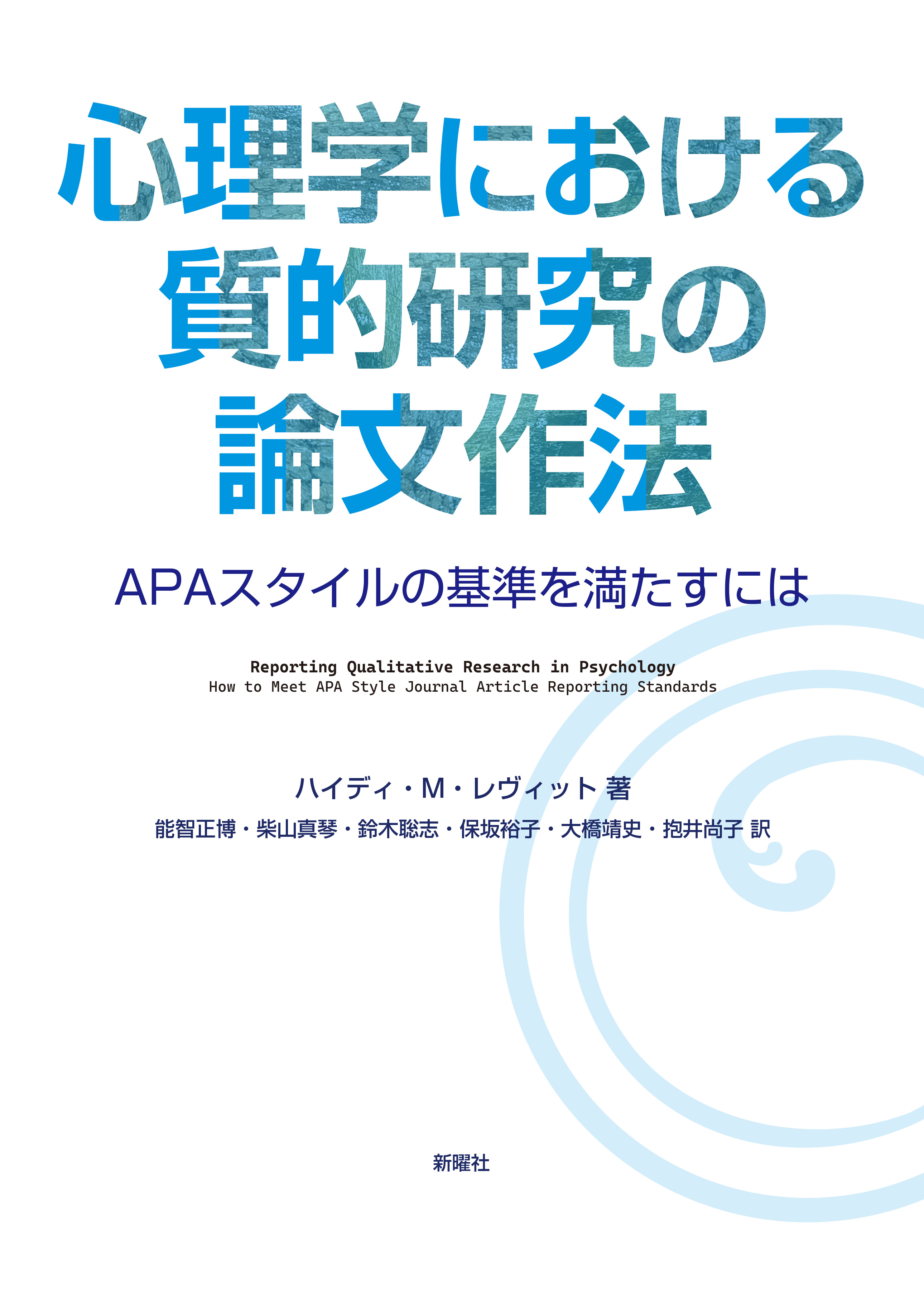
書籍名
心理学における質的研究の論文作法 APAスタイルの基準を満たすには
判型など
192ページ、B5判
言語
日本語
発行年月日
2023年11月10日
ISBN コード
9784788518285
出版社
新曜社
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
ここ30年ほどの間に質的研究は心理学の研究法としても定着した感がある。学会が設立され専門学術誌が発刊されたほか、そのテキストや論文集も数多く出版されるようになった。ただ、質的研究の学問的背景は多様で新たな方法が工夫されることも多く、質的研究の質の統一的な基準は認められなかった。そんななか、アメリカ心理学会 (APA) は「質‐JARS (Journal Article Reporting Standard for Qualitative Research)」を作成し、心理系の学術論文執筆全般の手引書APA Publication Manual 第7版 (2020) にそれを組み入れだ。本書は、その作成に携わった作業部会の部会長であるハイディ・M・レヴィットが出版した解説書、Reporting Qualitative Research in Psychology: How to Meet APA Style Journal Article Reporting Standards (APA,2021) の全訳である。
質‐JARSは質的研究を行って論文を書く際に、その成果を読者 (特に、学術雑誌の査読者) に伝えるためにどう論文を書くかを整理したものである。質の高い質的研究論文の基準を論文の著者に伝えるものであると同時に、質的研究をまだよく知らない査読者に対してその読み方を指南する役割ももっている。ただ、簡潔な文言で書かれた比較的短い基準なので、それだけを読んでも具体的なイメージがなかなか頭に浮かばなかったり、なぜそのような基準になるのかが理解できなかったりするかもしれない。本書は、心理学の質的研究を長らく牽引してきた筆者が、自身の体験や実際の質的研究論文からの引用を織り込みながら質‐JARSを中心に解説を行ったものである。
本書はまず質的研究の背景と広がりを述べることから始めるが、読者はそこで質‐JARSがカバーする心理学の質的研究の範囲を確認することになる。含まれるのは、現象学、グラウデッドセオリー、ナラティブ、批判理論、ディスコースと幅広い。次いで、論文の質を見る際のキイとして「方法論的整合性」の概念が解説される。これは、研究題材に対して「忠実性」があるどうか、また、研究成果が何らかの意味で「有用性」をもつことが示されているかどうかを示す。その後質‐JARSの規程が、序論、方法、結果、考察という一般的な論文構成のセクションごとに具体的な事例を引用しながら説明される。APAは質‐JARSとともに量的研究、混合研究法、質的メタ分析の論文執筆基準も発表しているが、次の章では、量的研究の基準を除いた他の2つの基準についても解説される。最終章では、論文を学術誌に投稿する際の注意点について、実践的な注意点が述べられる。
当然ながら本書は、質的研究を行ってそれを論文にしようとする際に役に立つ。しかしそういう段階にある研究者にとってのみならず、比較的初学者の段階で読んでも質的研究の背景や広がりを理解し、自分の研究の展開を考える上で役に立つだろう。質的研究は、自分の研究がどうなるかを考えつつ行ったり来たりを繰り返しながら進んでいく。その意味で本書は、心理学だけではなく様々な人文社会科学分野で質的研究を行う人にとって、研究実践の際の座右の書として役立つものと思われる。
(紹介文執筆者: 教育学研究科・教育学部 教授 能智 正博 / 2024)
本の目次
第2章 質的なストーリーを語る――研究目的は論文執筆にどう影響するか
第3章 方法論的整合性――研究の忠実性と有用性を高める
第4章 研究のミッションをどう定めるか――タイトルページ,アブストラクト,序論
第5章 探究のプロセスをどのように書くか――方法セクション
第6章 何を見出したのか――結果セクション
第7章 論文全体として何が言えるのか――考察セクション
第8章 質的メタ分析の論文執筆――主要な特徴
第9章 混合研究法――複数の論文執筆基準を架橋する
第10章 修辞スタイルと方法論的整合性について



 書籍検索
書籍検索