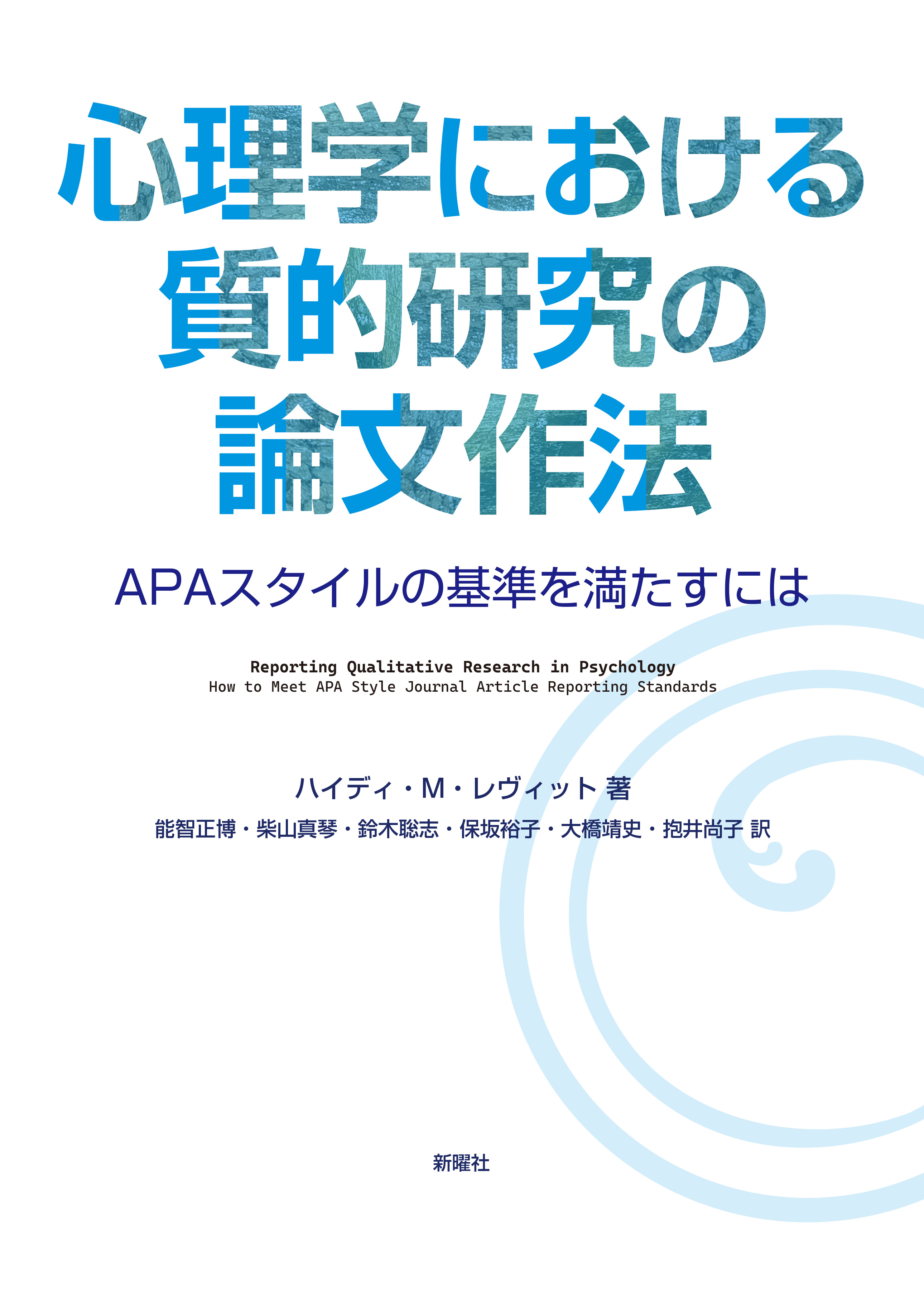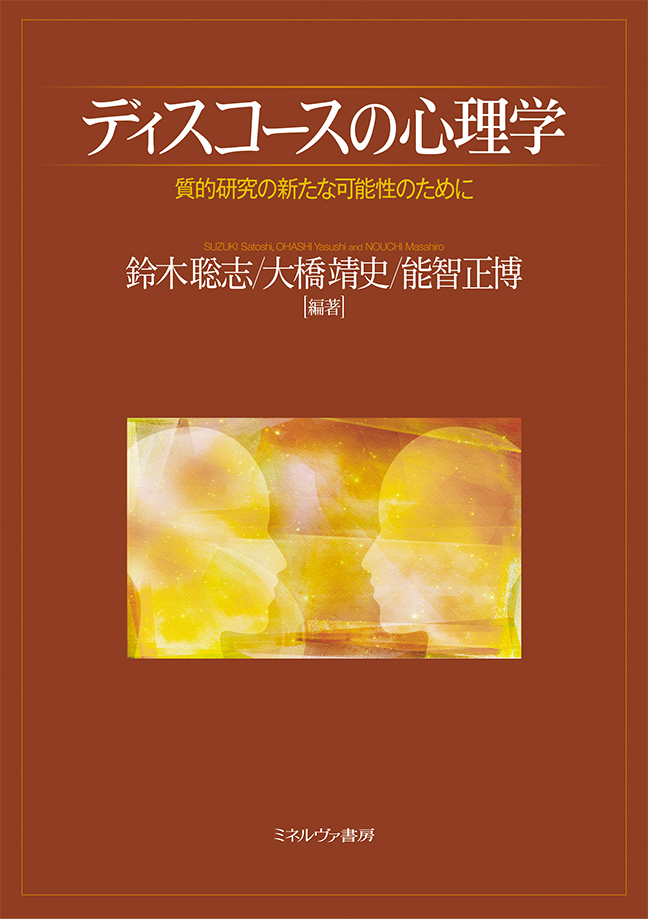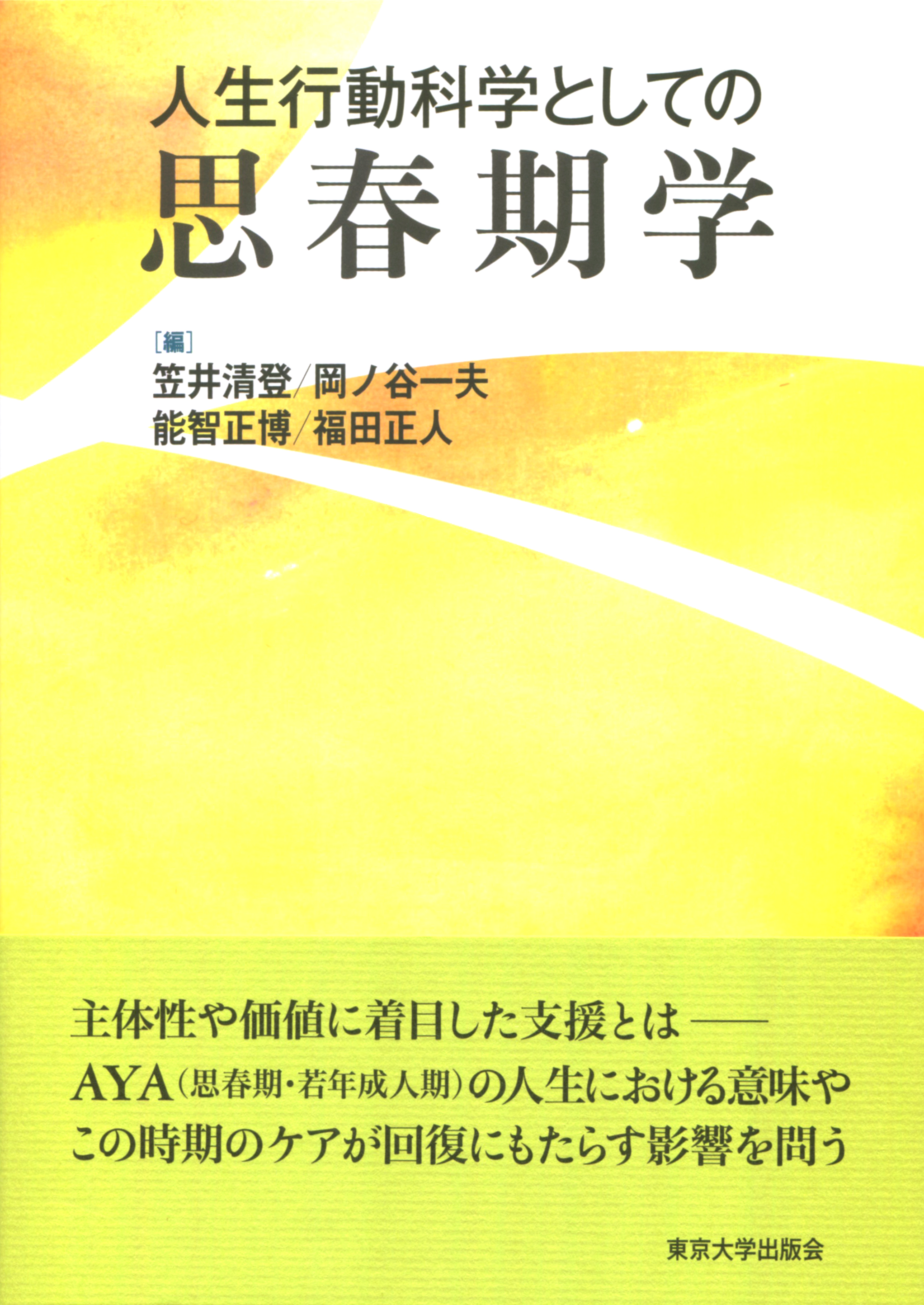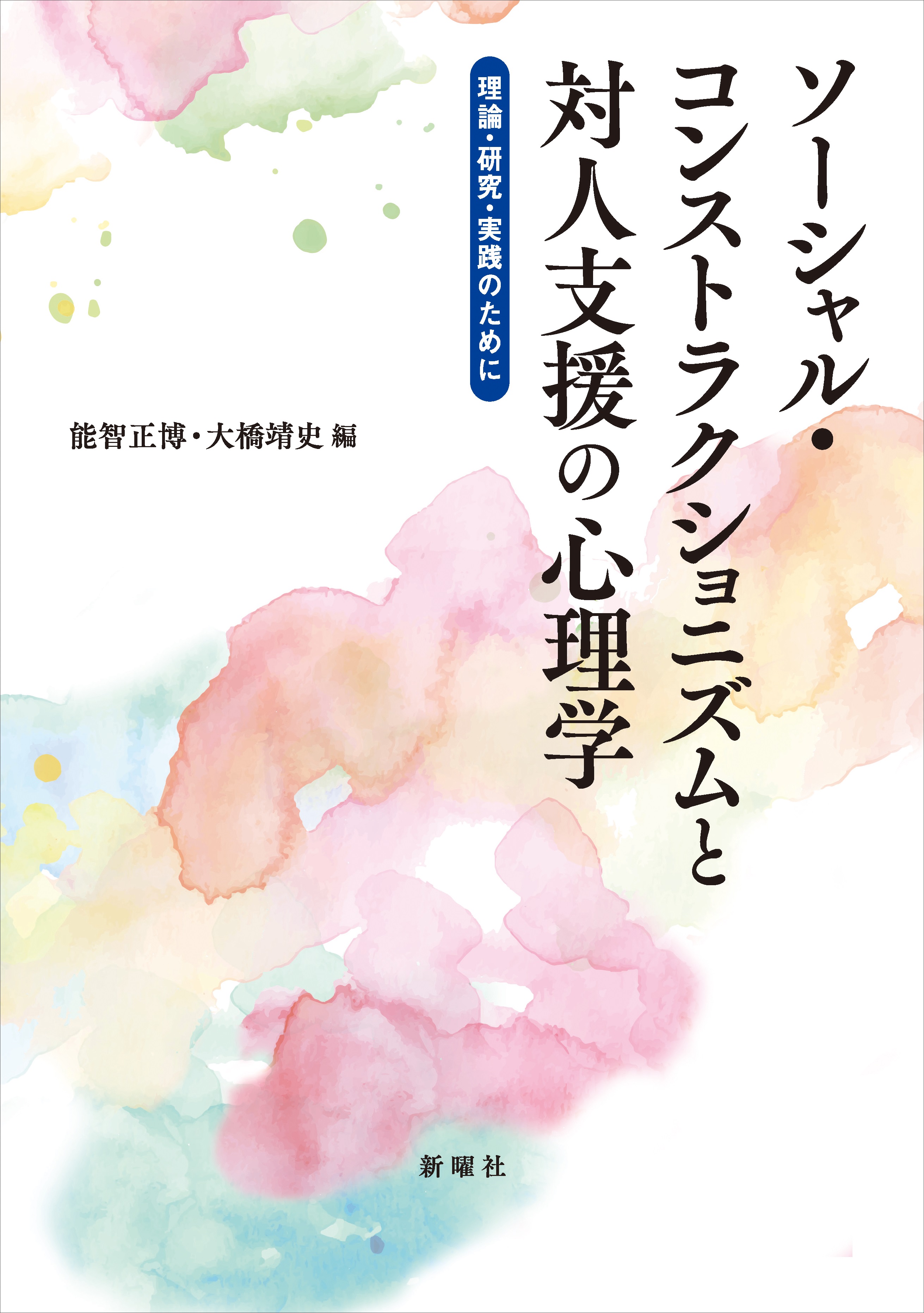
書籍名
ソーシャル・コンストラクショニズムと対人支援の心理学 理論・研究・実践のために
判型など
328ページ、A5判
言語
日本語
発行年月日
2021年12月31日
ISBN コード
9784788517509
出版社
新曜社
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
「ソーシャル・コンストラクショニズム」とは、「社会構成主義」「社会構築主義」などと訳される人間科学・社会科学の基礎理論です。自然科学に特徴的な論理実証主義の考え方では、研究対象の実在をまず仮定した上でその特徴を明らかにしようとするわけですが、ソーシャル・コンストラクショニズムでは対象を言語的な実践を通じて社会的に作り上げられるものと考えます。たとえば、「身体障害」も客観的に存在する機能欠損というよりも、社会のなかで作られてきた意味やその意味を用いる人びとの間の相互作用によって欠損のように見えるものとみなされます。近年この考え方は様々な学問領域に刺激を与え、心理学研究やそれをもとにした実践に対しても影響を与えています。ただその一方で、「理解しにくい」とか「どう使えばいいかわからない」という声も聞かれます。本書はそうした声に応える形で、ソーシャル・コンストラクショニズムの考え方とその応用を、特に対人支援の実践に注目しながら解説したものです。
本書は4部構成になっており、第I部は理論家として著名なV.バー教授による概説です。講演をもとにした章なので、初めてこの理論に触れる読者にもわかりやすい内容になっています。第II部では、他の理論と比較することで、ソーシャル・コンストラクショニズムの特徴を浮き彫りにすることを試みています。そこでは、現象学、対話理論、文化心理学、批判心理学といった立場から見るとそれがどのように見えるのかが議論されます。第III部は、ソーシャル・コンストラクショニズムが心理学研究に現在どう影響し、その視点から心理学研究がどう評価されるのかがテーマです。心理学は伝統的に自然科学志向が強い領域ですが、その志向への反省と今後の発展が展望されます。第IV部は、対人支援の専門家やそこに関わりながら調査をする研究者が書いた章からなります。そうした実践においてどうソーシャル・コンストラクショニズムの考え方を利用できるかが具体的に紹介されます。
ソーシャル・コンストラクショニズムは、実体としての「社会」が人の生を枠づけると考える社会決定論ではありません。本書に登場する理論家、研究者、実践者も、あるいは読者のみなさんもまた「社会」の一部であり、コンストラクションに関わっていることを忘れてはならないでしょう。対人支援の実践においてもこの点は重要です。その支援がどんな社会的な前提をもとに行われており、それがどんな社会的な意味を作り上げているのか、そしてその意味が支援をする側・される側にとってどんな体験をもたらしているのか考えることは、支援の行為を独りよがりのものにせず、広い視点で見直してそれを改善するための手がかりを提供してくれるはずです。本書が読者のみなさんにとって、そうした具体的な場面における内省のきっかけとなり、よりよい支援の土台になるとしたら、編者としては大きな喜びです。
(紹介文執筆者: 教育学研究科・教育学部 教授 能智 正博 / 2022)
本の目次
――言葉としてのソーシャル・コンストラクショニズム、そして対人支援
第 I 部 概 説
第1章 ソーシャル・コンストラクショニズムと心理学 / ヴィヴィアン・バー (沖潮満里子 訳)
第 II 部 ソーシャル・コンストラクショニズムへの視点
第2章 現象学的心理学の立場から / 田中彰吾
――ソーシャル・コンストラクショニズムとの対話と直接経験を超える心理学
第3章 対話理論の立場から / 田島充士
――バフチンが射程とする内的社会としての意識と異文化間交流
第4章 文化心理学の立場から / サトウタツヤ
――「実存の表現の多様性」の光と影
第5章 批判心理学からみた社会構成主義 / 五十嵐靖博
――理論心理学的アプローチとディスコース分析、リフレキシビティ
第 III 部 心理学研究とソーシャル・コンストラクショニズム
第6章 ディスコース分析とソーシャル・コンストラクショニズム / 鈴木聡志
――その多様性と認識論上の位置づけ
第7章 エスノメソドロジーからパーソナルメソドロジーへ / 大橋靖史
――心理学研究としてのソーシャル・コンストラクショニズムの可能性
第8章 子育てをめぐるディスコースの分析 / 青野篤子
――母子のイメージに着目して
第9章 ソーシャル・コンストラクショニズムからみた発達研究 / 東村知子
――新たな言説の創出を通して主体性の回復をめざす協同的実践
第 IV 部 対人支援実践とソーシャル・コンストラクショニズム
第10章 ナラティブ・セラピーの実践 / 国重浩一
――支配的なディスコースの脱構築
第11章 ホームレス支援における新たな言説の創造 / 熊倉陽介
――ハウジングファーストの社会的構築の展開
第12章 統合失調症をもつ患者の理解と支援 / 金原明子
――社会によってもたらされるものを理解し問い直す
第13章 クライエントのポジショニングと“極太ペン”としての診断 / 綾城初穂
――アスペルガー障害をめぐるやりとりについてのディスコース分析
第14章 失語症者の「主体性」の社会的構築 / 能智正博
――会話パートナーの実践を手掛かりに
おわりに /大橋靖史
関連情報
安達映子 評 (『こころの科学』224号 2022年7月)
https://www.nippyo.co.jp/shop/magazine/8817.html
書籍紹介:
自著解説 (田中彰吾の心理学 & 哲学研究室ホームページ 2021年12月28日)
https://embodiedapproachj.blogspot.com/2021/12/blog-post_28.html?spref=tw



 書籍検索
書籍検索