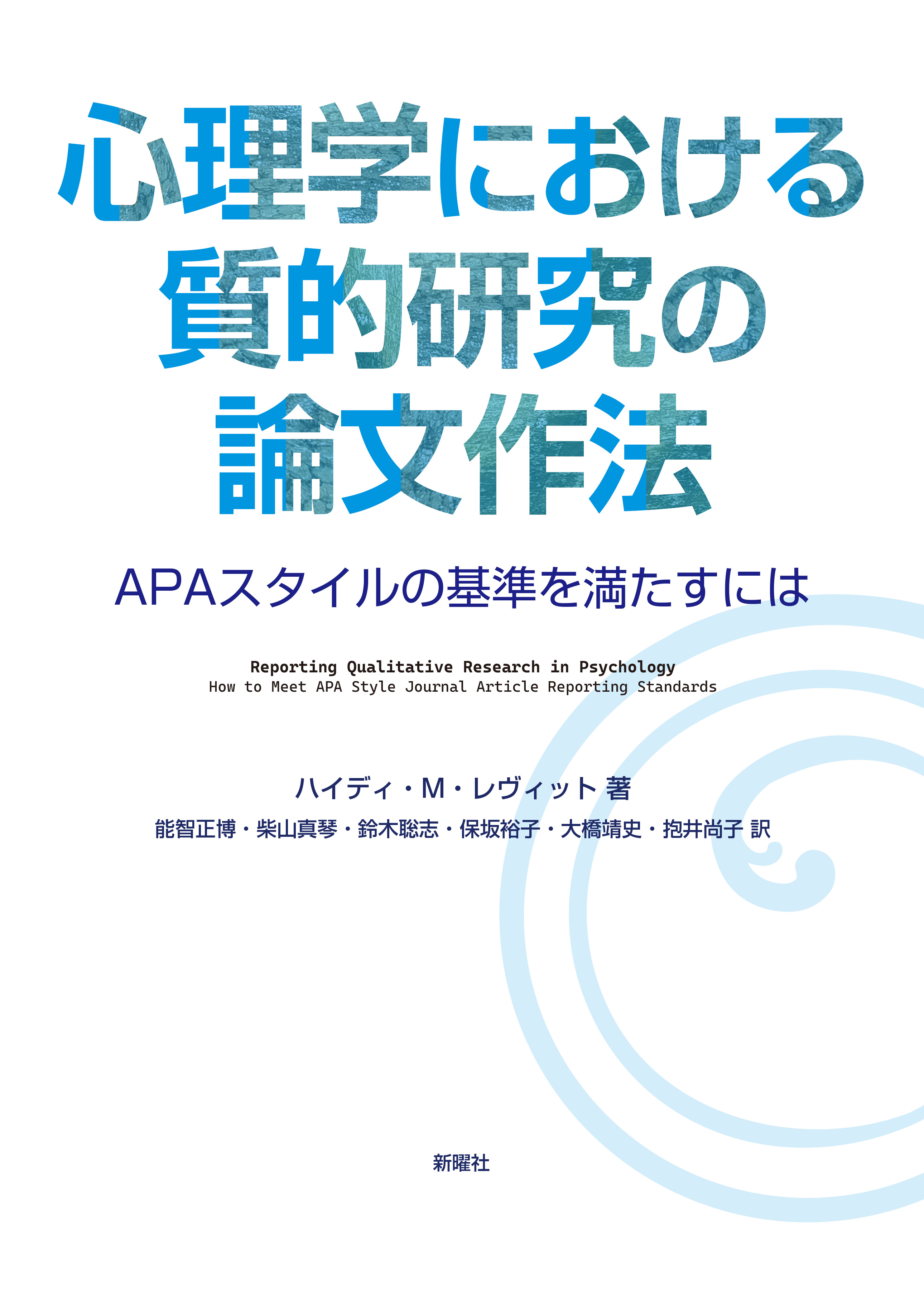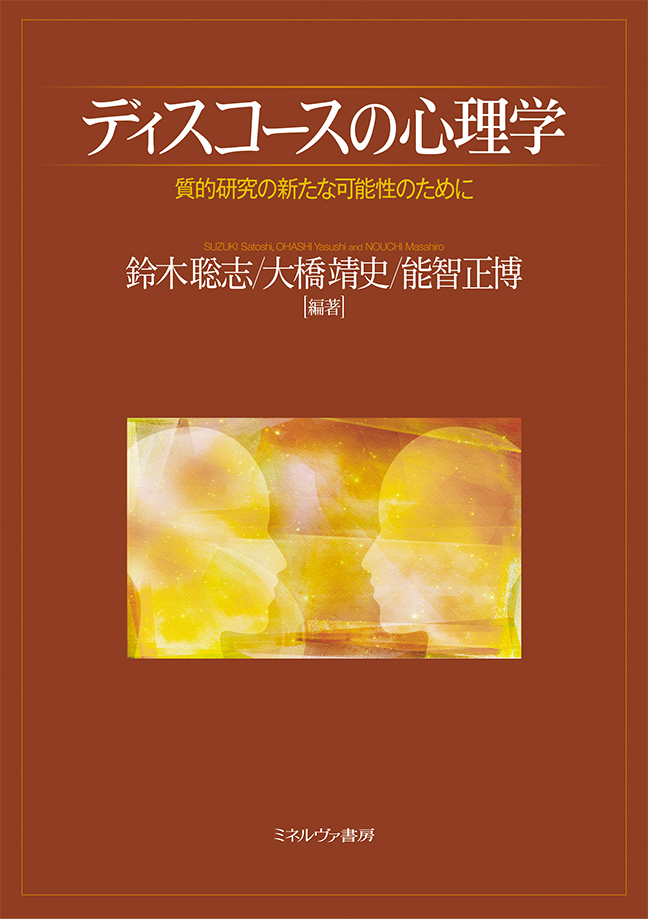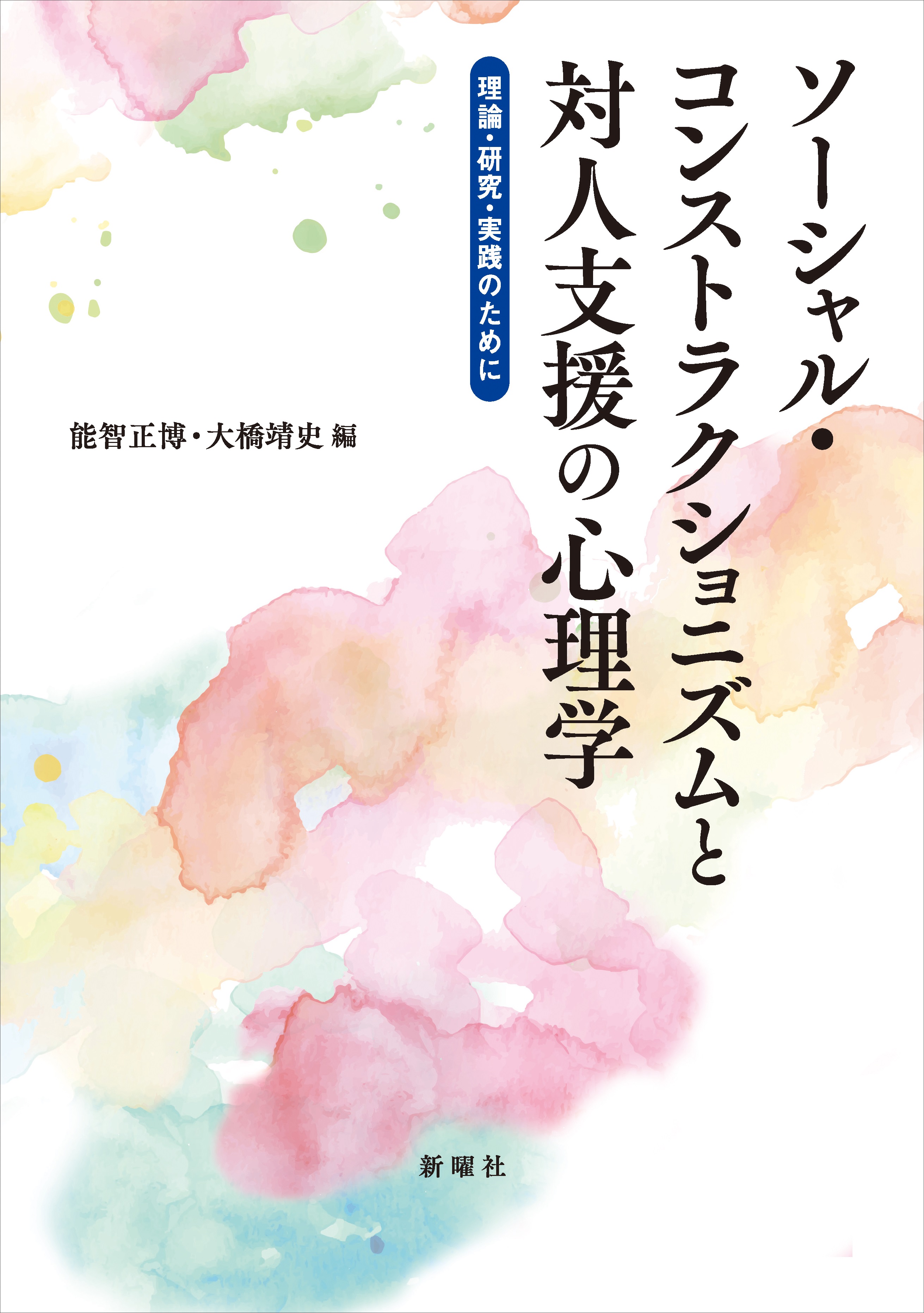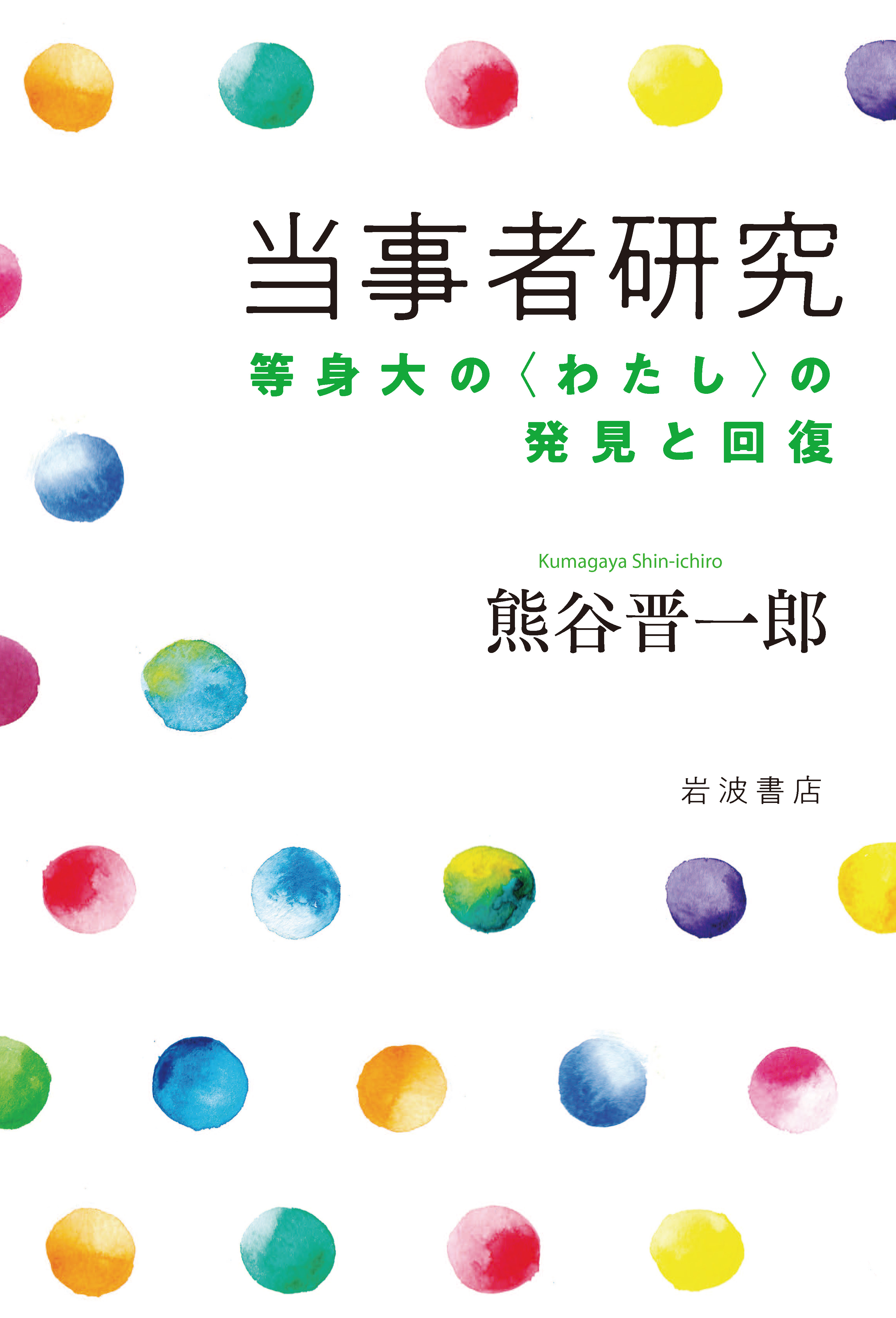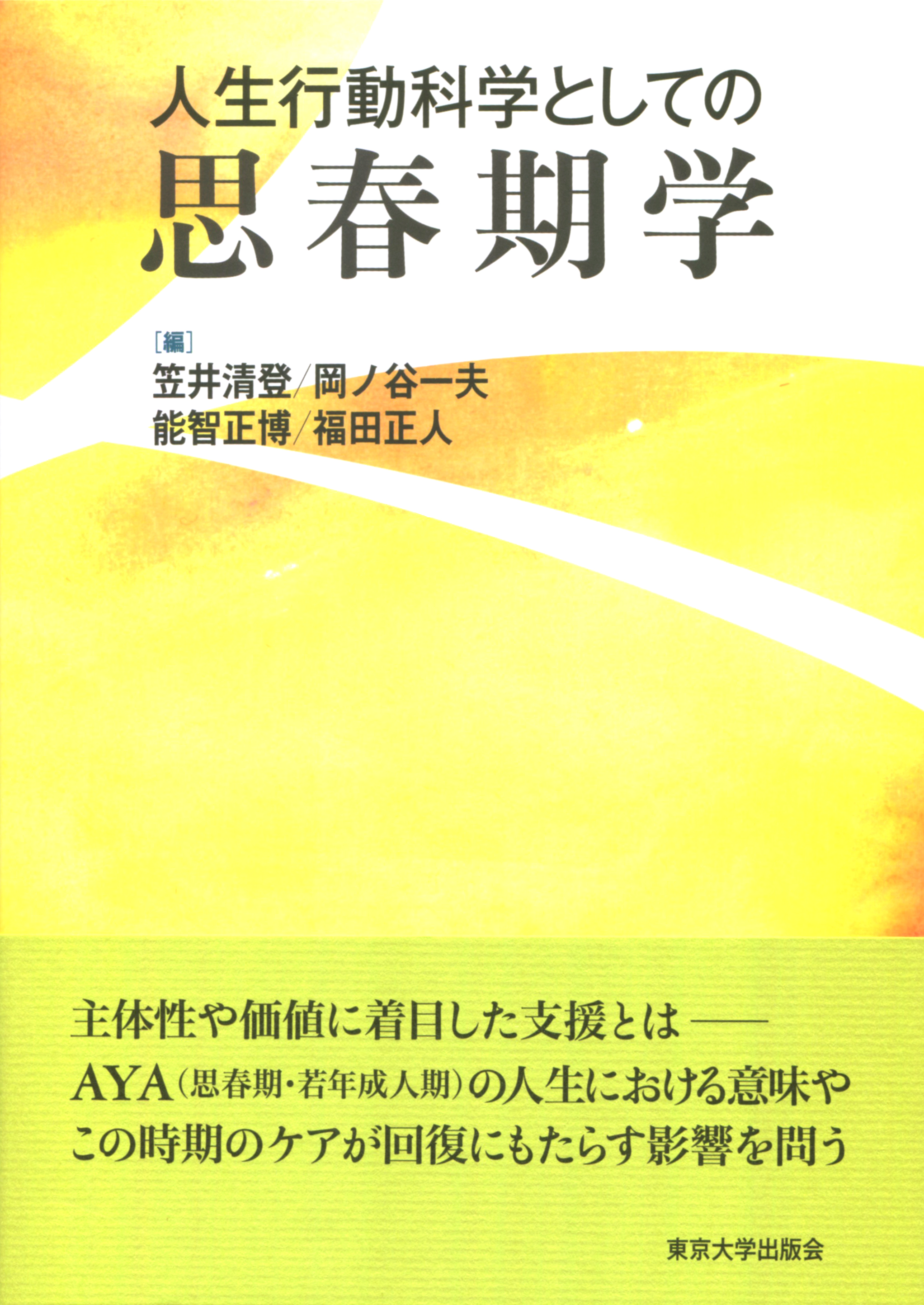
書籍名
人生行動科学としての思春期学
判型など
336ページ、A5判
言語
日本語
発行年月日
2020年9月18日
ISBN コード
978-4-13-011148-5
出版社
東京大学出版会
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
本書は、人生行動科学という立場から「思春期」をどう理解すればよいかを、第一線の研究者とその事例と関わる人たちに論じていただいたものである。「人生行動科学」という言葉はあまり聞いたことがないかもしれない。行動科学は人間の行動を実証的に研究して法則やモデルを作っていこうとする学問の総称なのだが、厳密な実証性を担保しようとすると、比較的短期間で完結する客観的に観察可能な行動が対象にされることが多い。ただ、私たちが日々生きている実生活は人生と呼ばれる長い時間の流れのなかにあり、そうした流れのなかでこそ喜怒哀楽が生じ、夢や希望も生まれる。自分や周囲の他者も含めて人を理解するとは、そうした人生という文脈を考慮した視点が必要になるだろう。本書は、「人生」を前にしてそれをどう科学的な言葉で対象化できるのかという大きな問題に向かい合い、格闘している著者たちの中間報告とも言える。
テーマとなるのは「思春期」とその周辺の「AYA世代」の理解である。まさにこの時代は自分の「人生」が意識され始め、それを展望しようとし始める時期である。ただ中にいる少年・少女にとっては、身体や社会環境など様々な変化のなかで心理的にも不安定になる時期であり、困難との出会い、不安、格闘、克服など様々なドラマがそこで生じる。これまで数え切れないほどの数の文学がこの時期を対象としてきたのは、この時代のそうした性格によると思われる。それに対して新たに科学的視線を向けたことの意義は、学の発展という意味で大きいことはもちろん、様々な問題を抱えがちな現代の思春期やAYA世代の若者をサポートする実践上のヒントももたらすことにもなるだろう。
本書は大きく5つのセクションに分かれており、それぞれ3人から6人の著者が独自の切り口から思春期やAYA世代について論じている。詳しくは以下の「目次」を見ていただいた方がよいのだが、人生という視点からそうした時代をどのように検討し分析すればよいのか理論的に検討したセクションから、そこで生きる人たちの現状と困難、そしてそれをどう支援すればよいかを論じたセクションまで、内容的には非常に幅広く話題も多岐にわたっている。読者の方々は、まずは章のタイトルを見て関心のある章から読み、それから読みの範囲を広げていただければと思う。その過程で、思春期やAYA世代にいる読者の方々は自己理解が深まり、これから生きていく上でのヒントが得られると、私たち筆者としてはうれしい。さらに、これをきっかけに「人生行動科学」に関心をもち、今後の研究の発展に貢献してもらえるような若い学生の皆さんが育ってくれるとしたら、私たちにとっては望外の喜びである。
(紹介文執筆者: 教育学研究科・教育学部 教授 能智 正博 / 2021)
本の目次
I 私たちはどう生きるかを脳・生活・人生から考える
1 人生行動科学――思春期/AYA世代に培う主体性(笠井清登)
2 生活史戦略から考える人生(長谷川寿一)
3 言語の起源――思考かコミュニケーションか(岡ノ谷一夫)
4 主体性と生活の脳基盤(柳下 祥)
5 ライフストーリーから考える「いかに生きるか」(能智正博)
コラム1 インターネットと生活行動習慣(森田正哉)
II AYA世代の健康と発達を調べる
6 思春期保健への国際的取り組み(安藤俊太郎)
7 世界の出生コホート研究と東京ティーンコホート(山崎修道)
8 AYAの脳科学(小池進介)
コラム2 セクシュアリティと主体性(正岡美麻)
III 精神的・身体的不調からの回復を支援する
9 人とのかかわりを通じて――発達障害と精神療法(青木省三)
10 言葉と内省にもとづいて――精神分析的心理療法(笠井さつき)
11 行動を手がかりに――認知行動療法と行動活性化(横山仁史・岡本泰昌)
12 主体性を大切に――求められる支援とは(山口創生)
13 心と身体の統合的支援(近藤伸介)
コラム3 学校改造計画――若者の当事者研究(向谷地生良)
コラム4 バリアフリーとコ・プロダクション(熊谷晋一郎)
IV AYAの人生行動を支援する
14 学校場面の心理発達と支援(市川絵梨子)
15 AYA世代と居場所(中原睦美)
16 いじめ・ひきこもり支援(平野直己)
17 自殺予防・危機介入(大島紀人)
18 加害少年の取り返せない過去に寄り添う(青島多津子)
19 身体・知的・精神の重複障害のある人のトランジション(熊倉陽介)
コラム5 トラウマインフォームドケア(亀岡智美)
コラム6 ピアサポートとリカバリーカレッジ――経験者だからこそできること(宮本有紀)
V 生活の中で人生行動科学を体験する
20 精神障害の子どもの親の立場から(島本禎子)
21 医療を必要とする子供の家族の立場から(三ツ井幸子)
22 ユースメンタルサポートColorの活動を通して(田尾有樹子)
コラム7 メディアを活用したAYAの健康啓発(中野彰夫)



 書籍検索
書籍検索


 eBook
eBook