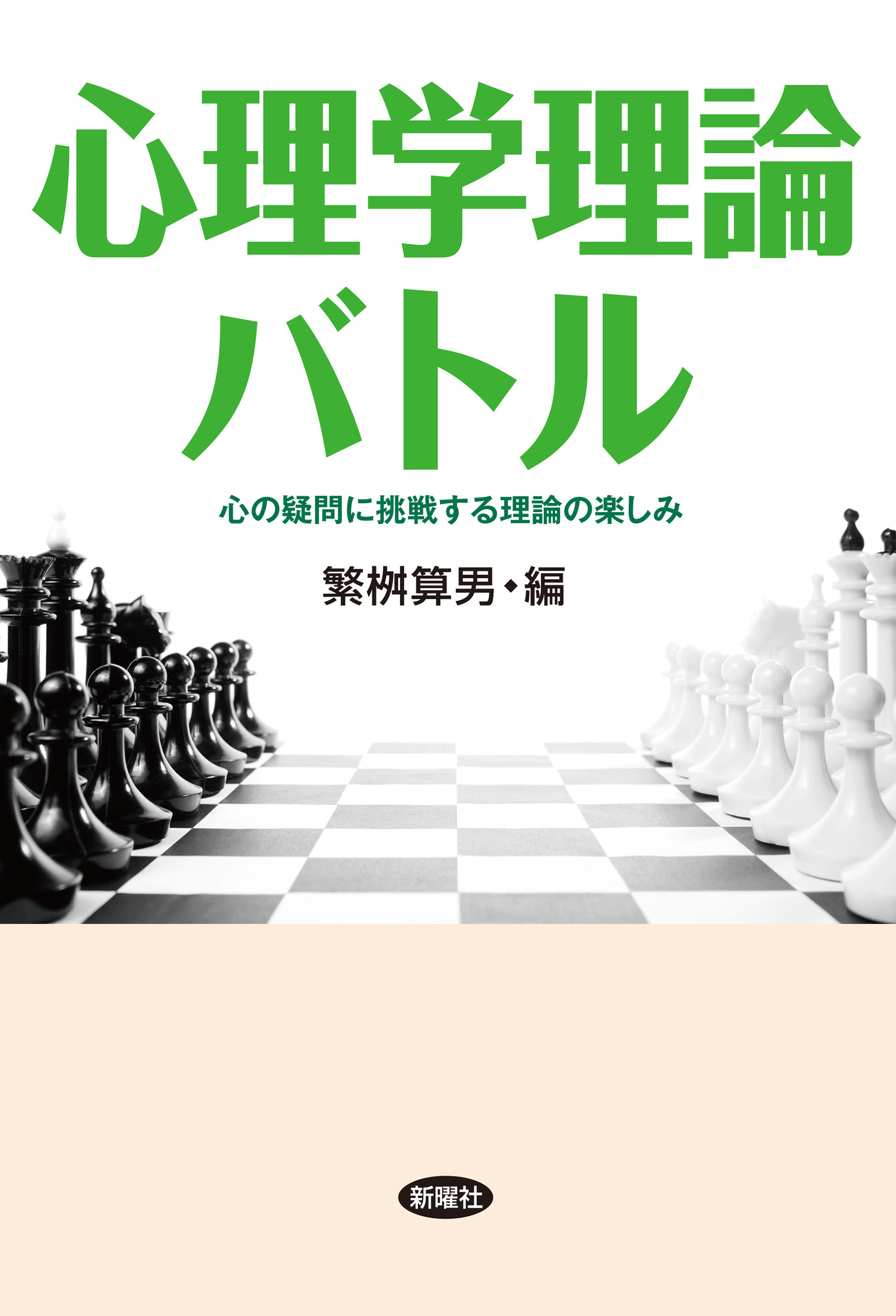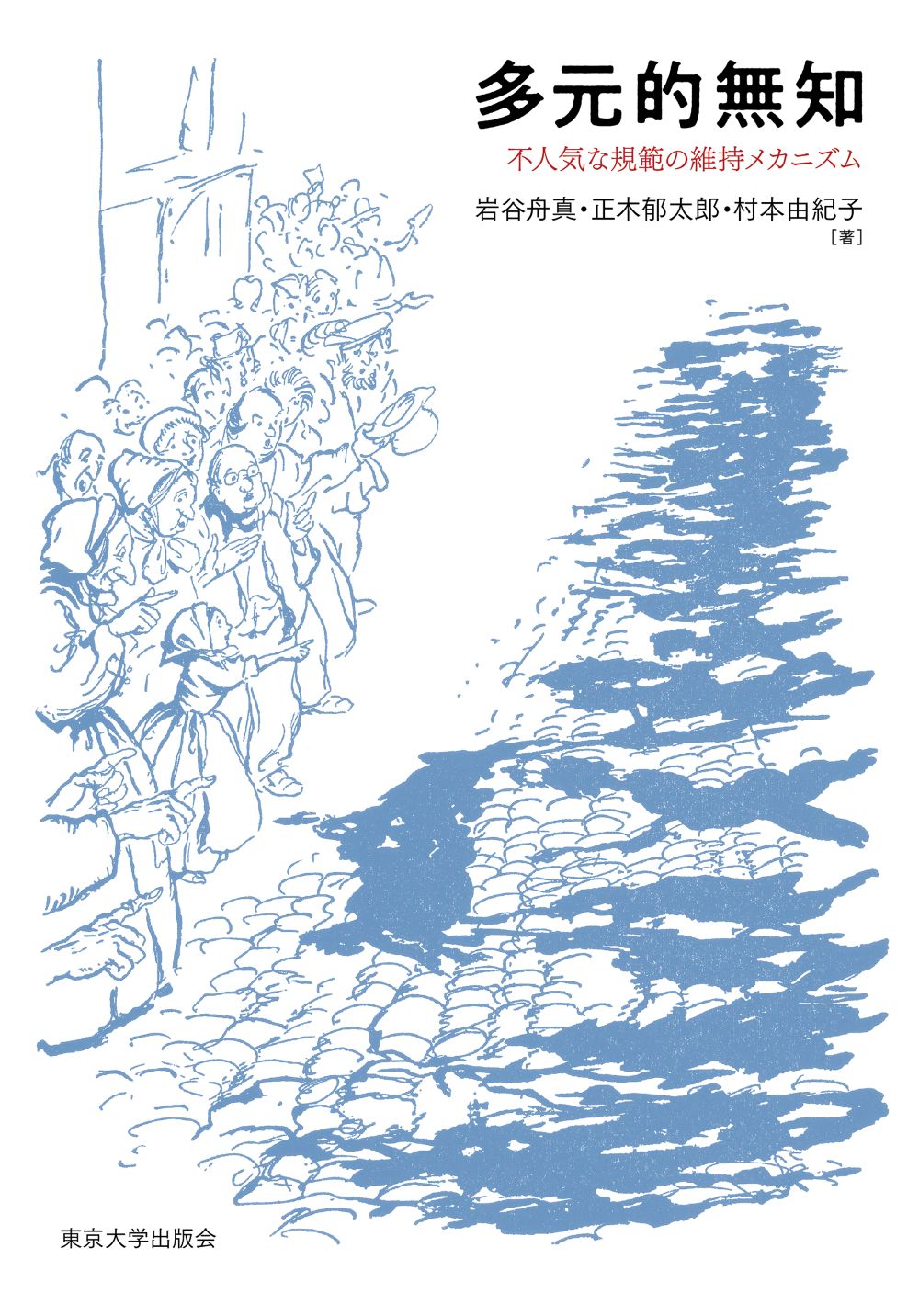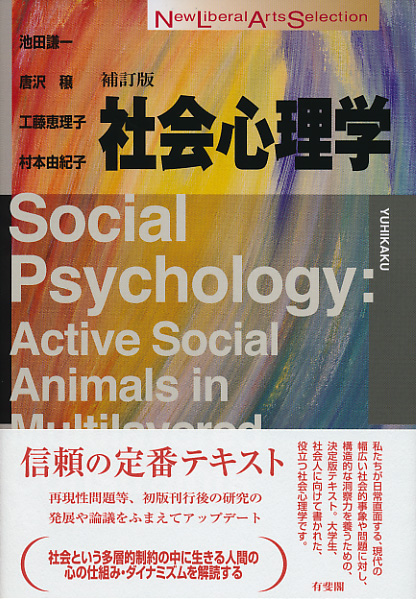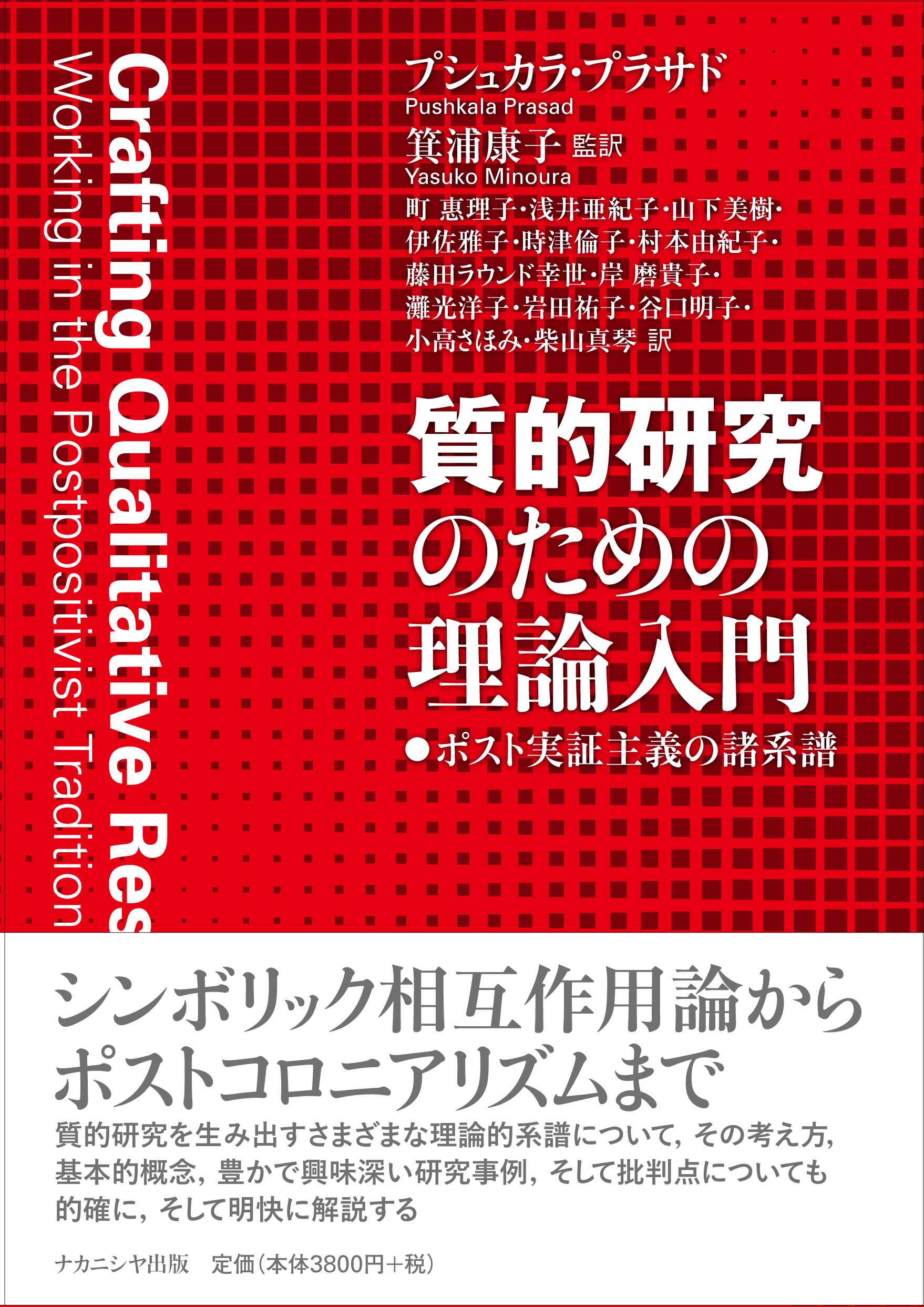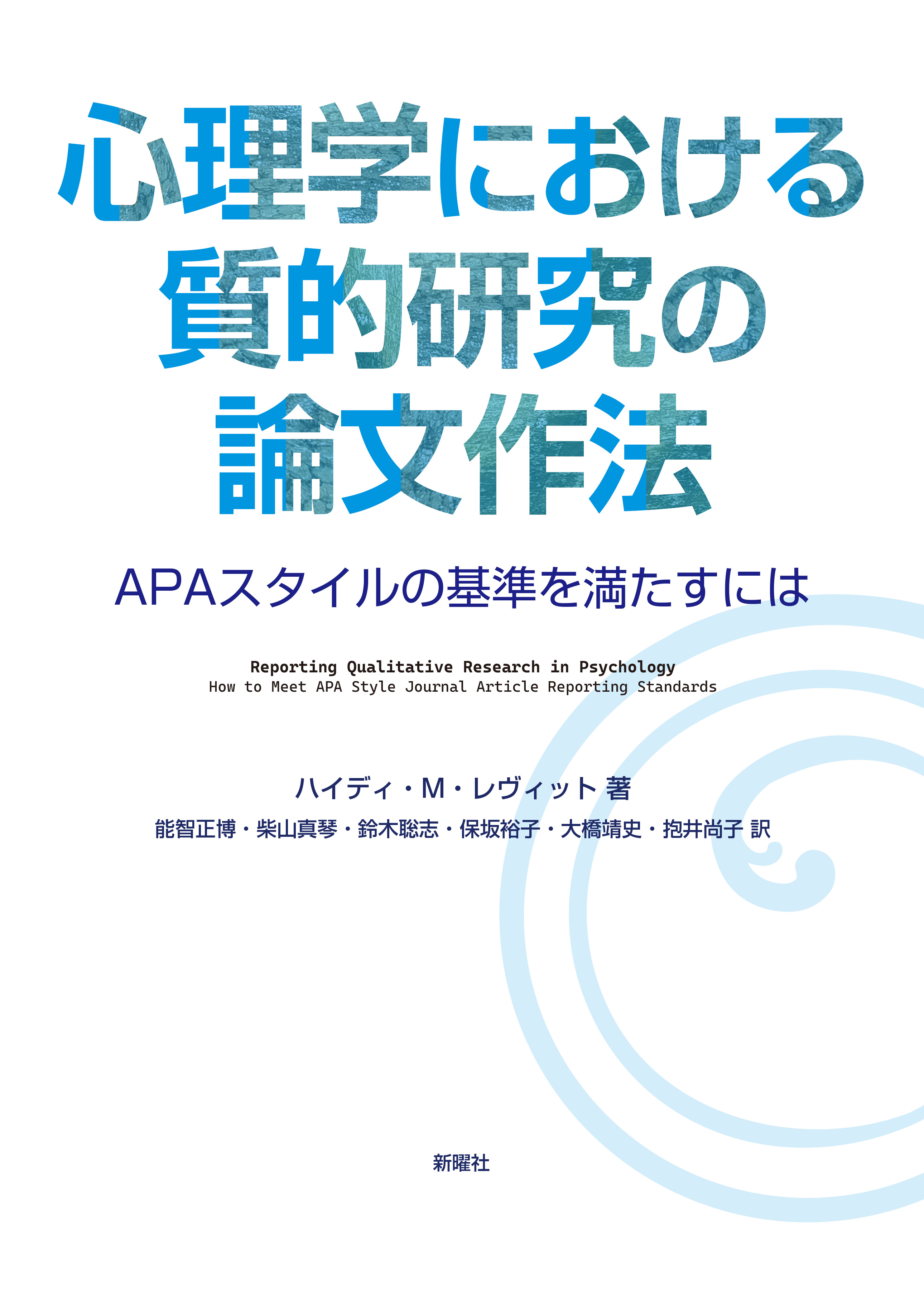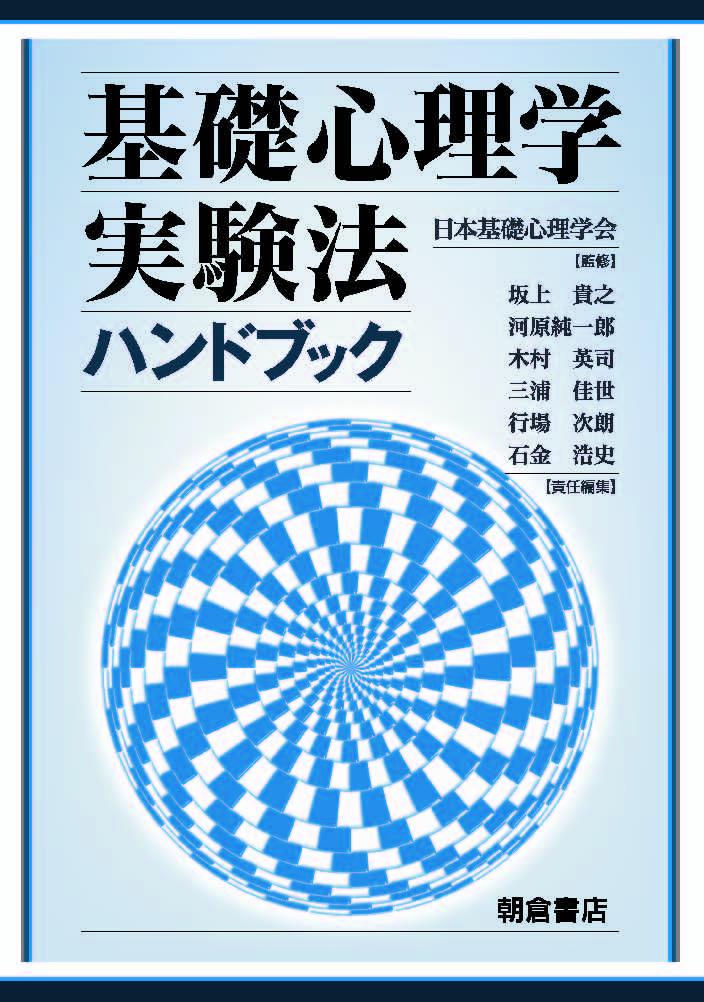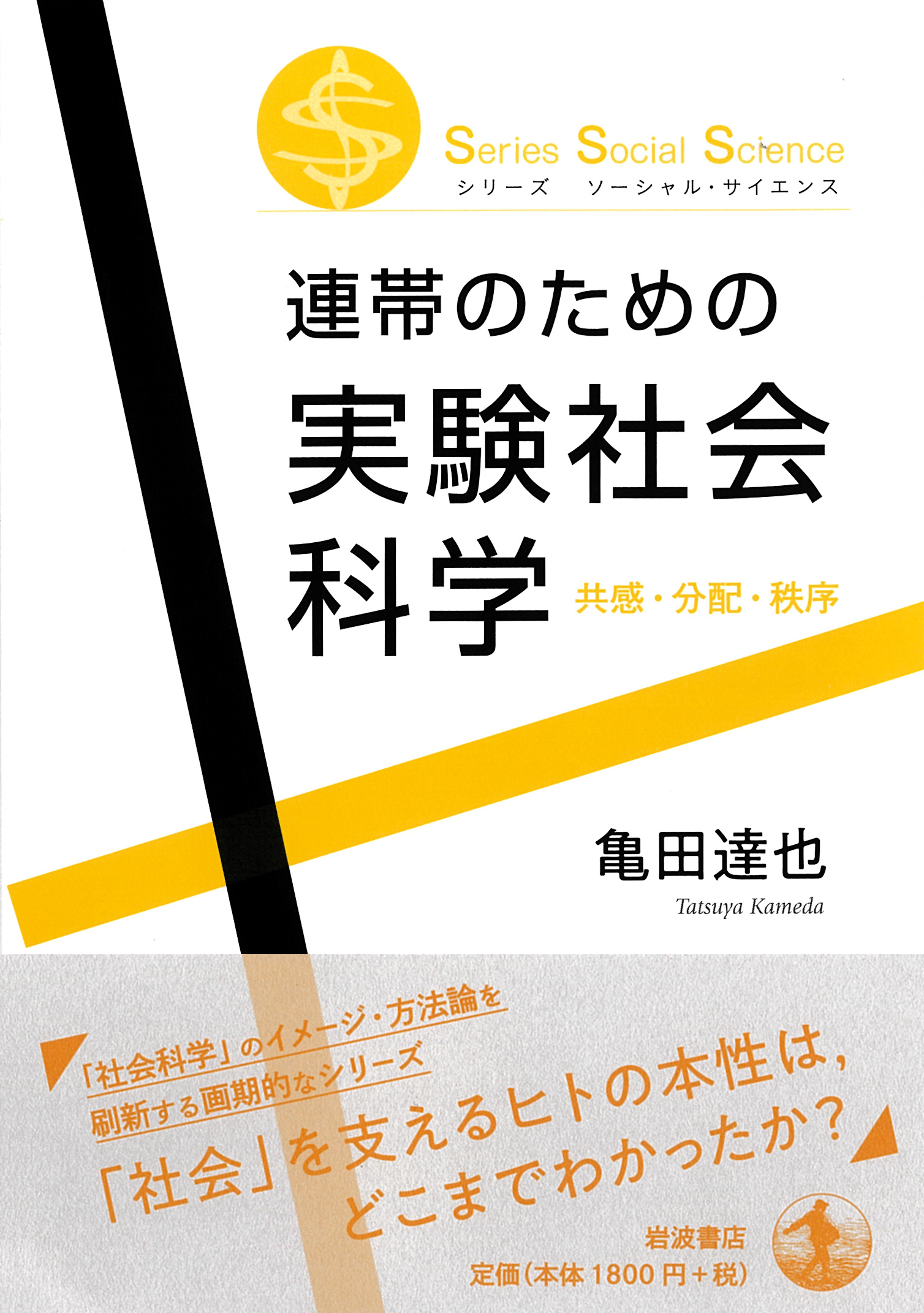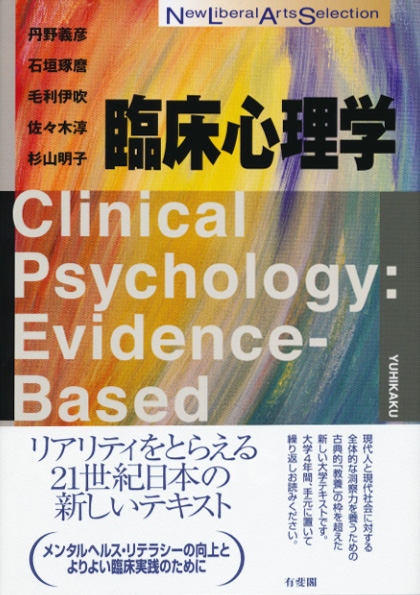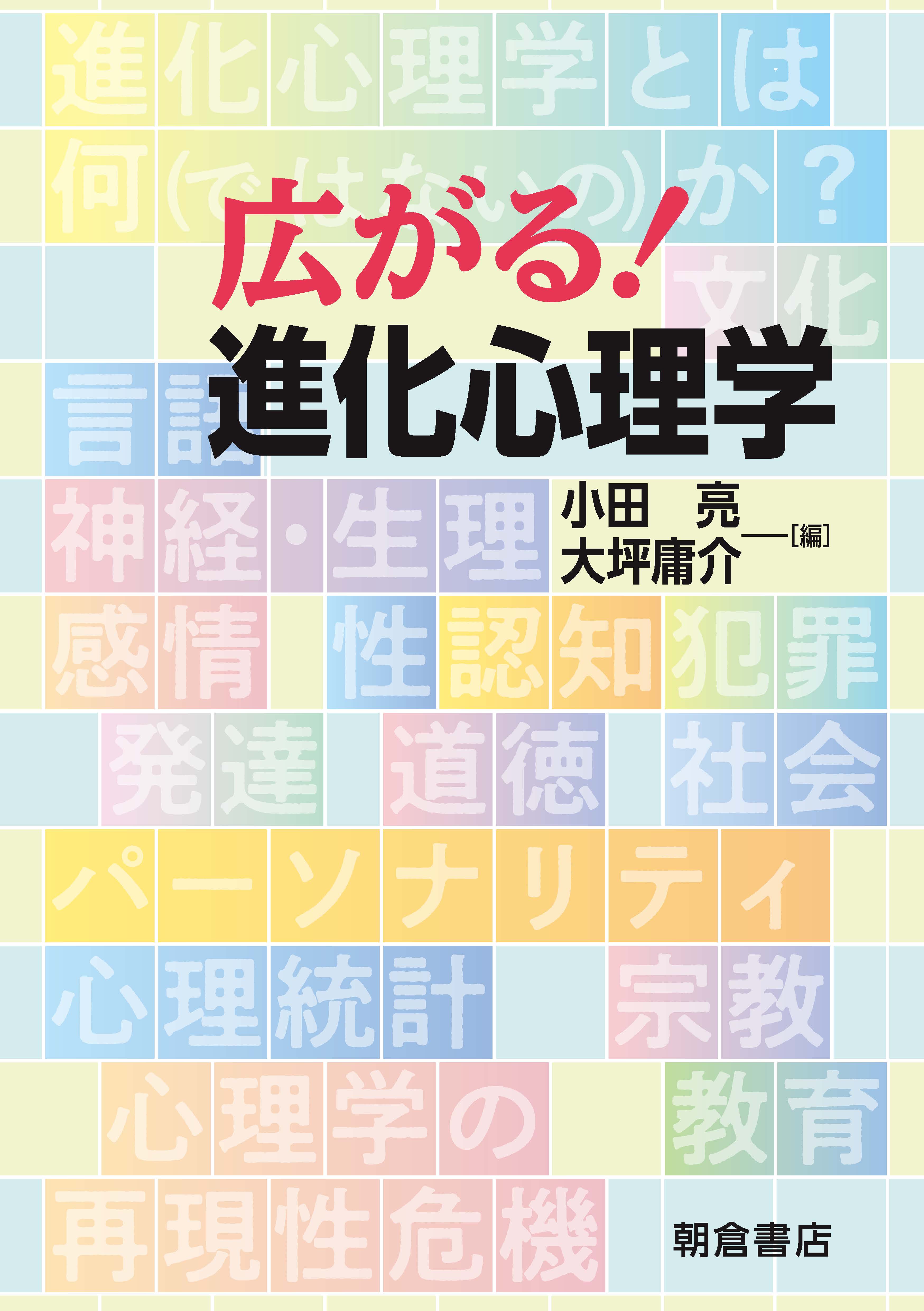心理学を学び始めた大学生の頃、手にしたテキストにはたくさんの「理論」が載っていました。当時の私はそれらの理論を知識として学ぼうとするだけで、理論をめぐって交わされる「バトル (闘い)」のことなど、考えもしませんでした。しかし、大学院進学後、質的研究の方法論に関する演習授業の中で、始めたばかりのフィールド研究の観察記録を報告したところ、先生から「あなたの見ているフィールドで起きていることは、今の社会心理学の集団理論では説明できないんじゃないの?」と言われました。「既存の理論を疑う」という研究姿勢について教わったのは、その時が初めてです。この授業での学びは、私にとって「既存の理論に対して健全なバトルを挑みつつ、やがてはオリジナリティの高い理論を自ら構築する」という、研究者としての大切な目標を認識するきっかけになりました。
本書にはまさに、心理学の理論構築の過程でなされた (もしくは現在進行形の) バトルの具体例が数多く紹介されています。章ごとに一つのテーマに関わる複数の理論が取り上げられ、比較されます。各章の著者は、特定の理論の明確な提唱者という場合もあれば、どの理論にも一定の理解を示しつつ、それらの統合を目指している場合もあります。比較される理論がいかなるレベルで異なっているかも章によって多彩です。たとえば2章では、子どもの発達段階に関するピアジェとヴィゴツキー (いずれも1896年生まれで20世紀を代表する心理学者) の二大理論が紹介されています。理論には両者の発達観の違いがよく表れており、ピアジェの理論が個人に内在する認知能力の普遍的な発達過程に焦点を当てているのに対して、ヴィゴツキーの理論は他者との交流が発達に及ぼす影響を重視しています。また、3章は「パーソナリティ特性はいくつあるのか」という問いを掲げ、現時点で最も支持されている5因子モデル「ビッグファイブ」と、それに対するいくつかの批判について検討しています。
私が担当した7章では、異文化に生きる人々の間に心理・行動傾向の差異が生じるメカニズムを解き明かそうとする、二つの理論的視座 (文化心理学アプローチと適応論アプローチ) を紹介しています。両者はいずれも、マクロな社会環境とマイクロな個人の心との相互構成過程を探究するという基本理念を共有していますが、どの方向から光を当てるかという点では大きく異なっています。文化心理学アプローチでは、「社会環境は個人の心に影響を与えるだけの単なる外的要因ではなく、心の内に埋め込まれている」と仮定し、内的な心理過程を解き明かそうとします。他方、適応論アプローチでは、個人の心の性質を「特定の社会環境の下で生き抜くための適応戦略の集合」として捉え、社会環境の特質を見極めることを目指しています。この章では、両者の違いが明確に表れた実証研究の具体例を挙げながら、心と文化に関する研究の今後の方向性を展望します。
本書の副題にある通り、読者は、こうした多彩な理論バトルに触れることによって「心の疑問に挑戦する理論の楽しみ」を知ることができると思います。どの章からでも、関心のある領域を選んでページをめくってみてください。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 村本 由紀子 / 2023)
本の目次
1章 錯視とは何か──エラー説と副産物説 (北岡明佳)
1 錯視の副産物説
2 記憶色説
3 ヒストグラム均等化説
4 色の対比か色の恒常性か
【Q&A】
2章 発達の二大理論と次にくる理論
──ピアジェの発達段階説とヴィゴツキーの社会的相互作用説 (上原 泉)
1 ピアジェの理論
2 ヴィゴツキーの社会的相互作用説
3 ピアジェの説 vs.ヴィゴツキーの説
4 これまでの理論や実践に足りなかった視点と今後の研究
【Q&A】
3章 パーソナリティ特性はいくつあるのだろうか──理論と予測 (小塩真司)
1 パーソナリティ概念とは
2 ビッグファイブ・パーソナリティ
3 ビッグファイブに対する批判
4 批判をどのように考えるか
【Q&A】
4章 なつかしさはなぜ起こるか──単純接触効果と自伝的記憶、デジャビュ (楠見 孝)
1 なつかしさと単純接触効果
2 なつかしさと自伝的記憶
3 デジャビュとなつかしさ
4 まとめ
【Q&A】
5章 ヒトはなぜ協力するのか──進化心理学と文化進化論 (小田 亮)
1 「万能酸」としての自然淘汰理論
2 進化心理学とは何か?
3 「文化的動物」としてのヒト
4 ヒトはなぜ協力するのか?
5 「強い互恵性」はあるのか?
【Q&A】
6章 幸福には道徳が必要か──快楽主義・幸福主義・原始仏教 (杉浦義典・丹野義彦)
1 幸福研究の三つの理論──快楽主義・幸福主義・原始仏教
2 強いネガティブ感情が不適応とはいえない──快楽主義への反論
3 一貫した道徳基盤から反社会的な行動が生じうる
──幸福につながる道徳とは
4 マインドフルネスは道徳(思いやり)を欠くと逆効果になる
──原始仏教と幸福主義への支持
5 止揚
【Q&A】
7章 「心の文化差」はあるのか──個人へのアプローチ、社会へのアプローチ (村本由紀子)
1 「文化的存在たる個人」への文化心理学アプローチ
2 文化的行動を引き出す「社会環境」への適応論アプローチ
3 二つのアプローチ、そしてその先へ──「心と文化」研究の課題と展望
【Q&A】
8章 人間は論理的か──進化心理学と二重過程理論 (山 祐嗣)
1 領域固有 対 領域普遍
2 進化心理学 対 二重過程理論
3 スローはファストを飼いならせるのか──歴史的自然実験
4 おわりに
【Q&A】
9章 経済人は合理的でないといけないのか──形式的合理性と実質的合理性 (竹村和久)
1 合理性と社会的行為
2 経済行動と形式的合理性
3 合理的な選好関係の経験的テスト──非循環性の経験的検討
4 顕示選好と合理性
5 意思決定の不合理性と顕示選好
6 まとめと今後の展望
【Q&A】
10章 後悔しない意思決定は可能か──直感的に決めることも悪いとは限らない (繁桝算男)
1 問題
2 人間は間違える
3 人は基本的に合理的である──当たり前から導かれる主観的期待効用理論
4 まとめ──後悔しない意思決定のために
【Q&A】
11章 脳機能計測でわかること、わからないこと
──fMRIを用いた研究で「メカニズムを解明」することは可能か不可能か (四本裕子)
1 脳機能研究の歴史と方法
2 fMRIの測定と単変量解析
3 多変量解析
4 混乱はどこからくるのか?
5 神経デコーディング
6 脳機能計測で何がわかって何がわからないのか
【Q&A】
12章 心理学と理論 (理論心理学)──心理学史の見地から (西川泰夫)
1 心理学における理論とは
2 心理学における理論の意義──理論の予測と再現性、日本独自の心理測定法と理論化の取り組み
3 独自の理論体系──革新的行動論者の排除すべき“理論”観



 書籍検索
書籍検索