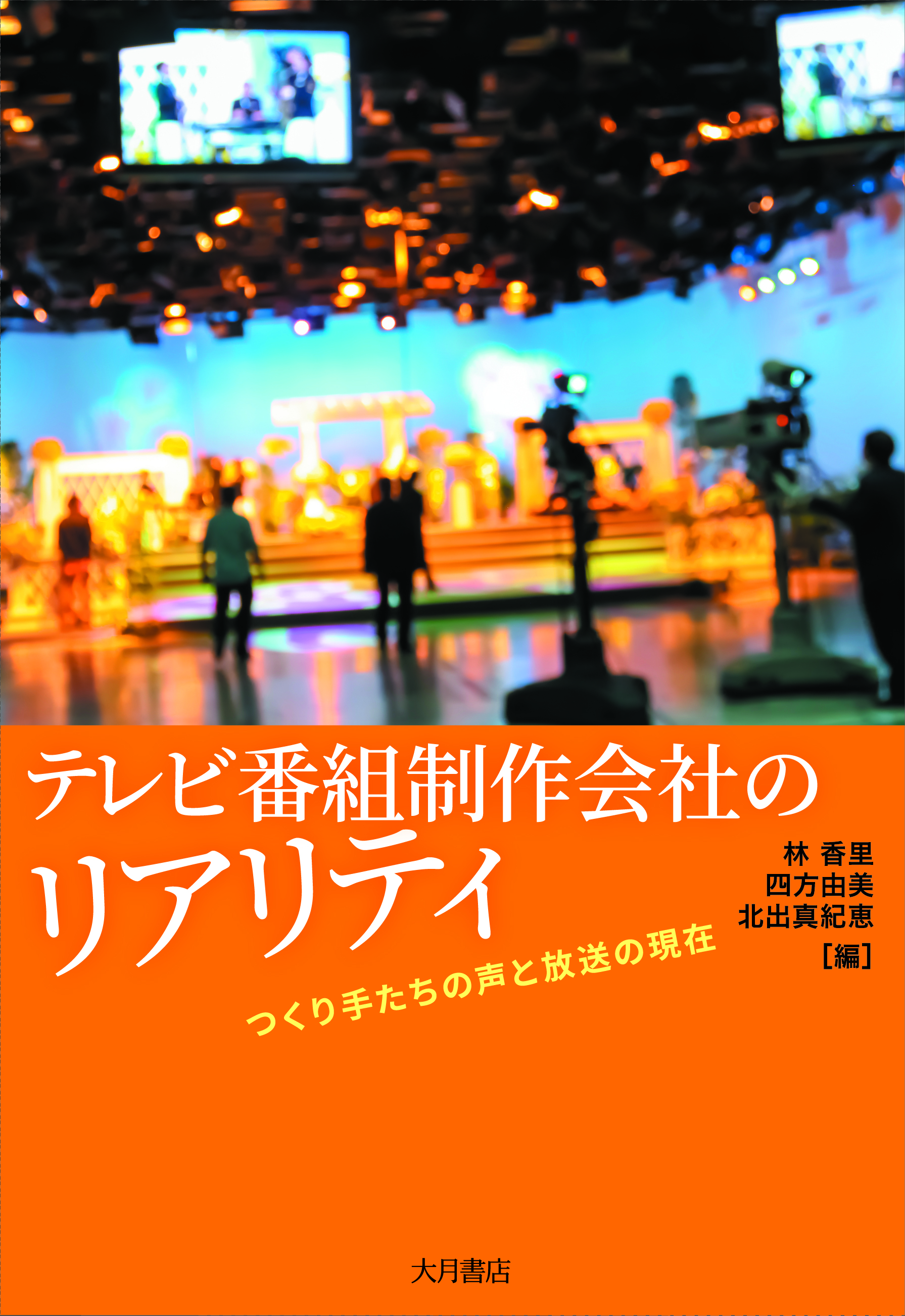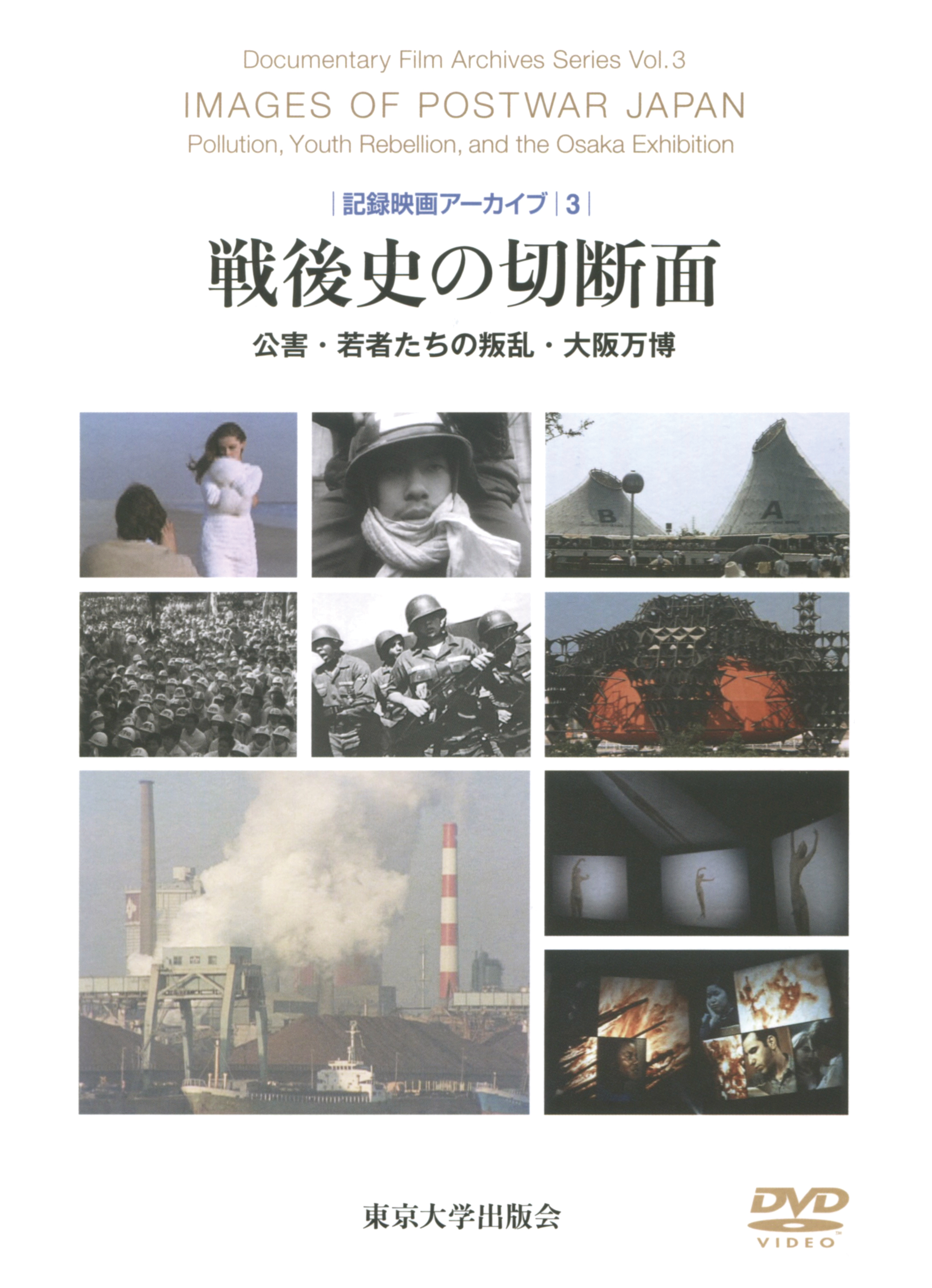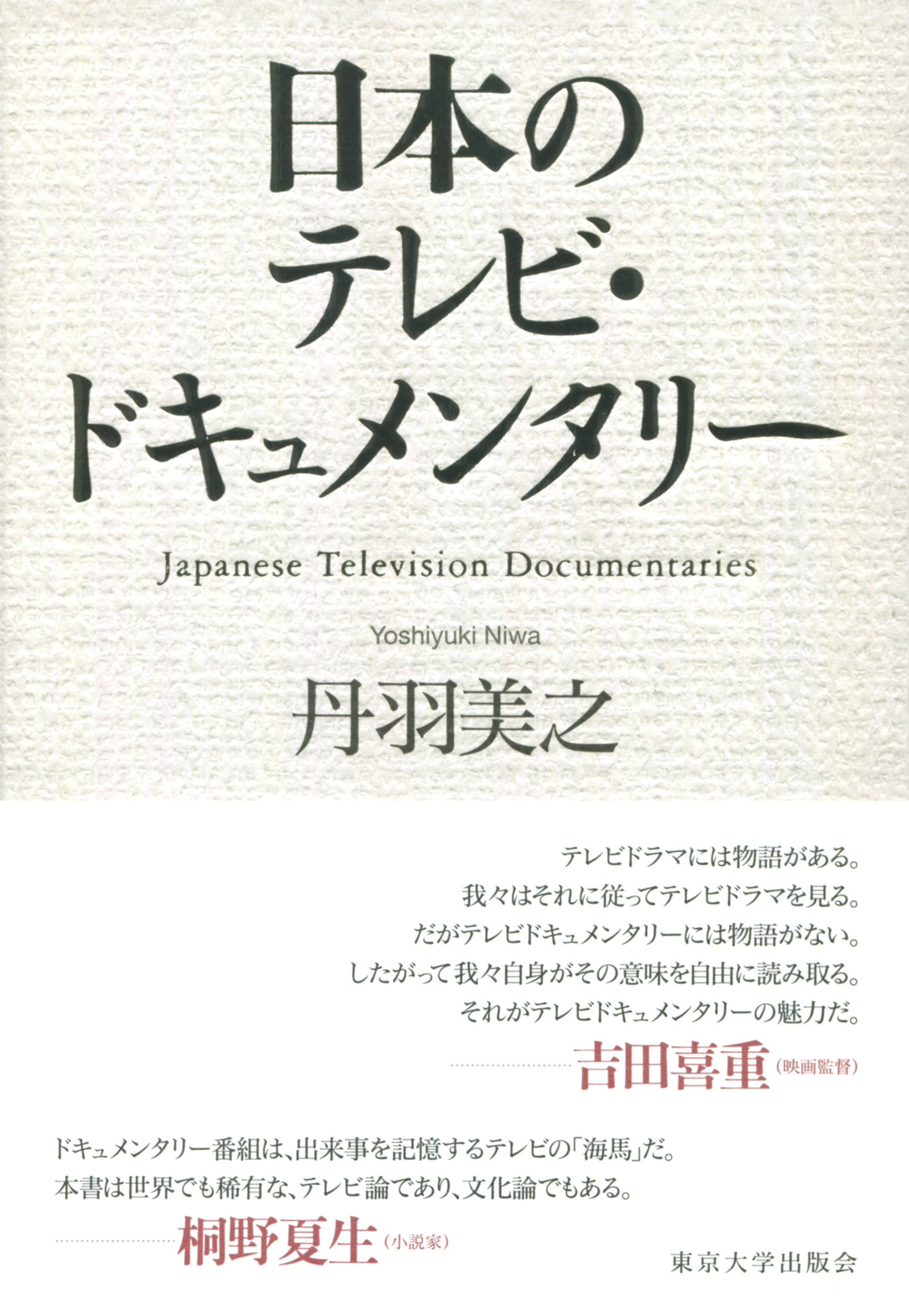
書籍名
日本のテレビ・ドキュメンタリー
判型など
288ページ、四六判
言語
日本語
発行年月日
2020年6月17日
ISBN コード
978-4-13-050201-6
出版社
東京大学出版会
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
この半世紀あまりの間に、日本のテレビは目覚ましい発展を遂げ、産業的にも文化的にも大きな影響力を持つようになりました。しかし、テレビ研究やテレビ批評の広がりという点では、残念ながら非常に遅れていました。その大きな理由のひとつは、テレビ番組のアーカイブが貧困だったからです。過去に放送された番組自体が残っていない。あるいは残っていても公開されていない。結果として、テレビに対する研究や批評は大きく停滞することになりました。
しかし近年、状況は大きく変わりつつあります。NHKアーカイブスや放送ライブラリーなど、日本でもようやくテレビ・アーカイブの整備がはじまりつつあります。これまでテレビでは、ドキュメンタリーやドラマ、ニュースやスポーツ、バラエティや歌番組、アニメやCMなど、膨大な数の番組が放送されてきました。これらの番組はテレビ史の貴重な記録であるだけでなく、時代を生き生きと映し出す鏡でもあります。今後はこれらのアーカイブを用いて、テレビ史や現代史を検証する作業が様々な角度から進められていくことでしょう。
本書はまさに、このようなアーカイブ時代に生まれた新しいテレビ研究の試みです。テレビの制作者たちはどのように時代と格闘し、戦後日本を記録してきたのか。新たな方法論をどのように開拓し、テレビの可能性を切り拓いてきたのか。本書は、アーカイブに眠る数々の番組と、それを作り出した制作者たちの言葉を通して、日本のテレビ・ドキュメンタリーの闘いと挑戦の歴史を明らかにします。
テレビの草創期に『日本の素顔』を作った吉田直哉、民放ドキュメンタリーの礎を築いた牛山純一、テレビの可能性を極限まで追求した萩元晴彦・村木良彦、様々なタブーに斬り込んだ田原総一朗、虚実ないまぜの作風で異彩を放った木村栄文、女性ドキュメンタリストの先駆けである磯野恭子、現在は映画監督として活躍する是枝裕和……。本書はこれまでにない「テレビ番組論」であると同時に、番組から見た「戦後社会論」でもあります。
テレビやジャーナリズムの歴史に興味のある人はもちろんのこと、将来ドキュメンタリーを作ってみたい人や、ジャーナリストになりたい人にもお薦めの一冊です。ネットとの本格的な融合時代を迎え、テレビとは何かが改めて問われる現在だからこそ、テレビの歴史を見つめ直すことが求められています。本書がドキュメンタリー番組の豊かな歴史に光を当て、テレビやジャーナリズムの未来を考えるための一助となることを願っています。
(紹介文執筆者: 情報学環 准教授 丹羽 美之 / 2020)
本の目次
第1章 テレビ・アーカイブの扉を開く
1 テレビ研究の貧困
2 はじまったアーカイブ研究
3 広がるアーカイブ研究
4 民放もアーカイブの公開を
5 過去を見つめ,未来をつくる
第2章 記録映画との訣別──吉田直哉と『日本の素顔』
1 録音構成からフィルム構成へ
2 記録映画との訣別
3 『日本人と次郎長』
4 偽装と素顔
第3章 人間くさいドキュメンタリー──牛山純一と『ノンフィクション劇場』
1 星の時間
2 日本テレビの第一期生として
3 『ノンフィクション劇場』の署名性
4 『ベトナム海兵大隊戦記』放送中止事件
5 テレビ民族誌『すばらしい世界旅行』
6 テレビに見た「夢」
第4章 お前はただの現在にすぎない──萩元晴彦・村木良彦と『あなたは…』
1 物語としてのテレビ
2 劇映画的手法を超えて
3 中継の思想
4 問いかけとしての『あなたは…』
5 コラージュとしての『わたしのトウィギー』
6 テレビの一九六八年
第5章 カメラとマイクという凶器──田原総一朗と『ドキュメンタリー青春』
1 テレビの青春時代
2 『ドキュメンタリー青春』
3 決死の「殴り込みコンサート」
4 若者,ジャズ,テレビ
5 テレビの自己批判
6 『朝まで生テレビ!』へ
第6章 ドキュメンタリーは創作である──木村栄文と『あいラブ優ちゃん』
1 自由奔放,変幻自在な作風
2 公害告発ではなかった『苦海浄土』
3 『筑豊の海原』の苦い経験
4 モヤモヤを吹っ切った『まっくら』
5 プライベート・フィルムとしての『あいラブ優ちゃん』
6 美しくて,哀しいものを描きたい
第7章 真夜中のジャーナリズム──磯野恭子と『NNNドキュメント』
1 ドキュメンタリー冬の時代に
2 ポスト成長期の自画像
3 鳥瞰図よりも虫瞰図
4 女性ディレクターの草分け,磯野恭子
5 ローカル発,全国へ
6 再生に挑む人々
第8章 固定しない精神で──是枝裕和と『NONFIX』
1 プロダクションの作り手たち
2 原点となった『しかし……』
3 ドキュメンタリーの再定義
4 「放送禁止歌」を放送する
5 記憶と忘却
6 テレビは終わらない
第9章 東日本大震災を記憶する──震災ドキュメンタリー論
1 ニュースの忘れ物
2 想定外の記録
3 記者たちの戸惑い
4 被災者に寄り添う
5 巨大津波の教訓
6 原発事故への問い
7 復興への道のり
8 ジャーナリズムの再起動
あとがき
関連情報
対談=丹羽美之×森達也<ドキュメンタリーの〈待つ〉姿勢、テレビ表現の豊かさ>『日本のテレビ・ドキュメンタリー』(東京大学出版会)刊行を機に (『週刊読書人』 2020年9月4日)
https://dokushojin.stores.jp/items/5f4e3a5dd3f16779a9c3c749
書評・紹介記事:
水島久光 (東海大学文化社会学部教授) 評「未だ定型を得ていないジャンルの輪郭を描く――待ち望まれた初の単著」 (『図書新聞』第3472号 2020年11月21日)
http://www.toshoshimbun.com/books_newspaper/shinbun_list.php?shinbunno=3472
鈴木嘉一 (放送評論家、元読売新聞編集委員) 評 (『GALAC』 2020年10月号)
https://houkon.jp/galac-post/no-281%ef%bc%8f2020%e5%b9%b410%e6%9c%88%e5%8f%b7/
戸邉秀明 (東京経済大学教授) 評 (朝日新聞朝刊 2020年8月29日)
https://book.asahi.com/article/13676475
石田佐恵子 (大阪市立大学教授) 評 (日本経済新聞朝刊 2020年8月8日)
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO62419400X00C20A8MY5000/
松山秀明 (関西大学准教授) 評 (北日本新聞朝刊 2020年8月1日)
(新聞研究 2020年8・9月号)
https://www.pressnet.or.jp/publication/kenkyu/200729_13685.html



 書籍検索
書籍検索


 eBook
eBook