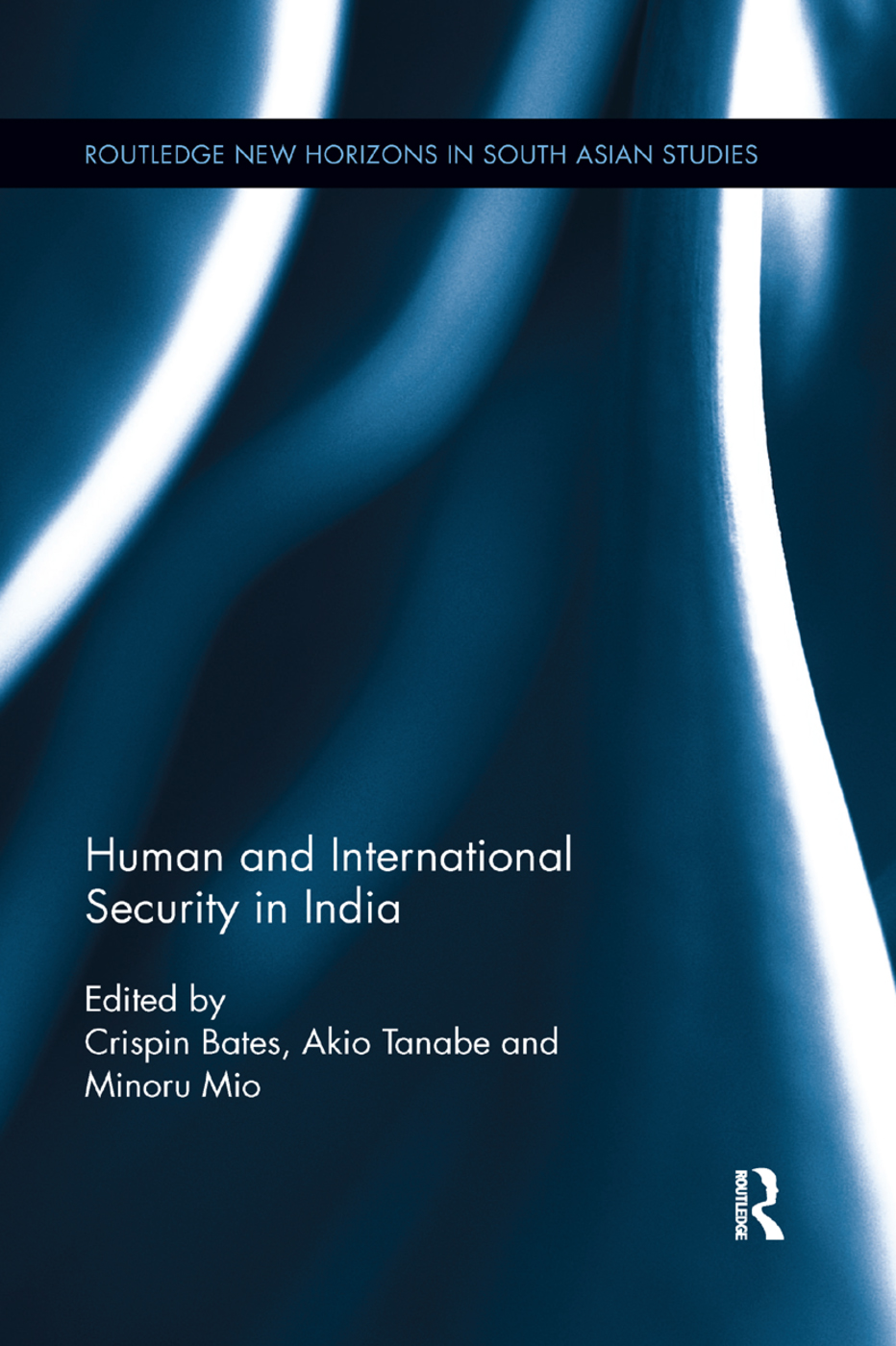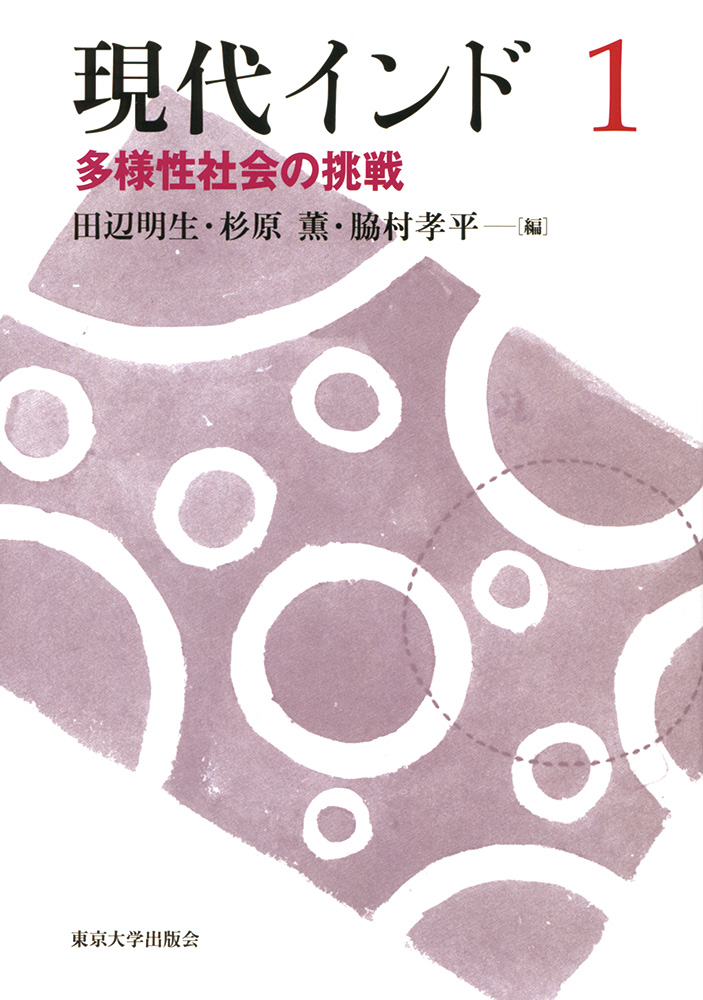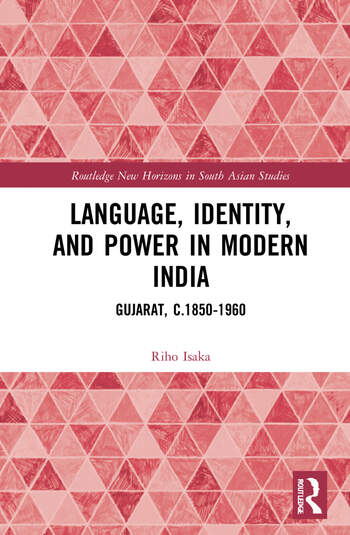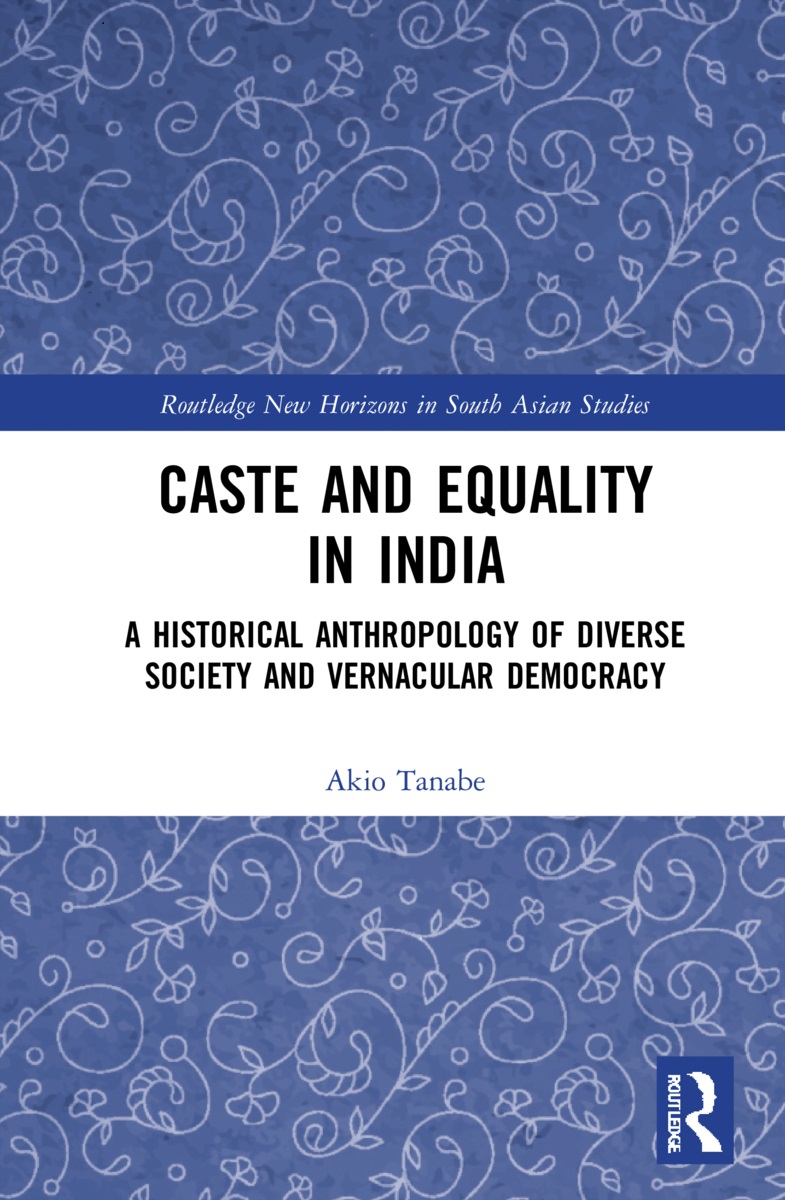
書籍名
Routledge New Horizons in South Asian Studies Caste and Equality in India A Historical Anthropology of Diverse Society and Vernacular Democracy
判型など
364ページ、ハードカバー
言語
英語
発行年月日
2021年7月30日
ISBN コード
9780367752286
出版社
Routledge
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
Caste and Equality in Indiaは、2010年に東京大学出版会から出版した『カーストと平等性 − インド社会の歴史人類学』をもとに、内容を改訂してアップデートした英文書籍である。本書は、インド地域社会におけるカーストの構造と変容を長期的な視点から明らかにすることを通じて、新たなインド社会観を提示することを目的とする。主たるフィールドはオリッサ州クルダー地方の農村社会で、扱う時代は18世紀から2006年までである。
これまでの近代インドの歴史学は、主に政治経済領域に注目し、地位と権力を軸として社会の発展や構造変化をとらえてきた。しかしそれは、インド史に通底するもうひとつの原理、すなわち<存在の平等性>という価値を見逃すものであった。本書は、植民地期以降長いあいだ、カースト・ヒエラルヒーや政治経済的な支配構造の影に隠れてきた、しかし日常生活の社会文化領域においては常に重要でありつづけるとともに、現在インド社会を律する原理として再登場しつつある、この平等性の価値を掘り起こし、1990年代半ば以降に現れつつある民衆主導の民主化の契機――<ヴァナキュラー・デモクラシー>――がそうした原理に裏打ちされた、歴史的な画期性をもつものであることを明らかにする。
ここでの焦点は、インド・オリッサの地域社会において一九九〇年代半ばから顕著となった民主化に伴う社会変容の意義を、長期の歴史のなかのカースト間関係の実践と意味の変化のなかで理解することにある。この時期からオリッサ地域社会では、従来は周縁化されていた「低」カースト民が政治過程に参加するようになり、社会政治的環境は大きく変わりつつある。そしてそれに伴って、カースト間関係を構築する実践の意味とパターンは新たな変化を遂げようとしている。
この社会変容の方向性と重要性を理解するためには、近年における制度的変化や民主的理念の浸透だけではなく、新しい地域社会のありかたをイメージしながらそれを現実化しようとする人々の行為主体性 (エージェンシー) と、そうした想像・創造の営みを支える文化と歴史の厚みに注目する必要がある。インド社会の民主化は、過去の文化と歴史の棄却の上に成立しているのではなく、建設的批判を通じたそれらの再構築においてこそ少しずつであれ可能となっている。ここでカーストは、民主化の邪魔物として単に捨て去られたのではない。むしろ民主化の過程において、カーストの存在意義についての再検討がなされ、カースト関係の再構成がなされてきたことに注目する必要がある。カーストにおけるヒエラルヒーと支配が、近年、特に低カーストから徹底的に批判され否定されてきたことは間違いない。しかし同時に、現在のオリッサ地域社会では、カーストの伝統の内奥にある存在の平等性という価値が新たな重要性を獲得し、地域社会の民主化の過程において大きな役割を果たすにいたっている。
こうした過程で人々の行為主体性が発揮されるなかで、カーストは創造的に再解釈され、多元的な社会集団が相互的な差異を承認しつつ平等な立場で協力するための文化資源として、新たな役割を担う可能性を持ち始めつつある。それは日常的な社会関係と理念が継続性を保ちながら変化を遂げ、民主化という現在的な世界状況と折り合いをつけていく過程であり、在地の日常性と世界の歴史性が接合しながら生活世界を革新していく画期的な動きである。
本書は次のような独創性を備えている。第一に本書は、歴史学研究と人類学研究をデータ的にも理論的にも融合させた本格的な歴史人類学のモノグラフである。18世紀の貝葉文書を在地で発見し、解読と分析を行った結果として、前植民地期の職分権体制およびその王権との関係が実証的に明らかになった。さらに地方文書、土地台帳、政府資料そしてオーラルヒストリーを利用し、民族誌的調査の成果と合わせることによって、地域社会の過去300年にわたる社会変容を全体的かつ緻密に描いている。
第二に本書は、カーストと王権に関する文化人類学的論争から現代インドの政治・社会状況をめぐる議論までを見据えた、深い理論的射程を備えている。特に支配とヒエラルヒーの側面ばかりが強調されてきたカーストについて、その内奥には存在の平等および供犠の価値があること、また現在の社会変容においてそれらの価値が新たな重要性を帯びつつあることを、歴史的、社会的、思想的な検討をもとに論じていることは、きわめてオリジナルな貢献である。
第三に本書は、現代インド地域社会に生まれつつあるヴァナキュラー・デモクラシーの姿を、民族誌的な厚さと現代政治の動態のなかで生き生きと描き出している。新たに政治参加を果たした低カーストや女性は、文化資源としてのカーストを創造的に再構築して、民主的協力に関する新しい社会ヴィジョンを提出している。本書は、現代インド社会・政治の実態に関する理解に資するだけでなく、民主主義の比較研究や理論研究のための新たな礎になることが期待される。
(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 教授 田辺 明生 / 2021)
本の目次
第二章 多様性の管理―フロンティア、森林コミュニティ、小王国
第三章 地域社会と王権―「カースト」、「コミュニティ」、「国家」再考
第四章 植民地初期における変容―二項対立構造の出現
第五章 植民地的二分法の確立―政治経済と文化的アイデンティティ
第六章 ポスト植民地社会における「伝統」―社会文化領域における生モラル
第七章 現金経済と派閥政治―政治経済領域における「魚の論理」
第八章 儀礼・歴史・アイデンティティ―女神祭祀からみた地域社会と国家
第九章 カーストの解釈をめぐって―下からの社会変容
第十章 ヴァナキュラー・デモクラシーに向けて―ポスト・ポスト植民地的変容
第十一章 ポスト植民地の彼方に



 書籍検索
書籍検索


 eBook
eBook