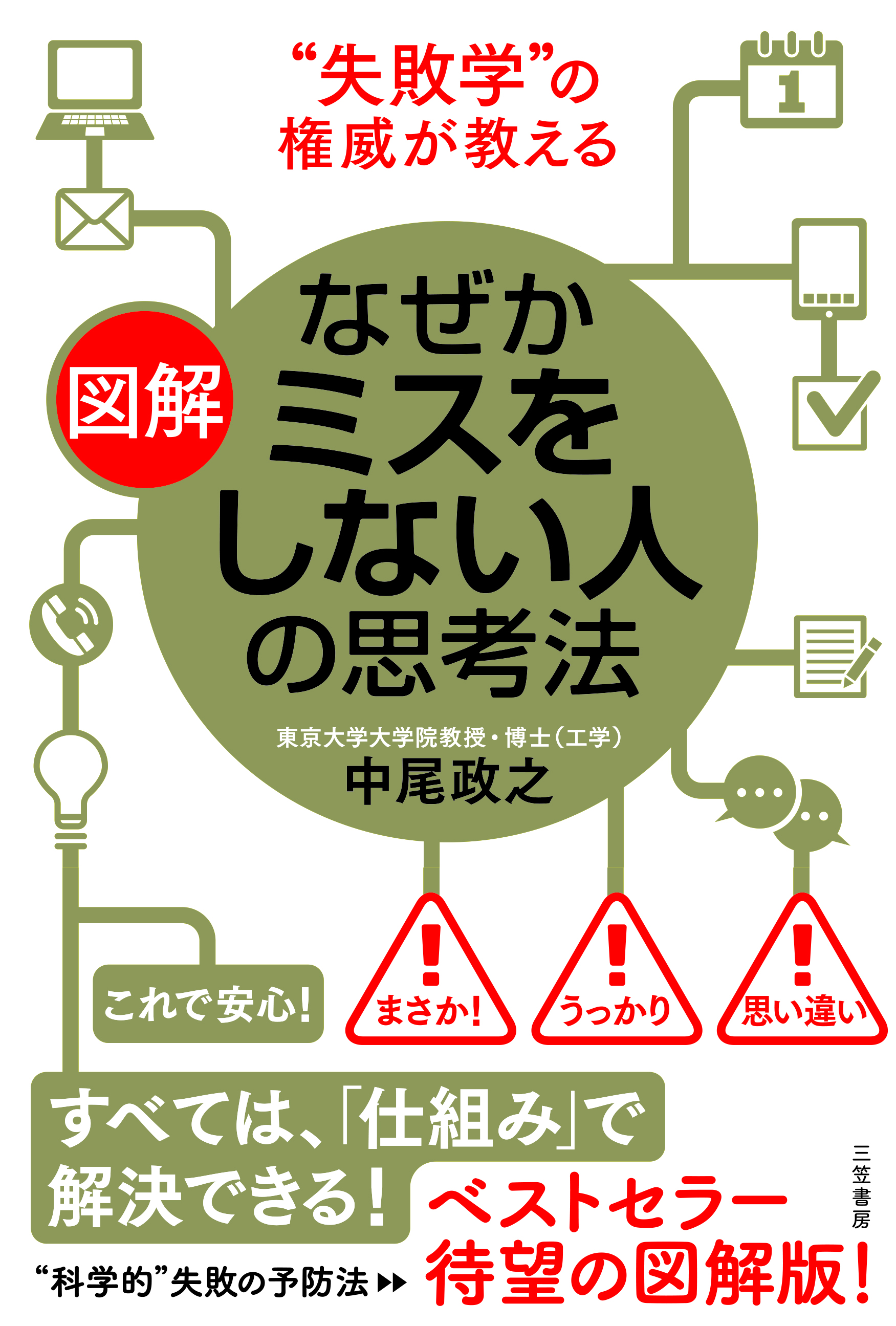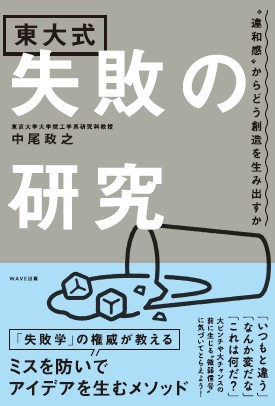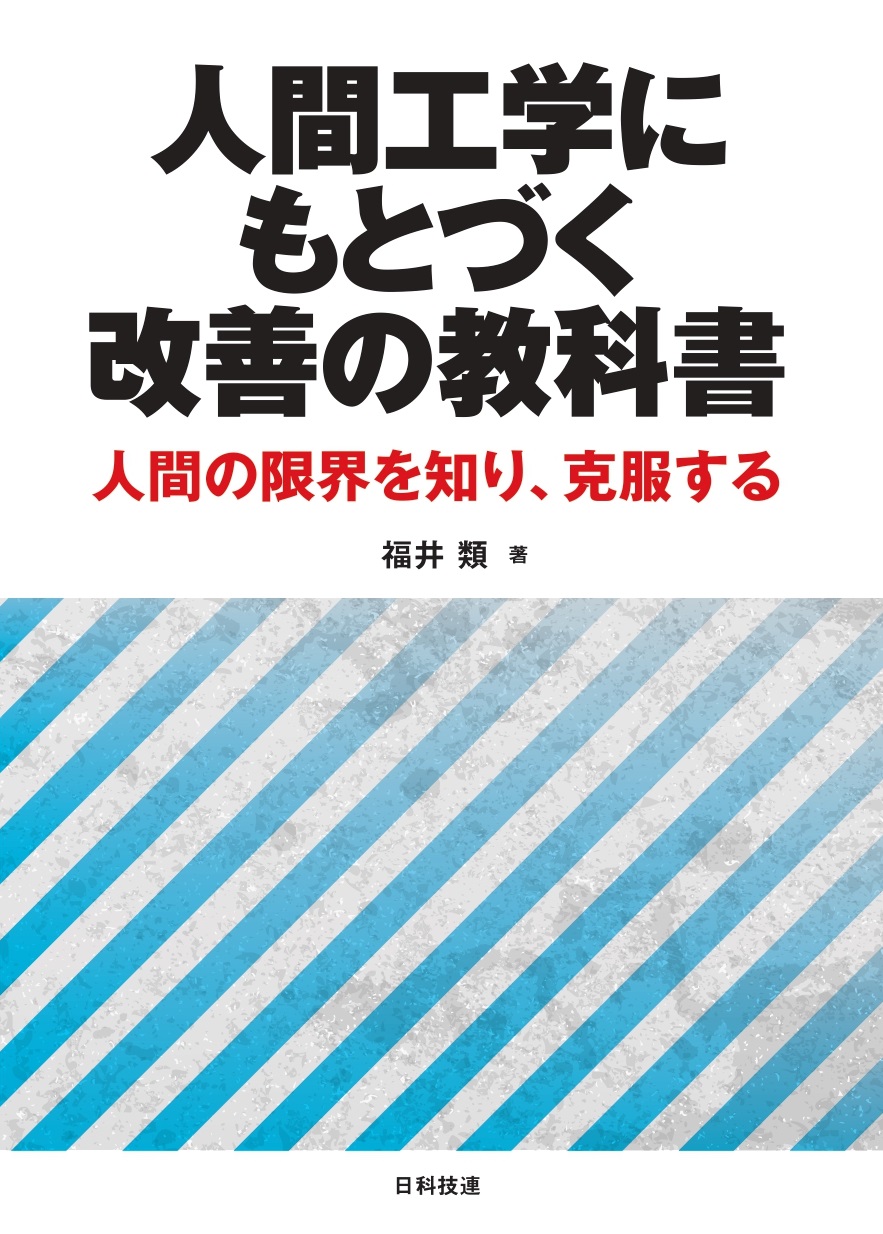
書籍名
人間工学にもとづく改善の教科書 人間の限界を知り、克服する
判型など
176ページ、A5判
言語
日本語
発行年月日
2021年10月
ISBN コード
978-4-8171-9741-2
出版社
日科技連出版社
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
本書は以下のような方におすすめです!
いつもミスばかりしてしまうから、なんとかしたい!
もっと作業の効率を上げたい!
自分の言いたいことが、なぜか相手に上手く伝わらない…
そもそも「人間工学」って何?
急に「何かを改善しろ」と言われたけど、どうしよう…
著者はロボット工学に関する研究・教育を行っている大学教員です。
「大学の、しかもロボット工学が専門の教員が、なぜ改善の本を書くの? しかもなぜ人間工学なの?」
と不思議に思われた方も多いでしょう。実は、現在の大学教員は特定の学術分野の専門家であるのはもちろんのこと、有限な資源 (人・場所・モノ・カネ) を適切に配分する管理者でもあるのです。管理システムがほぼゼロ (?) の大学の研究室を円滑に運営できるようにするには、自らシステムを構築し、日々改善を行うしかありません。
しかし、残念ながら多くの高等学校や大学では改善活動については教えてくれません。そもそも改善が学問としては未だ成立していないのだから仕方がないでしょう。さらに状況が悪いことに、実際に日々の改善を行うことを求める民間企業などにおいても、“改善活動の進め方”についてはほとんど教育をしていないことが分かってきました。
そこで本書はそんな学問として成立していない改善を、人間工学という学問の知識を広めようとする工学者の視点から、そして自らの組織の運営を円滑に行おうとする管理者の視点から議論しています。
さて、もう1つの疑問の、「なぜロボット工学の研究者が人間工学を重んじるのか」ですが、ロボットが広く社会に受け入れられるためには、どうしても乗り越えなければならない壁があります。それが「人間」です。
つまり、人間が行うのと同等またはそれ以上の速度・品質・経済性で作業をしなければロボットが人間に代わって作業を行うことの価値が十分に発揮されません。そこで、ロボットが乗り越えるべき壁である「人間」を詳細に知ることは、競合を知るという意味で大変重要なことになります。そして、人間がうまくできないことを知ることで、ロボットのほうがうまくできることを見つけることができるようになるわけです。これによって、すべての分野でロボットが人間を超えるのは無理だとしても、人間が苦手な分野にロボットが活躍の場所を見つけることができるようになると期待しています。
以上のように、まだ学問として成立していない改善活動に人間工学という学問の知識を加えることで生み出された、“人間工学にもとづく改善”は、世の中で活躍する皆さんにとって非常に強力な武器になると考えています。ぜひ一度、本書に目を通してみて下さい。
(紹介文執筆者: 工学系研究科 / 新領域創成科学研究科 准教授 福井 類 / 2022)
本の目次
第2章 人間工学的なモノの見方で改善を行うための基礎
第3章 できない相談をしていませんか? (人間工学から見た人間の限界を知ろう)
第4章 改善対象を発見しよう (その1: 人間の限界を試す悪例との比較)
第5章 改善対象を発見しよう (その2: 言い訳法による身の回りの問題の発掘)
第6章 ではどうやって改善するべきか?
第7章 難しい作業を簡単にするための原則を導入しよう!
第8章 人間工学的なモノの見方による具体的な改善の例
第9章 よい改善提案書を書こう!
関連情報
http://www.lhei.k.u-tokyo.ac.jp/
福井個人のWebページ
http://www.ra-laboratory.com/r/index.html
書評:
BOOK Review (『工場管理』2022年2月号 Vol.68 No.2 2022年2月)
https://pub.nikkan.co.jp/magazines/detail/00001083



 書籍検索
書籍検索