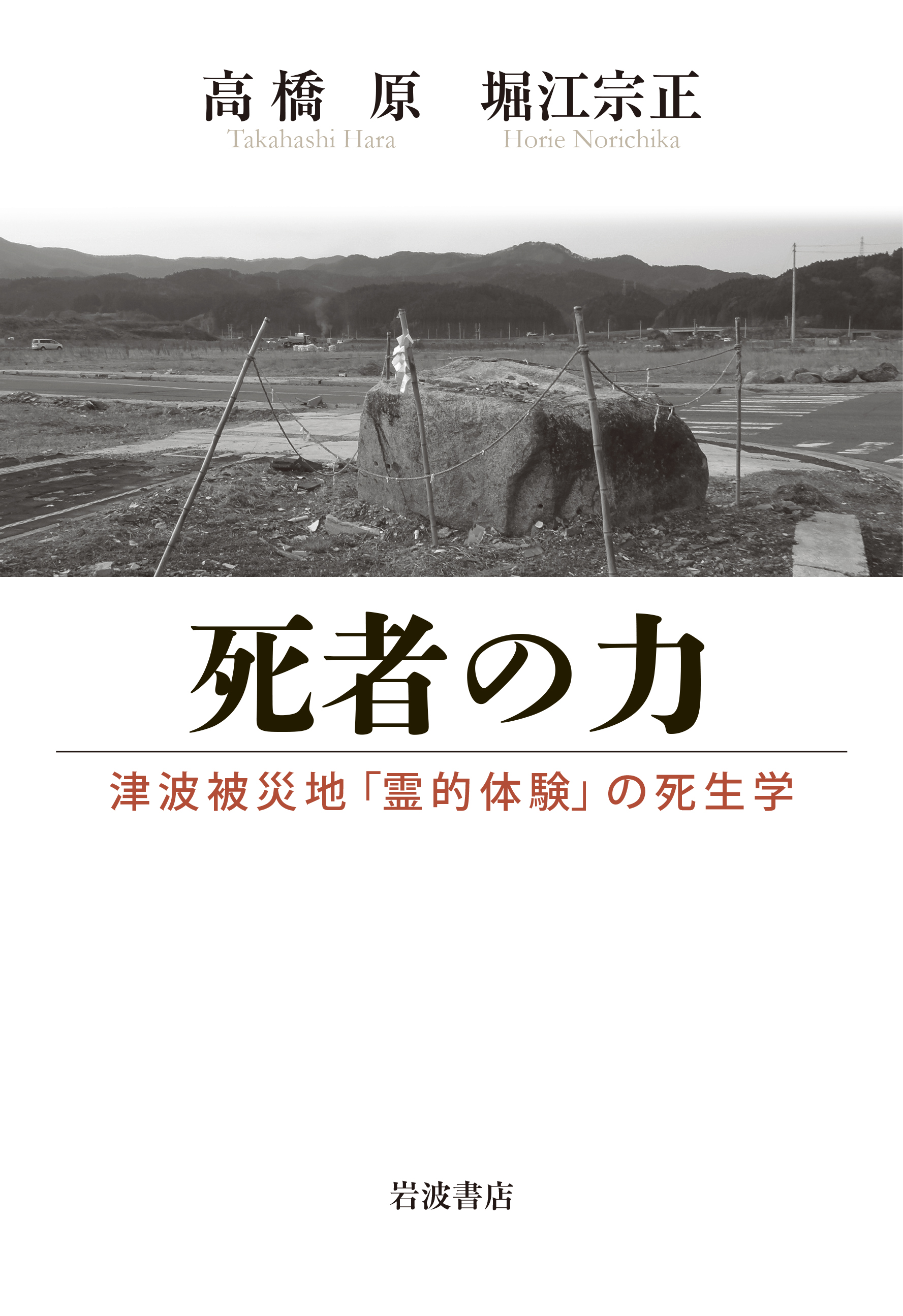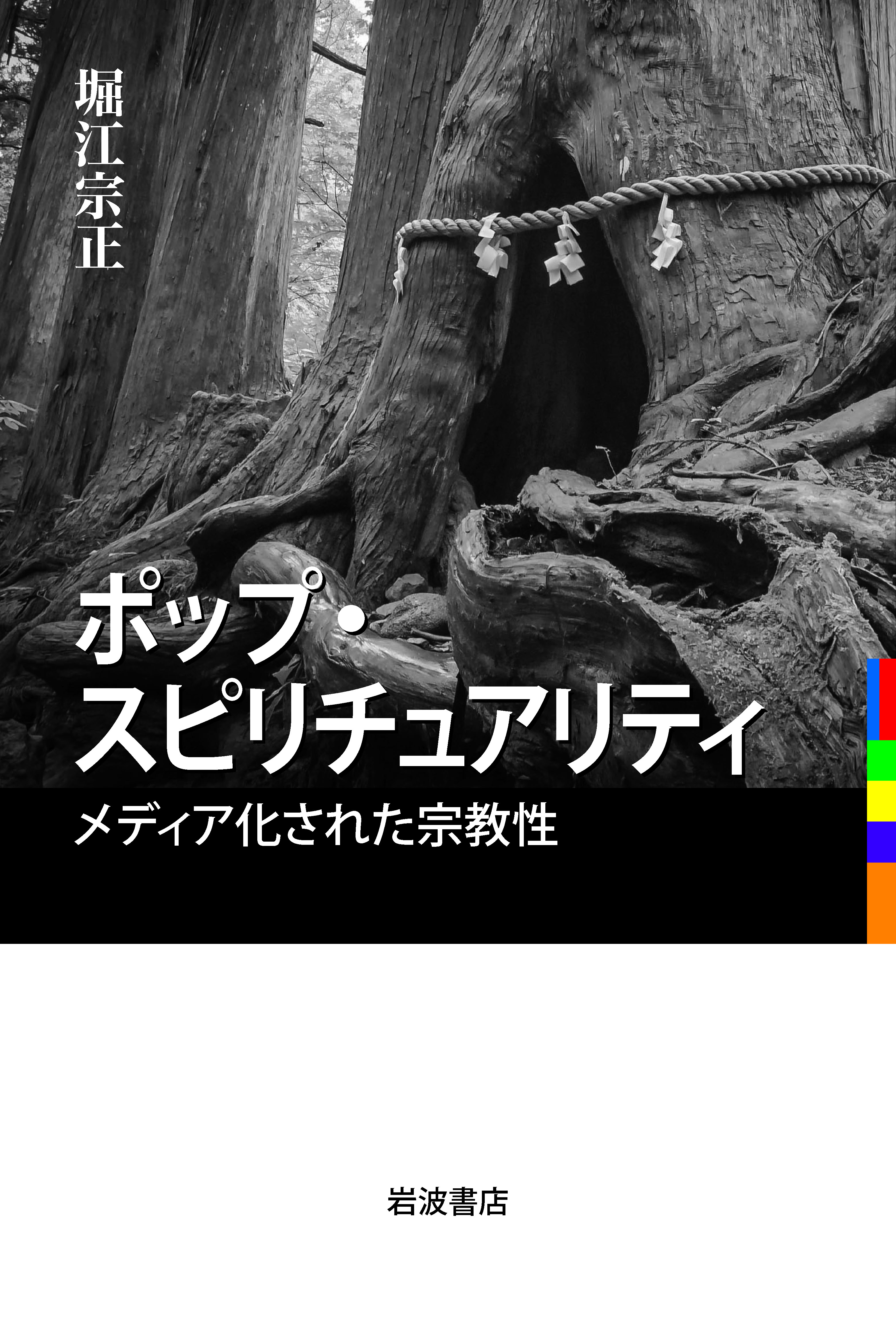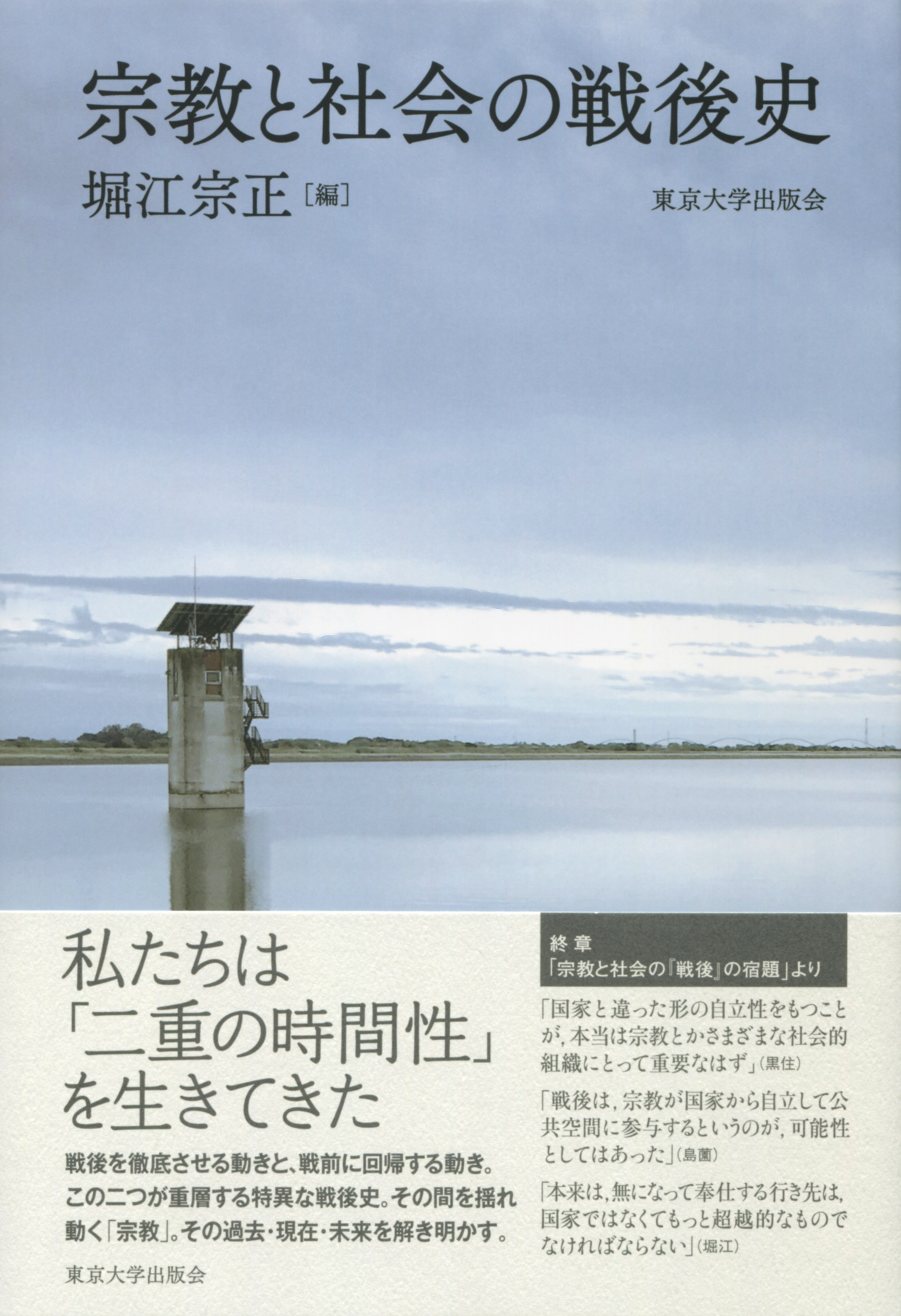1. 本書の概要
『死者の力──津波被災地「霊的体験」の死生学』は、東日本大震災の被災地で頻繁に語られる「霊」についての体験に焦点を当てた研究書である。共著者の高橋原とは、宗教学研究室に在籍していた大学院時代からの仲間で、二人とも宗教心理学を研究した後、スピリチュアルケアやスピリチュアリティの研究に進んだという共通点を持つ。本書は、被災地住民と宗教者への聞き取りに基づき、章ごとに以下のような問いを立て、それに答えてゆくという形式をとっている。
第一章「物語の力──被災地の霊的体験になぜひきつけられるのか」、第二章「儀礼の力──被災地の宗教者は霊的体験にどう対処したのか」(以上は高橋原)、第三章「絆の力──被災者たちは亡き人との絆にどう支えられているのか」、第四章「共同体の力──霊的体験の地域差はなぜ生じたのか」、第五章「信仰の力──被災地の外から来た信仰者は霊的体験をどのように見たのか」。
これらの章を通して、「死者の力」に迫る内容となっている。そして、当初、生者を脅かすような力としてとらえられていたものが、死者と生者の共通性が発見された後に、生者が死者とともに生きる力を活性化してゆくという「和解と連帯のドラマツルギー」が、語りや対話の中に見出される。
被災地での霊的体験は、「怪談」や「幽霊体験」などと表現され、様々な事例をまとめた本が多数ある。しかし、われわれはアンケートやインタビューを駆使した社会調査のアプローチを試みた。また、宗教や宗教者が霊的体験にどのように対処したかに焦点を当て、そこで得られた知見を宗教学や死生学の理論と関連づけた。
2. 学術的意義
学術的意義としては、宗教学、死生学、宗教心理学をベースとしており、またこれらの分野への理論的貢献をなしていることがあげられる。まず、霊的体験を身近な霊と未知の霊に分類した上で、それが二人称の死、三人称の死という類型や、先祖と無縁仏などの類型とどう対応するかを論じた。未知の霊が身近な霊に包摂されるような地域共同体では、死者と生者の分断、地域内の分断、住民の精神的苦痛が和らいでいることを指摘した。このことを、悲嘆研究における死者との「継続する絆」に関連づけながら、絆というよりも連帯に近いと修正を提案した。また、霊観念は実体的なものではなく、「物語的現実」と呼ぶようなものとして理解されると指摘し、この新しい概念を既存の宗教心理学や哲学の理論と関連づけた。
3. 社会的意義:
東日本大震災は言うまでもなく、日本社会を震撼させた大きな出来事であった。発災から間もない時期には、被災地で宗教学の観点から調査研究をおこなうことは、被災者の気持ちを傷つけることにつながるとタブー視されていた。しかしながら、私は、物質的あるいは心理的な面での支援をおこなうボランティアとして被災地の人々と関わる中で、一部の被災者が彼らの見聞きした霊的体験を、宗教学者である私に話したがっていることに気づいた。私自身は、宗教者でもないし、心理学や精神医学の専門家でもない。本書では、あくまでも宗教学者として、被災者支援に携わった宗教者らが被災者と、霊をめぐってどのような対話を持ち、語りを紡いでいったかを記述することに集中している。その結果、霊的体験は単なるきっかけに過ぎず、それを語ること、または悩まされて宗教者に儀礼を求めること、あるいは「霊」と共存し、絆を温めることを通して、「死者の力」が表象され、「生者の力」を活性化し、外部の宗教者も交えた死者と生者の連帯を形成してゆくことが明らかになった。本書の書評を書いた佐藤啓介によれば、「社会的なグリーフケアの可能性」が示唆されているとのことである。
本書は死者との関わりを通して、生者がどのように支えられるかを示したものである。それは、地震や津波の被災地のみならず、無縁社会や孤独死が問題となっている多死社会を生きる都市住民にとっても大きな意味を持つことになるだろう。社会的に孤立し、誰からも顧みられることのないまま亡くなる人を身近な死者であるかのように、われわれの社会は包摂することができるだろうか。もしそれが可能なら、孤立しながら生きている人もまた包摂される、居心地のよい社会になるのではないだろうか。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 堀江 宗正 / 2023)
本の目次
第一章 物語の力──被災地の霊的体験になぜひきつけられるのか……………高橋 原
メディア報道
亡き人との再会
未知の霊、身近な霊(見知らぬ死者、身近な死者)──阪神・淡路大震災との違い
たとえ幽霊でもいいから会いたい
犠牲者遺族の夢
物語の力
心霊現象と被災地復興のフェーズ
第二章 儀礼の力──被災地の宗教者は霊的体験にどう対処したのか……………高橋 原
儀礼の効用──「楽になりました」
宗教的応急手当て(Religious First Aid)
相談内容──オガミヤとの関係
仏教教団の霊魂観
宮城県の宗教者の「心霊現象」観 (一)仏教僧侶
宮城県の宗教者の「心霊現象」観 (二)神職
宮城県の宗教者の「心霊現象」観 (三)キリスト教牧師
儀礼の力
むすび
第三章 絆の力──被災者たちは亡き人との絆にどう支えられているのか……………堀江宗正
調査に至った経緯──塞翁さんの話
継続する絆──調査の目的と鍵となる概念
日本人にとっての「継続する絆」
方法論
霊の実在の肯定か否定か──語られた現実への限定
悲嘆、記憶、前向きさ
自然な霊的体験──四分の一が気配を感じ、メッセージを受け取っている
悲嘆共同体
震災後の宗教性の高まり?
身近な霊に関する心温まる物語の典型
(夫の霊を近くに感じている女性たち)
被災地外の人が体験する未知の霊についての怪談
(1 自動車の運転手の話/2 工事関係者の話/3 ボランティアの話)
第四章 共同体の力──霊的体験の地域差はなぜ生じたのか……………堀江宗正
「未知の霊」の「身近な霊」への包摂
身近な霊と未知の霊の間
(イエを越えた隣人との絆/地区住民への思い/未知ではないが包摂しがたい霊)
被災地内で語られる「未知の霊」
(宮城県B市のコンビニ怪談/岩手県A市の信号待ち怪談/コンビニ怪談と信号待ち怪談の比較/岩手県A市の回答者の状況/宮城県B市の回答者の状況)
両市の違いを生む三つの要因
(地理的要因/心理的要因/宗教的要因)
「死者の力」を支える「宗教の力」
平時の悲嘆と非常時の悲嘆
第五章 信仰の力──被災地の外から来た信仰者は霊的体験をどのように見たのか……………堀江宗正
被災地における「宗教」
スピリチュアルケアの可能性
復興世俗主義のなかでの宗教者の活動
調査の枠組──信仰者たちの視点の異質性
調査対象者の条件・特徴
被災地での霊的体験
(伝聞への関心の低さと疑い/霊視された被災地──残存思念・実存思念・未浄化霊・祈りの重層性/面識がある人の霊的体験/被災者からの供養の依頼──地域の宗教者には頼めないこと/被災地での信仰者の実体験──複数の現実への開かれ/被災者への傾聴は、すなわち死者への傾聴/高次の霊、仏、神に関わる信念と体験/祈りの体験──震災を起こした神の悲しみと浄化)
霊・霊魂についての見解
(慎重な態度をとる信仰者/霊を認める仏教者/多宗教の信仰者の共通言語としての「霊」と「魂」)
霊的体験への対応の仕方
(憑依への対応──あくまで普通の被災者の霊として/拝み屋による対応/行方不明者の遺体への関心/なぜ東日本大震災では「幽霊」が出るのか)
死者と生者の「継続する連帯」へ
(苦を通しての連帯──仏教系信仰者の場合/霊としての連帯──スピリチュアリズム系信仰者の場合/悲嘆における連帯──神道系信仰者の場合/再び塞翁さんの話)
ポスト近代の悲嘆文化
結 論……………堀江宗正
1 物語的現実としての死者・霊
(現代日本人の一般的な死後観/物語的現実という概念/死者が「ここにいる」という語り/物語的現実の理論的背景/物語によって生きる人間/変容する物語、変容する自己/死者の変容/重要な他者となる死者──阪神・淡路大震災の先行研究から/日本語の「ものがたり」の含意──「かたり」と「はなし」/生々しい死者の物語、生き生きとした死者の物語)
2 霊概念の三モデル
(辞書に見る「霊」/変容する霊──霊の疫病モデル/霊の電磁波モデル、霊の情報モデル/霊の情報モデルの理論的基礎/集合的無意識の噴出とは)
3 死者の力をめぐって
(震災後の死者論/死を経てなお生きる力/和解と連帯のドラマツルギー)
あとがきに代えて──片方の調査者から見た主観的現実……………堀江宗正
参考資料
参考文献
関連情報
著者コラム:
堀江宗正「「亡くなった人はここにいる」…震災被災地の「霊的体験」が私たちに教えてくれること——「多死社会」へのヒント」 (『現代ビジネス』 2021年10月17日)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/88344
高橋原(東北大学大学院文学研究科死生学・実践宗教学教授)「幽霊を見たという相談に僧侶にしかできない傾聴と儀礼の力」 (『月刊住職』 2022年2月号)
https://www.kohzansha.com/back/back202202.html
関連記事:
死者の力が被災者支える、心温まる霊的体験…[死と生を見つめて]第1部 <3> (読売新聞オンライン 2023年2月16日)
https://www.yomiuri.co.jp/life/20230208-OYT8T50068/
書評:
宮澤安紀 評 書評へのリプライ (『宗教と社会』vol.29 2023年6月)
http://jasrs.org/publication/journal2.html#vol29
岩崎美香 (明治大学意識情報学研究所) 評 (『トランスパーソナル心理学 / 精神医学』Vol.22, No.1, p.100-101 2023年3月)
http://jatp.info/gakkaishi.html
谷山洋三 評 (『スピリチュアルケア研究』Vol.6, p.159-163 2022年)
https://www.spiritualcare.jp/aj/
島薗進 (大正大学) 評 (『宗教研究』p.275-281 2022年96巻2号 2022年9月30日)
https://doi.org/10.20716/rsjars.96.2_275
金菱清 評「被災地の霊的体験はどのように位置づけられるのか――物理的ではなく「物語的現実」として死者や霊を捉えようとする」 (『図書新聞』第3533号 2022年3月5日)
https://toshoshimbun.com/news_detail?article=1704210986203x856827012738089500
<東北の本棚>生者を支え 共に生きる (河北新報ONLINE 2022年2月6日)
https://kahoku.news/articles/20220206khn000006.html
本よみうり堂:加藤聖文 (歴史学者・国文学研究資料館准教授)「読書委員が選ぶ2021年の3冊」 (読売新聞オンライン 2022年1月7日)
https://www.yomiuri.co.jp/culture/book/feature/CO036371/20211227-OYT8T50033/
佐藤啓介 評 (紀要『グリーフケア』第11号 2022年)
https://sophia-griefcare.jp/publication/kiyou1.html
書評 (キリスト新聞KiriShin 2021年12月30日)
https://www.kirishin.com/book/52090/
若松英輔 評「(東日本大震災の)被災地では集合的無意識が噴出している」 2人の宗教学者の“死者”という現象をめぐる探究 (『週刊文春』 2021年12月23日号)
https://bunshun.jp/articles/-/50804
鎌田東二 評 (『週刊読書人』 2021年12月10日)
https://jinnet.dokushojin.com/products/3419-2021_12_10_pdf



 書籍検索
書籍検索