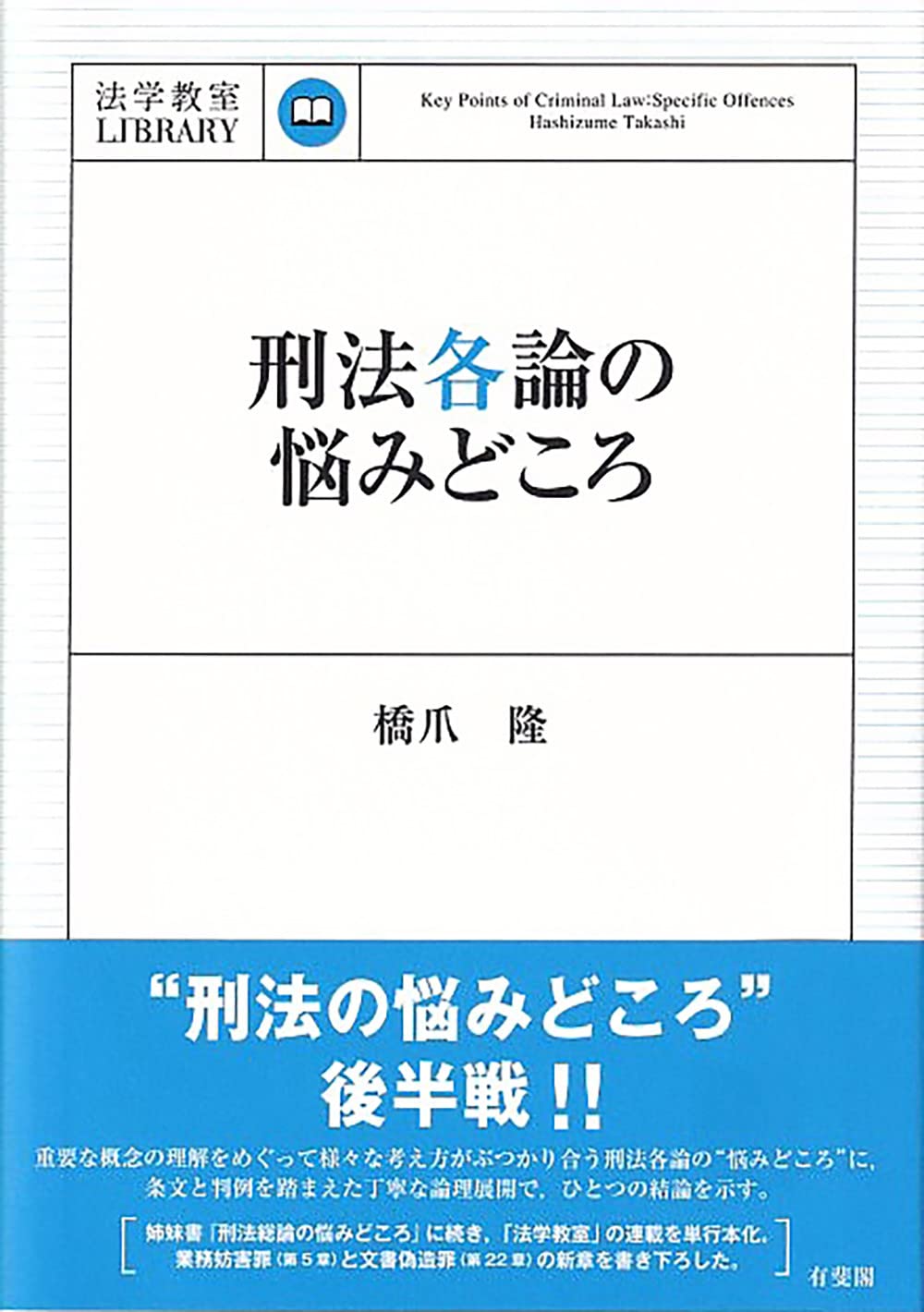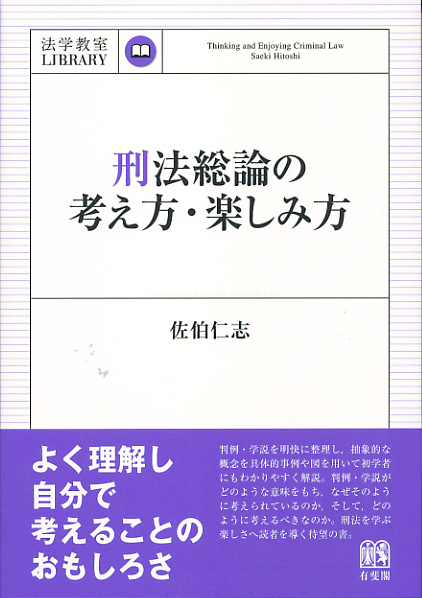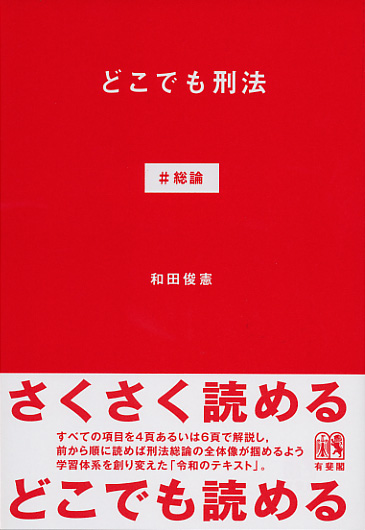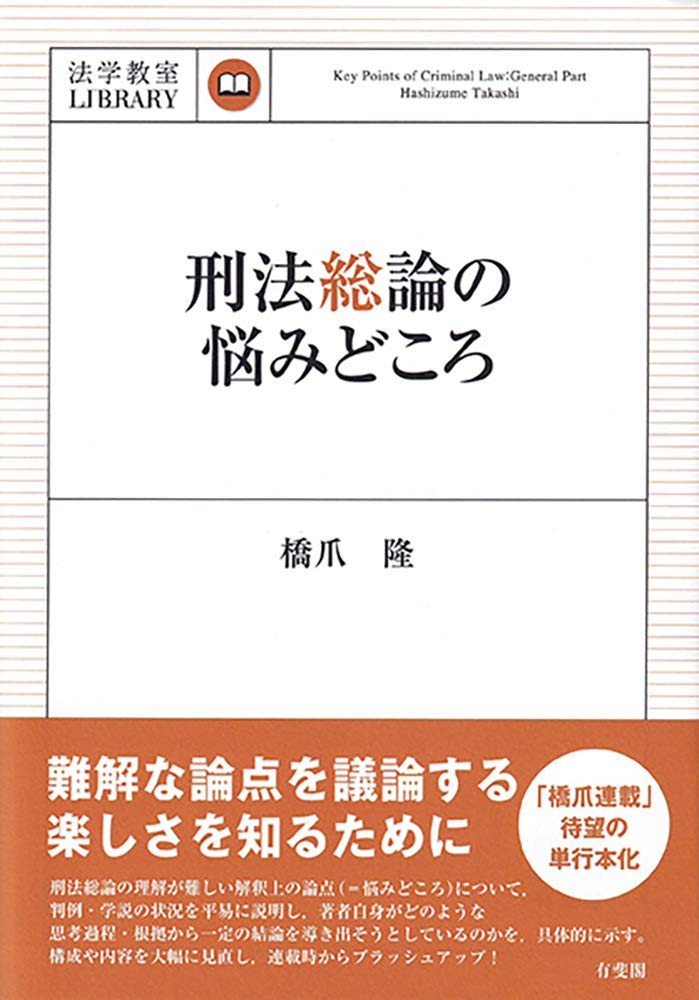
書籍名
法学教室ライブラリー 刑法総論の悩みどころ
判型など
490ページ、A5判、並製
言語
日本語
発行年月日
2020年3月
ISBN コード
978-4-641-13940-4
出版社
有斐閣
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
本書『刑法総論の悩みどころ』は、雑誌「法学教室」の同名の連載に、その後の判例・学説の動きを踏まえて、加筆・修正を行ったものです。この本では、刑法総論を学ぶ際に、学生のみなさんにとって理解が困難な解釈論上の論点について、議論の状況や問題点を整理した上で、一定の考え方を示すことを目的としています。その意味では、本書は、学部や法科大学院で、刑法総論をある程度勉強した人が、さらに学びを深めるために読んでいただくことを想定していますが、刑法総論をはじめて勉強する学生のみなさんにとっても理解できるように、基本的な内容を省略せずに、できるだけ平易に説明するように工夫してみたつもりです。また、法曹実務家や研究者の読者を想定して、最新の実務や学説の動向について、筆者なりの分析を加えているところもあります。
本書は全体で19章から構成されていますが、そのうち、共犯論の項目が6章あります。共犯論の分量が多くなったのは、共犯をめぐる議論が一番複雑であり、議論の内容をできるだけ分かりやすく説明したいと考えたからです。
私の杞憂かもしれませんが、刑法総論では抽象的な表現で難解な議論が展開されていることもあり、その学習においても、議論の実質や具体的な内容を正確に理解することなく、抽象的なキーワードや結論だけを覚えてすませる傾向があるように思われます。しかし、刑法総論の議論も、抽象的な議論をするために存在しているわけではなく、現実の事件を解決し、また、正しい法適用の在り方を模索するために存在しています。抽象的な言い回しを覚えているだけでは、刑法総論の解釈を具体的な事例に適切に適用することはできませんし、何よりも刑法の議論の楽しさが伝わりません。このような問題意識から、本書では、判例・学説の状況をできる限り平易に説明した上で、なぜ、このような問題が議論されているのか、どのような観点から見解の対立が生じているのか、それぞれの見解から結論がどのように異なるのか、などの点を詳しく論ずることで、読者の方に、刑法総論の議論状況を追体験してもらえるように努めたつもりです。このような目的がどこまで達成できているかについては、あまり自信はありませんが、読者の方が刑法総論の議論を面白く感じていただけるのであれば、筆者としては大変うれしく思います。
(紹介文執筆者: 法学政治学研究科・法学部 教授 橋爪 隆 / 2023)
本の目次
第2章 実行行為の意義について
第3章 不作為犯の成立要件について
第4章 正当防衛状況の判断について
第5章 過剰防衛の成否について
第6章 誤想過剰防衛をめぐる問題
第7章 事実の錯誤について
第8章 遅すぎた構成要件実現・早すぎた構成要件実現
第9章 過失犯の構造について
第10章 過失犯における結果回避義務の判断について
第11章 「原因において自由な行為」について
第12章 実行の着手について
第13章 共同正犯の構造 (1)──共犯としての共同正犯
第14章 共同正犯の構造 (2)──正犯としての共同正犯
第15章 共犯関係の解消について
第16章 承継的共犯について
第17章 共同正犯と正当防衛・過剰防衛
第18章 不作為と共犯をめぐる問題
第19章 包括一罪の意義について
関連情報
編集担当者から (法学教室475号 2020年4月)
https://www.yuhikaku.co.jp/static_files/BookInfo202004-13940.pdf
関連動画:
「東京大学法学部教員メッセージ (刑法・橋爪隆)」 (東京大学YouTubeチャンネル 2022年12月1日)
https://www.youtube.com/watch?v=B0bHwHe0V4Q



 書籍検索
書籍検索


 eBook
eBook