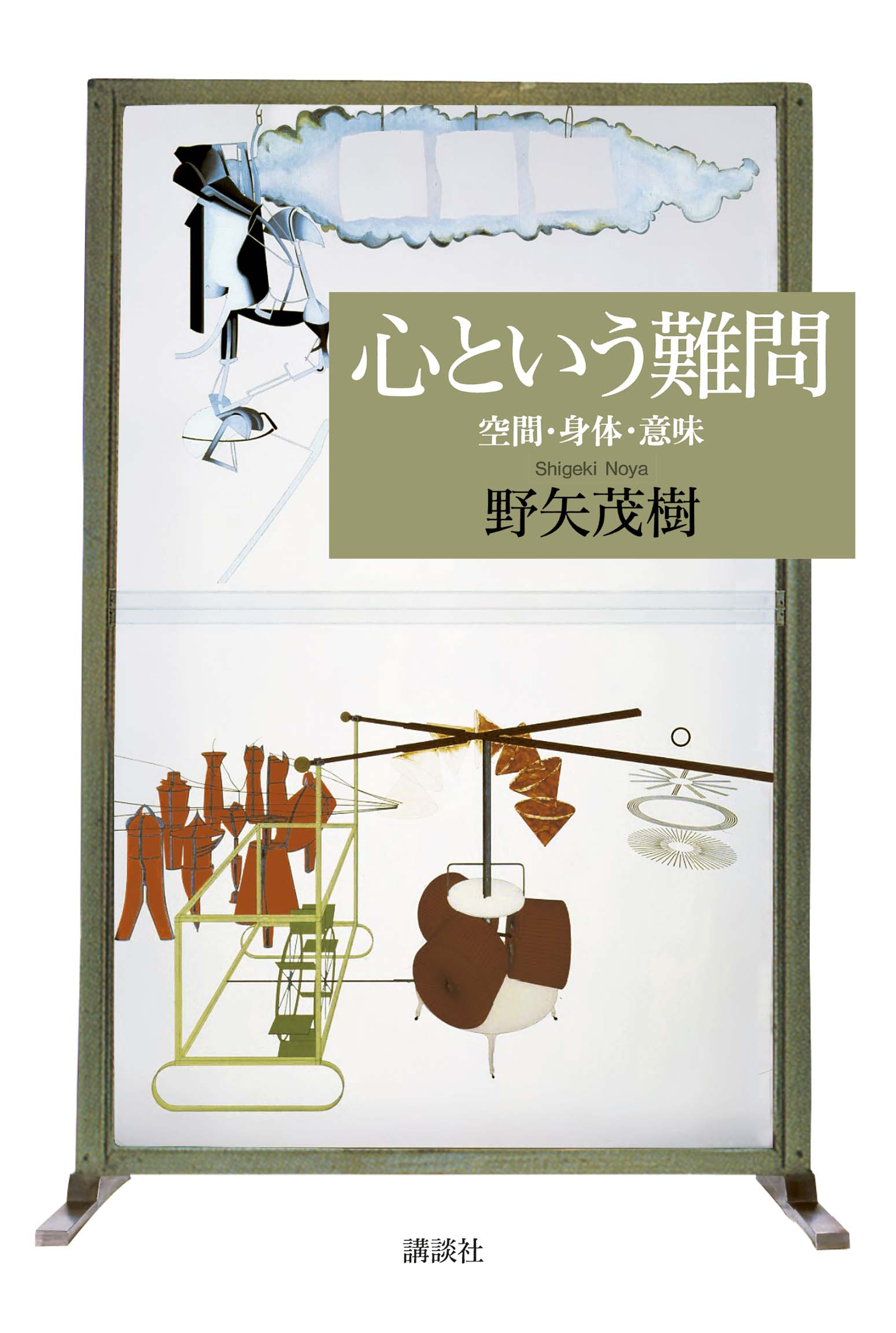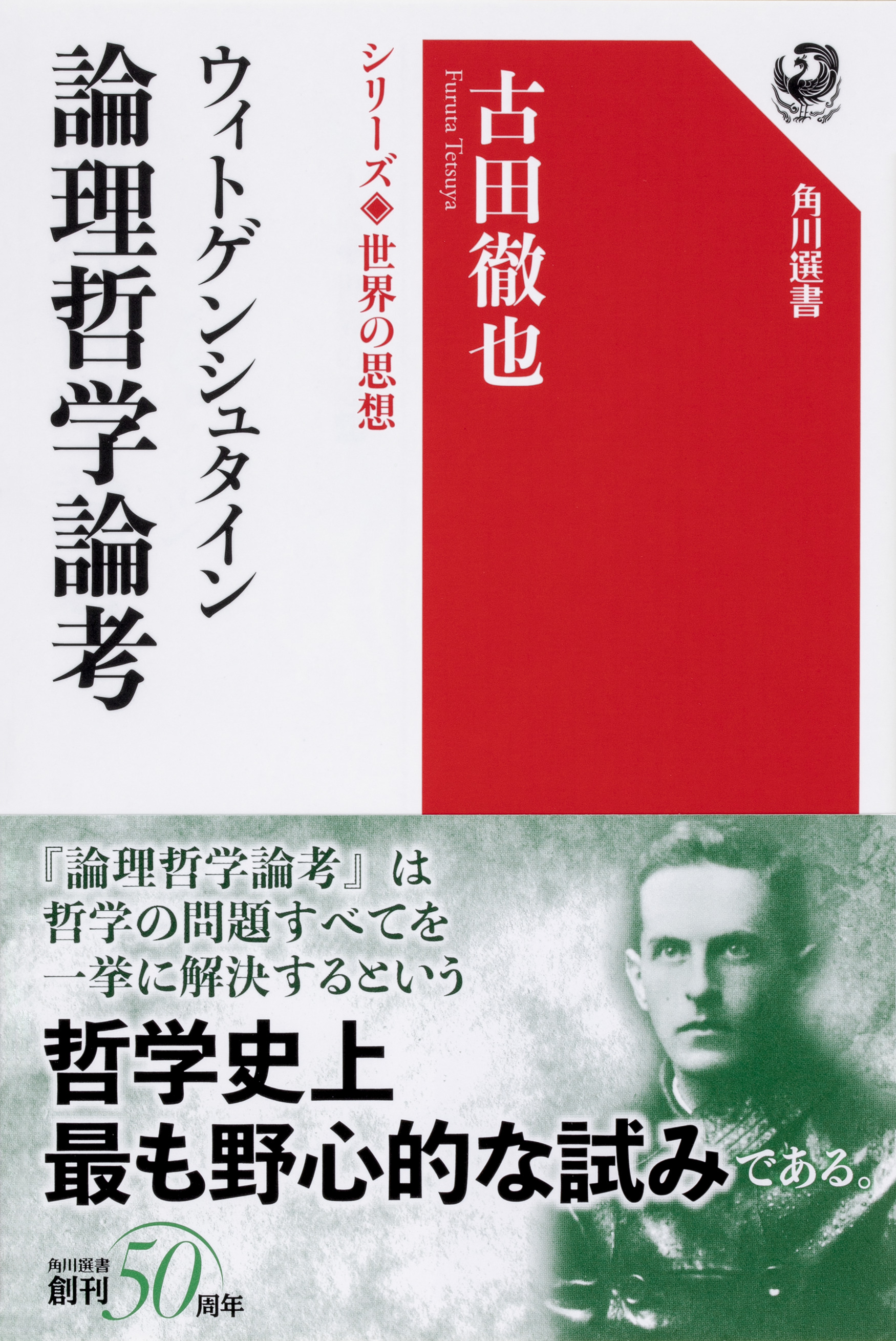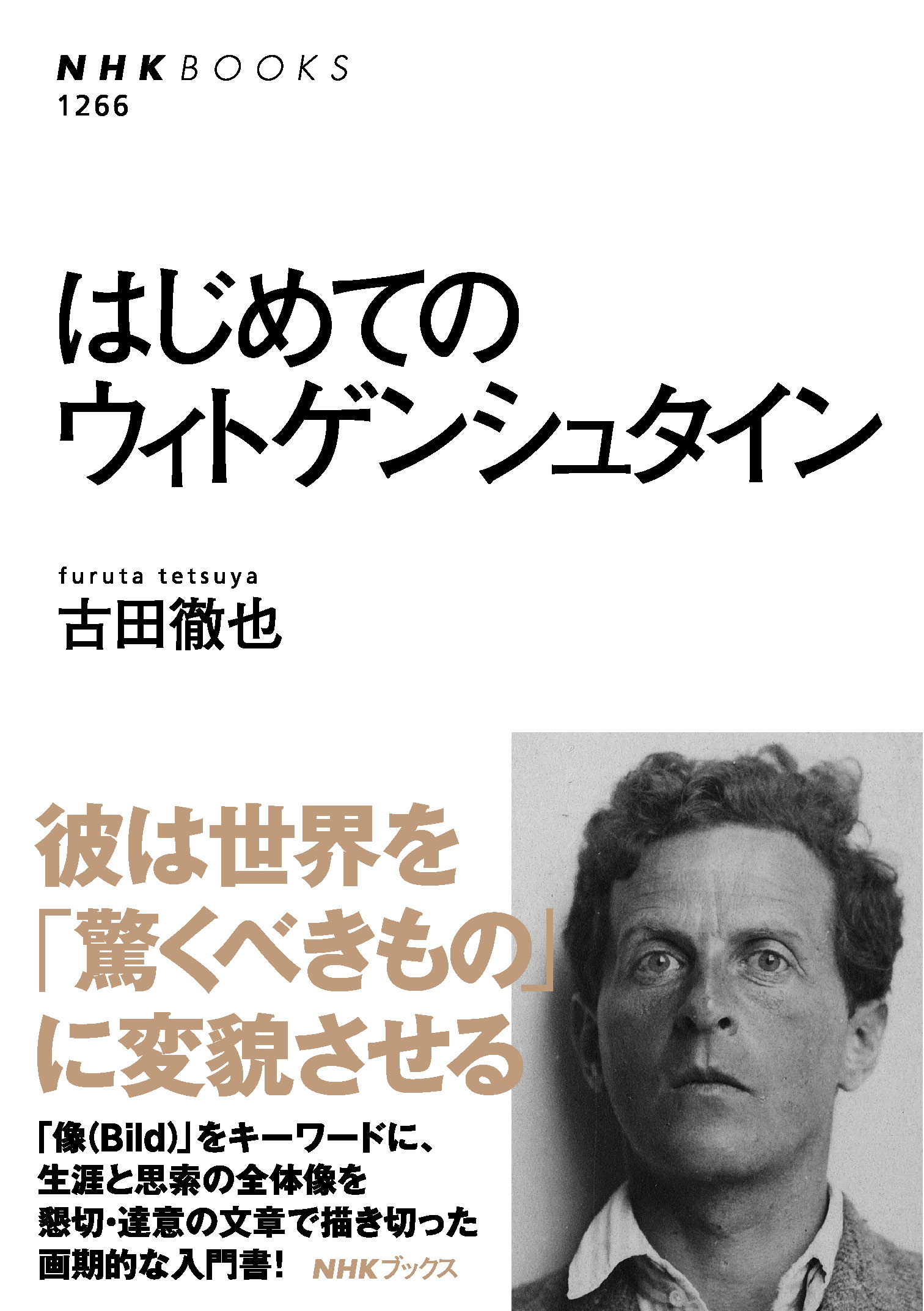本書に収められているのは、現代日本を代表する哲学者である野矢茂樹と、野矢の哲学から様々に影響を受けてきた後の世代の哲学者達との格闘の模様である。
野矢はこれまで、L. ウィトゲンシュタインの哲学と英米圏の分析哲学をベースに、知覚、心、行為、意味、論理などの様々な領域に関して多くの著作を生み出してきた。ただし、その哲学の全体像がまとまった形で論じられる機会はこれまで多くはなかった。本書は、野矢が展開してきた多種多様な広がりを持つ議論を包括的に扱う点で、まずもって貴重なものである。
とはいえ、それは野矢の思想を解説したり、他の哲学者と比較することによって果たされるのではない。本書の執筆者である9人の論者は、それぞれが専門とする分野から野矢の議論を徹底的に吟味する。時に真正面からそれを批判し、時に野矢の提示したことの先へ提案を行う。その中で、野矢がこれまで論じてきたことの (もしくは論じてきたこと以上の) ディテールが浮き彫りになる。
本書が類書に比べて際立つ点は、野矢がそれぞれの論考に対し、個別に再応答を与えるところにもある。実はこのスタイルは、野矢の師である大森荘蔵とその弟子筋による『哲学の迷路』という著作で採られたものであった。その際に最年少の執筆者であった野矢が、今度は同じスタイルで若い世代の哲学者を迎え撃つのである。
例えば自由意志を専門にする私 (李) は第5章を担当する。哲学ではしばしば、「自由と決定論の対立」という構図のもとで人間の自由が問われてきた。私たちは自らが何を行うかを選択できる自由を持つのか、それとも私たちがどう振る舞うかは全て決定されているのか。この問いに対して野矢は自由を擁護する立場から論を展開するが、私はその議論に照準を定め、批判を行う。野矢の議論が、自由概念の「自己決定」の次元に踏み込めていないことを指摘し、野矢の哲学の全体像を考えた時、むしろ人間に自由の余地がほとんどなくなることを主張する。それを受けて野矢は、決定論に対する私 (李) の不十分な理解ゆえに、そこで取りこぼされてしまっている議論が存在することを指摘し、そのうえで「自由」とはどのようなものなのか分かり切らない部分が自らにあることを吐露する。
いずれの章でもそこで示されているのは、研究の蓄積を背景に、哲学を専門にする者同士が、ある事柄について忖度も遠慮もなく考えうることを考え抜いた先でたどり着いた地点である。それゆえ本書は、野矢哲学の魅力の一つである分かりやすさや記述の平明さを備えるとは言いがたいかもしれない。しかし本書は、野矢の議論が長い哲学の歴史に裏打ちされ、確固とした哲学の論理に基礎づけられているという、野矢哲学の別の魅力を鮮やかに描き出すものになっている。
野矢哲学に魅了された人。ヴィトゲンシュタインや分析哲学について一歩進んだ理解を持ちたい人。哲学者研究者同士の議論に興味がある人。いずれの人にもお勧めしたい本である。
(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 助教 李 太喜 / 2024)
本の目次
解説1 眺望論と相貌論……………金杉武司
解説2 ウィトゲンシュタインと野矢哲学……………髙村夏輝
第1章 物語のポリフォニー……………塩野直之
応答 物語を読むことと共に生きること……………野矢茂樹
第2章 世界には何があるのか──相貌なき対象の必要性……………山田圭一
応答 どうして一つの同じ対象があると言えるのか……………野矢茂樹
第3章 どこでもないところからの眺めは必要か──有視点把握と無視点把握の関係……………鈴木雄大
応答 「ここ」も「あそこ」からすれば「あそこ」になる……………野矢茂樹
第4章 「物語」としての知覚論──意識の繭に閉じ込められた生き方はありうるか……………森永 豊
応答 「相貌」というあまりにも曖昧な概念……………野矢茂樹
第5章 自由の可能性──場と相貌の二元論から考える……………李 太喜
応答 自由の正体がまだ見えない……………野矢茂樹
第6章 意味するという事実のありか──根元的規約主義を批判する……………金杉武司
応答 3階建ての建物を平屋だと思うと変なことになる……………野矢茂樹
第7章 意図はどこにあるのか──「内と外」の比喩のゆくえ……………竹内聖一
応答 問いがあるから意図が生まれる……………野矢茂樹
第8章 「論理の他者」という謎……………髙村夏輝
応答 ザラザラした大地へ戻れ!……………野矢茂樹
第9章 規則のパラドクスを解決する──相貌の自己知に訴えるアプローチ……………島村修平
応答 一人称権威の謎……………野矢茂樹
思考不可能なものは存在するか……………野矢茂樹
哲学の風景──あとがきにかえて……………金杉武司
執筆者紹介



 書籍検索
書籍検索


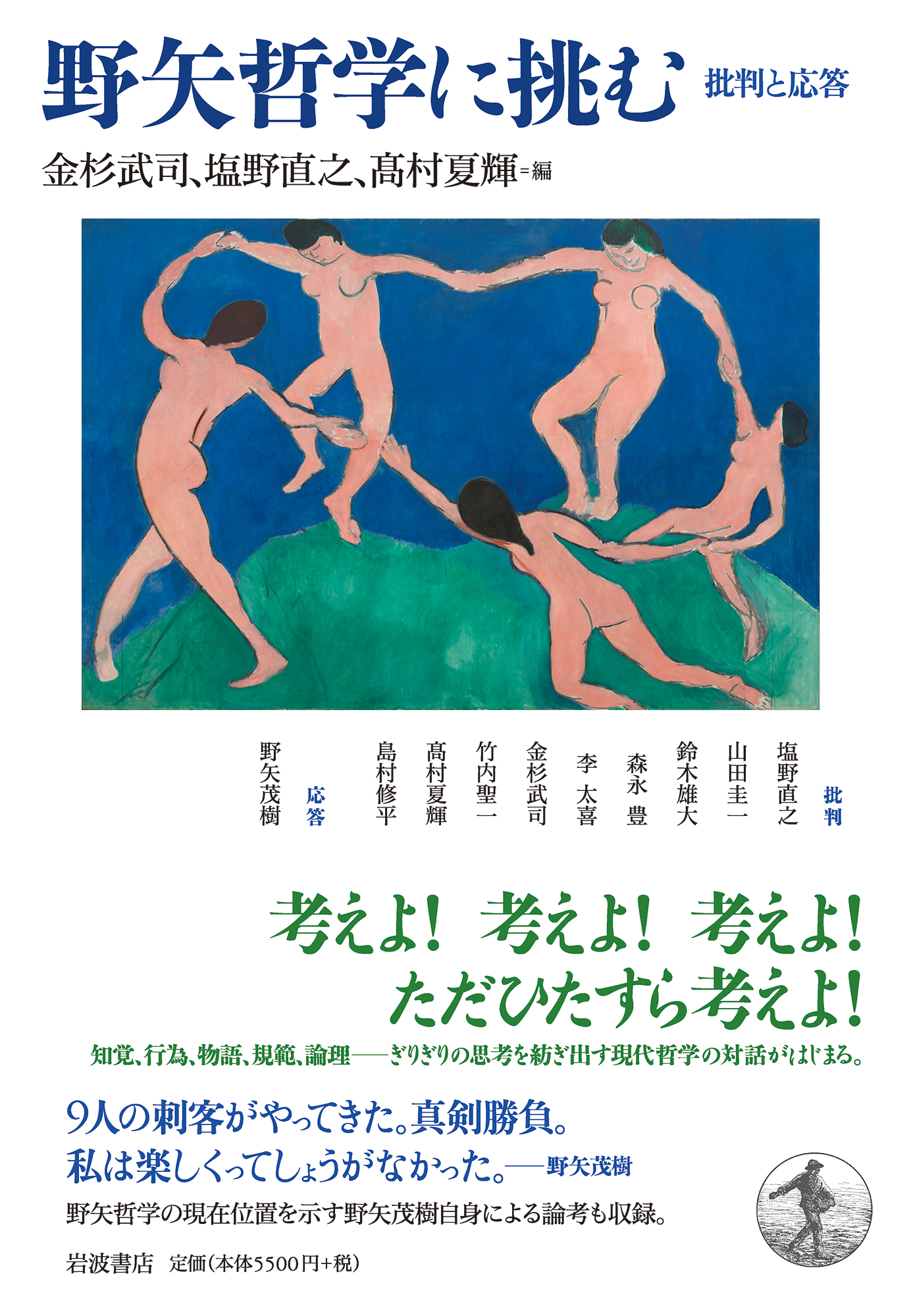
 eBook
eBook