経済学で考える誰もが生きやすい社会 ダイバーシティ&インクルージョン研究 01

このシリーズでは、様々な観点からダイバーシティ&インクルージョンに関連する研究を行っている東京大学の研究者を紹介していきます。

経済学研究科 教授 山口慎太郎
―― 経済学の視点から結婚や出産、育児を研究してきたとのことですが、どうしてこの分野を選んだのですか。
私の専門は労働経済学で、アメリカで学位を取ったのちにカナダの大学で仕事をはじめました。当時は北米のデータを使って分析していたのですが、5 年ぐらいしてテニュア(任期なし教員ポスト)が取れた時に、残りのキャリアでは日本のことをやりたいと思うようになったんです。テニュアを取るまでは、男性のキャリアの初期にどういうメカニズムで賃金が上がっていくか、具体的には転職を通じてなのか、それともスキルアップを通じてなのか、といったことが研究の中心でした。それも面白かったのですが、前々から日本と北米の労働市場の大きな違いは女性の活躍度だと感じていました。今でこそ日本もだいぶ変わりましたが、少なくとも私が博士号を取った2006年頃は日本の女性の就業率は低かった一方、アメリカには管理職の女性がとても多かったのです。また、少子化は日本にとって大きな社会的課題で、労働力不足が問題になるだろうことを考えると、女性が活躍できるようにしたほうが日本社会にとっていいだろうなと真っ先に思ったんですね。それが始まりでした。
―― 研究を通じて分かったことは?
論文をたくさん読んでいるうちに、日本社会の当たり前は当たり前じゃないという印象を強くしました。日本社会しか知らないと、女性が活躍していることがイメージできないから、「やはりそうは言っても女性が活躍とか向いてないんじゃないの」といった意見が出てきます。言っている人からしたら悪気もない。さらには、「子育ては男にはできない」もしくは「子育ては女のほうが向いているんじゃないか」とか、「子どもが3 歳になるまでは母親が子どもの面倒を見たほうがいい」といった三歳児神話のようなものまでたくさんあるわけです。でも、科学的研究をたくさん積み上げていくと、そうした言説のほとんどに根拠がなくて、かなりの部分が社会的な規範によって決まっているということを実感しました。そういう意味では、研究をやればやるほど固定観念が壊されていくという感覚がありました。
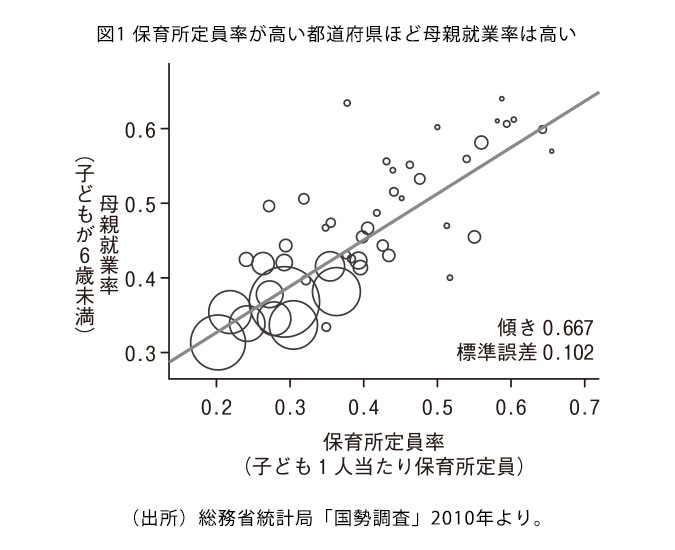
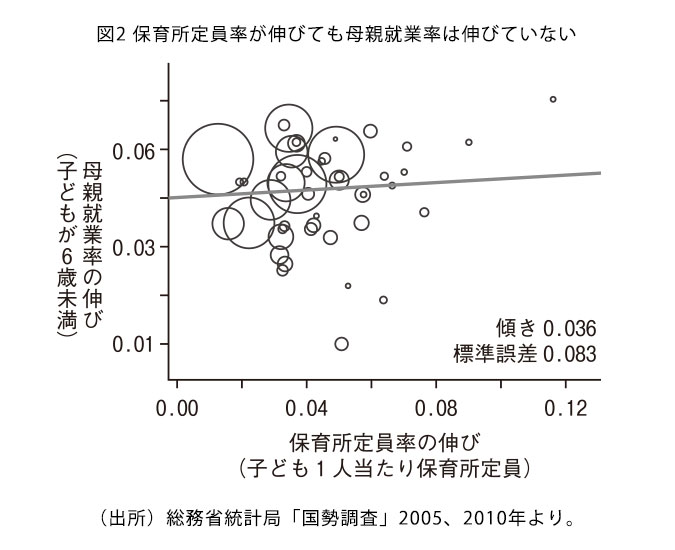
―― 2019年出版の著書『家族の幸せの経済学』には、医学論文などが多く引用されています。経済学はお金に関する学問だと思っていましたが・・・。
経済学は実験ができず、観測しかできない状況から因果関係を見出すことがもともと得意な分野なので、同様の課題を抱える他領域にどんどん入ってきています。例えば、帝王切開した方がいいのか通常分娩がいいのか、というのを実験で検証するのは倫理的に難しいわけですよね。帝王切開の子どもの発達への影響を調べる際、もともと経済学で発達していた分析手法が応用可能でした。このように、伝統的に経済学で使っていた分析ツールが他分野にも適用可能だということがわかってきて、経済学者が医療や教育などにも顔を出すようになってきました。30~40 年前だったら、労働経済学の分野では失業率や雇用者数、賃金などのマクロ統計に注目することが中心だったと思います。しかし、経済学そのものは人がなぜどのように行動するのかを考える枠組みを提供する学問です。出産や子育ては意思決定の連続で、その意思決定の背後にどういう制約や損得勘定があるのかを考慮していくと、経済学の枠組みというのは当然あてはまるわけです。社会における人間の行動は何でも研究対象になるという感じですね。
―― 出産と結婚、子育てはプライベートな事柄でもあります。子どもを持ちたくても持てない人もいる中で、どのように制度設計を進めていけばよいでしょうか?
最終的に目指すのは、子育てがしやすいだけの社会ではありません。まず具体的な第一歩として、育休を取りやすい社会を作ろうとしていると考えてください。その次に、病気になったり介護する必要が生じたりしたときに会社を休みやすい社会、そして気づかれにくいメンタルの病気になった時に休みやすい、さらには自己研鑽のために休みやすいというように、最終的にはみんなにとって生きやすい社会を目指していくのです。子育てしやすい社会が最初に選ばれているのは対象者が多いこと、そして少子化という社会的な問題があるから。ただ、その背後にある思想というのはまさにダイバーシティ&インクルージョンです。シングルで生きていくつもりの人でも病気になることはあるだろうし、友人や家族を助けたくてちょっと休みを取りたい時もあるかもしれない。そういう時に、例えば家族持ちで子どもが大きくなった人がバックアップに入る、というように、お互い助け合えるような職場や組織を作っていくことがゴールだろうと思っています。
―― 社会を多様かつインクルーシブにするために何か一つ変えられるとしたら何に取り組みますか?

世の中に自分が直接手を入れて動かせるとしたら、特に政治の世界でジェンダー・クオータを導入したいですね。なぜ政治かというと、政治不信があると言われつつもやはり政治が一番社会に対して影響力が強いからです。日本社会全体の意思決定というのは政治によって行われている。ジェンダー・クオータを導入することによって、ダイバーシティが社会全体に広がっていくんじゃないでしょうか。そうすれば、経済や大学の世界にも影響が波及してくると期待しますね。海外ではすでに導入されています。比例代表名簿に男女交互に上位から候補を載せて、得票数に応じて議員になります。例えば自民党 で30 人当選したら男性 15 人、女性15人が議員になるわけです。また、女性に限らずいろんなマイノリティーグループに対して代表枠があるのが望ましいと思います。
東大の女子学生比率向上についても、推薦入試の枠をもっと広げていくのがいいと思います。東大に女子学生が少ないのは、高校や親の影響、あるいは大学を出てからのキャリアパスが女性に有利ではないことが原因に含まれるので、大学単体で変えることに限界はあるでしょう。ただ、東大が大学入試全体に与える影響は大きい。
学力試験って一発勝負だから、すごいリスキーなんです。男性の方がリスクを積極的に取りに行くということは研究上よく知られています。アメリカの大学入試で使われるSATという共通試験のデータによると、男子はわからない問題について当てずっぽうで答えを書くけれども、女子は答えを書かない傾向があることがわかっていました。これは、SATでの誤答は減点されるためです。女子はリスク回避傾向が強いので、減点のリスクを避けようとして当てずっぽうで答えを書かないため、点数が低めに出ます。したがって、結果的に知識の量や思考力ではなく、リスクに対してどんな行動を取るかで人を選んでしまっていた側面があったんですね。テストが意図しない形でバイアスを持つということは十分あり得るので、今の入試というのは男性に有利な形になっていたとしても全く不思議ではありません。日本社会は筆記試験を神聖視しています。アメリカでは筆記試験以外の方法に比重を置くため、社会的に恵まれた人たちばかり入学させてしまうという問題はあるのは確かですが、日本でもAO 入試のような制度をもっと取り入れたほうが、大学がイノベーティブな場になると思います。
取材日: 2021年8月4日
取材・文/小竹朝子
撮影/ロワン・メーラー







