マクドナルドのメニューはなぜ見づらいの?→阿部 誠|素朴な疑問vs東大

「なぜ?」から始まる学術入門
言われてみれば気になる21の質問をリストアップし、その分野に詳しそうなUTokyo教授陣に学問の視点から答えてもらいました。知った気でいるけどいざ聞かれると答えにくい身近な疑問を足がかりに、研究の世界を覗いてみませんか。
Q.14 マクドナルドのメニューはどうして見づらいの?
マクドナルドに限らずファーストフード店で目につくところにあるメニューは見づらいことが多い気がします。何か秘密があるんでしょうか。店側はお客の判断パターンを熟知している
マクドナルドのディスプレイには、キャンペーン商品やセット商品の写真が大きく示され、単品や100円商品などの安価な商品は普通表示されません。フルメニューはカウンターにあるため、ディスプレイにない品を選びたい人は順番が来た後にあわてて探す必要があります。そのとき後ろに長い列ができていて「早くしないと」とプレッシャーを感じ、結局セットを選んでしまう人も多いでしょう。
| ヒューリスティック処理 | システマティック処理 |
|---|---|
| 経験的 | 合理的 |
| 直観 | 推論 |
| 周辺的ルート | 中心的ルート |
| 高速 | 低速 |
| 並列的 | 逐次的 |
| 自動的 | 制御的 |
| 努力を要さない | 努力を要する |
| 連想的 | 論理的 |
| 情動的 | 理性的 |
意思決定の際に時間的圧力を感じると、人は直観で素早く近似的な解を導くヒューリスティック(heuristic)処理という簡便なやり方を採ります。もとはプログラミングで使われた言葉で、時間をかけて分析し最適解を選ぶシステマティック処理とは対照的なやり方です。ヒューリスティックを使うと、厳密に吟味するのではなく、効用がおよそ最大になるセット商品を素早く選ぶことになります。通常は満足できるレベルのベターな判断になりますが、状況によっては間違い(バイアス)を引き起こすこともあります。店側はこうしたバイアスのパターンを熟知し、消費行動原理に基づいて消費者を誘惑します。単価の低い商品よりも高いセット商品を選んでもらうほうが店側にとっては利益につながるわけです。
経済学は、経済的合理性を重視して意思決定をする人間、ホモ・エコノミカス(homo economicus)を前提とします。たとえばシャンプーを買うとき、経済的合理性を重視するならすべての商品を吟味して判断することになりますが、実際はなじみのある数種の商品から選ぶのが普通です。理論と現実にはずれがあります。そこで、実際の人間の行動を考慮してもっと現実を捉えようと1980年代に生まれたのが、心理学と経済学を結びつけた行動経済学です。
そのなかで私が注目するのは「選好の逆転」 の研究です。人の好みは文脈や状況に応じ、 対象との距離によって解釈のしかたと評価が変わることが、心理学でいう解釈レベル理論から提案されています。この理論を行動経済学の「割引」という概念と結びつけることによって、「選好の逆転」現象を統計モデルで記述し、どれくらいの割引が生じるのかを推定しています。
消費者として非合理的な判断を下す可能性があることを知るのはとても重要です。売り手と買い手が持つ情報の非対称性により買い手が損をすることがあります。背後にある原理を知って不本意な消費は避けたいものです。
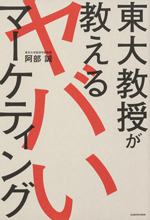
『東大教授が教えるヤバいマーケティング』(KADOKAWA、2019年)
経済学部で行われている授業をもとに、行動心理学や認知心理学の面から数々のマーケティング論を紹介する一冊。



 回答者/阿部 誠
回答者/阿部 誠


