 極圏、砂漠、火山島に無人島、
極圏、砂漠、火山島に無人島、
5640mの高山から5780mの深海まで
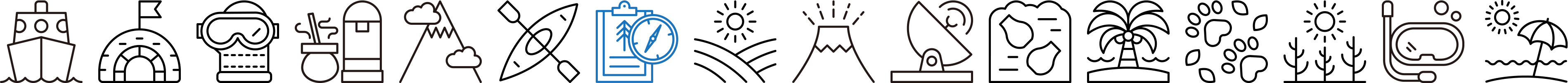
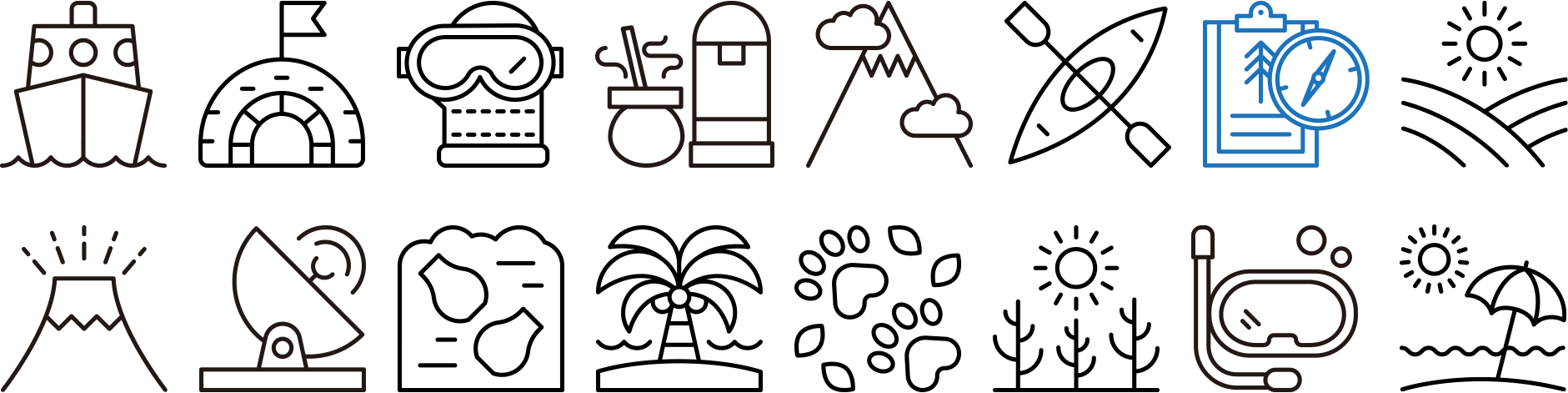
スリランカの西南海岸地域にある一つの老人施設。
主に身寄りがない老人が入居するこの施設でスタッフとして働きながら、フィールドワークを行った中村先生に、そこでの経験や民族誌などについて話を聞きました。
文化人類学 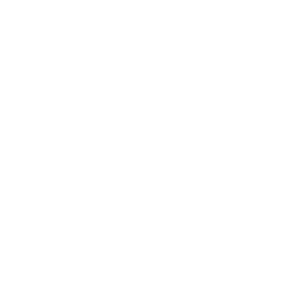 アジア
アジア
スリランカの老人施設に住み込み働きながら日々の営みを記述する
中村沙絵
NAKAMURA Sae
総合文化研究科 准教授

慈善型老人施設でのフィールドワーク
初めてスリランカを訪れたのは学部生時代の2005年。課外活動をしていたNPO法人のスマトラ島沖地震復興支援の一員としてでした。その後、卒論のために再び現地を訪れ、出会ったのが西南海岸地域に住むスリランカ人の老夫婦。安宿に滞在していた私を心配し、無償でホームステイをさせてくれました。実の娘のように真剣に関わってくれたその夫婦に心動かされ、高齢者を研究することにしました。ある意味、理想化した高齢者像を描きながらの始まりでした。
2007年から2010年にかけて断続的にスリランカに滞在し、取り組んだフィールドワークの一つが老人施設です。当時スリランカには200以上の老人施設があり、その多くが慈善団体によって運営されていました。高齢者の世話はその家族が担うことが社会的には期待されていますが、実際は家族の出稼ぎや経済状況、配偶者の不在などさまざまな理由で、一定数の高齢者が施設で生活しています。それらの施設は、施設外の人たちによる食事などの寄付によって支えられています。
シンハラ語(スリランカの公用語の一つ)を習得し、複数の施設で聞き取りを行いましたが、訪問での調査に限界を感じ、一つの施設で住み込みを始めました。入居者は約150名。その多くは未婚や寡夫・寡婦など身寄りがない人たちです。入居した時点では、身の回りの世話を自分でできますが、だんだん身体機能が低下していき、ご家族がいない場合は施設で亡くなります。私は食事の配膳や皿洗い、病院への付き添いなどを行いながら、入居者や従業員と雑談し、見聞きしたことを書き留めていきました。食事や水浴び介助の仕方への不満や、家族との関係、老いを生きる不安や憤り。そして入居者たちの苦悩を感じ、「響応」するスタッフ。
看取りにも関わりました。とても印象に残っているのが、あと数日で亡くなるかもしれないと思っていた女性が、突然「飲みたい、食べたい」と話し始め、回復しているのかと思いましたが、私が食事を介助した次の日に亡くなったことです。そのような看取りの経験に動揺し、どう考えていいのか分からなくなりました。


戸惑いを代弁してくれた小説
帰国後、助けられたのが志賀直哉の短編小説「城の崎にて」でした。主人公が投げた石が当たってイモリが死んでしまう場面があります。全くその気がなくても、石を投げたらイモリが死ぬぐらいのヒリヒリとした距離感で過ごした感触を志賀直哉が代弁してくれている気がしました。結論がない小説だというのもポイントで、そこから民族誌を書き始めることができました。
大学ではいわゆる「古典」の民族誌にふれますが、それ以外の作品が豊かにあるということを知りました。ある世界にさらされて、そこから何を考えるのかということと格闘しているようなものです。日本語に翻訳されていないものがほとんどなので、多くの人が読めるようにするのは大事なことだと改めて思っています。



『響応する身体 スリランカの老人施設ヴァディヒティ・ニヴァ—サの民族誌』(ナカニシヤ出版、2017年)

スリランカの老人施設でのフィールドワークをベースにした民族誌。施設入居者やスタッフの日常の営みや苦悩、看取りなどをとおして、老病死を支える関係性などを考察しています。






