 極圏、砂漠、火山島に無人島、
極圏、砂漠、火山島に無人島、
5640mの高山から5780mの深海まで
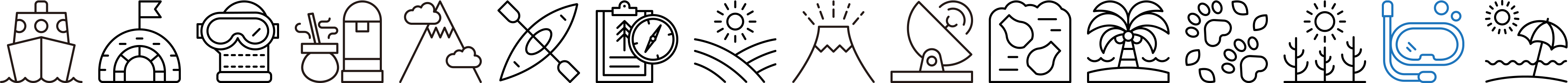
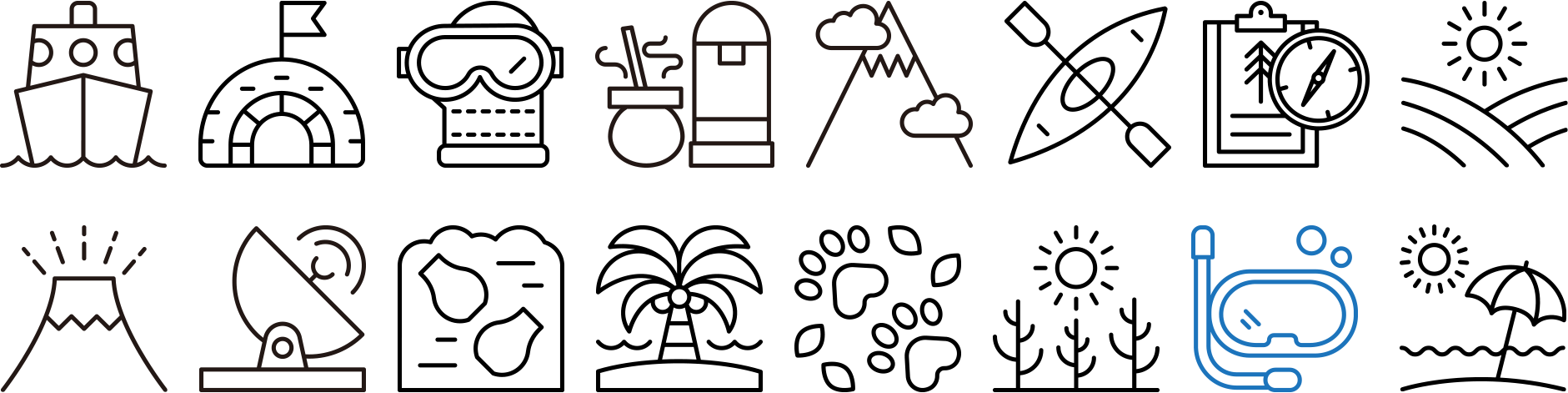
日本で最も東にある離島、南鳥島。
その周辺海域には大量の金属やレアアースが存在します。
その実態を調べるために、潜水調査船で水深5780mまで潜った大田先生。
深海に広がる世界、そして海底鉱物資源と海洋循環の関係などについて紹介します。
資源システム学  深海
深海
水深5780mの海底に潜航しびっしりと広がる鉱物資源を調べる
大田隼一郎
OHTA Junichiro
工学系研究科 講師


マンガンノジュールが密集する理由
小笠原諸島の南鳥島周辺の海底にはコバルトやニッケルなどの金属が含まれているマンガンノジュールやレアアース(希土類)を含む泥が大量にあることが知られています。それらの海底鉱物資源ができる条件などを理解するために、潜水調査船「しんかい6500」に乗船し、南鳥島周辺の海底を調査しました。2016年と2017年に計3回、最大で水深5780mまで潜りました。
マンガンノジュールは、海水中の金属が岩石や魚の骨などを核としてその周りに沈積し、長年かけてできた丸い塊です。レアアース泥も同様で、海水に含まれる微量のレアアースが魚の骨に吸着し、それが泥の中に溜まったもの。マンガンノジュールの下にあることが多く、同じ場所から見つかります。それらが実際に海底にどのように分布しているのか、またどういう大きさで、そのような形なのかといったことを調べました。


2人のパイロットと乗船し、時速2キロくらいのスピードで約2時間半かけて降下しました。水深500mぐらいまでは明るく、小さな生き物などが見えましたが、そこを超えると真っ暗です。窓から光る生き物が見えましたが、何かは分かりません。窓越しとはいえ、人間がいることができない深海が手の届きそうなところにあることが不思議でした。
海底で自由に動けるのは3時間。5、6か所に狙いを定め、ロボットアームを使って50cm角の正方形の枠を海底に置き、その中のマンガンノジュールの数を調べました。分かったのは、海流が強い場所に密集しているということ。そして、海山の裾野に多いということです。この海域には大きな海山がいくつも存在するのですが、その斜面から転げ落ちてきた岩石がマンガンノジュールの核になったためだと考えられます。


 」@工学部3号館4階。
」@工学部3号館4階。海洋循環の中でできたレアアース泥
魚の骨を大量に含むレアアース泥も海山のふもとから多く見つかっています。オスミウムという元素の同位体と魚の化石などを使って年代測定したところ、このレアアース泥は約3,450万年前に生成されたと推定されました。地球が寒冷化した時期です。南極に氷ができ、冷やされた海面の海流が沈み、海がぐるぐると循環する。その海流が南鳥島周辺海域の海山にぶつかり、上昇することによって、海の底に溜まっていた微生物が栄養とする栄養塩が光の届く海の表層に上がっていく。その結果、微生物が増え、魚も増え、魚の骨もたくさん海底に沈むことになります。この壮大な海洋循環の中で、レアアース泥が海山周辺に生成されたと考えられます。
最近は陸上の鉱山研究にも取り組んでいます。海でできた資源がプレート運動によって日本列島に近づき、大陸の下に沈み込み、それがマグマによって地上に鉱山が形成されるという循環があると考えています。日本列島もそのような地球の循環によって生まれました。この日本列島の起源から現在までの資源形成の全歴史を明らかにして、いつか歴史書としてまとめたいです。

顕微鏡で見たレアアース泥。魚の歯や骨が大量に含まれています。






