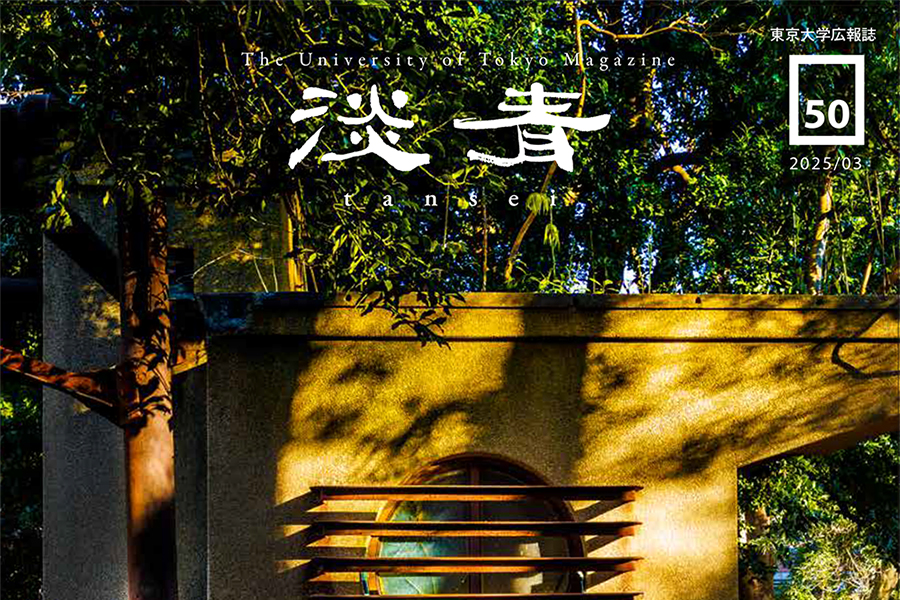理学部2号館が老朽化している
1877年に発足した理学部生物学科の本拠地として、生物科学に多くの革新をもたらしてきた理学部2号館。
しかし、建物の老朽化が進み、冷房設備の不備や外壁の損傷、漏水といった問題が進行しており、通常の使用はもちろん、研究活動にも支障をきたしています。
学生時代をこの2号館で過ごし、現在は生物科学専攻の長を務める東山哲也先生が、率直に窮状を訴えます。
壁崩れ床傾いて窓閉じず 嗚呼黄昏の理生の学舎
現代の耐震基準もクリア

HIGASHIYAMA Tetsuya
理学系研究科 教授
理学部2号館は1934年の竣工で、内田祥三設計の建築のなかでは中期のものです。関東大震災を受け、耐震性の強い建物を作ろうとするなかで生まれた建物です。おかげで現在の耐震基準もクリアしています。この棟に入っているのは、1877年発足の生物学科(生物科学専攻)です。NHKの朝ドラ「らんまん」に出てきた青い建物の植物学教室は、いまの薬学部の辺りにありました。その後、動物学教室と離れて植物園に移りますが、2号館ができて再び合流し、人類学教室も加わっていまに至ります。
しかし、竣工から90年が経過して外壁が崩れてきており、装飾部は特に傷んでいます。危険なので外構には防護網を張り巡らしています。建物内部では、床が傾き、天井はたわみ、閉まらない窓や開かずの扉も。古い電気ブレーカーが残り容量も小さく、新しい実験機器を入れたいときは一般的な100V機器であっても電源確保が大変。給排水管も古く、すぐ詰まります。生物科学では無菌状態での培養が必須ですが、私の研究室ではコンタミネーション※が頻発します。クリーンベンチで操作しても、空間に胞子が多いのか、培養器に入れておくとカビが生えるのです。何度か空調面の改善を試みましたが、解決できず、仕方なく培養は共同研究先に頼んでいます。
※科学実験における汚染、混入
我慢すればなんとか過ごせるレベルですが、無意識に活動を抑制する傾向が蓄積しています。もちろんできることはやってきました。昨年度は、専攻の蓄えを投入し、研究科の支援も得てトイレ改修を行いました。以前は用のたびに隣の建物へ向かう構成員も少なくなかったのです。蓄えは尽きましたが、勉強をがんばって入学した学生に劣悪な環境で学ばせるのは教員として忸怩たる思いです。






生物学の歴史息づく建物
一方で、この歴史ある建物をもっと役立てたいとの思いもあります。たとえば中庭。二つあるうち、動物学科が管理した北側の庭には噴水の跡があり、昔は水が噴いていましたが、長く使われていません。植物学科が管理した南側の庭には植栽がありましたが、荒んでいます。中庭の壁も傷みが激しく、出入口に防護用のトタン屋根をつけ、立ち入る際にはヘルメットを着用したり壁沿いを歩かぬよう注意したりしています。ここをうまく整備して、地域の人や中高生に生物学の歴史や最新研究を伝える場にできないかと思っています。
私は「らんまん」でも描かれたイチョウ精子発見の系譜に連なる研究をしており、主に被子植物の受精がテーマです。花粉が付くとそこから管が伸びて受精に至ります。管はどうやって卵細胞の位置を探すのか、仲間の花粉のときだけ受精するのはなぜかといった機序の研究です。助手時代にここで進めた研究のなかで、卵の方向を教える花粉管誘引物質を発見し、「ルアー」と名付けました。釣り好きが多い研究室でインスパイアされての命名でした。
5月には、建築ファンが都内の建物を巡る東京建築祭 というイベントに参加します。大隅良典先生など多くの生物学者が過ごした理学部2号館。生物学の歴史が息づく建物にインスパイアされに来てみませんか。
というイベントに参加します。大隅良典先生など多くの生物学者が過ごした理学部2号館。生物学の歴史が息づく建物にインスパイアされに来てみませんか。






老朽化が進む理学部2号館が存続の危機にあります。建物の修繕・整備を行い、基礎生物学の次の100年へバトンをつなぐためのご支援を。