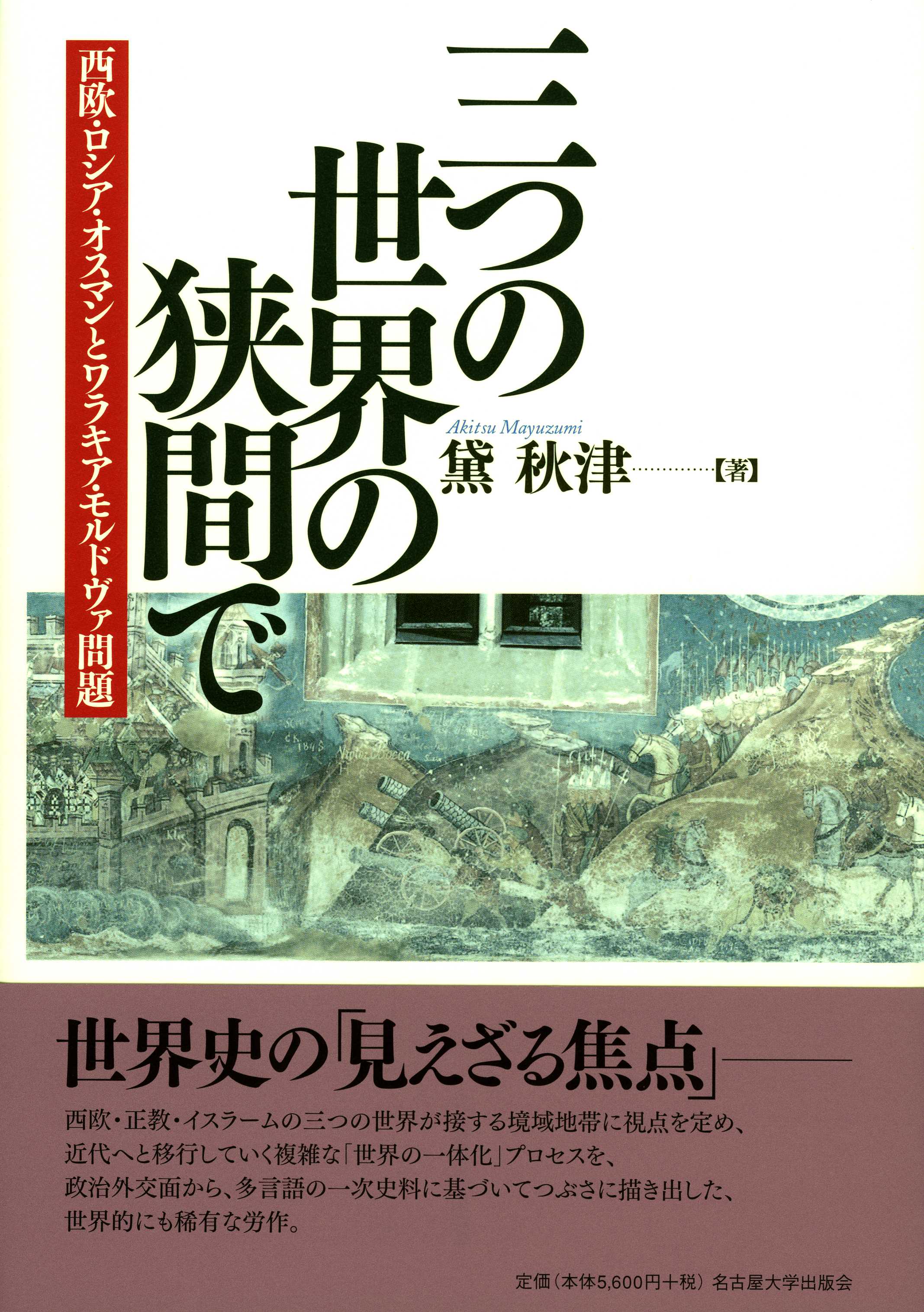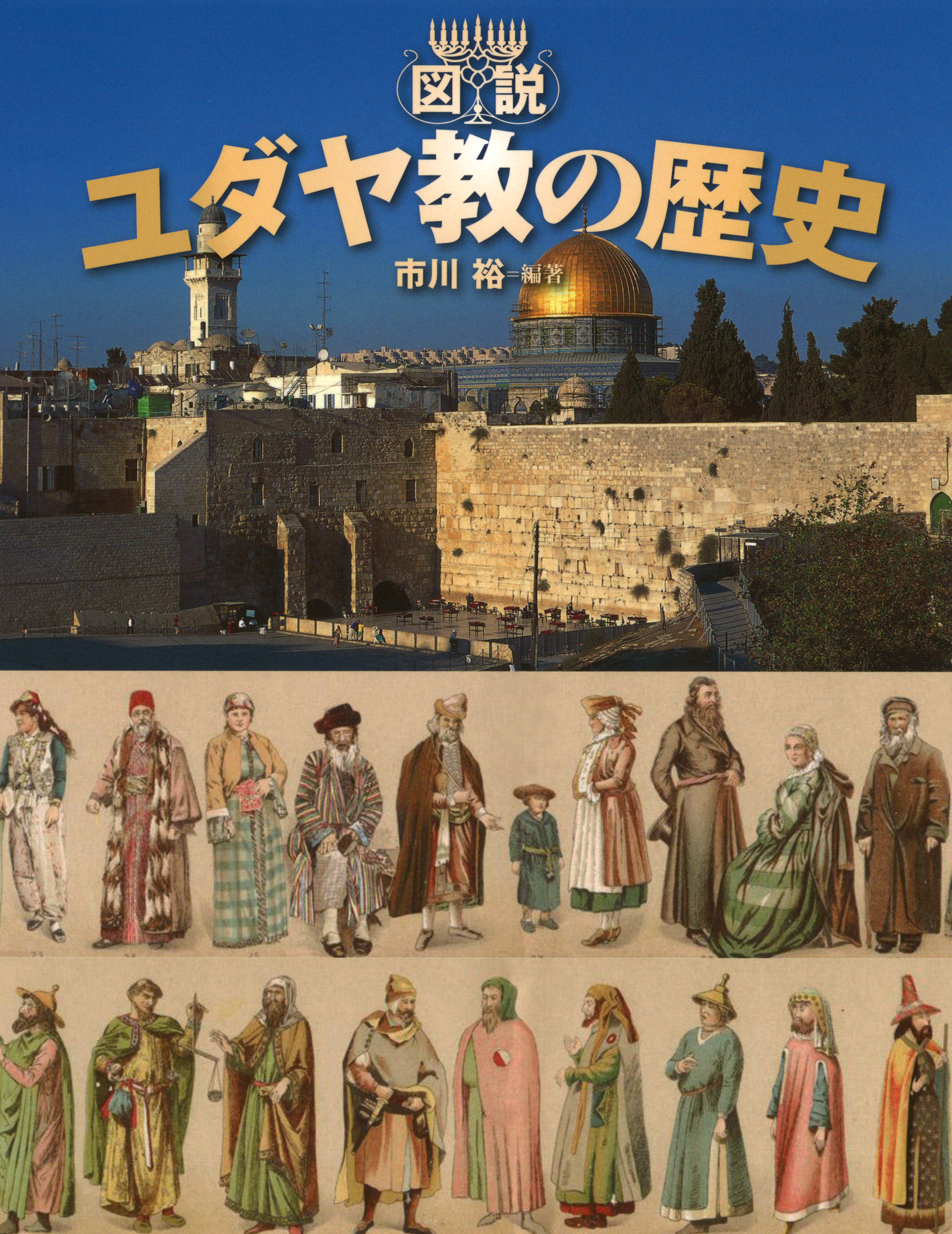副題に『ワラキア・モルドヴァ問題』とあるものの、本書はルーマニアの歴史の本ではない。ワラキアとモルドヴァという、領域的に現在のルーマニアの主要部分を成す二つの公国に焦点を当てながらも、その周囲に位置する西欧諸国、ロシア帝国、オスマン帝国が、18・19世紀にこの両公国の問題にどのように関わりそして相互に関係を深めていったのかを、それぞれの史料を参照しながら検討したものであり、近世近代移行期におけるヨーロッパ大陸周縁部の国際関係を扱った本である。
一般に、現代グローバル世界形成の歴史的過程として、前近代まで地球上の各地に存在していた「文明圏」あるいは「文化世界」としての諸「世界」が、近世以降の「西欧世界」による対外進出により、次第に西欧中心のシステムに包摂され、その結果、地球を一つのシステムが覆うことになった、と理解される。もちろん大枠ではそのような理解が妥当だとしても、その実際の歴史的プロセスはそれほど単純なものではなかったに違いない。では、具体的にどのようにして結びついていったのか? カトリックを文化的基盤とする「西欧世界」の諸列強、ギリシア正教圏としての「東欧世界」の盟主ロシア帝国、そして「イスラーム世界」を代表するオスマン帝国という、三つの「世界」の諸政治勢力が激しくせめぎあったバルカン、その中でも、18世紀後半から19世紀前半のワラキア・モルドヴァ、という時間と空間に限定して、具体的実証的にその結びつきの過程を検証したのがこの本なのである。
現在のルーマニアの地はオスマン帝国による征服後も自らの国を持ち続け、属国として帝国秩序に連なった。帝国辺境という地理的条件に加え、こうした間接支配であったがゆえに、18世紀になるとこの両公国には、他のバルカン地域に先がけて諸外国の影響が見られることになる。18世紀後半のロシアによるこの地域への本格的な関与を皮切りに、ハプスブルク帝国、フランス、イギリスが次々と進出を開始し、18世紀後半以降、それまでオスマン帝国の内政問題であった両公国問題は、列強が深く関与する重要な国際問題になった。その結果、同問題をめぐってロシア、オスマン帝国、西欧諸国という政治勢力は相互に関わりを深め、三つの「世界」がさらに結びついてゆく。同じことは、セルビア、ギリシア、ブルガリア、黒海通商、イスタンブル海峡通行などの様々な問題を通じても起こっており、こうした一連の積み重ねにより、いわゆる「世界の一体化」がおし進められることになったのである。
本書は、オスマン帝国辺境の属国の問題を通じて、オスマン帝国とロシアが共に、西欧諸国が形作るシステムに巻き込まれてゆく国際政治のダイナミックな動きを描いている。そのような問題にご関心のある方にご一読いただければ幸いである。
(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 准教授 黛 秋津 / 2016)
本の目次
序 章 西欧・正教・イスラーム世界の狭間で
1 本書の課題
2 「世界の一体化」とワラキア・モルドヴァ
3 オスマン帝国秩序の中のワラキア・モルドヴァ
4 研究史
5 史料について
6 本書の構成
第1章 18世紀前半までの西欧・正教・イスラーム各世界間の政治的相互関係
—— オスマン帝国の優位から西欧・ロシア・オスマンの均衡へ
1 17世紀後半までの西欧世界・正教世界・イスラーム世界
2 17世紀末-18世紀前半の西欧・ロシア・オスマン関係の変化
第2章 18世紀前半までのワラキア・モルドヴァと周辺世界
—— オスマン帝国との宗主-付庸関係、西欧・ロシアとのつながり
1 17世紀後半までの両公国をめぐる国際関係
2 18世紀ファナリオット時代の両公国と周辺諸国
第3章 キュチュク・カイナルジャ条約
—— 国際問題としてのワラキア・モルドヴァ問題の出発点
1 ロシア・オスマン戦争(1768-74)の開始と両公国の状況
2 和平への動き
3 ロシア・オスマン間の和平交渉とキュチュク・カイナルジャ条約
第4章 1774年以後の三世界間の政治的相互関係
—— ロシアとハプスブルク帝国によるワラキア・モルドヴァ進出の開始
1 両公国へのロシアの進出とその挫折
2 ロシア・ハプスブルク帝国の領事館開設問題と1784年の協約
3 公任免問題とロシア・オスマン戦争(1787-92)
第5章 共和国フランスのワラキア・モルドヴァ進出
—— フランスとイギリスの両公国問題への関与の始まり
1 共和国フランスの両公国進出
2 1802年のワラキア・モルドヴァ公宛勅令とその背景
第6章 ナポレオン戦争期のワラキア・モルドヴァ問題
—— フランス・ロシア・オスマン帝国の狭間で
1 ロシア・オスマン戦争(1806-12)の勃発要因としての両公国問題
2 戦争中の動きとブカレスト条約
終 章 近代移行期における三世界の中のワラキア・モルドヴァ
—— その後の展望とまとめ
1 ウィーン体制下の両公国問題 —— 概観と展望
2 まとめ
あとがき
注
文献目録
索 引
関連情報
松井真子氏 評『歴史学研究』No.942 (2016年3月) pp.56-60
http://www.unp.or.jp/syohyo2015#16030102
https://cir.nii.ac.jp/crid/1010000782295118850



 書籍検索
書籍検索