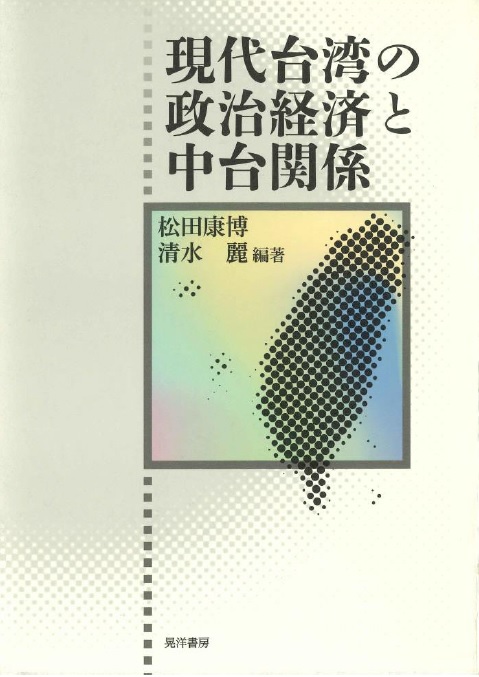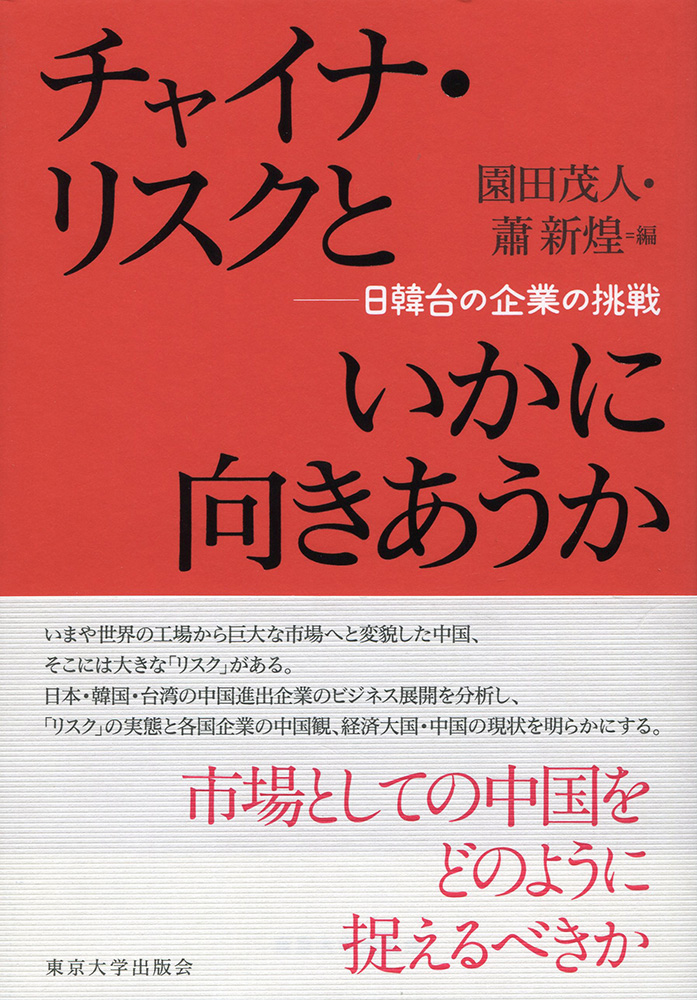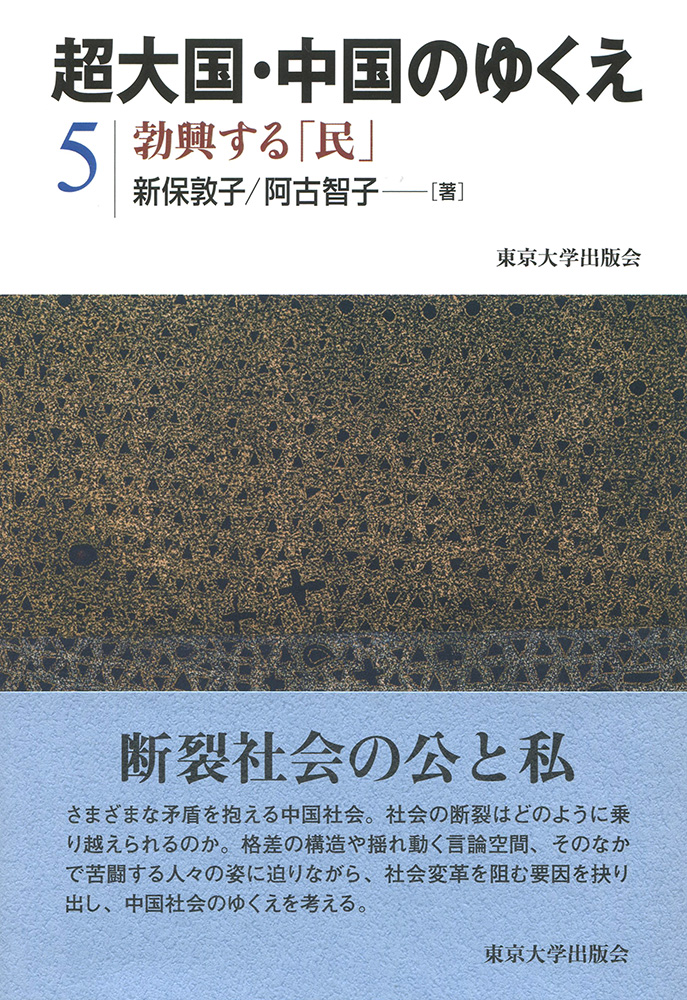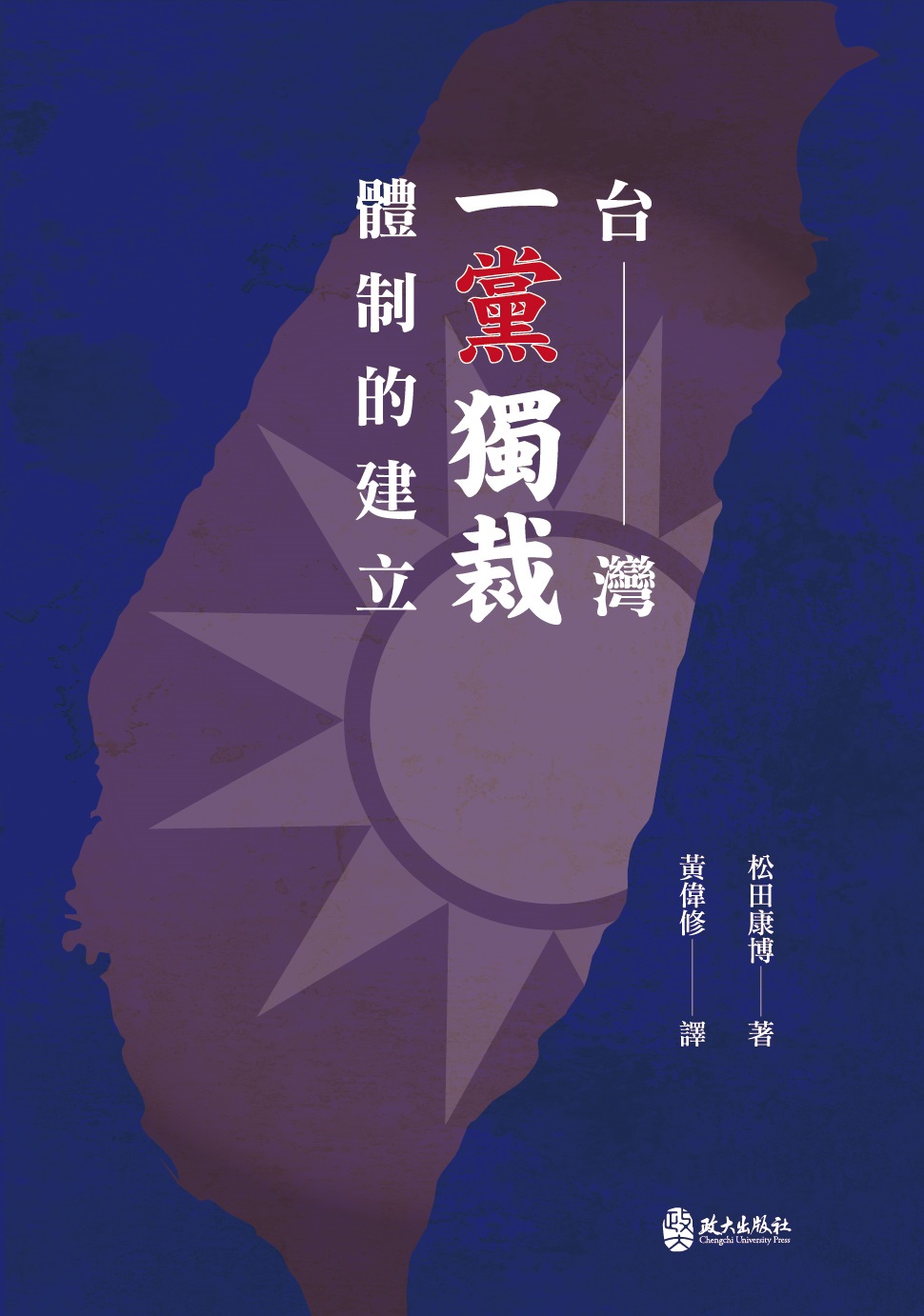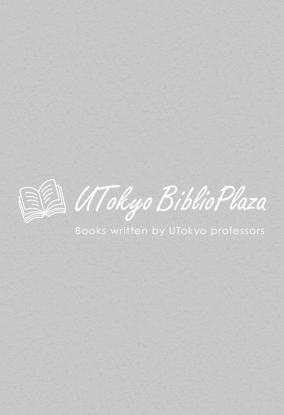
書籍名
Journal of Contemporary East Asia Studies (Vol.4, No. 2, 2015) “Cross-Strait Relations under the Ma Ying-jeou Administration: From Economic to Political Dependence?”
本誌の特集号は、科研費プロジェクトである「繁栄と自立のディレンマ - ポスト民主化台湾の国際政治経済学」(2010年度~2012年度)の研究成果を発表した『東洋文化』 (第94号、2014年3月) 所収論文の一部を、英訳してアメリカの国際会議で発表し、加筆修正の上あらためて公刊した論文集である。
本研究プロジェクトの目的は、中国が大国化したことにより、台湾が「繁栄と自立のディレンマ」に陥るようになった中台関係の構造を明らかにすることにある。誰が政権の座に着いても、台湾が直面する課題は非常に対処困難なものである。中国の経済力・軍事力・外交力が急速に増大しているためである。
他方で、台湾は承認国が少なく、同盟国もなく、武器を売却する国も僅かである。今やアメリカを例外として、中国の圧力をはねのけて台湾に武器を売却する国はほとんどなくなった。台湾の存在は米中という大国の政策に依存しているのであり、基本的な安全が保障されない構造の下で、台頭する中国に相対する台湾の選択肢は、年々狭まっている。
伝統的に、台湾は国防強化と米日両国との実質的な関係強化を重視してきたが、21世紀に入ると中国に対する単純な勢力均衡政策は、すでに不可能になっていた。陳水扁政権 (2000-08年) が、アメリカや日本に露骨な対中包囲網形成を呼び掛けてもうまくいかなかったのはこのためである。かといって、中国に対する安易な妥協は、台湾の「主権」を弱める作用を生む。
何よりも、台湾経済の対中国依存は年々強くなっている。台頭する中国に対して、台湾が中国からの自律性を維持しようとすれば、繁栄を犠牲にしなければならず、逆に繁栄を追求すれば自律性をある程度犠牲にしなければならない。こうしたディレンマの中で、馬英九政権は、繁栄がなければ台湾の自律性もない、そして中国との関係改善によって初めて台湾の国際空間は確保・拡大可能になるというロジックの下、中国との経済関係深化による繁栄の維持を選択した。
馬英九政権は、就任一年あまりの間に中台間の非公式対話を再開させ、直航便を定期化し、中国からの観光客を受け容れ、中国からの投資を拡大し、金融協力や犯罪者の引き渡しなどの諸協定を結び、また3年目には野党の激しい反対にかかわらず経済協力枠組みも締結し、急速に中国との関係緊密化を進め、再選された。また、馬英九政権は、アメリカの支持を回復し、中国の黙許の下で、世界保健機関 (WHO) のオブザーバー参加さえ実現したのである。
他方で、経済を優先して中国との関係を処理する馬英九政権は、台湾内部で、経済繁栄のために自立や主権および安全保障を犠牲にしているとの批判を浴びた。中台関係安定による経済的な発展は必然的に政治的な変化をもたらし、その他隣国との関係も変化する。本特集号所載の各論文はこうした変化に焦点を当て、台湾政治、中台関係、日台関係、日中関係などの分析に取り組んでいる。
(紹介文執筆者: 東洋文化研究所 教授 松田 康博 / 2017)
本の目次
Yasuhiro MATSUDA
Policymaking in Taiwan’s Semi-Presidentialism: A Case Study of the Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA)
Mitsutoyo MATSUMOTO
Ma Ying-jeou’s Doctoral Thesis and Its Impact on the Japan-Taiwan Fisheries Negotiations
Yoshiyuki OGASAWARA
The Role of the KMT in the Ma Ying-jeou Administration’s Mainland Policy Making: A Case Study of the KMT-CPC Platform
Wei-Hsiu HUANG
The Development of Japan-China Relations in the Period of Stability in Cross-Strait Relations
Akio TAKAHARA
関連情報
ァイルにて入手可能
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/24761028.2015.11869083



 書籍検索
書籍検索


 eBook
eBook