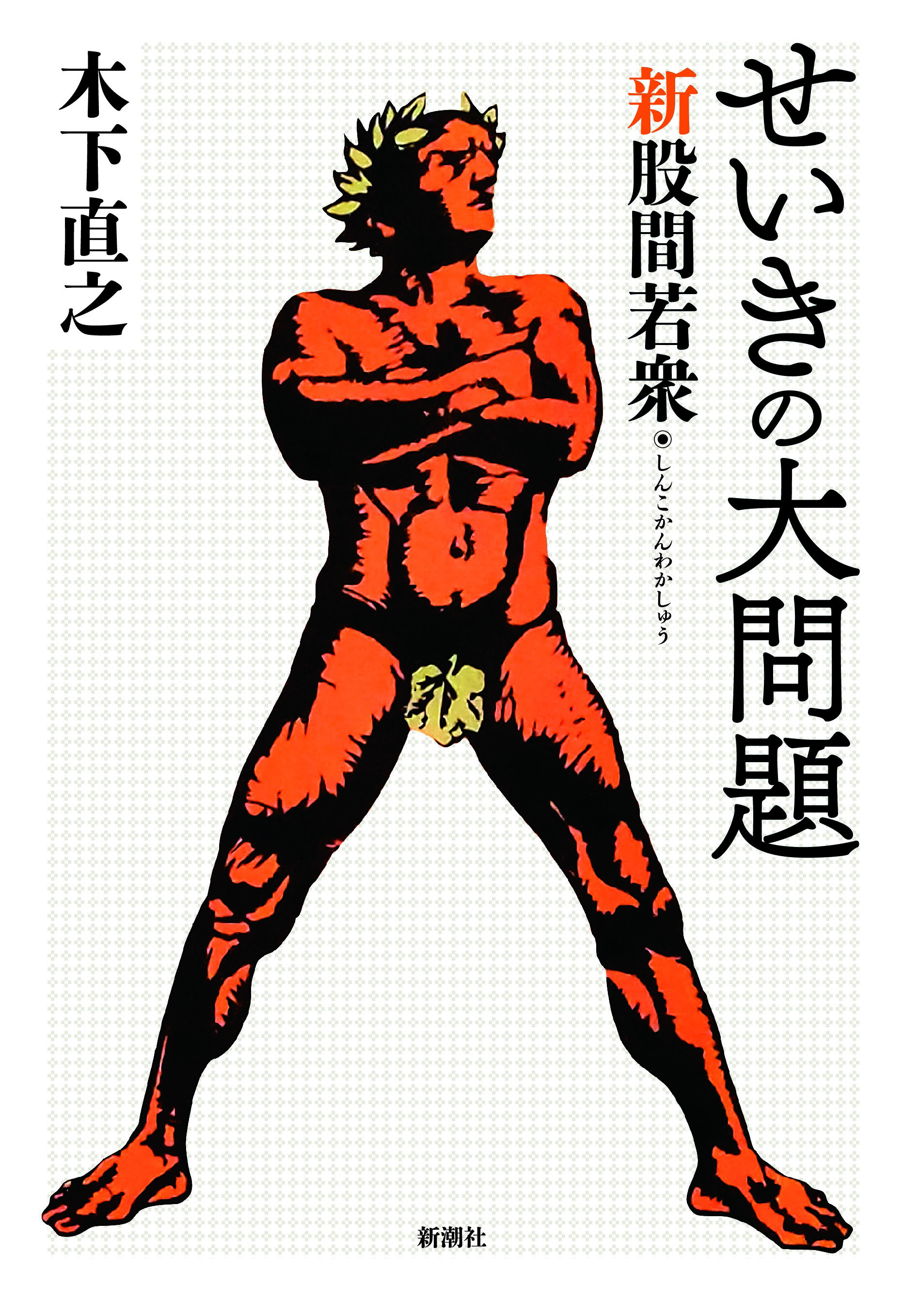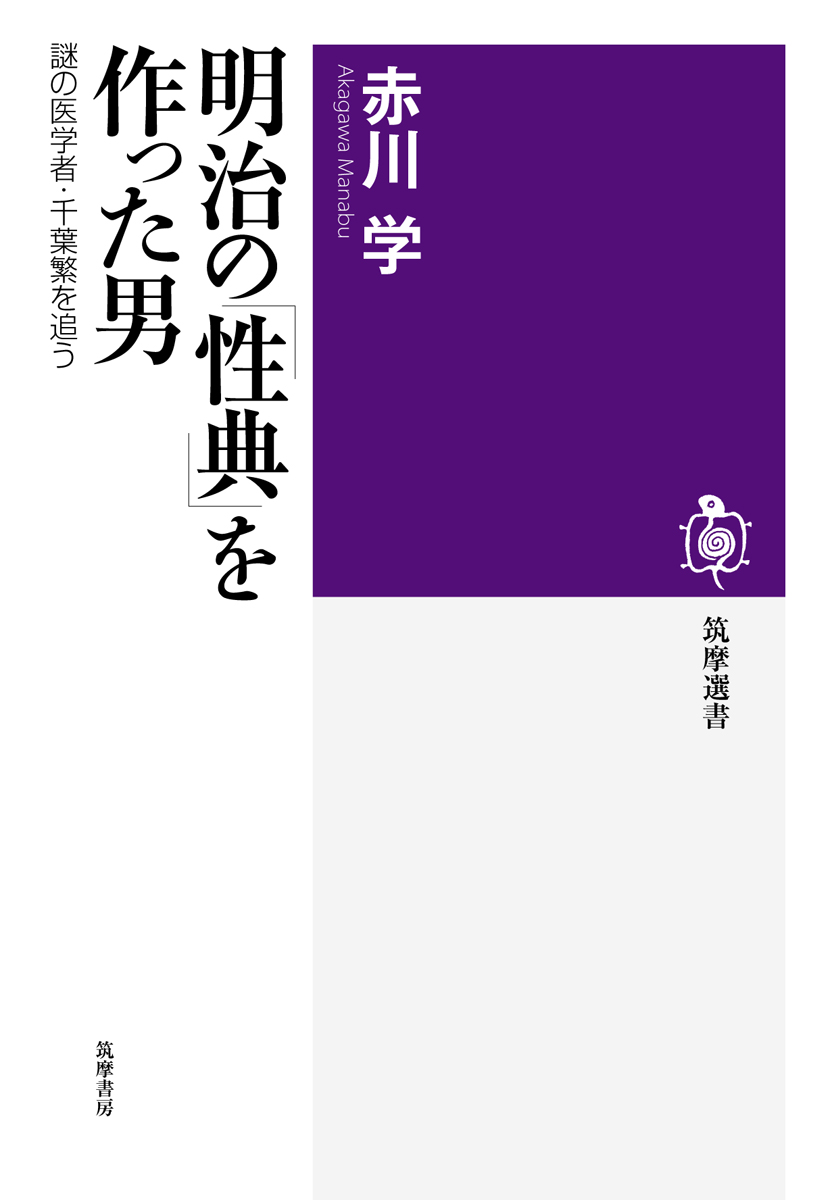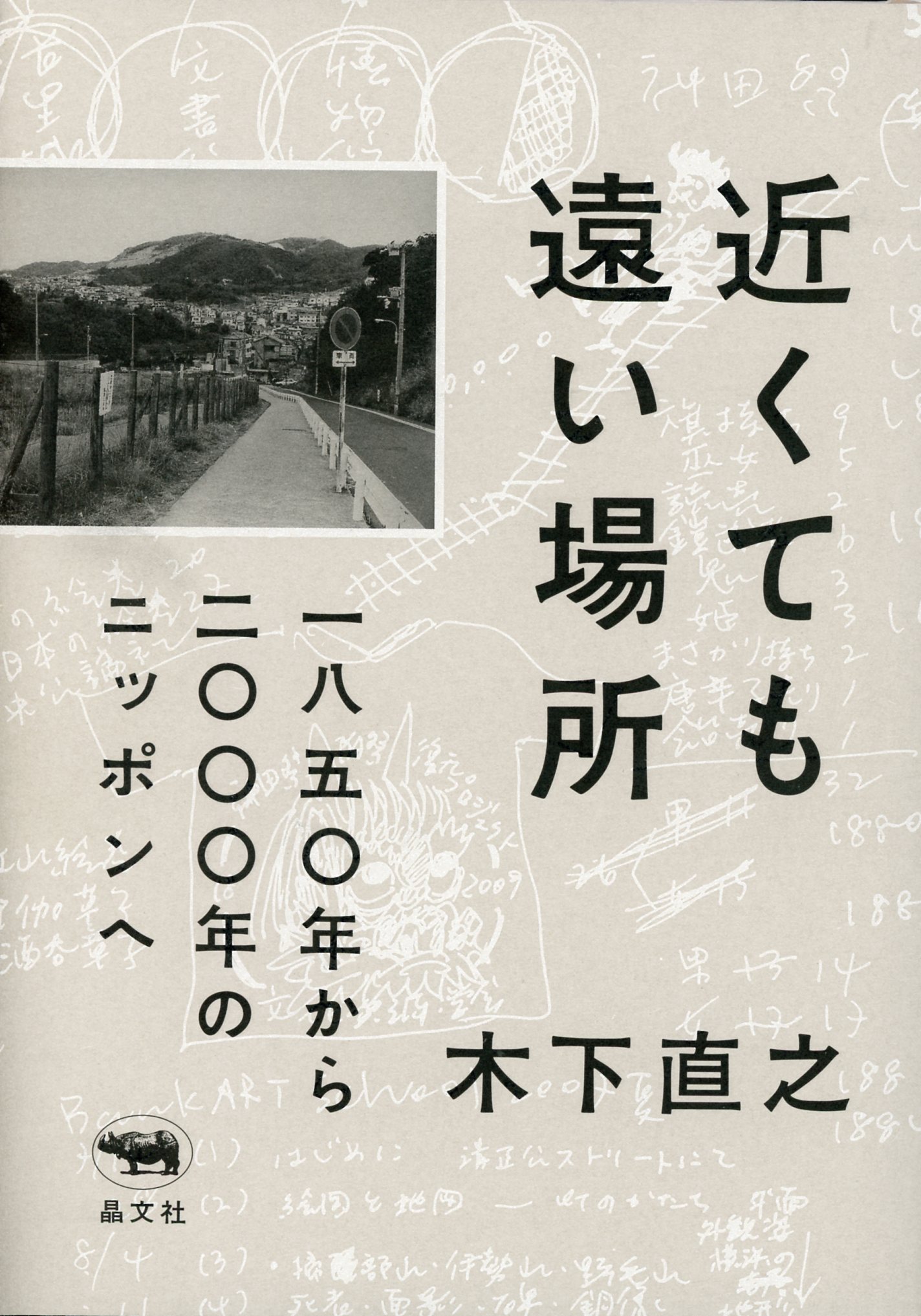書名の「せいき」とは、第3章「日本美術の下半身」に収めた「清輝の、性器の、世紀の大問題」という論考に由来し、少なくとも3つの意味を重ねた、要するに駄洒落である。真面目な問題をふざけて書くという姿勢がいつの間にか身についてしまったため、書名を決めなければいけない最後の段階に至ると、この内なる圧力から逃れられない。願わくば、大真面目な論文の注や参考文献にこのふざけた書名がそっと差し込まれんことを、などと考えているのだから始末に負えない。
ではこれがいかなる「大問題」であるかをお話しよう。
第1の「清輝」は黒田清輝、明治の洋画家、法律学を学びにパリに留学し、画家になって1893年の日本に帰ってきた。西洋美術のヌードが芸術であることを日本人に伝えようとした。しかし、それはなかなか伝わらず、裸を描いた猥褻な絵だと受け止められた。すでに禁じられていたとはいえ、春画が身近にあった時代だ。
とりわけ第2の「性器」が問題視された。しかし、当時は性器という言葉は用いられず、造化機とか生殖器とか呼ばれたが、それは医学用語であって、黒田の描いたヌードを評する際には局部とか陰部とかが用いられた。両足の付け根の部分がなぜこれほど問題になるのか、話は旧約聖書のまだ人類が2人しかいなかった時代にまでさかのぼる。
第3の「世紀」は大問題と一番相性がいい。文字どおり世紀の大問題だと思うのは、20世紀が幕を開いた1901年に、白馬会展に出品された黒田の「裸体婦人像」(静嘉堂文庫美術館蔵) が警察のお咎めを受け、描かれた女の下半身が隠れるように、絵画の下半分に布が巻かれるという珍妙な光景が出現したからだ。これを「腰巻事件」と呼ぶ。
この3つの「せいき」が重なり合って生じたことは、西洋に追いつけとばかりに背伸びをした明治の日本の特異な出来事だっただろうか。そんなことはない。2014年の夏、愛知県美術館の展示室に並んでいた写真家鷹野隆大さんの作品に警察が撤去を求めるという出来事があった。美術館と写真家が相談の上、被写体である2人の裸の男の下半身を布で覆った。20世紀の大問題は21世紀の大問題でもあった。
要するに、芸術か猥褻かという二項対立が19世紀から20世紀にかけて成立し、現代の日本社会にもしっかり生きていることを、第6章「猥褻物チン列頒布論」において明らかにした。鷹野隆大事件と同じ夏に、鷹野さんとは異なり、逮捕され拘置所にまで入れられた美術家ろくでなし子さんの起訴、公判、判決までを追いかけた。弁護団から求められて東京地方裁判所に提出した「ろくでなし子裁判に対する意見書」も収録している。
春画も視野に収めた。近代社会が隠そう隠そうと努めてきた「性器」を、前近代の春画は逆に好んで誇張した。このふたつの社会の連続と断絶をとらえることが本書の問題提起である。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 教授 木下 直之 / 2018)
本の目次
股間風土記
日本美術の下半身
頓珍漢な約束
清輝の、性器の、世紀の大問題
腰巻事件前夜
筋骨隆々股間葉々
ゆるい男
被爆者の下半身
春画ワ印論
春画のある風景
暁斎の旬の春画を味わう
春画と明治日本
性地巡礼
猥褻物チン列頒布論
2014年夏の、そして冬の性器をめぐる二、三の出来事
ろくでなし子裁判に対する意見書
ろくでなし子裁判傍聴記
あとがき



 書籍検索
書籍検索