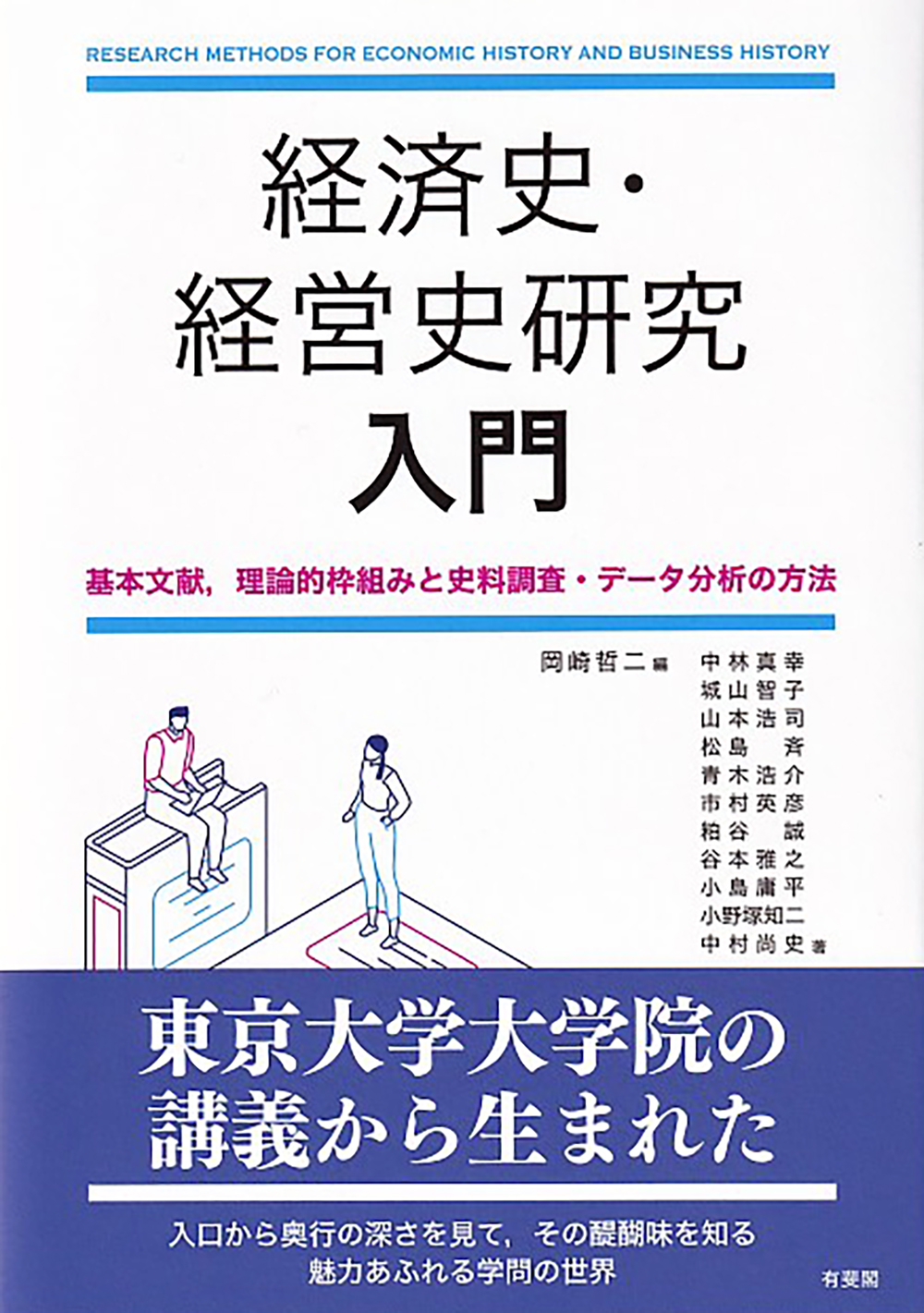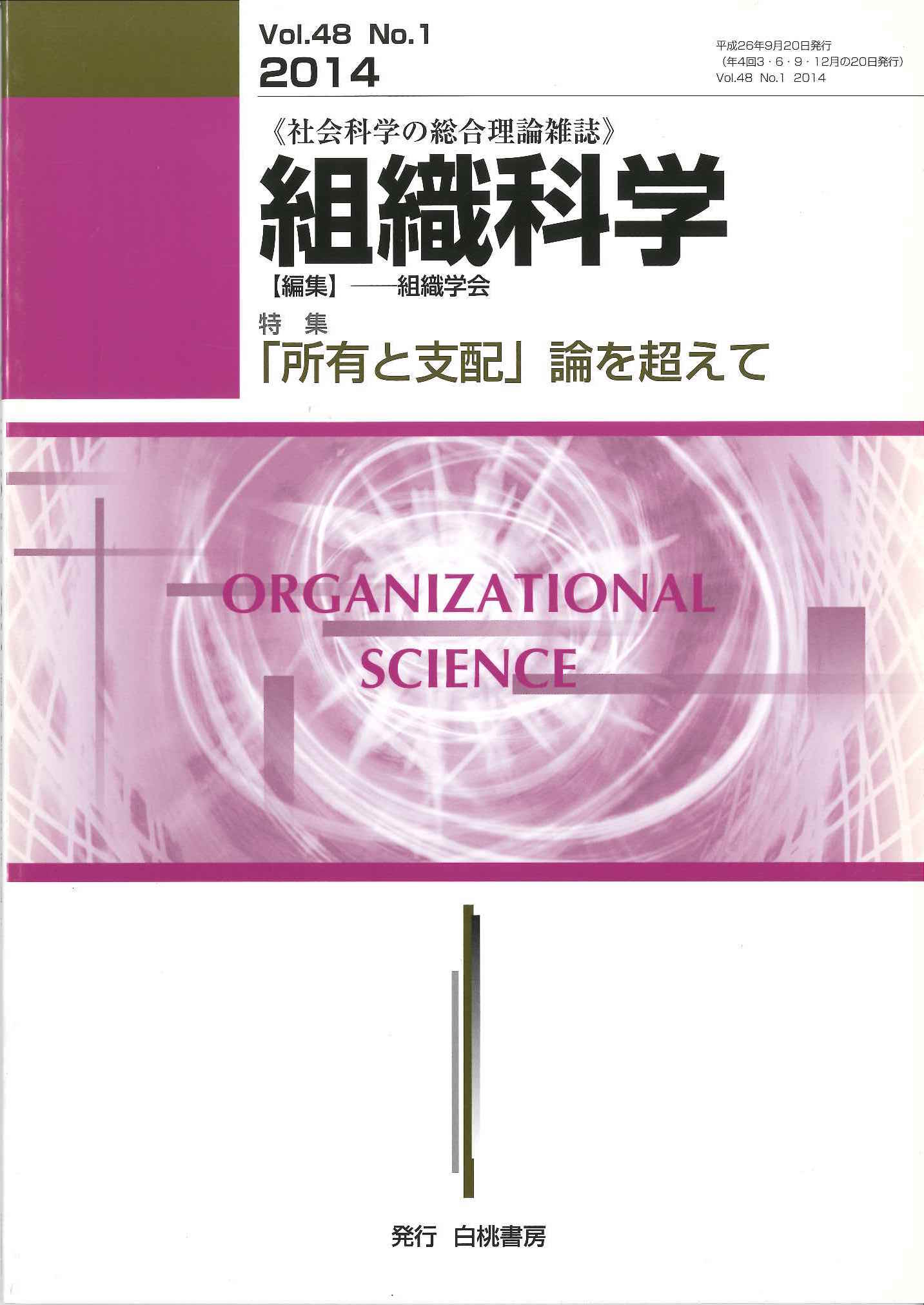本書は、Philip Scranton and Patrick Fridenson, Reimagining Business History, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2013の全訳であり、日本語版の刊行に当たって著者より日本語版への後書きが加えられた。
経営史学は20世紀に生まれた新しい学問である。20世紀初頭には発展段階説が有力で、法則史観的な考え方が有力であった。ところがハーバード大学にビジネススクールが開設され、ケースメソッドによる教育が始まり、そこで経営史の授業がおこなわれるようになると、経営者の判断によって企業の命運が左右される局面が取り上げられることとなった。当初の経営史学は、法則史観へのアンチテーゼとして、企業の個性を描き出す作業に没頭し、多数の著作が刊行された。しかし企業の個性の重視は、多様な個性を打ち出すことで何を得られるのか、という積極的主張に欠けることが自覚されるようになった。
この限界を突破したのが、Alfred D. Chandler, Jr., Strategy and Structureであり、1950年代に明確となった事業部制組織の形成過程を、当時の一流企業の組織発展の深いケース分析にクロスセクションの事業部制採用の動向を組み合わせて、説得的に展開していた。当時のミクロ経済学が企業を「質点」とみて、生産関数としか理解できなかったことの弱点を突いたのである。チャンドラーにより、巨大企業の出現、組織管理、多角化戦略と事業部制組織の採用 (戦略と組織) などの「軸」が発見されたことにより、個性の描写に一般性が与えられるようになったのである。
ところがチャンドラー説は、1980年代以降に、大きな挑戦を受けることとなった。チャンドラー説は情報の非対称性を含むウィリアムソンの説と親和的であったが、コーポレートガバナンス理論の発展が、経営者が必ずしも株主の利害に沿わないことがあり得ることを明らかにしたし、IBMの経営危機に象徴されるように統合された多角化経営が、必ずしも企業経営の発展方向といえないのではないか、ネットワークなどの柔軟な発展があり得るのではないか、との疑問も提起されるにいたったのである。
これにより経営史学は、ポスト・チャンドラーの時代に入り、世界の経営史学者は新しいパラダイムがありうるのかも含めて新しい方向を求めている。チャンドラーの次の世代に位置するスクラントンとフリデンソンというアメリカとフランスの一流の経営史家が、その「一つの」方向を示したのが本書である。本書は西洋でのさまざまな学問分野の概念が、新しい経営史のツールとしていかに有用であるかを示したものであり、西洋の新しいトレンドを知る上で、極めて重要な著作といえる。
(紹介文執筆者: 経済学研究科・経済学部 教授 粕谷 誠 / 2017)
本の目次
第I部 罠―経営史家が避けるべきこと
1: 間違った具体化
2: 国家が常に「なかに」あることを認識しない誤り
3: (必要な) 制約としての時期区分
4: 企業を特権化すること
5: 後付けの合理化
6: 新しい支配的パラダイムの探求
7: 科学主義
8: 言説を真に受けて,数字を当然のように受け取ること
9: 合衆国 (あるいは西洋) を基準・規範とみなすこと
10: 急いで現代に向かうこと
第II部 機会―主題の領域
1: 人工物
2: 創造と創造性
3: 複雑性
4: 即興
5: 極小ビジネス
6: 軍隊と戦争
7: 非営利団体と疑似企業
8: 公と私の境界線
9: 再帰性
10:儀式的および象徴的行為
11:失敗の中心性
12:不確実性の多様性
第III部 展望―最新の文献にみられる期待されるテーマ
1: 所有権の脱構築
2: 詐欺といかさま
3: 帝国から新興国へ
4: ジェンダー
5: 専門的サービス
6: プロジェクト
7: 古典的なテーマの再評価
8: 規格
9: サバルタン
10: 国境を越えた交流
11: 信頼、協力、ネットワーク
第IV部 資源―創造的な概念と枠組み
1: 想定
2: 実践共同体
3: 流れ
4: 主体を追いかけろ
5: 過ぎ去った未来
6: 記憶
7: 近代
8: 危険
9: 空間性
10: 時間
結語
日本語版への結語



 書籍検索
書籍検索