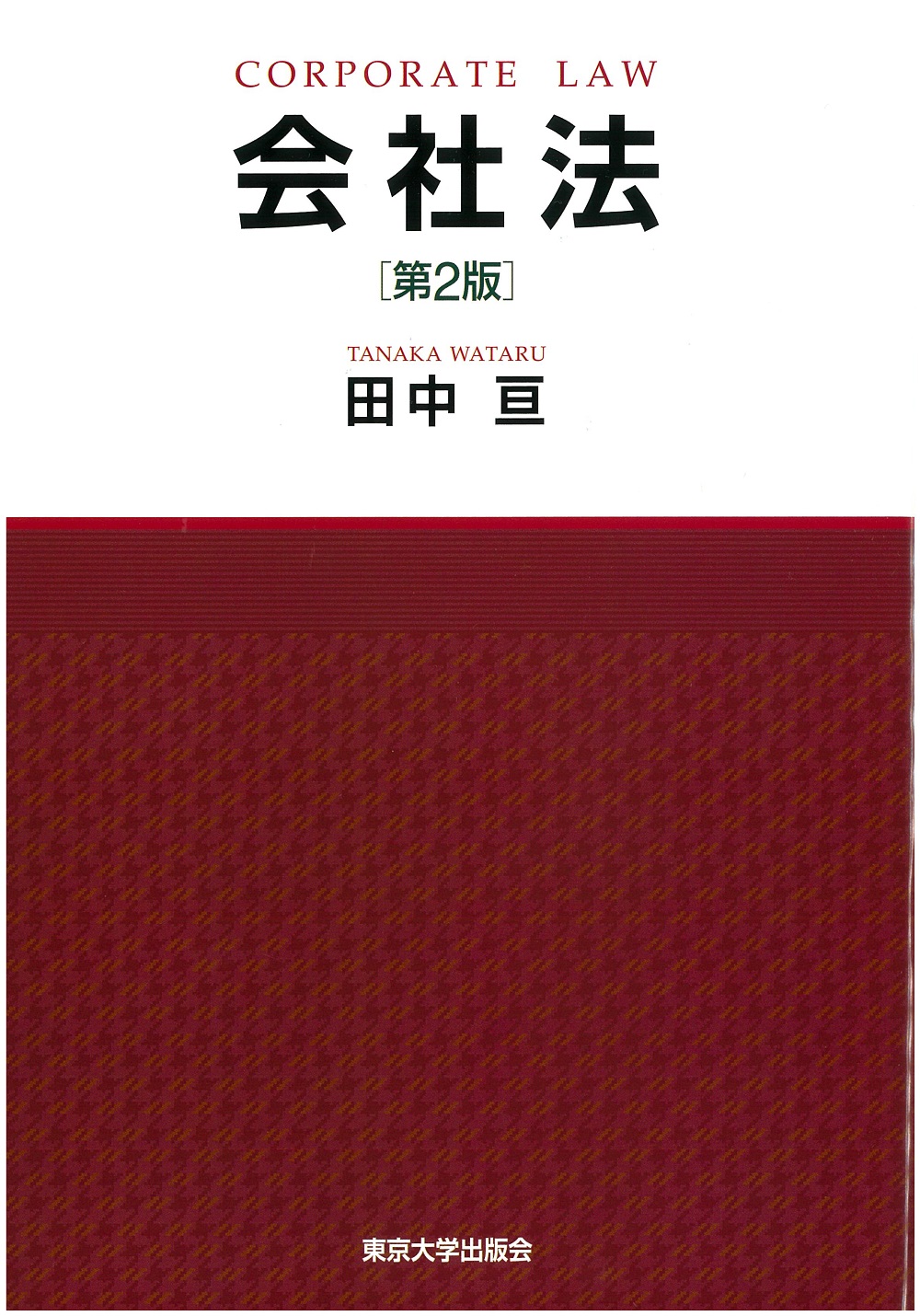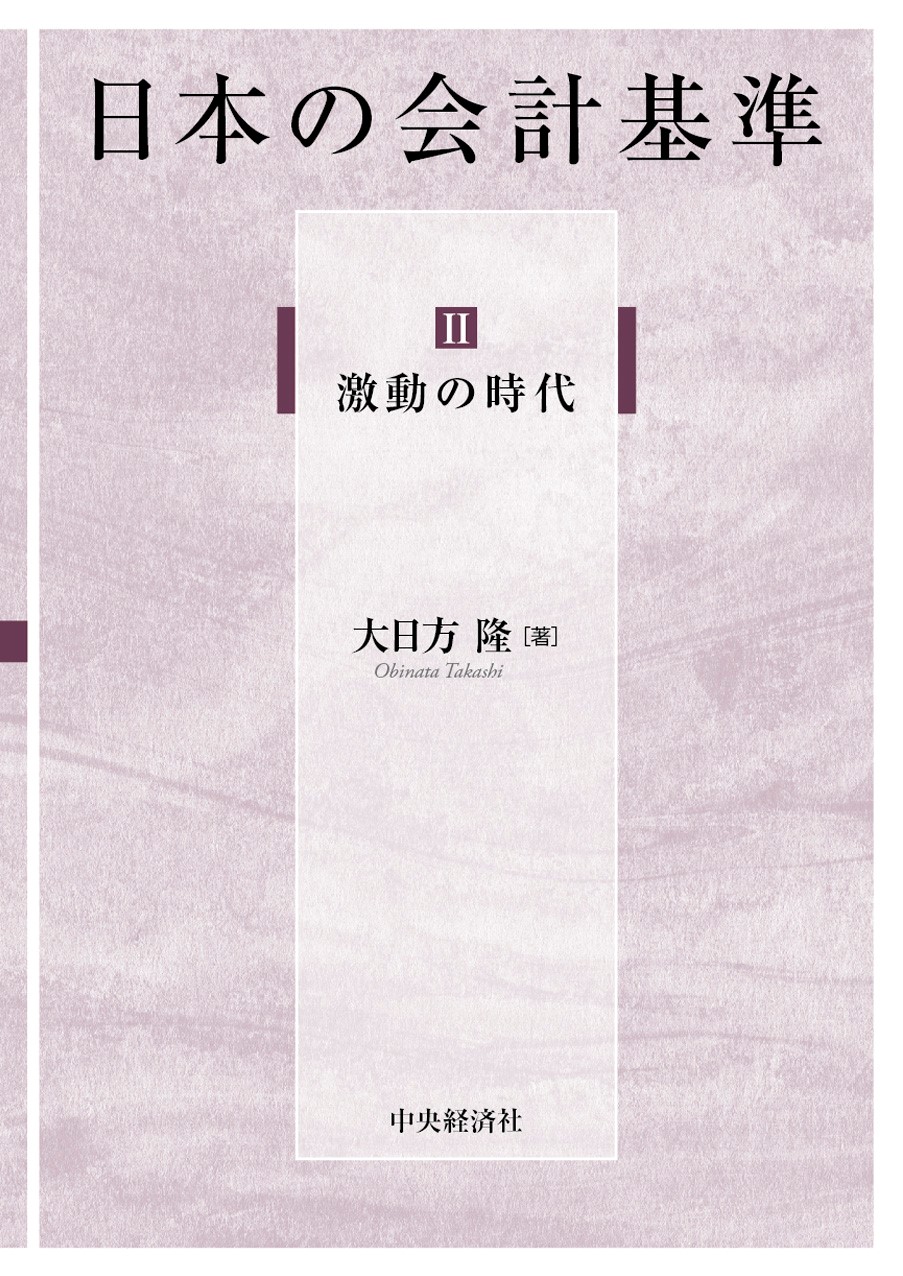初対面の人に自己紹介をする際「経営学者で、最近は経営と法律との関係を研究しています」と言っても、あまり違和感を持たれないらしい。最近でも、コーポレート・ガバナンスや会計不正、あるいは過労死など、経営と法に関する様々な問題が出てきていることにもよるのだろうが、「へえ、そうなんですか」というぐらいが普通の反応である。
しかし、実のところこれまで、経営学と法学との間の接触は驚くほどに少なかった。経営学者は法律的な問題については若干触れても積極的に論じようとはせず、一方法学者 (特に会社法の研究者) は特定の事件について判例評釈をすることはあっても、会社経営の中身についてはせいぜい注釈で触れるぐらいであった。
経営学の側から見て、上のようになった理由は実はよく分かる。法律あるいは法学は前提知識が多すぎて手が出せないのである。一方、法学の側で経営について積極的に論じなかった理由はわからない (経営学に必要な前提知識はおそらく法学より少ないので) が、そもそも法学というのはあくまで法律について論じるものだという自己規定があったように見える。いずれにせよ、経営学と法学、特に会社法学は同じ対象を扱ってきたにもかかわらず、お互いに距離を保ってきた。
この論文は、このような状況に一石を投じる試み、ということになろう。この論文において著者が行おうとしたのは、ある企業が現実に行っている経済活動と、その企業を法的に映し出す会社あるいは法人というものとの関係を、実際に事業活動を営む組織に注目して明らかにしようということであった。考えてみれば、実際の事業活動とその法的な表現である会社や法人との間に何の関係もないというはありえない。逆に言えば、いわゆるヒト (自然人) でないにも関わらず、法律上ヒトとして扱われる法人というものを考えたときには、その背後にどのような活動を想定するのかを考える必要がある (この点は、例えば法人に刑事責任を課そうとする場合に問題になる)。この論文では組織というものに注目することによって、組織的な活動を法的に扱おうとするときに、ある状況では法人という法律上のフィクションを当てはめることが適切であることを示している。
近年、会社制度、とりわけ会社形態のメニュー (株式会社、合名会社、合資会社等) と経営との関係は経営学及び経営の歴史を扱う経営史学において注目を集める分野となっており、例えば国際学会等でもセッションが設けられるようになっている。この数年、筆者自身もこのようなネットワークに参加し、日本における会社制度の発展についての発表を行ってきているが、この論文はそのような研究の潮流における理論的な礎石―というには小さな石であるが―を置こうとした研究といえるだろう。
決して長い論文ではないが、それなりに野心を持った論文なのである。
(紹介文執筆者: 総合文化研究科・教養学部 准教授 清水 剛 / 2017)



 書籍検索
書籍検索


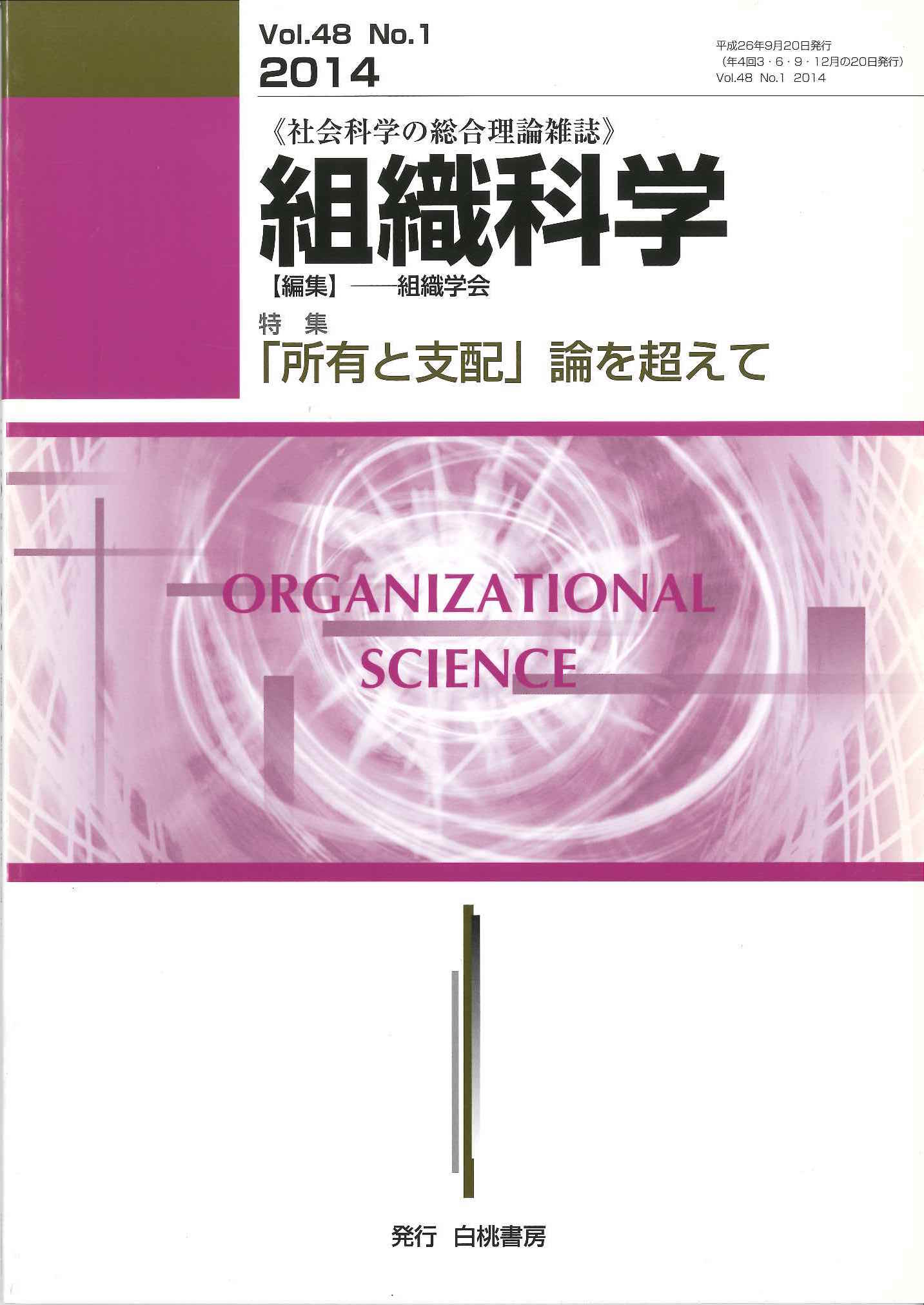
 eBook
eBook