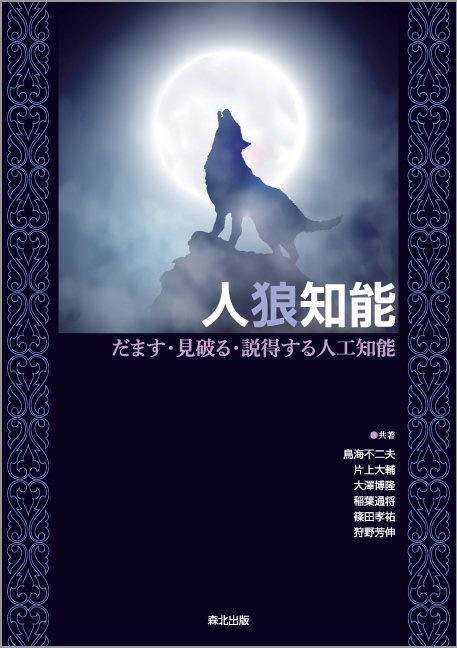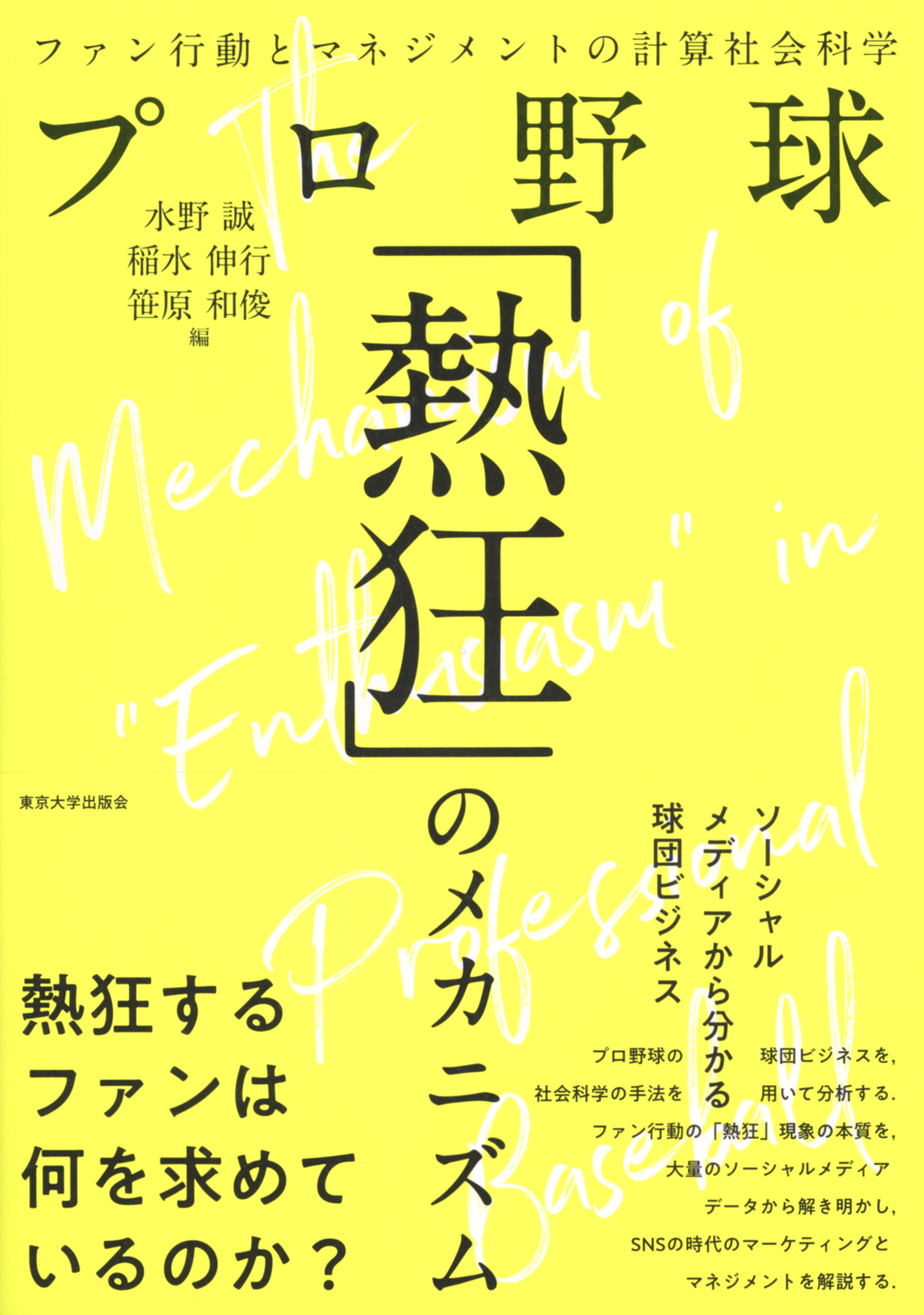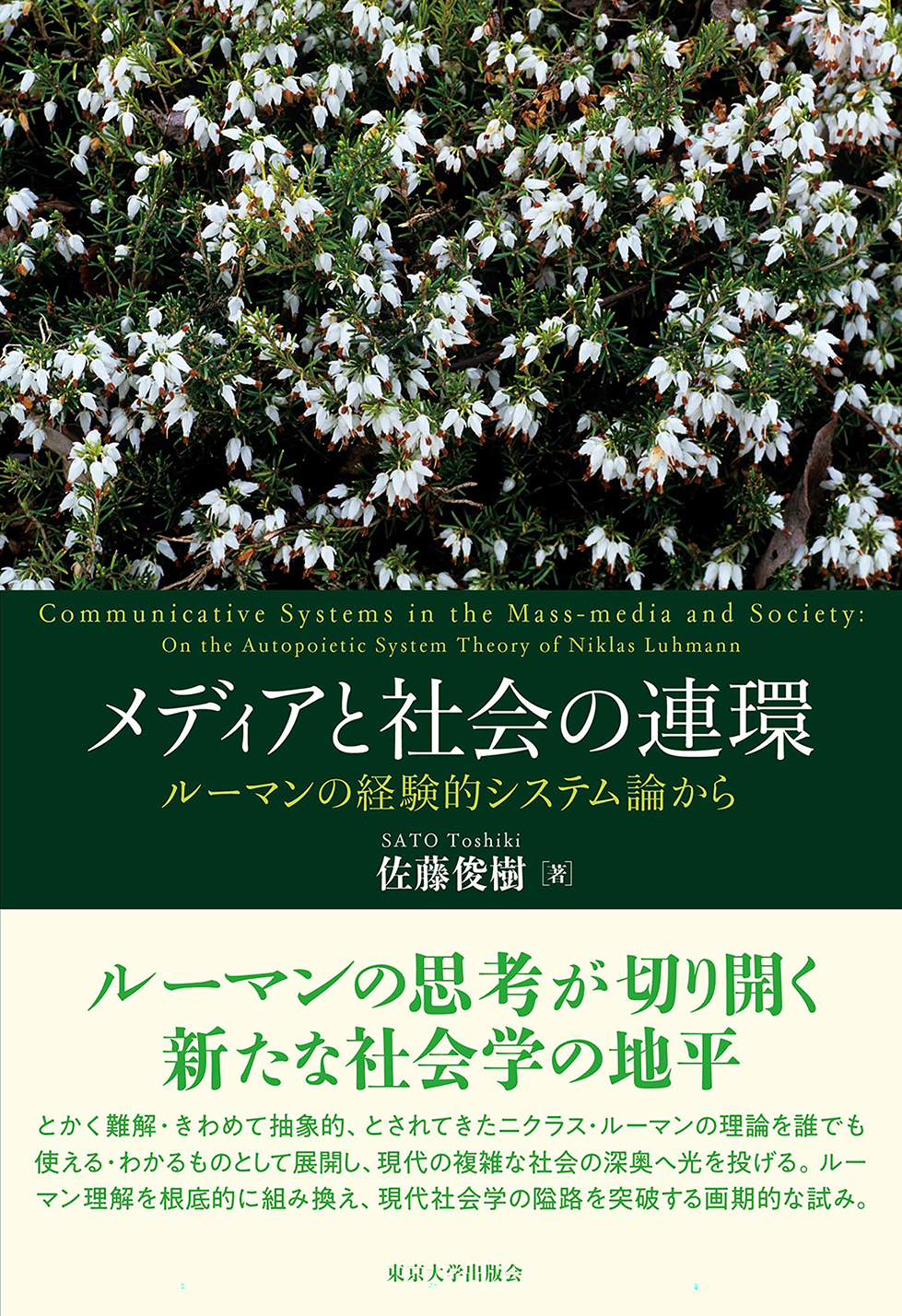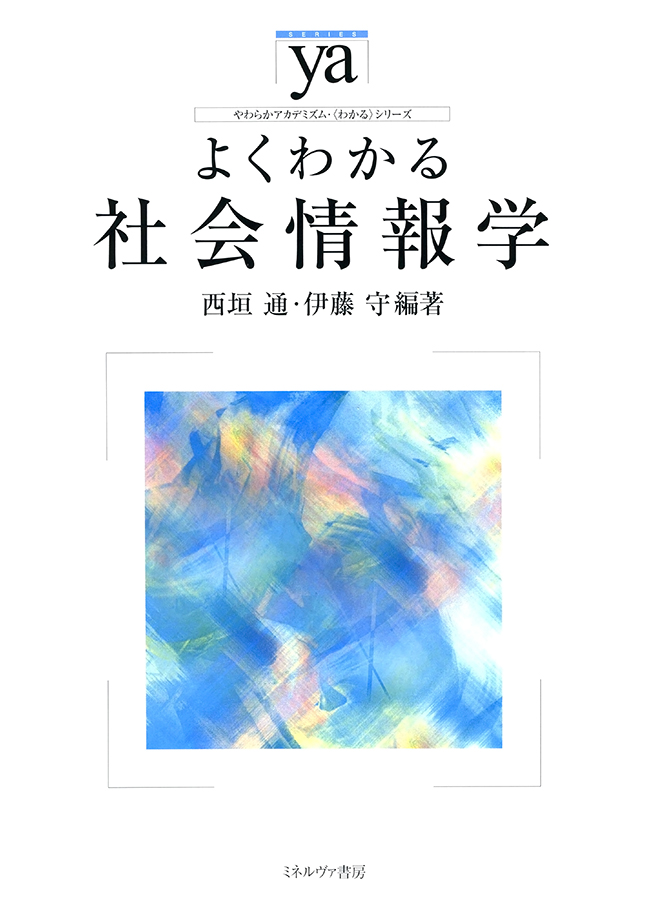
書籍名
やわらかアカデミズム・<わかる>シリーズ よくわかる社会情報学
判型など
232ページ、B5判
言語
日本語
発行年月日
2015年5月20日
ISBN コード
9784623073597
出版社
ミネルヴァ書房
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
HUNTER×HUNTERという漫画をご存じだろうか。週間少年ジャンプで1998年から20年以上にわたって連載されている人気漫画である。人気も高いが休載も多いことでも有名である。
そのHUNTER×HUNTERの登場人物は「念」という能力を持っていることは読んだことのある方ならご存じだろう。念能力は「強化系」「変化系」など6つの系統に分かれており、各キャラクターはそれぞれ得意とする一系統の念能力を持ち、それに応じた個別能力を持っている。しかしながら、一部のキャラクターは「得意とする念能力」と「会得した個別能力」の系統が異なる場合がある。この場合、個別能力の威力は一致している場合よりも格段に下がるようである。
さて、この得意とする念能力と会得した個別能力の関係は、研究能力と知的好奇心の関係に似ている。我々の住む世界での研究能力は、どうやら「理系」「文系」「医学系」などの能力に分かれており(実際にはもっと細分化されているのだろうが)、大学入試という水見式を経て得意の系統の能力を伸ばす学部に入学する。しかし、数学が得意な高校生の興味は必ず理系に向いているのかといえば、そうでも無かったりもする。大学に入学してから「こういう勉強をしたかったわけではないんだけどな…」という思いに駆られる学生も多いことだろう。まさに得意能力と会得したい能力の不一致である。
東大においては進振り時に理転文転のチャンスがあるが、同様に学部を変更するチャンスはどの大学にも用意はされているだろう。しかし、実際に転向できる人数はそれほど多くなく、狭き門であり、成績が良くなければ実現できないことが多い。「文系に来たけど、理系に転向したい」と思った人が文系科目で高い得点を取らなければならないというのはなんとも本末転倒な話である。
さて、そんな念能力の不一致に悩んでいる学生にお勧めなのが境界領域の学際分野である。私が所属している情報系の分野であれば、社会情報学がある。ということで、ようやく本のタイトルにたどり着いた。
社会情報学はその名の通り、社会における情報現象を対象とし、理論的・実証的にその特性を明らかにすることを目指している。そのため、その扱う分野は非常に幅広く、そのすべてを網羅することは困難なくらいである。しかし、逆に情報科学を学んでその技術で社会データを分析し社会の成り立ちを明らかにしたい、あるいは社会学の視点からデジタル社会を分析したいといった研究分野は、概ね社会情報学の一部であると考えて良い。このような学際領域は、近年ますます盛んに行われるようになっている。社会情報学に近いところでも、よりコンピュータサイエンスに近い側から社会科学全般を扱おうとする「計算社会科学」などはFacebookやマイクロソフトなどの企業も注目し、世界的にも研究が盛んになってきている。
「よくわかる社会情報学」は社会学と情報学を結ぶ「社会情報学」について文理双方の62名もの研究者によって、社会情報学の成り立ちから研究方法まで様々な視点の記事がコンパクトにまとめられており、誰にとってもどこかに必ず興味を引かれる記事が存在する。そのため、「得意な能力」と「会得したい能力」が異なってしまった方であれば、「自分の能力と好奇心を生かすのはここだ!」と思えるテーマが必ず見つかるだろう。
本書は、情報学に興味がある文系学生や、社会学に興味のある理系学生に是非読んでいただきたい一冊である。
(紹介文執筆者: 工学系研究科 准教授 鳥海 不二夫 / 2018)
本の目次
I 社会情報学の成立
1 情報科学 (Computer Science) の勃興
2 情報学 (Informatics) の成立
3 社会情報学 (Socio-Informatics) の生成
4 社会情報学の研究方法
II ネオ・サイバネティクスと生命圏
1 総 論
2 生命と情報
3 脳の発達と情報
4 言語の成立
5 感性的コミュニケーション
III 情報過程の歴史的階層性
1 総 論
2 オーラル・コミュニケーション
3 文字を書く・読む技術
4 光学メディア
5 シネマ
6 ブロードキャスティング・システム
7 近代社会の情報論的構造
IV コンピュータのつくる言語映像圏
1 総 論
2 コンピュータの情報処理
3 マルチメディア
4 ウェブとデータベース
5 人工知能とロボット
V コミュニケーション空間
1 総 論
2 ソーシャルメディアとコミュニケーション
3 デジタルネイティブの進化
4 ネット空間のコミュニティ
5 テレビの未来と社会的受容
6 ネット社会と情報行動の変容
7 ネット評判社会
8 ビッグデータと社会情報学
VI 社会的意思決定と情報
1 総 論
2 社会的ジレンマ
3 会議と合意形成
4 社会的選択理論と情報
5 グループウェアと意思決定支援
6 社会シミュレーション
7 インターネットと選挙
8 公共圏と熟議民主主義
9 厚生主義と非厚生主義の視点
10 社会的意思決定と自己組織性
VII 社会システムへの応用 (1)
1 総 論
2 行政情報
3 地域コミュニティ
4 医療・福祉
5 都市・交通
6 教 育
7 災 害
8 オンライン・ショッピング
9 電子マネー
VIII 社会システムへの応用 (2)
1 総 論
2 観 光
3 デジタル・ミュージアム
4 ピア・プロダクション
5 音楽 / 映像配信システム
6 ゲーム
IX デジタル化される文化
1 総 論
2 オンライン・ジャーナリズム
3 記憶・記録・アーカイヴ
4 Googleの世界
5 電子書籍
6 デジタル化する博物館・美術館
7 移動とスクリーン
8 ポスト記号消費社会
9 情報資本主義
10 監視社会
X 法・政策と情報
1 総 論
2 表現の自由・メディア・アーキテクチャ
3 通信・放送の融合・連携
4 情報公開とプライバシー・個人情報保護
5 政府規制・自主規制・共同規制
6 地域情報化政策とコミュニティ
7 音楽とコンテンツ産業
8 写真・映画と著作権
9 セキュリティーと情報倫理
XI 近未来の社会と情報技術
1 総 論
2 ネットと近未来組織
3 オープン・データ
4 集合知
5 ヴァーチャル・リアリティ
6 ポスト近代社会のメディア
XII 研究者紹介
1 クロード・シャノン
2 ニクラス・ルーマン
3 ノーバート・ウィーナー
4 ウンベルト・マトゥラーナ
5 フランシスコ・ヴァレラ
6 アラン・チューリング
7 ヴァルター・ベンヤミン
8 マーシャル・マクルーハン
9 ジル・ドゥルーズ/フェリックス・ガタリ
10 ジャン・ボードリヤール
11 グレゴリー・ベイトソン
さくいん



 書籍検索
書籍検索