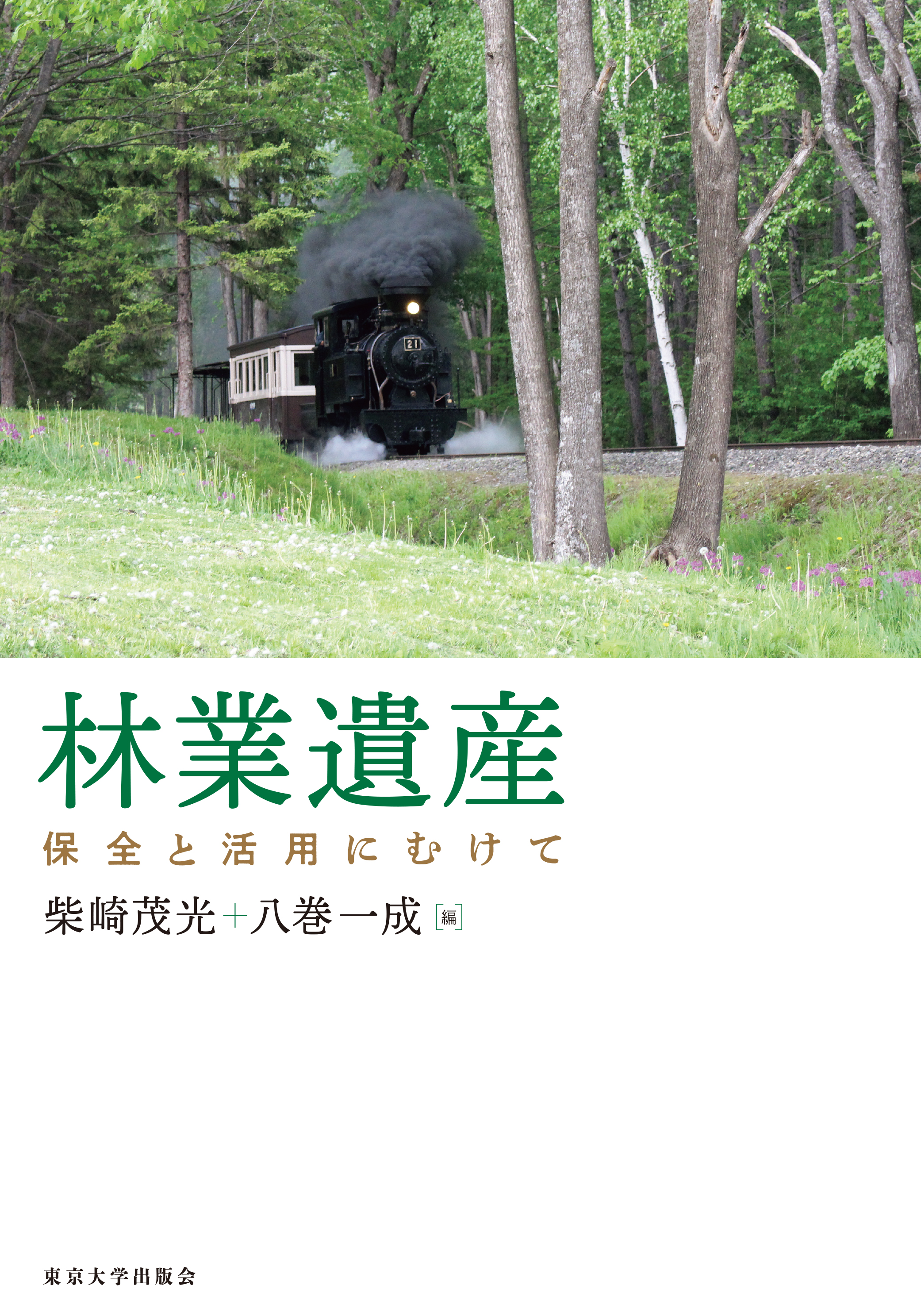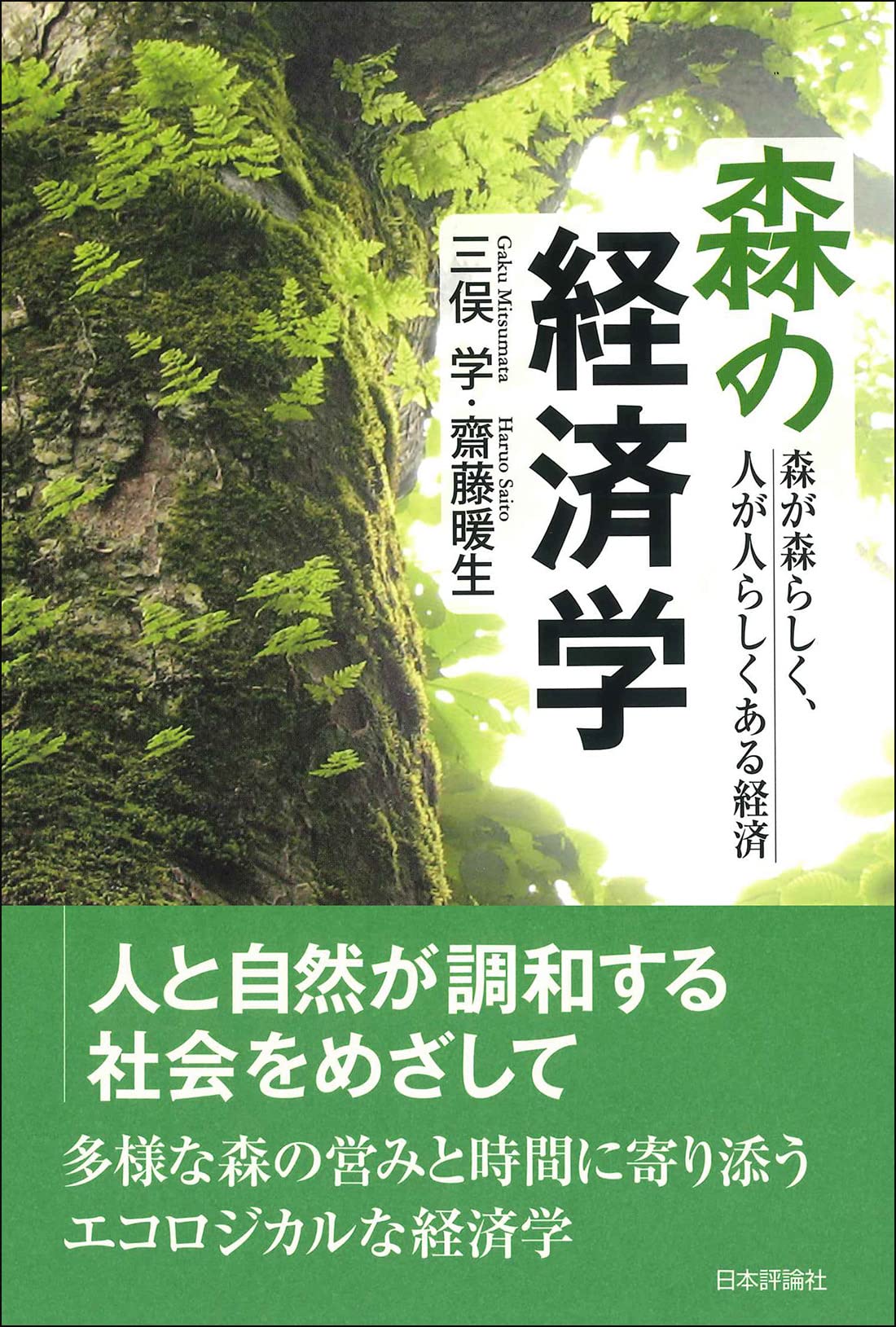本書は、東京大学での「林政学」あるいは「森林政策学」という名前で行われた講義の録音を素に、「林政学」とは何かを論じた書籍です。録音を素にしているので、臨場感のある分かり易いものになったと思っています。
林政学とはなにか。それは森、林に住む人たちの暮らしにかかわる学問です。私は暮らし、あるいは生活を重視したいと考えますので、経済学的な観点からとらえているつもりですが、そこで暮らす人と人との関係も重要であり、社会学、あるいは政治学的な観点も重要であり、歴史的観点も重要であると考えています。さらには、今日の人と人の関係には行政や法的な関係も考慮に入れる必要があります。学問分野ないし分析手法から話を進めましたが、分析対象は森林、その産物である木材や非木材森林産物、水源涵養機能や山地災害防備といった森林の環境維持機能や、観光資源としての森林と山村、また山で暮らす人々をはじめ、森、林、山にかかわる人々や社会制度も対象です。
高度に発達した人間社会は地球環境とどのように折り合いをつけて行ったら良いのかを考えなければならなくなってきました。昨今、Sustainable Development Goals (SDGs) が重要視されるようになったのもそうした背景があってのことといえるでしょう。SDGsを達成するためにも森林と人間のあり方を考え直す必要があり、ますます「林政学」が重要になってきたといえるでしょう。
林政学が森林と人との関係を論じるものなので、本書では世界の森林の状況を初めに押さえます。世界の森林の変化、熱帯を中心とする森林減少を、経済発展のなかでやがて森林増加に転じるとみるU字型仮説という観点からとらえます。
次に世界の森林の変化をみるのに重要である林野所有制度が、日本の明治以降の歴史のなかでどのように定着していったのかを学びます。
戦後の木材需給の動向を振り返り、戦後の所得の変化がどのように木材需要の変化に結びついたのかをみます。この需要の変化が、国産材供給と外材供給によってどのように賄われたか、需要曲線とそれぞれの供給曲線を描くことで明らかにします。
この需給の動きを経済原論から考え、厚生経済学の基本定理に照らして、なぜ森林や林業に関しては政府の関与が必要であるのか、つまりどのように市場が失敗するのかを述べます。また森林の生育が長期にわたることから、時間軸を中心においた資源配分を行う必要性を述べます。さらに、権利関係の明示と取引費用がある種の最適な資源配分に重要であることを学び、森林法制のあり様を学んで行きます。
(紹介文執筆者: 農学生命科学研究科・農学部 名誉教授 / アジア生物資源環境研究センター 特任教授 永田 信 / 2019)
本の目次
第1講 世界の森林の現状
第2講 熱帯林減少のメカニズム
第3講 日本の森林所有の形成
第4講 明治以降の経済と森林
第5講 日本の木材需要
第6講 日本の木材供給
第7講 市場経済システムと効率性
第8講 市場と社会厚生
第9講 森林の多面的機能と経済評価
第10講 公共財供給の最適条件
第11講 コースの定理と森林法制
おわりに
主要参考文献(参考書)
引用文献
[付録]1 森林・林業にかかわるアクター/2 林政学のための情報活用法/3 主要事項年表
索引
関連情報
藤掛一郎 (宮崎大学農学部) 評 (『林業経済』68巻12号p.21-24 2016年)
https://doi.org/10.19013/rinrin.68.12_21
三木敦朗 (信州大学学術研究院農学系) 評 (『水資源・環境研究』29巻1号p.17-18 2016年)
https://doi.org/10.6012/jwei.29.17
韓国語版:
2017年に金世彬・鄭夏顕・閔庚鐸・金亮希による韓国語訳が忠南国立大学出版局より出版されている。



 書籍検索
書籍検索


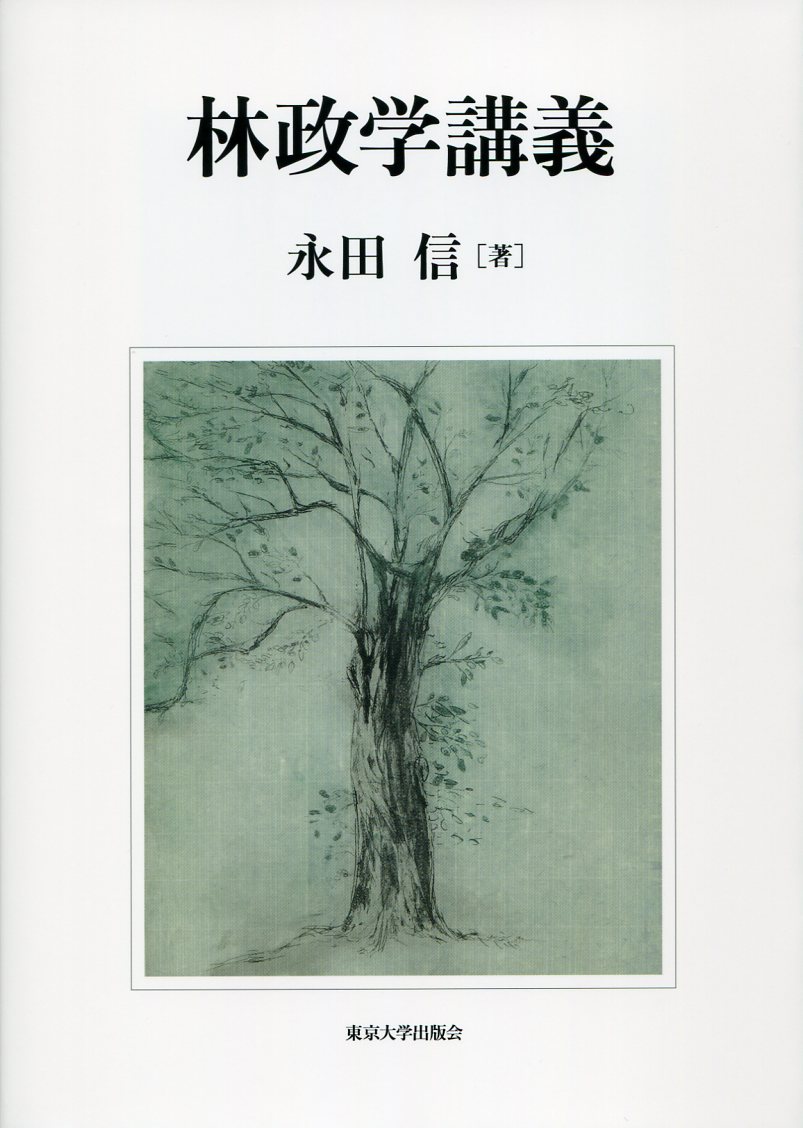
 eBook
eBook