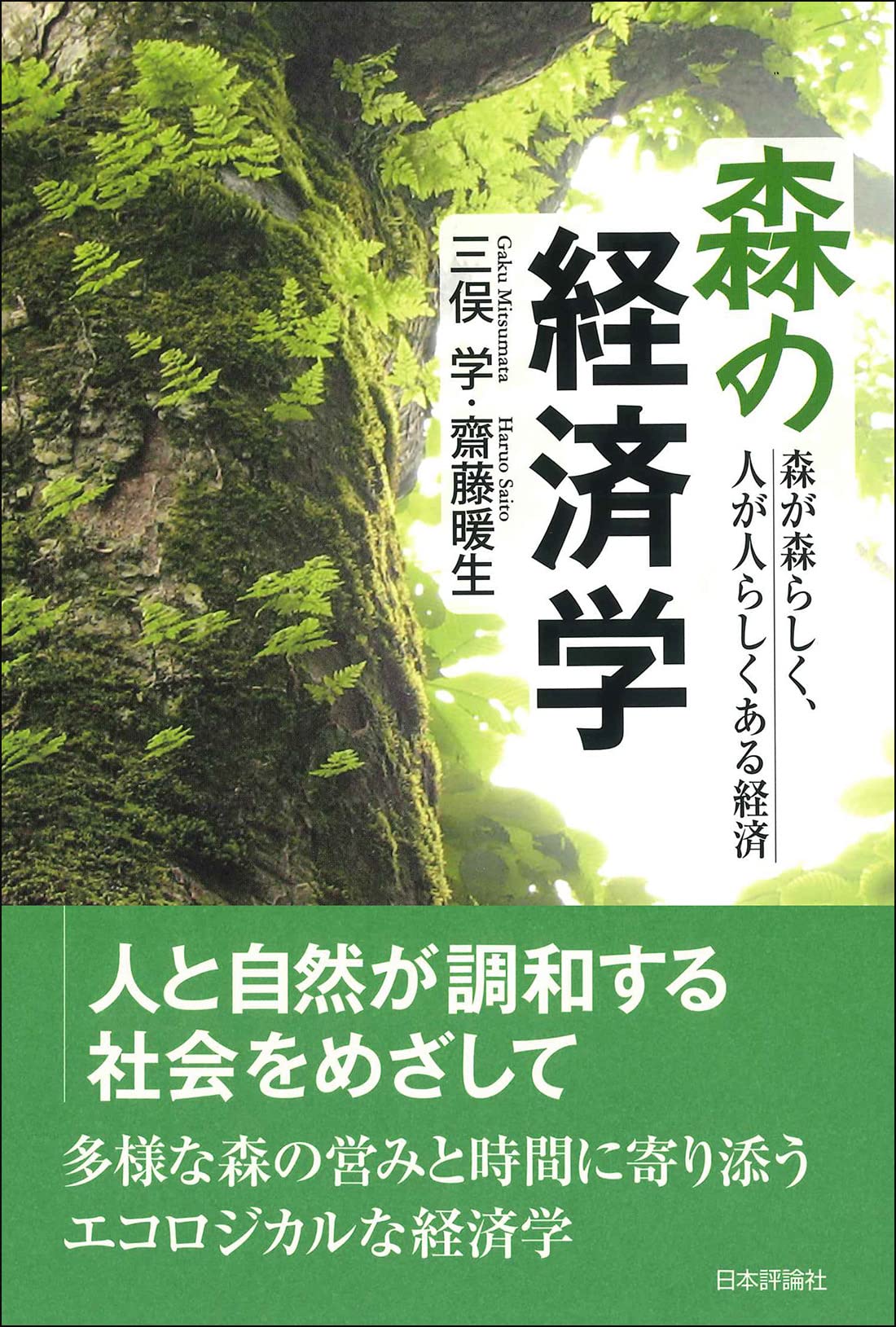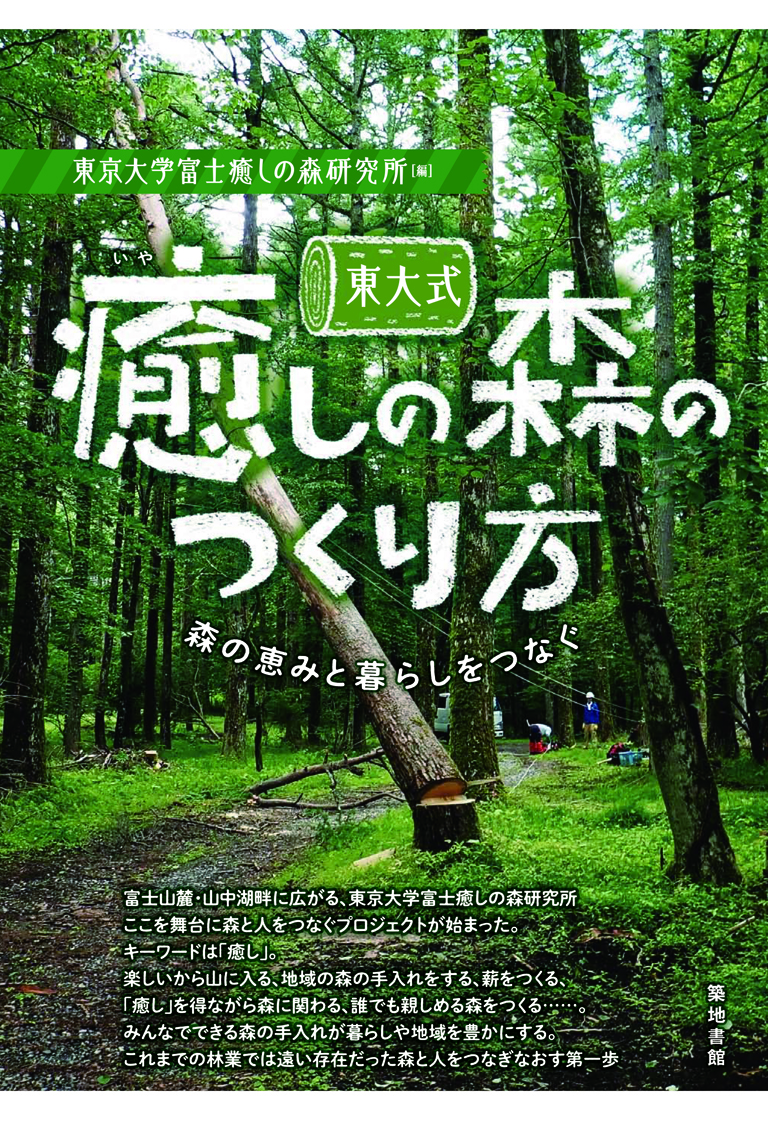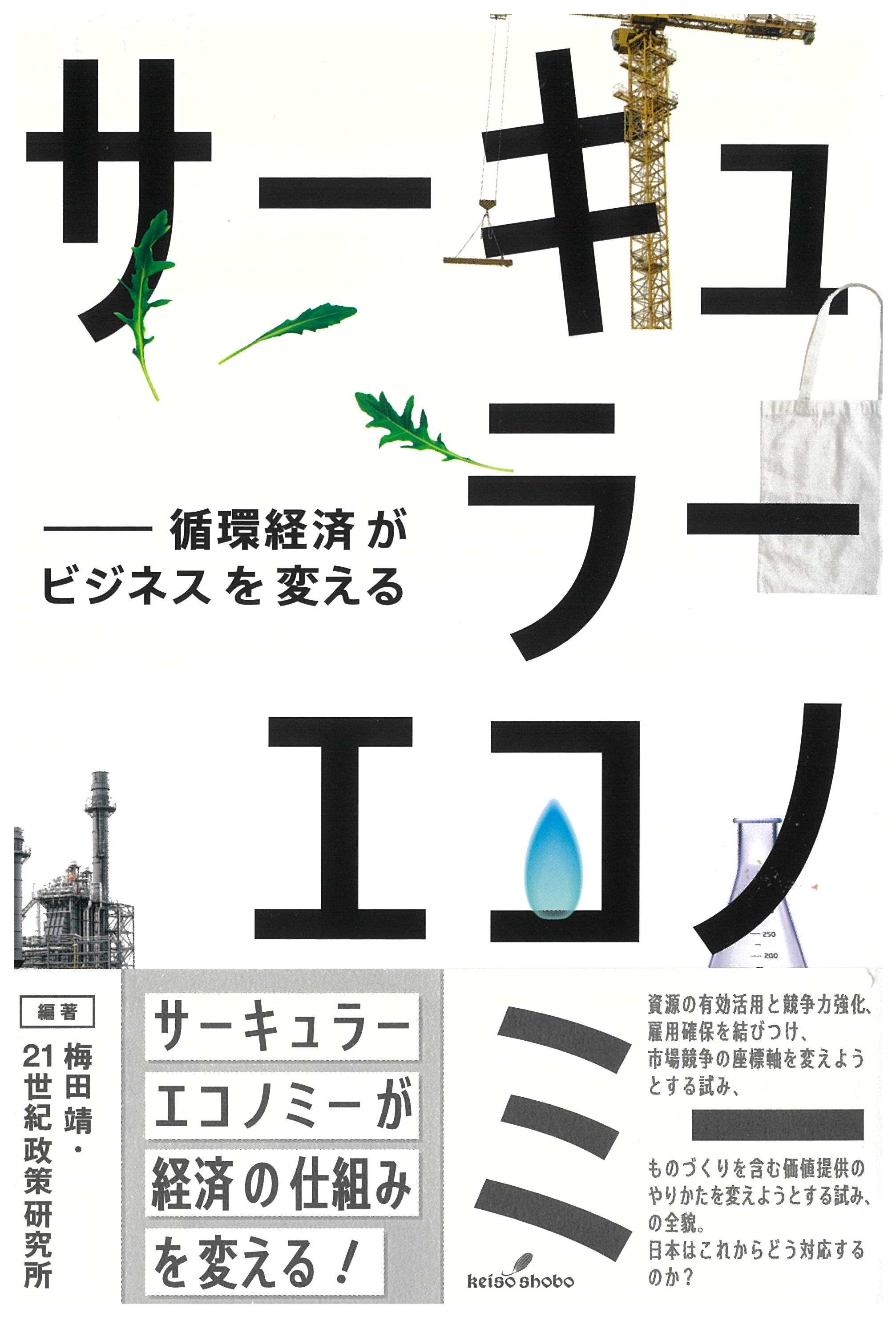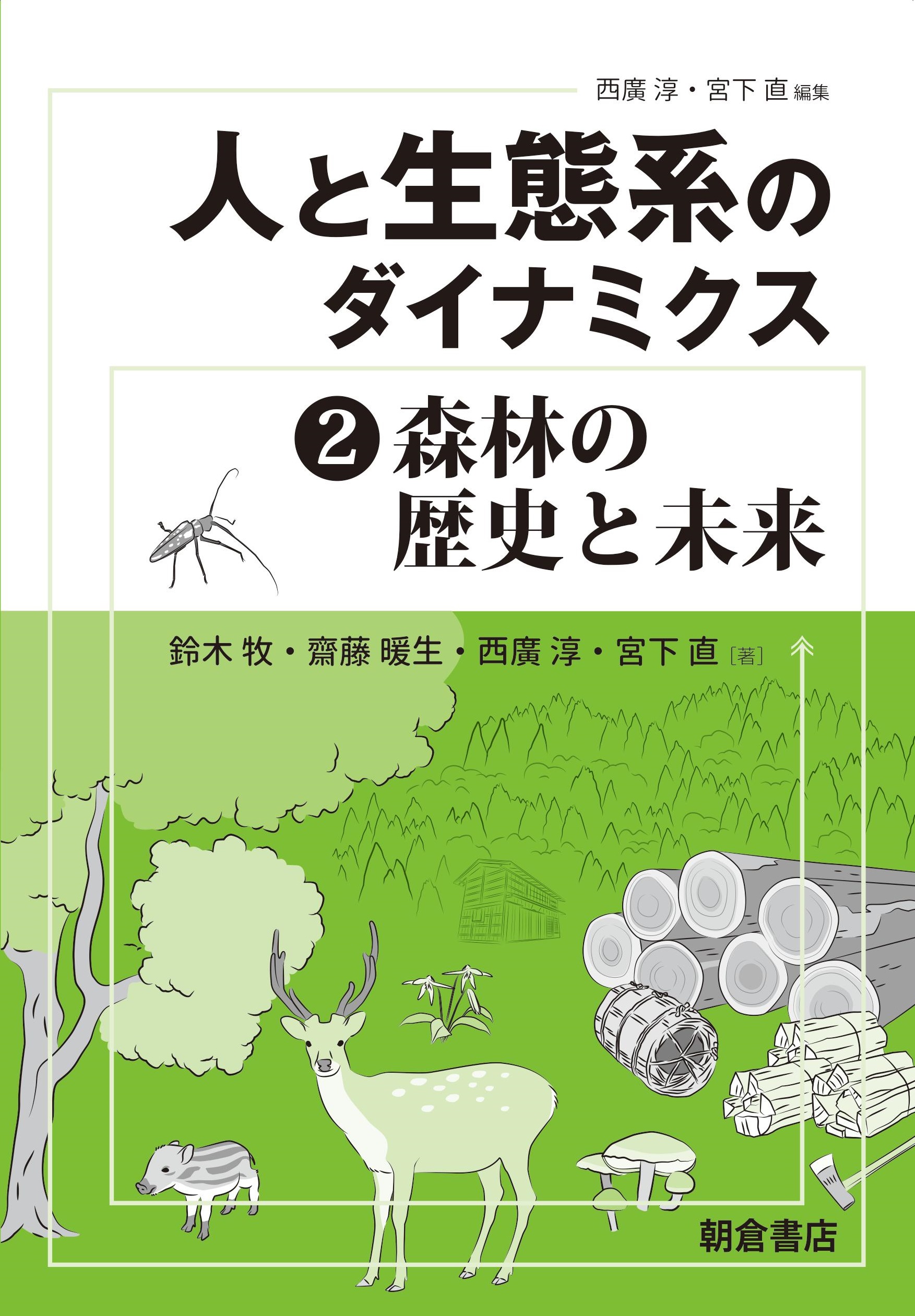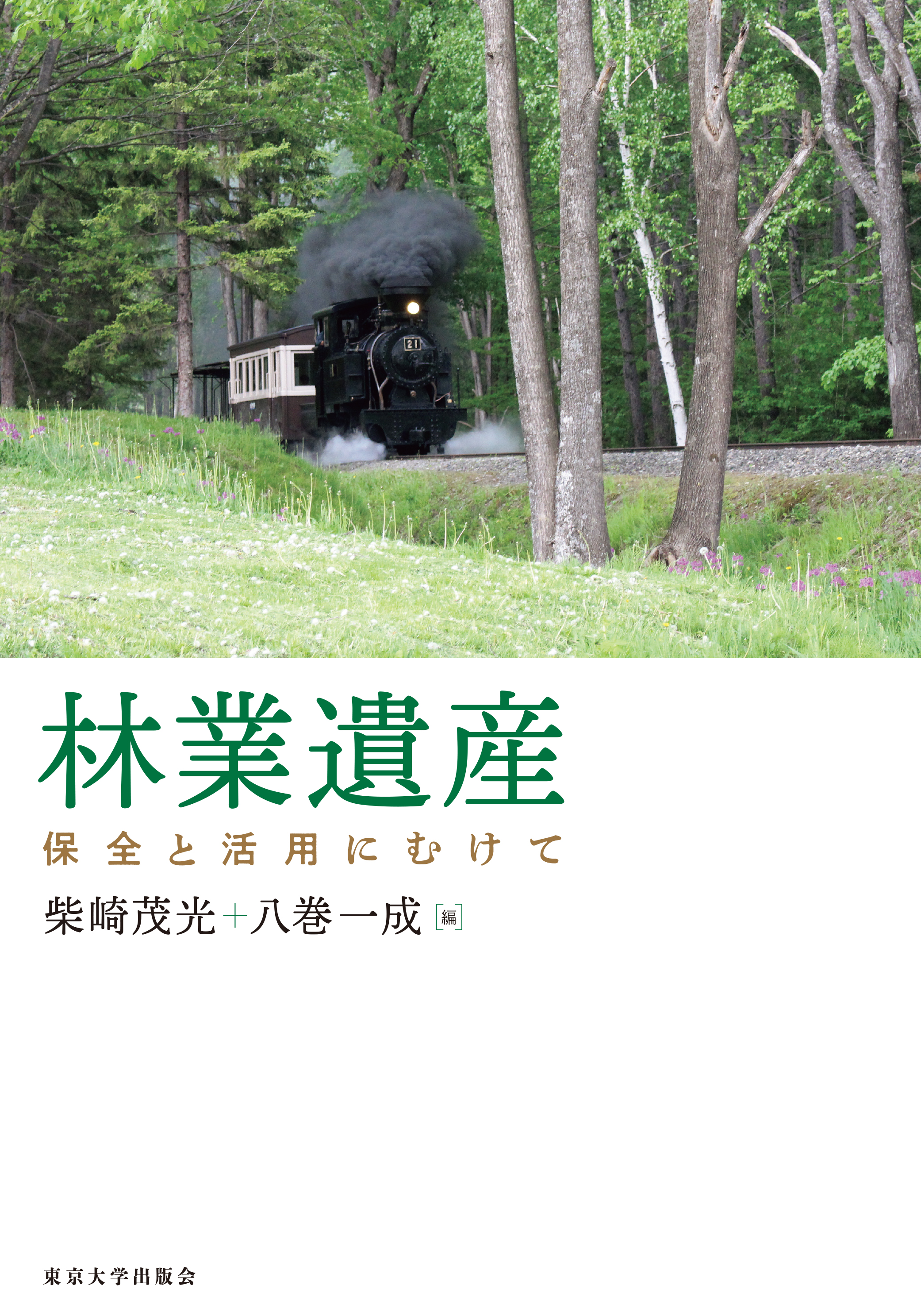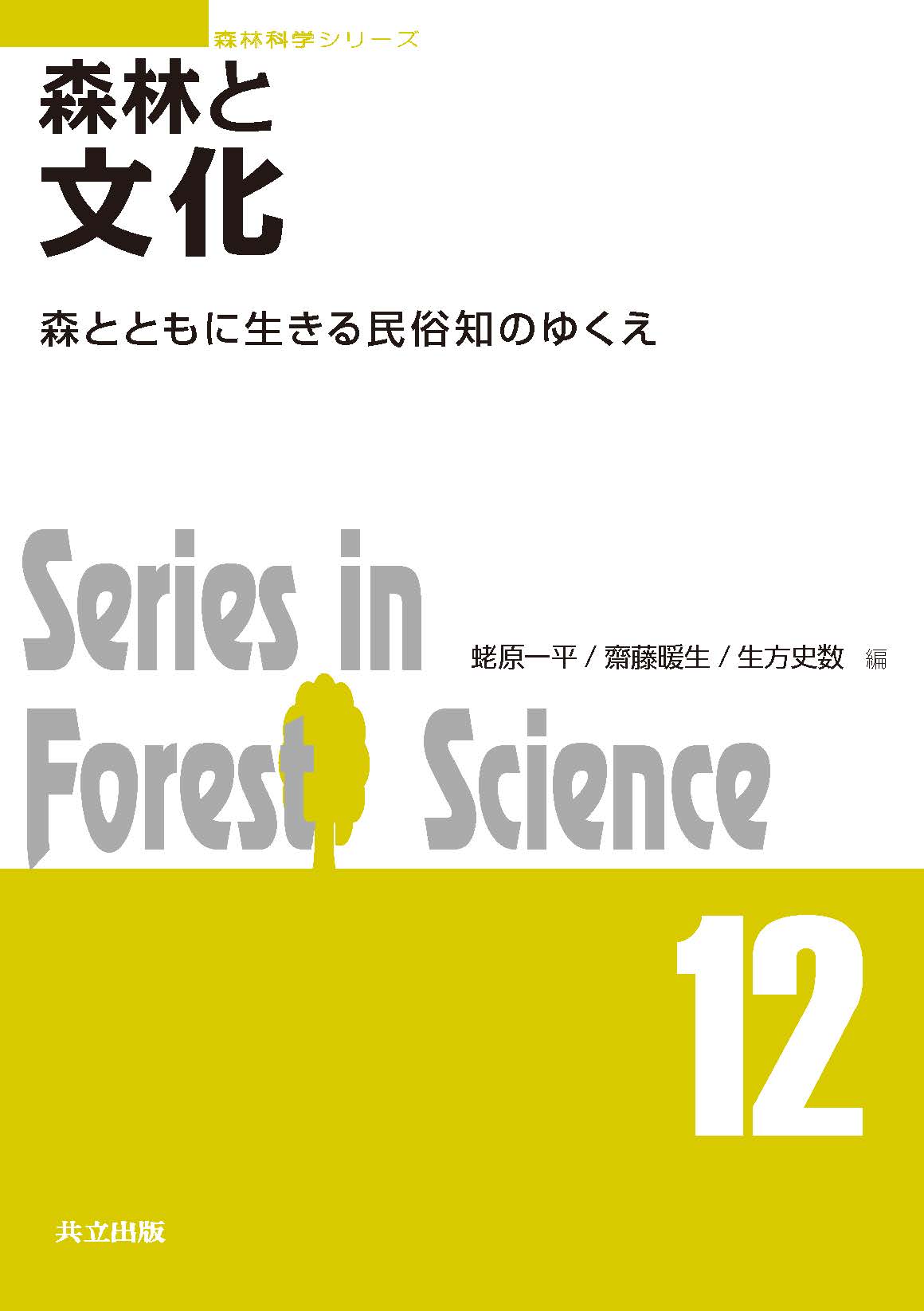本書は、森林について専門的に学んだことのない読者を想定し、森林と人間社会の営み (経済) の関わり合いについてなるべく平易に解説したものである。「森の経済学」と銘打ったが、森林資源を経済的に活用するための実践的な方策には、基本的に触れていない。本書が目指すのは、森林の成り立ちや経済のあり方を原点に立ち返って理解し、森と人間社会の関わりようの「いま」を見直し、「これから」を柔軟な発想で創造するために必要な視座を提供することである。そのため、既存の森林学や経済学の教科書では取り上げられてこなかったような見方も、少なからず盛り込んだつもりである。初学者向けではあるが、すでに森林や経済学をある程度学んだ読者にとっても、新たな視点を提供しうるものと考えている。
本書が原理原則と考える「森の経済」の考え方をかいつまんで紹介しよう。
まず、森は空間的にも時間的にも連続的な存在である。ある森の所有者がどんなに頑張っても、清涼な空気や水といったその森の恩恵を独占することはできない。ある時、自然災害や伐採によって森林が消しても、その土地はやがて草原を経て森になりうるし、出来上がった森の姿も時間経過によって大きく変わりうる。
次に、人の資源として森を見た時、人の営みと、森の営みの時間的スケールがしばしば齟齬が生じる、ということに注意が必要である。特に、現代社会に至って、何が価値を持つのかは目まぐるしく変わるようになってきた。樹木の生育スピードを考えれば、そうした急な需要には対応できないばかりか、その樹木の再生産が危うくなることは想像に難くないだろう。
人は長い歴史を通じて、森を構成するさまざまな生き物を資源として利用してきたし、時に脅威として対抗もしてきた。それらがまさに森と対峙する人間社会の経済である。こうして、「森の経済」を、森と人の間の直接的なやりとりと、森を背景に取り結ばれる人と人のやりとりを含むものとして捉える視座に立つことができる。
経済学は多くの場合、生き物が織りなす自然環境を、人の経済の範疇として捉えてこなかった。しかし、上で指摘したように、自然の営みも考慮しなければ、経済社会の持続可能性は危うさを内包することになる。近代社会では、市場でやりとりされる価値を最大化することが重視され、これに都合の良いように森を作り変える努力が払われてきた。その結果として日本社会の「いま」に表出した現実は、数十年かけて充実した資源と、需要される資源とのミスマッチであり、近くにあるにもかかわらず人との接点が極めて希薄になった森の存在である。
「森の経済」が歩んだ近代は、利潤最大化のために単純化されてきた歴史であったと、本書は捉える。利潤最大化の呪縛から離れ、多様な森と人の関わりを取り結んでいくことが、「森が森らしく、人が人らしくある経済」に近づく大前提と考えるが、読者の皆さんはどう考えるだろうか。
(紹介文執筆者: 農学生命科学研究科・農学部 講師 齋藤 暖生 / 2022)
本の目次
第1章 人間にとっての森
1 連続的な空間としての森
2 森を見るまなざし
3 資源としての森
4 脅威としての森
5 森の時間――資源の有限性と無限性
第2章 森とともに歩んできた生活世界と経済の発展
1 生計を支えた森の資源
2 共同体の経済と森
3 複雑化する社会と森
第2部 森の経済をとらえる学問のまなざし
第3章 自然環境に対する経済学のまなざし
1 経済学とは
2 標準的な経済学におけるいくつかの前提
3 主流派経済学における変化の兆し
第4章 森林をめぐる学問の歩み――森林学のまなざし
1 林学の誕生と森林学
2 森林をシンプルにとらえ、体系的に管理する技法
3 森林を複雑な系としてとらえ、管理する技法
第3部 日本の森がたどった近代
第5章 日本の林業・木材加工の技術史
1 「林業」という言葉をめぐって
2 樹木を育てる技術
3 森林伐採と搬出の技術
4 木材加工の技術
第6章 経済が変える森の姿
1 姿を変える森
2 人々の資源利用と森の姿
3 近代化と森の変容 (近代~戦後)
4 人工林の拡大と利用の空洞化
第7章 農山村における近代――コモンズ解体と「高度利用」の神話
1 コモンズとしての自然――「自然の公私共利」の原則
2 日々の生活を支えてきた村の中の「共」――入会の森を利用する
3 森の近代――入会消滅政策=高度利用の果てに残ったもの
4 非商品化経済をとらえなおす――高度利用の神話が生んだ放置と無関心
第8章 森林エコロジーの劣化と遠ざかる森
1 森林の「充実」を説明する理論
2 過少利用の森林が抱える諸問題
3 遠くなった森が生み出す世代を超えた問題
第4部 ゆたかな森林社会へ
第9章 エコロジカルな経済へのパラダイムシフト
1 近現代の経済の発展と矛盾
2 エコロジーをゆたかにする経済は可能か
3 共的部門の再評価――一九九〇年代の二つのコモンズ論
4 パラダイムシフトに向けた運動
5 新たな公・共・私と基盤としての自然アクセス
第10章 パラダイムシフトにおける「公」「私」の役割
1 社会と自然の結び直し
2 森をめぐる制度の変容
3 変容する生産と消費のかたち
第11章 共創するコモンズ――森林をめぐる協治の胎動
1 伝統的コモンズにおける協働の試み
2 都市と山村をつなぐ――森林ボランティアの広がり
3 海・川・森をつなぐ漁民の森運動――「森は海の恋人」
4 森林の教育利用――学校林という森
5 非商品化経済の営みが創る新しいコモンズ――環境の本源的な価値を求めて
第12章 エコロジカルな経済を支える自然アクセス――みんなの自然を取り戻す
1 入浜権運動で問われた「自然はだれのものか?」
2 英国のコモンズをめぐる歴史
3 北欧・中央諸国に広がる自然アクセスの世界
4 多の世界を創る自然アクセス制から学ぶこと
5 非商品化経済をゆたかにする――森林社会の基盤をなす森の経済学へ
おわりに
関連情報
森の経済学写真館
『森の経済学』の著者、三俣学、齋藤暖生らに撮影による森や木々の写真です。
https://www.nippyo.co.jp/55993_photo/
著者インタビュー:
自然とつき合う経験を失うことは、人間の生存能力を失っていくこと (esse-sense 2022年9月5日)
https://esse-sense.com/articles/63
書評:
佐藤宣子 (九州大学) 評 (『森林技術』No.969 p.36 2023年1月号)
https://www.jafta.or.jp/contents/shinringijuts/25_month1_detail.html
山本信次 (岩手大学農学部) 評 (『森林科学』96号p96 2022年10月号)
https://www.forestry.jp/publish-posts/forsci-index/%E6%A3%AE%E6%9E%97%E7%A7%91%E5%AD%A6%E3%80%80no-96%E3%80%80%EF%BC%882022%E5%B9%B410%E6%9C%88%EF%BC%89/
池上 惇 (京都大学名誉教授) 評 (『林業経済』75巻8号P24-30 2022年)
https://doi.org/10.19013/rinrin.75.8_24



 書籍検索
書籍検索