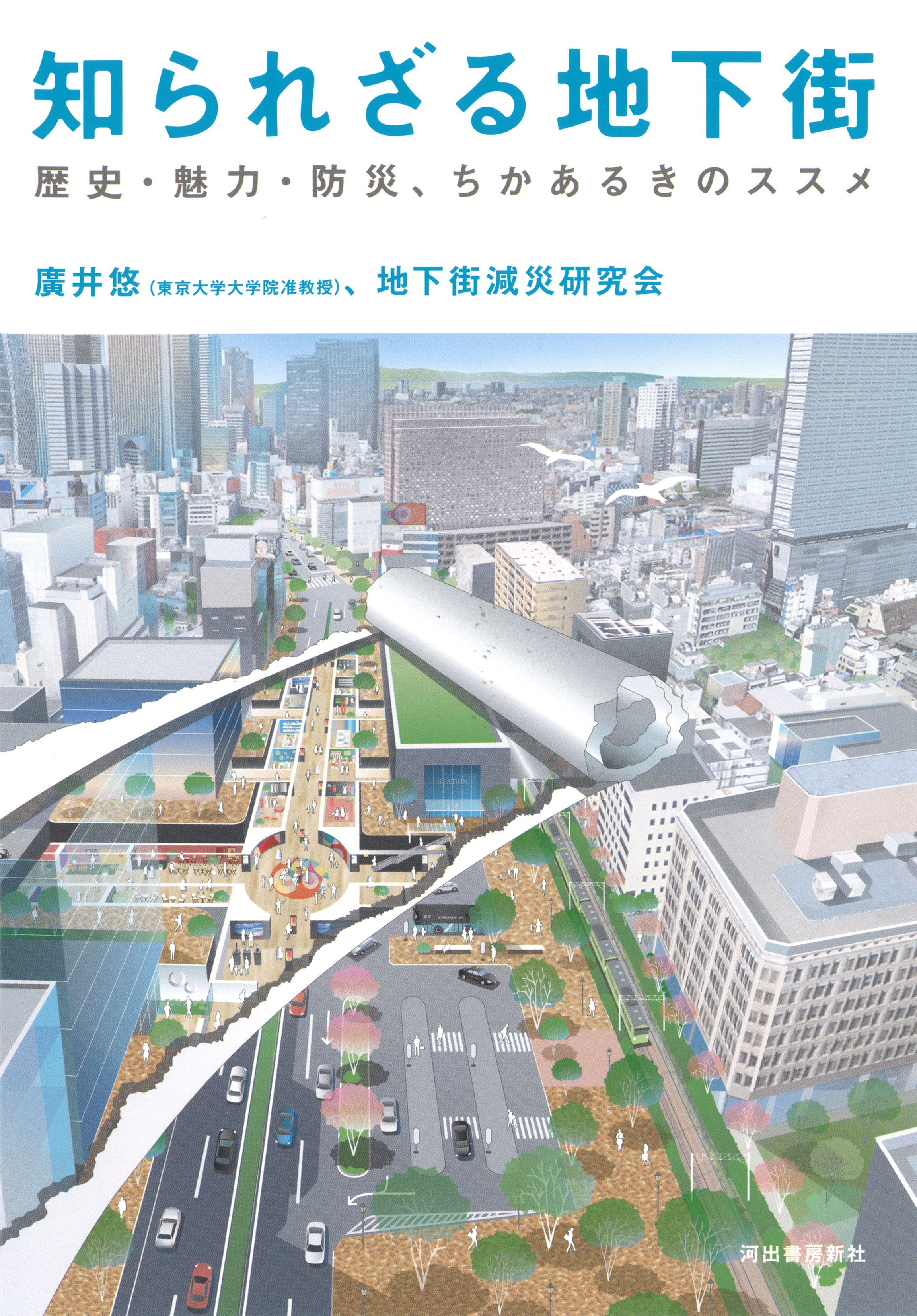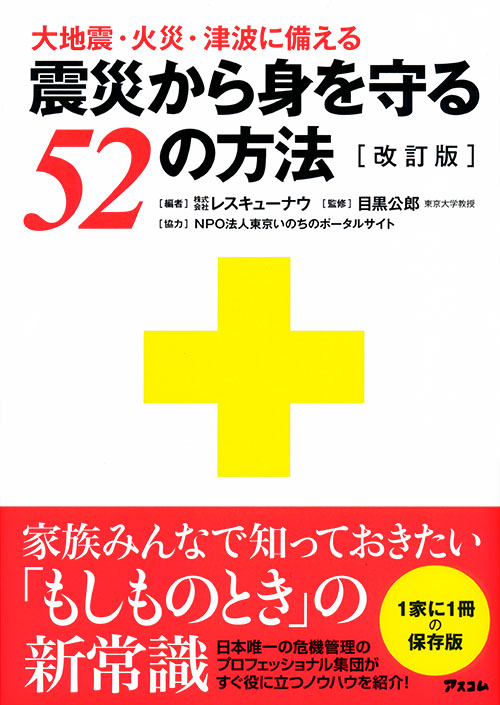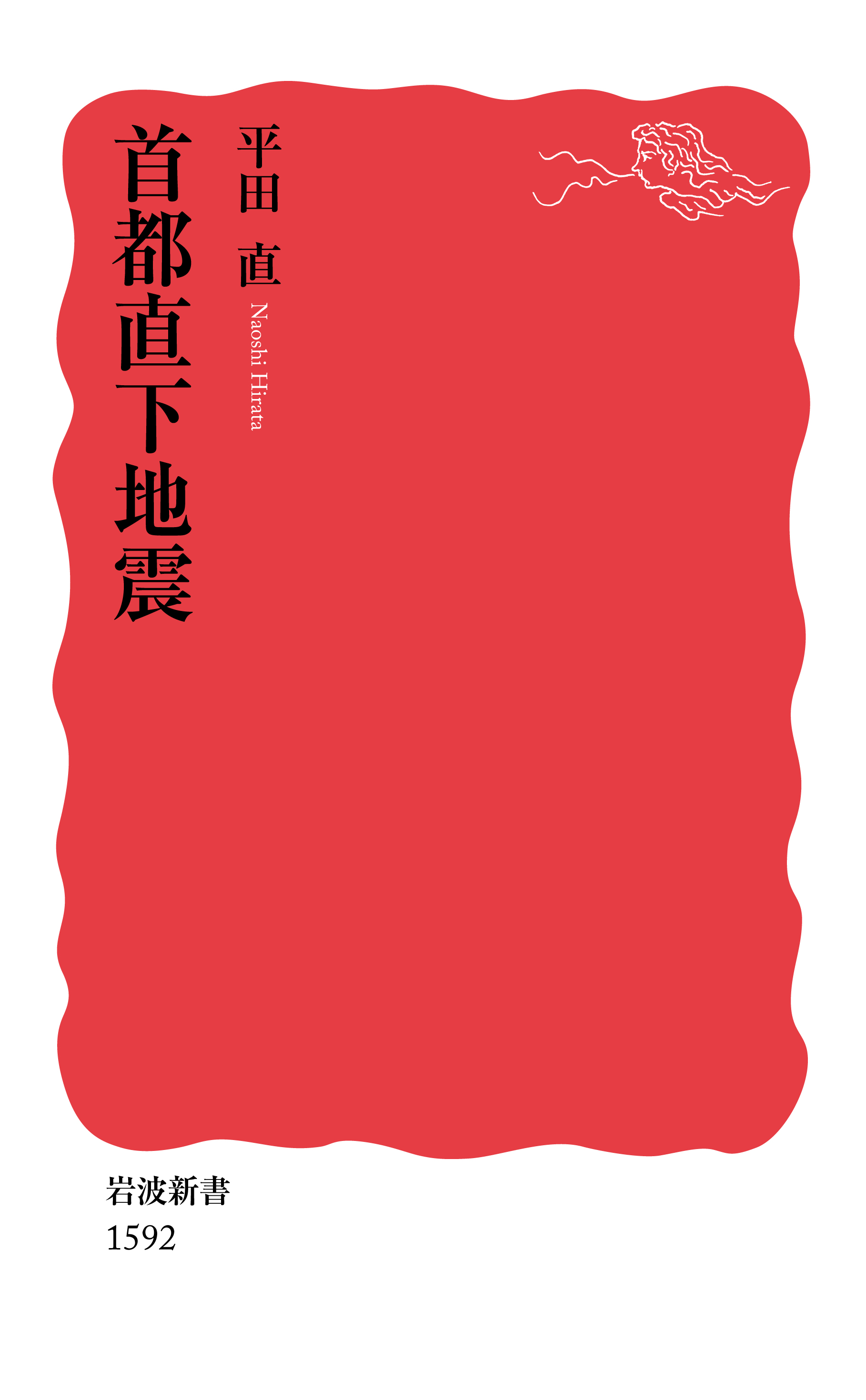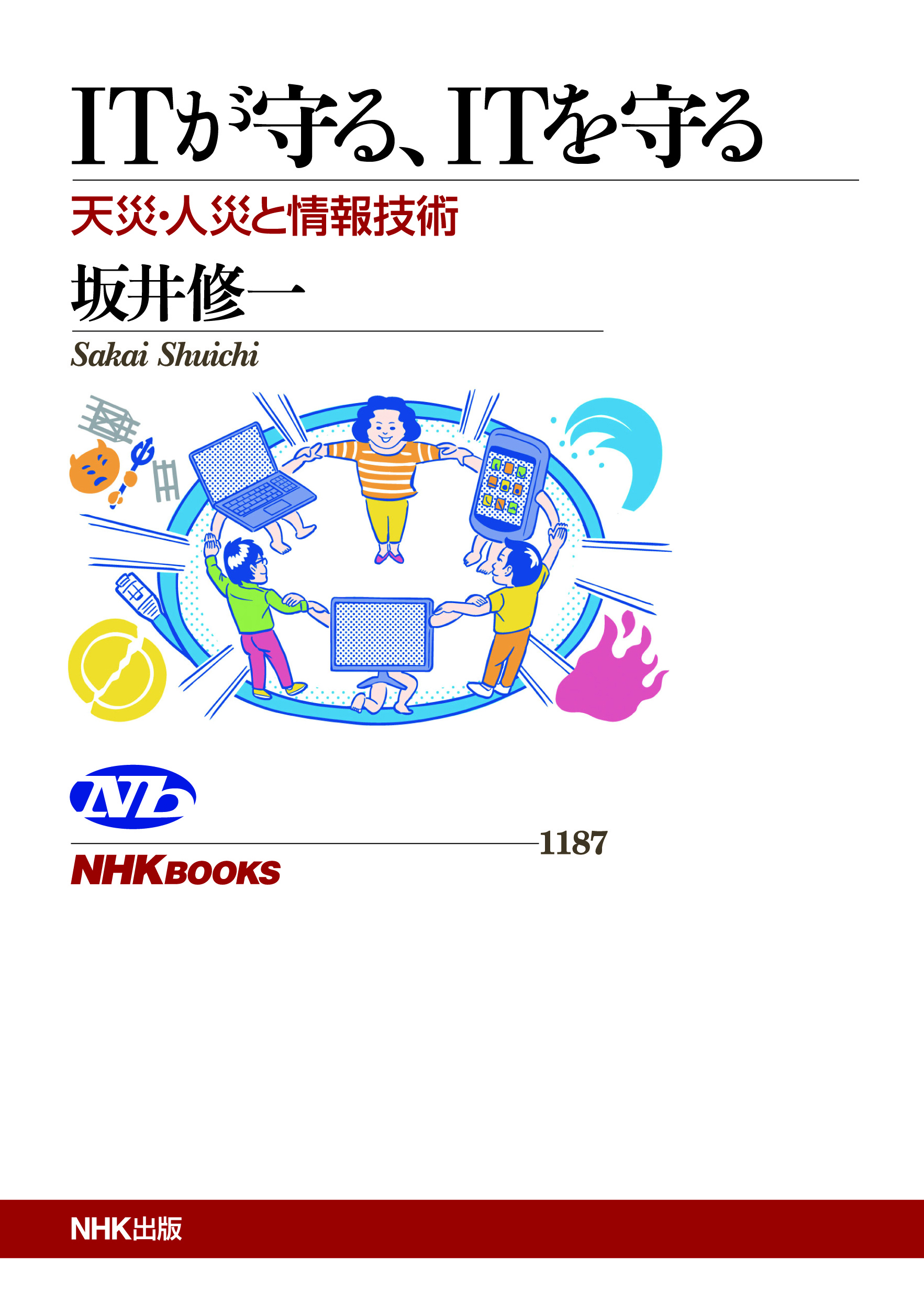
書籍名
NHKブックス No.1187 ITが守る、ITを守る 天災・人災と情報技術
判型など
240ページ、B6判
言語
日本語
発行年月日
2012年2月28日
ISBN コード
978-4-14-091187-7
出版社
NHK出版
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
本書の主題は、人間にとって真に幸福なIT社会はどうやったら実現できるか、ということである。安心・安全な社会を築くために、今後のITのあるべき姿とはどのようなものか。情報工学者でもあり歌人でもある著者が、システムと人心の両側面から、その方向性を探り、提言を行う。
東日本大震災とそれに伴う原子力発電所の事故を機に、ITの諸問題が顕在化した。かつてない非常時に、政府、企業、マスメディア、そしてソーシャルメディアなど、各情報システムはどう機能したのか。それぞれの脆弱性および柔軟性を技術面から検証する一方で、過去の震災を伝えた古典なども取り上げ、「情報」が有する情緒表現の重要性などを説く。
本書ではまず、自身の震災体験に触れ、ライフラインとしてのITの現状について検討し、ITが人の安全・安心にいかに寄与するか、また、そうしたIT自体の安全性・信頼性をいかに担保するかが重要であることを述べる。さらに、鴨長明や寺田寅彦など古典や近代文学に見える大震災について報告し、ここで、心理や感情も情報である、「文明が進むほど天災の損害は増える」(寺田寅彦)、映像や音声による情報伝達には限界がある、などの知見を示す。
本書は、さらに本論として、非常時のITはどう機能したかを、地震検知システム、津波警報、テレビ・新聞・週刊誌・電話など従来のメディア、ソーシャルメディアなどに分けて論じ、近年のITの世界で顕著なベストエフォートの得失について論じる。次に原発事故と情報開示の問題を論じる。ここでは、特に蓋然性の高い事故情報を公開するべきであること、完全保障型でないシステムをそのように見せることが非常に危険であることなどを述べる。続いて、義援金口座への過剰アクセスによるみずほ銀行のシステムダウンについて検討し、CIOの重要性や、事故が単純・簡単な作業の中で起こることについて、『徒然草』などを引用しながら論じる。さらに、震災時のデマやフィッシングについて調査し、デマやフィッシングに引っかからないための方策を示す。最後に、被災地訪問の報告からあるべき情報伝達の姿を考察するなどし、幸福なITとはいかなるものか、生命・財産に加えて感情生活の支援という点から検討と提言を行う。「最善設計、最善リカバリー」のIT的思考で未来を築いていく、そういう時代を迎えていることを強調して本書は結ばれる。
(紹介文執筆者: 情報理工学系研究科 教授 坂井 修一 / 2019)
本の目次
第一章 古典の伝える大震災
第二章 非常時のITはどう機能したのか
第三章 原発事故と情報開示
第四章 情報インフラの信頼性 ―― みずほ銀行システムダウン
第五章 非常時のデマとフィッシング ―― 情報セキュリティ
第六章 社会情報と個人情報 ―― 大きさと個別性
終 章 幸福なIT社会の実現に向けて
関連情報
情報マネージャとSEのための「今週の1冊」- 失敗は、「簡単なこと」「当たり前のこと」で起こる (ITmedia エンタープライズ 2012年3月13日)
https://www.itmedia.co.jp/im/articles/1203/13/news117.html
書評:
読売新聞、日経新聞
受賞歴:
第21回 大川出版賞受賞 (2012年)
http://www.okawa-foundation.or.jp/activities/publications_prize/list.html
http://www.okawa-foundation.or.jp/new/20130401.html



 書籍検索
書籍検索