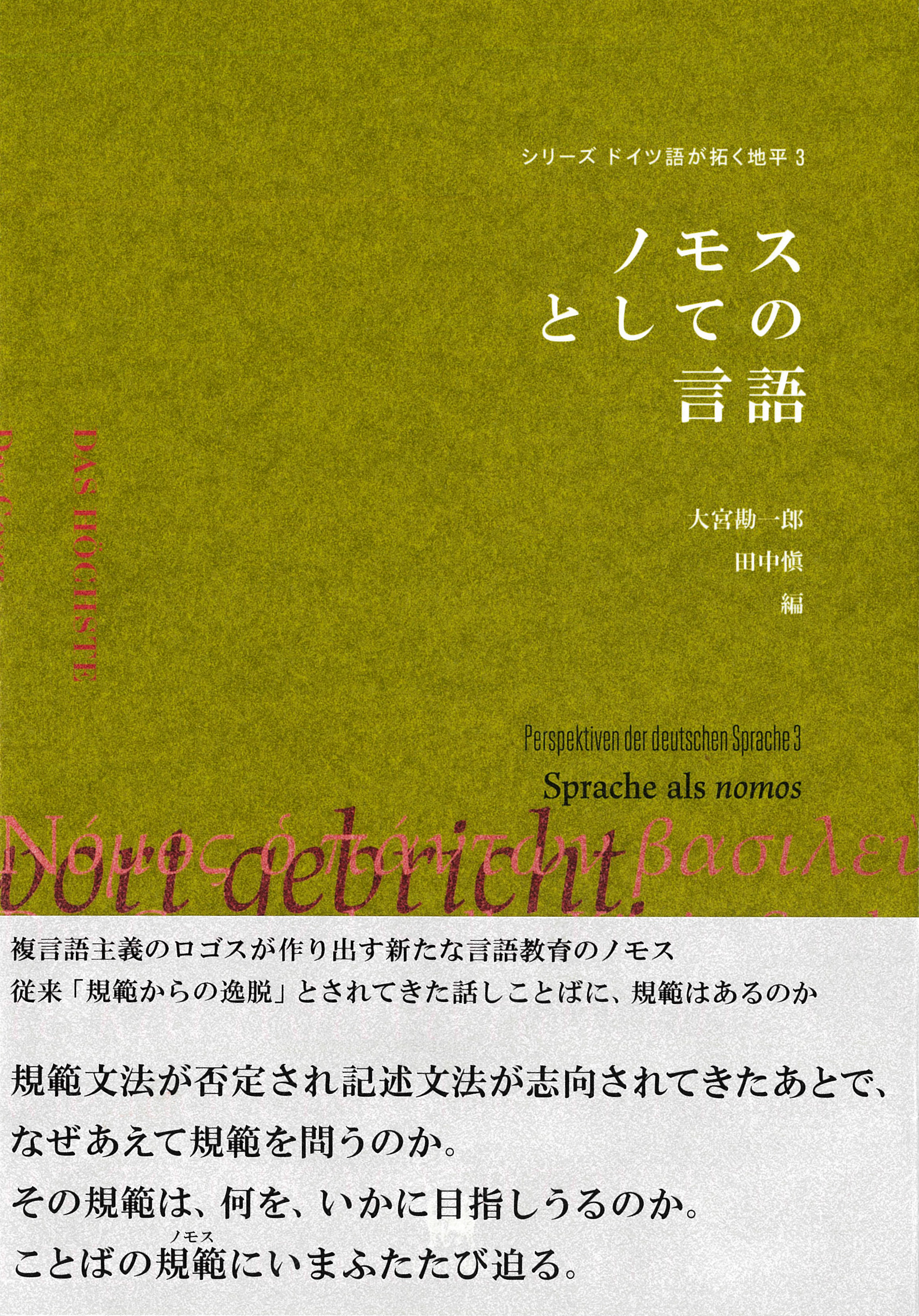書籍名
Wie Goethe Japaner wurde. Internationale Kulturdiplomatie und nationaler Identitätsdiskurs 1889–1989
判型など
191ページ
言語
ドイツ語
発行年月日
2020年
ISBN コード
978-3-86205-668-2
出版社
Iudicium Verlag
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
ゲーテ (Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832) は日本でどのように読まれ、理解され、語られてきたのでしょうか。本書の目的は、日本におけるゲーテ受容史という短い歴史を「世界文学 / World Literature / Weltliteratur」という枠組みのなかでとらえることです。ここでいう「世界文学」とは文学研究における専門用語の一つで、おおよその意味としては、各国・各地域・各言語を発生源とする文学がそれぞれドイツ文学やイギリス文学とよばれるに対して、そのような各国文学の境界をこえて全く別の文化のなかへと受容されてさらにそこで広範囲にわたる影響力をもつようになった文学を指しています。
本書の見どころは、近代国家におけるアイデンティティ形成に大きく寄与してきた各国の「国民文学」がそれと同等の役割を他の国や文化圏でも担うようになっていく過程を、ドイツの文豪が遠く離れた日本で受け入れられ、19世紀末以降徐々に日本化ひいては日本人化されていく様子―「nostrification」の過程―を見渡すことができる点です。
ゲーテはすでにドイツ本国で、19世紀のドイツ統一にいたる過程でのアイデンティティ形成において最重要ともいえる位置を占めてきました。彼の文学作品がその読者たちを「ドイツ人」として自覚的に結びつけたのと同時に、彼自身がきわめて「ドイツ的」な主権者を体現する者として神聖視されていたわけです。ですが、実はゲーテのほかにもう一人、ドイツ国内でこの役割を担った作家がいました。それはなんと、イギリス人のシェイクスピアです。ドイツのロマン派作家たちは、シェイクスピアの中に豊かなドイツ精神を見出し、声高に「我々のシェイクスピア」「ハムレットこそドイツ」と謳ったのでした。この、いわばシェイクスピアがドイツ人へとなっていく経緯は、比較文学の領域ではすでに研究が進んでいます。その比較文学の技法を手助けにして、本書は、ゲーテが日本人になっていく過程をあきらかにしていきます。それはまさに、ある文化的なものが他文化へ吸収され、そしてそこで適合化されたり再加工されたりする過程なのです。
そもそも、日本を日本的にするものとは、いったい何なのでしょうか。日本の知識人たちはこの問いに答えるとき、折に触れてゲーテを引きあいに出してきました。その筆頭に挙げられるのは森鴎外です。夏目漱石と並んで20世紀初頭を代表するこの作家は、若き軍医としてドイツのベルリンで4年間を過ごし、それ以降多くのゲーテ作品を翻訳していくことになります。近代日本の「国民作家 / national author / Nationalautor」になるという志を抱きながら、鴎外はかなり多面的にゲーテの人生や作品を参考にしていたと思われます。彼はゲーテの足跡をなぞるかのようにして、その生涯を文学人としてのみならず、自然科学者そして官吏としておくりました。いつの間にかゲーテ作品と自分の作品との境界線が曖昧になっていったのでしょうか、1913年出版の長編悲劇『ファウスト』の翻訳の表紙にはゲーテの名前はなく、ただ鴎外の名前だけが記されていました。
「鴎外二世」として知られた木下杢太郎は、ゲーテの荘厳な風景描写をつかって、なじみ深い日本の美を再発見しようと試みます。この技法をさらに政治化させていったのは、1930年代に登場した親ドイツ的な若い知識人たちからなるいわゆる日本浪漫派でした。ゲーテを通じて日本的価値を気づくにいたったというようなことが、亀井勝一郎『人間教育 ゲエテへの一つの試み』(1937年) や、安田與重郎『ヱルテルは何故死んだか』 (1938年) などの浪漫派代表作の中で繰り返し述べらているのはとても興味深いものです。
また、自死をとげた「若きウェルテル」は、ゲーテが生み出した数々の主人公のうちでとりわけ日本の知識人たちからの共感を得た一人でした。その共感がひいては、「自殺の国」という日本のセルフイメージへの道筋をつくったといっても過言ではないでしょう。尾崎紅葉、北村透谷、松岡荒村といった明治期に若くして死んでいった作家たちの存在も、ウェルテルへの畏敬の念を深めるのに一役かったはずです。それに続く大正期を生きた芥川龍之介の自伝ともいえる『或阿呆の一生』でもまた、主人公が自死への傾斜をすべりおちていくなかでゲーテの自伝『詩と真実』と『西東詩集』にふれるのです。ちなみに、この『西東詩集』の中には、燃え立つ炎の中へと自ら飛びこんでいく蛾をうたった詩「昇天のあこがれ / Selige Sehensucht」がおさめられており、この詩は太平洋戦争中に神風特攻隊として出陣を待つ若い男子学生たちによく読まれたという悲しい歴史をもちます。
20世紀初頭の「哲学としての禅」という試みに際してもゲーテはその起源の一端を担っています。西田幾多郎と鈴木大拙 (D. T. Suzuki) は新しい仏教思想の解釈を、ゲーテの作品を触媒として、広がりいく世界へとむけて発信していきます。「現象の背後になにかを探ろうとするなかれ / 現象それ自体が教えなのだから」「感覚こそがすべてである / 名前などは単なる音節かゆらめく煙にすぎない」。これらはゲーテの言葉なのですが、西田や鈴木は、これらを近代的なマントラへと仕立て直していきました。そこでゲーテは、精神の自由の象徴として、また、一瞬の中に永遠を見出す者として位置づけられ、西欧文化の中にいながらにして仏陀の正当な理解者であるというステイタスをも手に入れたのでした。
本書を締めくくるのは、ゲーテが文字通りその全生涯にわたって取り組んだ大作『ファウスト』が日本でどのように発展していったかというケーススタディで、黒澤明の『生きる』、手塚治虫の遺稿となった未完のストーリー漫画『ネオファウスト』、そして、「ゲーテ」をコスモポリタンな趣味と自信のシンボルとして扱う月刊誌『GOETHE』を扱います。
18世紀から今日まで、懐かしさや憧れ、そして尊敬の念、さらにはある種のアクチュアリティをもって生き続けてきたゲーテ。彼の日本での活躍をぜひ本書で経験していただければ幸いです。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 准教授 KEPPLER-TASAKI, Stefan / 2020)
本の目次
【※ドイツ語原文は英語のページを参照してください※】
I. はじめに:「国民」意識の創造とゲーテ1. ドイツ人ではない「ゲーテ」とは?
2. 日本人「ゲーテ」の誕生
II. 「日本におけるゲーテ」
1. 日本のドイツ文学研究とゲーテ: 木村謹治
2. 日本の哲学とゲーテ: 西田幾多郎
3. 1945年以降: 三つの流れ
III. ゲーテ、鴎外、日本の文化的セルフイメージ
1. 国民文学作家とゲーテ: 森鴎外
2. ゲーテ、フランス、イタリア
IV. ゲーテと日本の自死言説
1. 遅ればせのウェルテル熱
2. 自死と「死して生きよ!」
V. ゲーテという仏陀:禅の一主題
1. 禅という「公然の秘密」: 西田幾多郎とエドアルド・シュプリンガー
2. 世界の中の仏教: パウル・カルスとD.T.スズキ
3.「内面から湧き上がる存在」: 仏教と中産階級
4. ニヒリズムとしての仏教?: ゴットフリート・ベン
VI. トーマス・マン、日本、ゲーテを媒介とする外交
1. 「日本の若者に宛てて―ゲーテ研究の一つの試み」: 背景と状況
2. パシフィックパリセイドと「東京の親戚たち」
3. 日本人たちとの文通
VII. ファウストと黒澤明『生きる』
VIII. ファウストと手塚治虫『ネオファウスト』
IX. ゲーテというブランド:むすびにかえて
関連情報
(ドイツ文化会館 (OAGドイツ東洋文化研究協会) ホームページ)
https://oag.jp/books/wie-goethe-japaner-wurde-internationale-kulturdiplomatie-und-nationaler-identitaetsdiskurs-1889-1989/
本書紹介ビデオ:
https://vimeo.com/417444412



 書籍検索
書籍検索