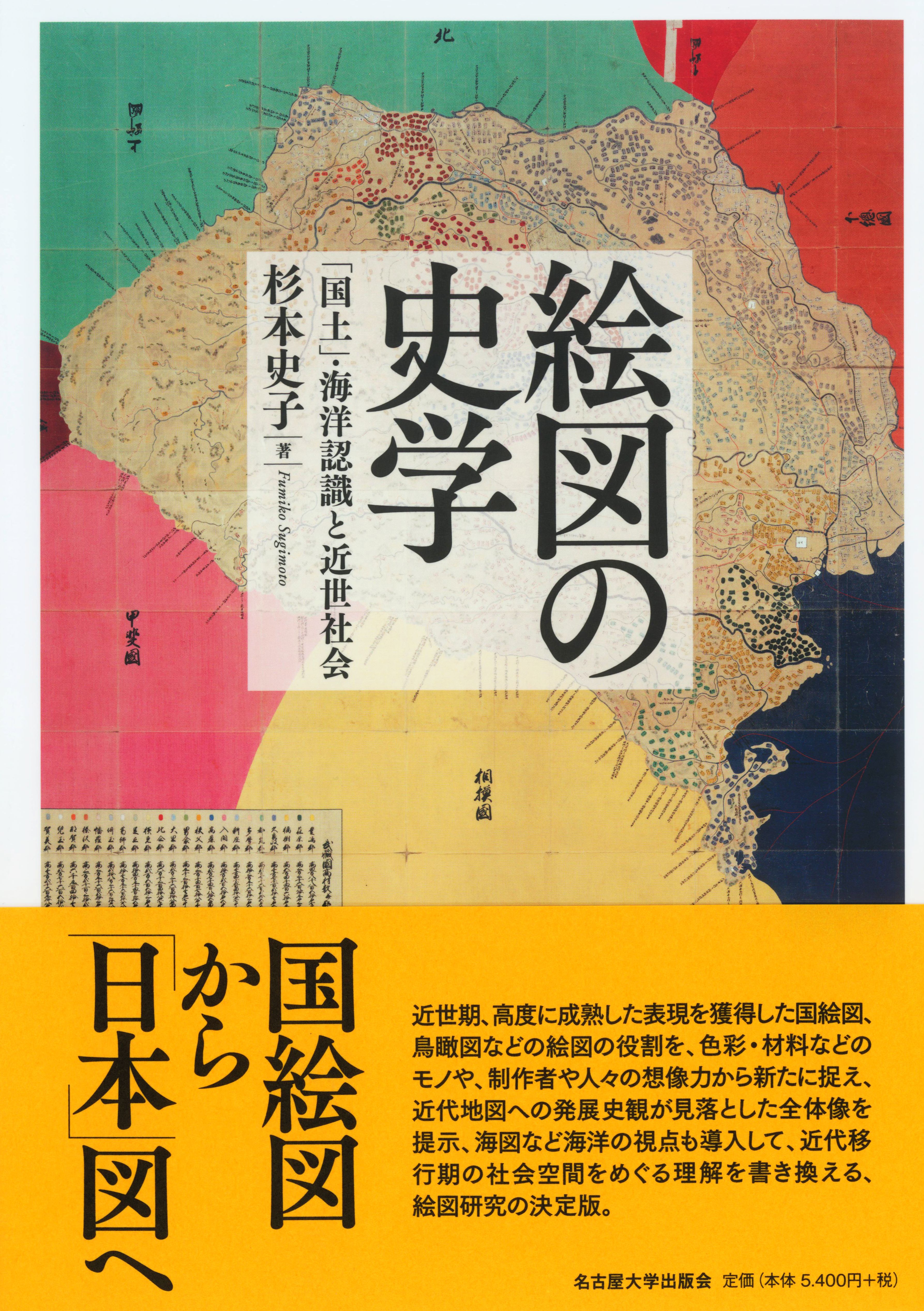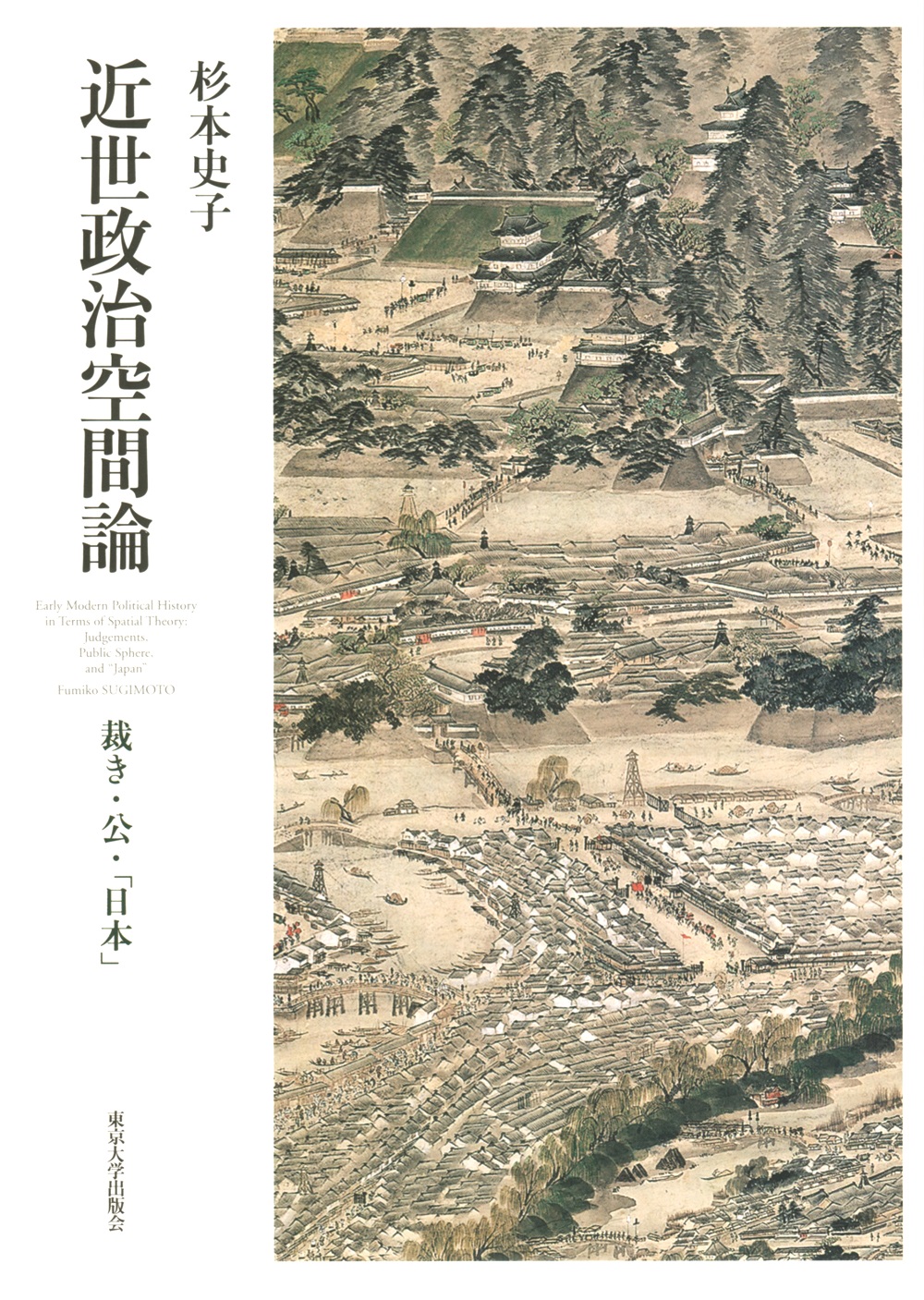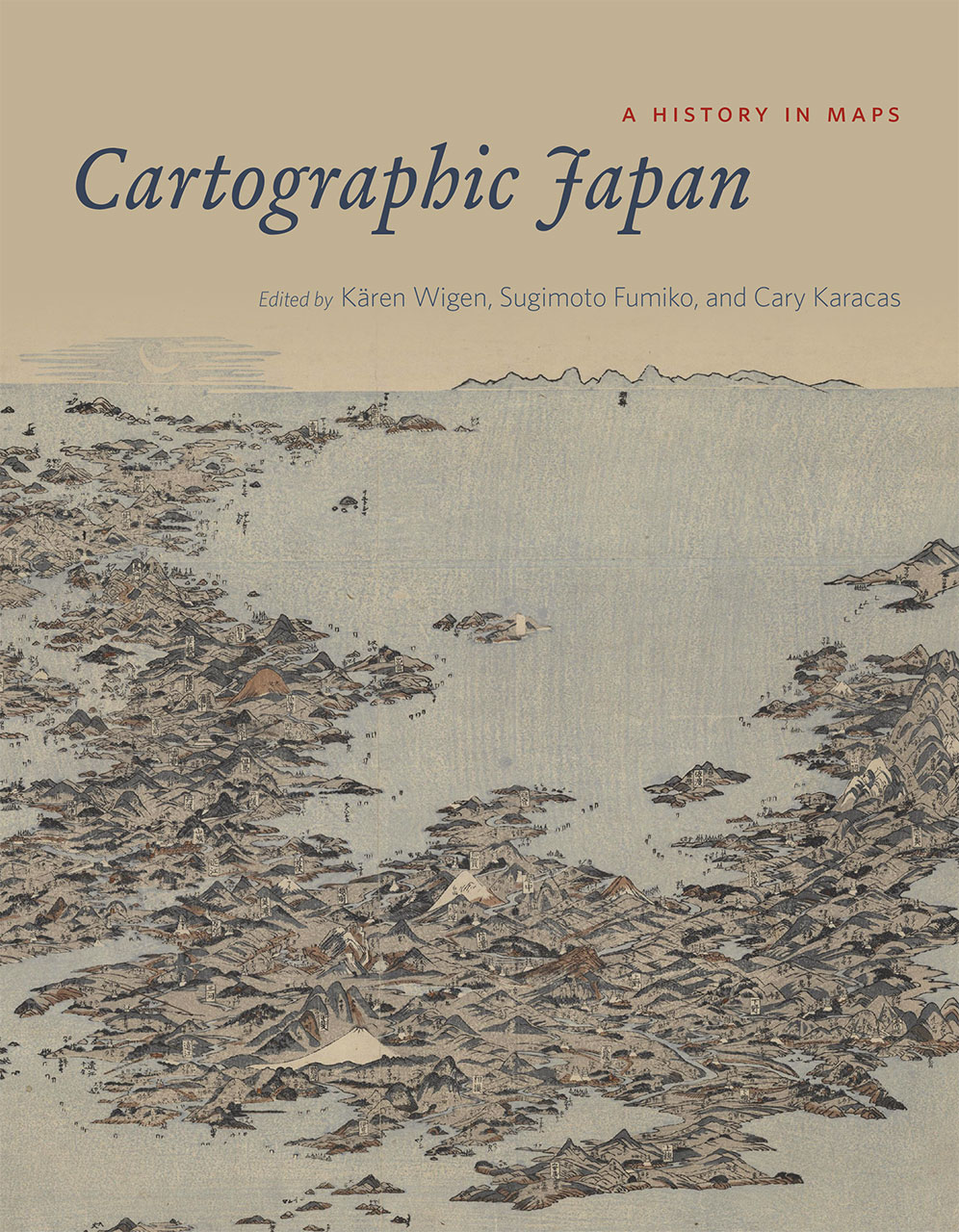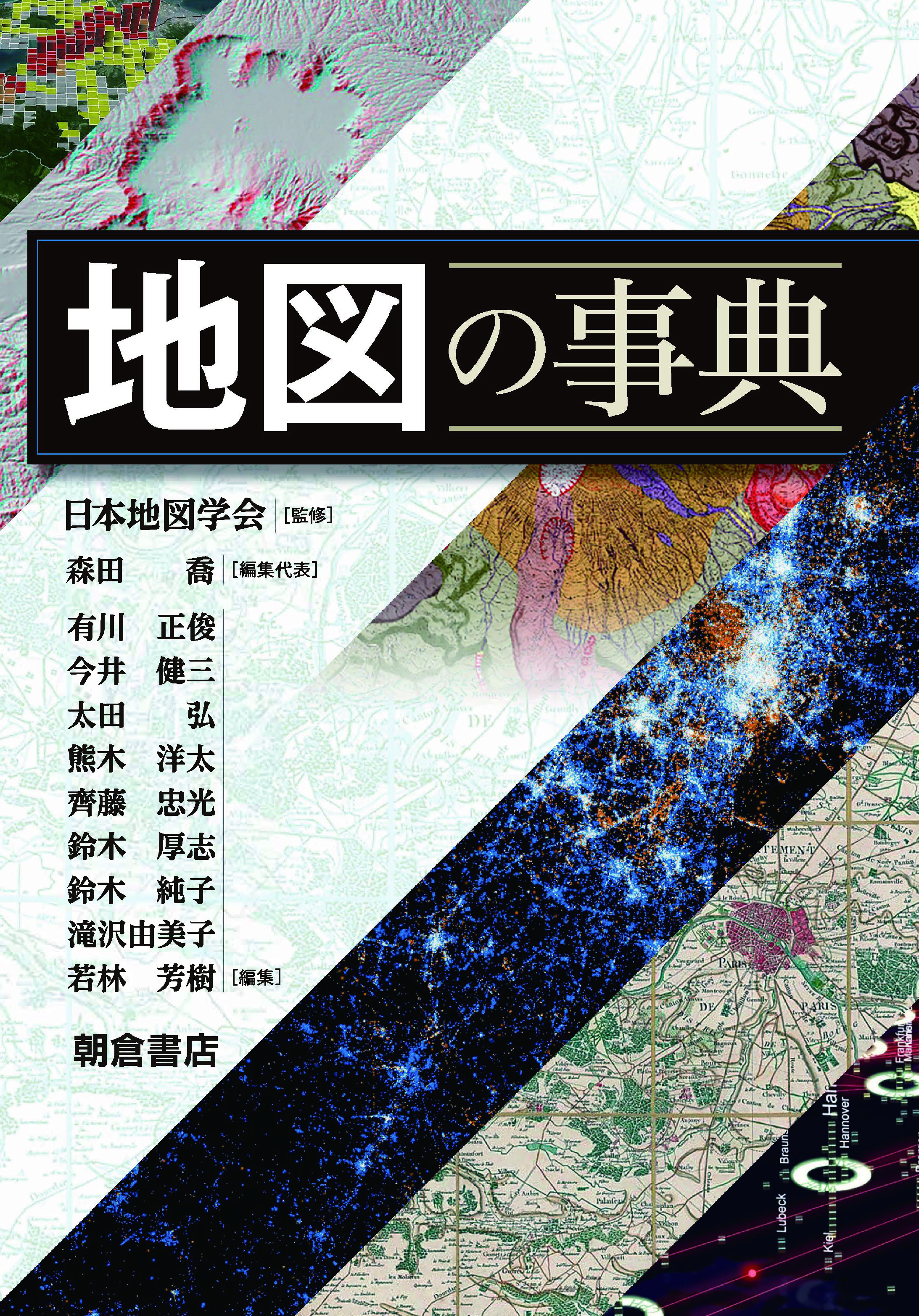地図とは、限定的な共同体を超えた「他者」に語りかけ働きかけるための重要なツールである。本書はこの理解にたち、歴史における地図作成行為の意味を論じた。
*本書をはじめとする諸論考の中では、「近代的地図」とは異なる特質を持つ近世日本の空間表現を指す用語として、当時の史料用語である「絵図」を用い、両者を包含する概念として「地図」を使用してきた。
本書の前提となったのは、助手時代に採択された、科学研究費補助金・国際学術研究共同研究「日本中近世における社会情報と政治文化- 絵図史料を中心として」(研究代表者・東京大学教授黒田日出男、1995~1997年度) を皮切りに、国内外の研究者・多様な職掌の専門家たちと、さまざまな共同研究体制を組み、「地図とは何か」という問いを追究した、二十余年に及ぶ道程であった。
本書をまとめながら、原本調査の場で得られた所見をそれぞれの専門を生かしながら議論する楽しさ、その結果今まで見えてはこなかった新たな風景が次々と眼前に現れてくる、共同研究の醍醐味を思い返さずにはいられなかった。
前述の国際共同研究の成果として刊行した、『地図と絵図の政治文化史』(黒田日出男、メアリ・エリザベス・ベリ、杉本編、東京大学出版会、2001年) の序文に編者として指摘したのは、地図をかつてのような「自然を映す中立的な鏡」とみて単線的な科学的地図発達史のなかに位置づけるのではなく、複雑で多価な世界を、選択し解釈して二次元表現に転換したものであると理解する、1980年代以降の諸分野横断的な潮流であった。 この研究潮流の中では、地図作成の持つ権力性が注目されてきた。
本書ではさらに、高度に成熟した絵図文化を創り上げていた近世日本を舞台に、社会のなかのさまざまな勢力や集団が、地図作成によって、他の集団や自然と対峙し生き抜いていく具体像を描き出した。その際、その地図の作製や使用にかかわる関連文字史料の分析を詳細に行うと同時に、色彩や図・線を駆使した単なる文字記述を超えた表現方法である地図を分析するために、身分制社会における色彩やモノの意味、制作者や読者の特質まで視野に入れ、地図を作るという行為がどのような意味をもっていたのかを問うという方法論をとったことが、本書の特質のひとつとなっている。
本書のもうひとつの特質として、海洋からの視点で「日本」史を見直すという視点を提示した点をあげることができる。東京大学史料編纂所が前身の政府組織から引き継ぐ書類保管庫 (赤門書庫) に、十九世紀の航海用の地図 (海図) 群を発見し、公開に向けての史料学的検討を行う事業を主宰したことは、それまで無意識に陸の視点から歴史を眺めていたことに気づかせてくれた。
そこから、経緯度データをもち、国家が測量から制作・販売まで統括した海図を「近代的海図」として捉え直し、この「近代的海図」や蒸気帆船の実用化よってもたらされた、海洋と人との関わりあいの変化という新たな視角を見出した。近代化過程において、この変化が、国土観や、陸上に構築された社会を変容させていったことを明らかにするという、それまでに移行期研究を問い直す歩みを進めることなった。
このなかでは、19世紀半ばに刊行された木版日本図『官板実測日本地図』が、実は、開成所 (幕府の洋学教育研究機関。頻繁に名称が変更されているので、開成所と総称する) が創り上げた、史上初の、「日本」の範囲をいかに表示するかという問題意識に基づいた「国土」図であり、当時の太平洋をめぐる政治情勢をみすえた、薄氷を踏むような慎重な表現をとっていたこと、近世的「国土」観から近代的国土把握へと移行する過程をその描写に体現した稀有な地図であることを突き止めた。
終章の文章をもって、この紹介文をしめくくろう。
人間は、生きのびるために集団を作り、自然や、他者と、闘ってきた。そのなかで、地図という表現はその全体をみることはできない世界や社会に理解可能な姿をあたえるものであり、人間がそれらに対して何らかの行動を起こすことを可能にする、強力なツールとなってきた。世界や社会を図化し可視化するという行為は、他者に対しての、支配や、合意や、主張と、深くかかわっている。
本書で明らかにしてきたように、世界や社会の視覚化は、各時代の特性を背負ったこのような営み・衝突・合意・駆け引きの動態のなかに置いたとき、はじめて、その時代において有していた意味や機能を雄弁に語り始める。
「絵図の史学」の意義は、ここにある。
(紹介文執筆者: 史料編纂所 教授 杉本 史子 / 2024)
本の目次
はじめに
1 基礎的考察
2 近世 —— 絵図の「開花の季節」
3 海陸の視座をもった近世・近代移行期論へ
4 本書の構成
第I部 国絵図と日本図
—— 近世の「国土」把握
第1章 アジアのなかの政治地図
—— 国絵図と日本図
はじめに
1 徳川政権下の巨大地図
2 徳川型政治地図の成立
3 新しい海洋の登場と統一的国土表現の試み
おわりに —— 絵図の時代の終焉と「地形図」の登場
第2章 国絵図と近世社会
はじめに —— 歴史のなかの国絵図
1 「公儀」と空間把握 —— 元禄国絵図
2 空間把握の展開 —— 天保国絵図
おわりに
補 論 境界上の地名は誰のものか
第3章 国絵図研究の歩みを俯瞰する
—— 19世紀から21世紀へ
はじめに
1 研究前史
2 国絵図研究の本格化
3 国絵図に関する国際的な研究発信
おわりに
第II部 新たな海洋把握と「日本」の創出
——「国土」の変容
第4章 新たな海洋把握と「日本」の創出
—— 開成所と幕末維新
はじめに
1 新たな海洋把握とその意味
2 「日本」の創出
3 日本図布告
おわりに
第5章 可視化された首都と政体
—— 近代的海図と船艦の19世紀
はじめに
1 近代的海図と船艦
2 日本沿海測量問題と海洋情報 —— 文久元年の異例の老中弁明書
3 可視化された首都と政体 —— 海図 Gulf of Yedo
4 船艦というアクター ——『戊辰己巳官軍諸艦記事略』から
5 船艦保有情報の統合と海洋知再編の試み
おわりに
第6章 近代国家形成過程再考
—— 海洋から見たジオ・ボディ
はじめに
1 状 況
2 ジオ・ボディの創造
おわりに —— 海陸の視点をもったジオ・ボディ概念へ
第III部 表現する人々
—— 社会の側から諸世界を構想する
第7章 歌舞伎作者並木正三
—— 交差する複数「世界」と「日本」
はじめに
1 「三千世界商往来」の時空
2 「日本」とその外
3 作者としての並木正三
4 近世身分秩序のなかの役者と作者
おわりに
第8章 一覧図絵師五雲亭貞秀
—— パノラマ式広域鳥瞰錦絵が描く激動の政治社会
はじめに
1 五雲亭貞秀研究史と本章の視点
2 貞秀の出版図の2つのジャンル —— 地図と錦絵
3 文久行列図の位置と特質
4 変動期の社会と貞秀の出版図
おわりに
第9章 書かれたものに対する統制
—— 出版検閲体制のなかの絵図と錦絵
はじめに
1 統制の流れ
2 天保改革と検閲分掌体制
3 絵図に対する検閲
おわりに
第IV部 モノと色彩
—— 空間表現を支えるもの
第10章 史料学の試み
——「モノとしての史料」を問い直す
はじめに —— 歴史研究という行為
1 「日本古文書学」の成立と史料学の展開
2 「古文書・地理の解放」「物語からの解放」としての近代
3 「モノとしての史料」を問い直す
おわりに —— 歴史研究という表現
第11章 構造体としての絵図
はじめに
1 モノとしての絵図
2 内容表現の思想
おわりに —— 構造と動態のなかの絵図・地図
補 論 復元研究が明らかにしたこと
第12章 色彩の時代
はじめに
1 色をかたちづくるもの
2 自然は何色か —— 彩色材料から見た絵図
3 2つの緑色 —— 空間分割の技法
4 輝きと普遍 —— 秩序表現としての彩色
おわりに
終 章 国土・海洋認識と近世社会
はじめに
1 近世的「国土」とその変容
2 世界や社会を描く
おわりに
関連情報
第1回 (2023年度) 中川久定記念基金由学館賞 受賞 (一般財団法人中川久定記念基金 2023年12月8日)
https://nakagawahisayasu.org/
講演会:
第一回 中川久定記念由学館賞 記念講演会
杉本史子「海の地図と陸の地図から江戸時代を問い直す―研究の道程と『絵図の史学』」 (一般財団法人中川久定記念基金 2024年5月18日)
https://nakagawahisayasu.org/notice_files/r6_01_lecture_a.pdf
書評:
上杉和央 評 (『日本歴史』第904号 2023年9月)
https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b10044177.html
後藤敦史 評 (『歴史評論』第881号 2023年9月)
http://www.maroon.dti.ne.jp/rekikakyo/magazine/contents/kakonomokuji/881.html
後藤敦史 評 (『史学雑誌 2022年の歴史学会-回顧と展望』第132編第5号 2023年6月)
https://www.yamakawa.co.jp/product/13205
川村博忠 評 (『地図情報』Vol.43, No.1, No.165 2023年5月)
https://chizujoho.jpn.org/01_chizujoho/43/mi43_1.html
平井松午 評 (『人文地理』第74巻 第4号 2022年)
https://doi.org/10.4200/jjhg.74.04_458



 書籍検索
書籍検索