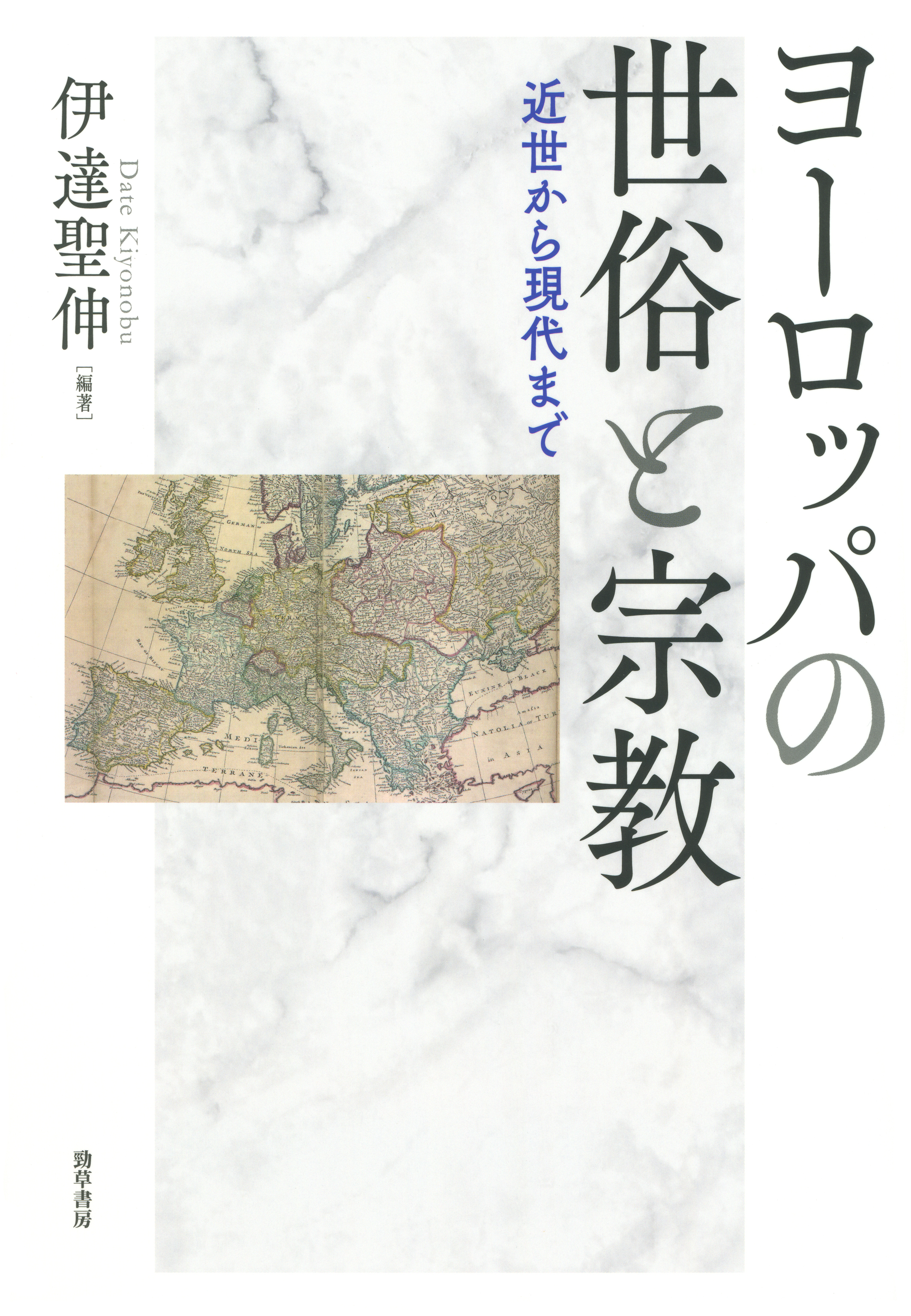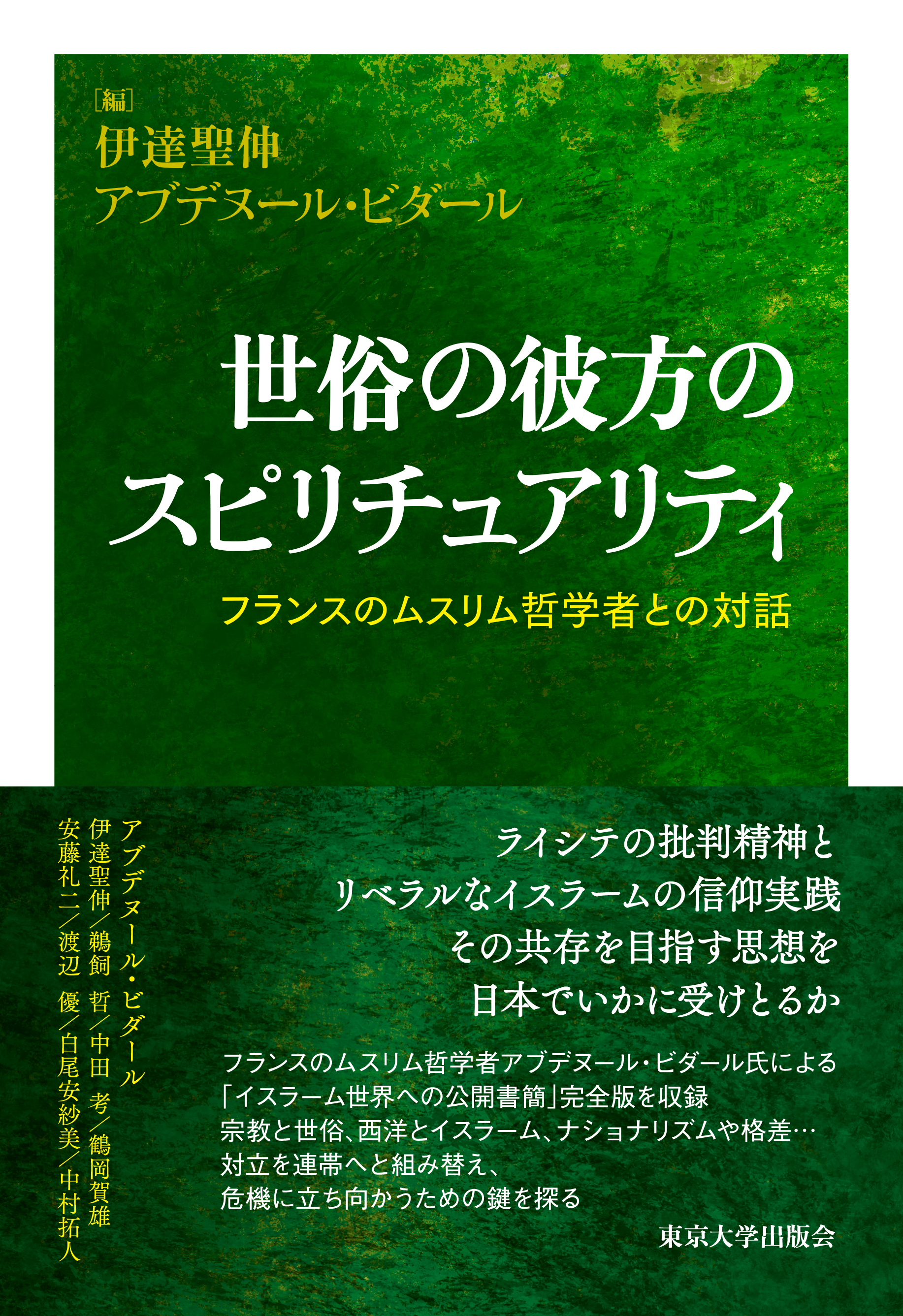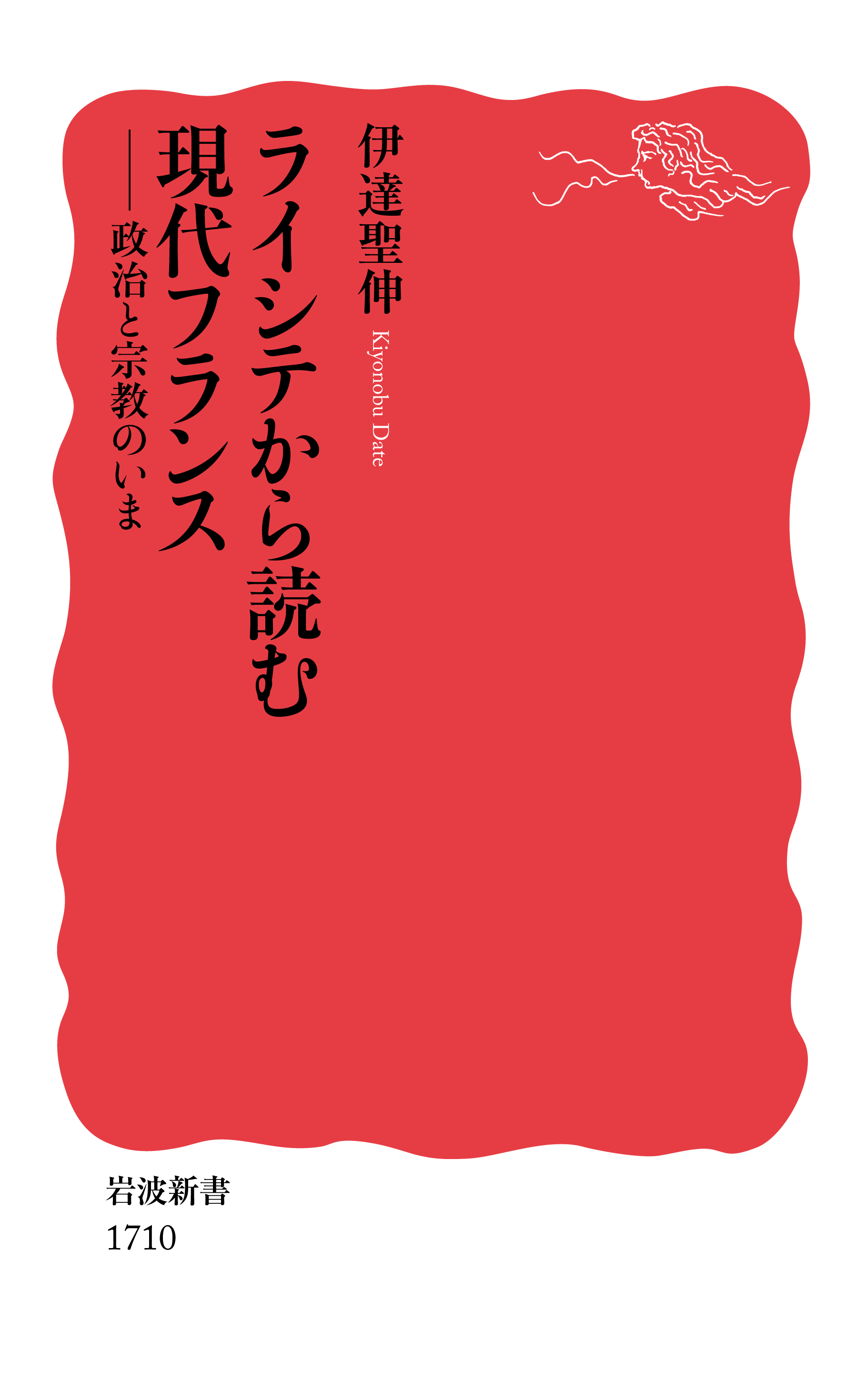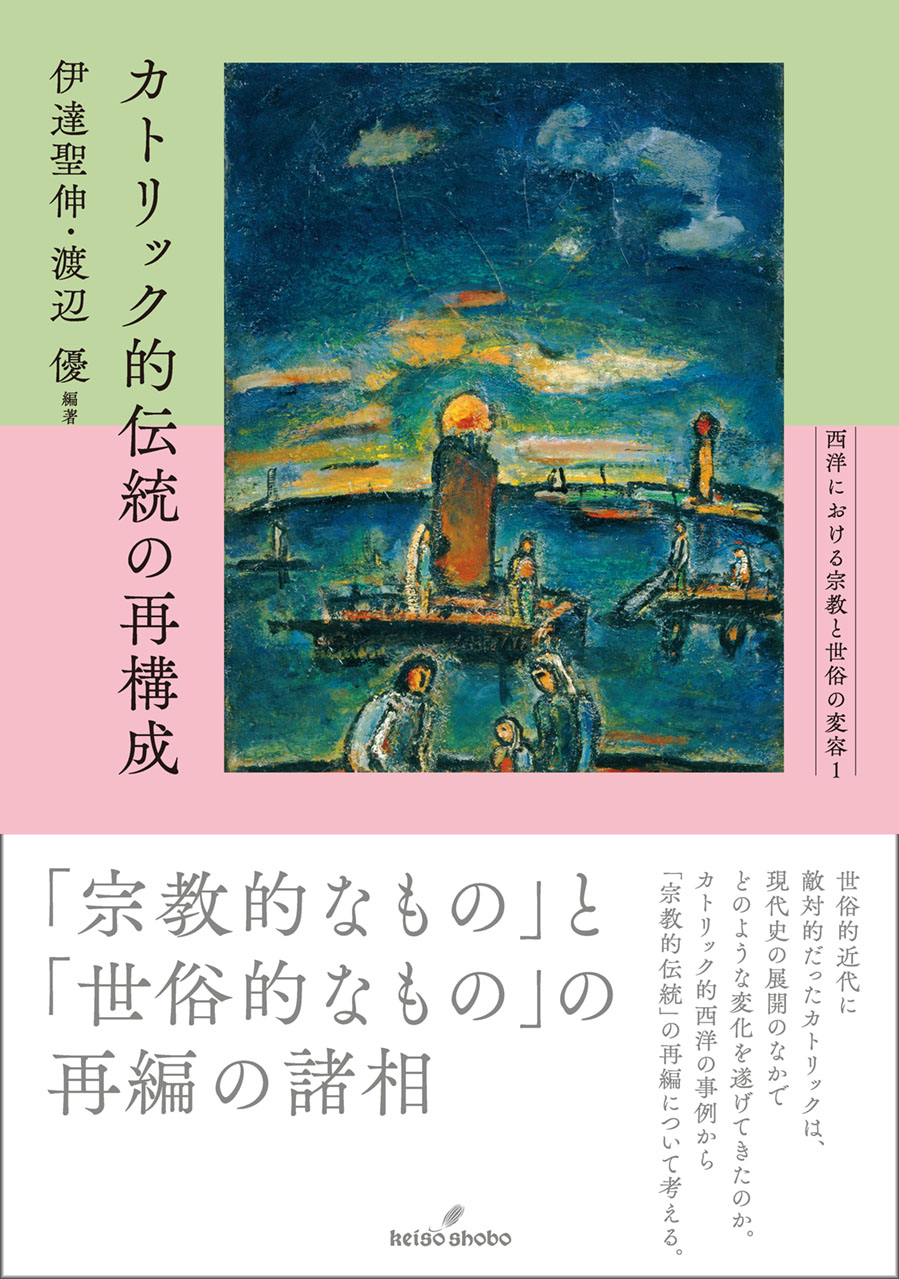
書籍名
西洋における宗教と世俗の変容 カトリック的伝統の再構成
判型など
336ページ、A5判
言語
日本語
発行年月日
2024年1月
ISBN コード
978-4-326-10333-1
出版社
勁草書房
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
世俗の時代の進展とともに、宗教はその社会的存在感を失い、人びとの認識と実践が近代化するにつれて衰退していく――マックス・ウェーバー以来、歴史学者や宗教学者たちの宗教理解を深く規定してきたこの「世俗化」のテーゼは、とりわけ1970年代以降、世界的な宗教復興の動きによって再考を余儀なくされた。しかし、現代世界に起こっている事象はたんなる宗教の時代への回帰ではないだろう。世俗の時代が加速するなか、「世俗」と「宗教」は、それぞれに質的変容を遂げ、複雑に交錯しながら、新たな関係性を出現させている。本シリーズ「西洋における宗教と世俗の変容」は、西洋的な負荷を背負った宗教と世俗の二分法を脱却しつつ、西洋という地理的空間内部の多様性に光を当て、宗教と世俗の再編の諸相を、地域間比較の視点から浮き彫りにすることをねらっている。
第1巻は、長らく西洋の基礎文化を形成してきたカトリック的伝統の再構成を主眼とする。本書に収められた9本の各論は、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、アイルランドといった西欧諸国から、カナダ (ケベック)、ポーランド、アルゼンチン、オーストラリアといった非西欧諸国まで、多様な地域を対象としながら、ひとつの歴史的見通しを共有している。それは、20世紀半ば以降、とりわけ1960年代を分水嶺として、西洋における伝統宗教としてのカトリックの自明性が根本的に揺るがされるに至ったということだ。カトリック教会が公式に近代化を打ち出した第二ヴァチカン公会議の重要性は、教会史においてはそれこそ自明だけれども、その政治的社会的インパクトについてはなお明らかにすべきことが多い。とくにフランスにおける近年の研究は、公会議の結果、人びとの信仰を規定していたカトリック的伝統の脱自明化が進んだことを明らかにしている。本書では、まさにそのような動向が、さまざまな形で「伝統の再構成」を促していることに注目した。
諸地域のスペシャリストである複数の研究者の共同研究の成果である本書は、カトリックというトランスナショナルな宗教運動の近代的な多様性と動態を、しばしばそれが内に抱えている困難や葛藤とともに描きだしている。ジェンダーやセクシュアリティをめぐる問題は、カトリックのゆくえを見極めるためにも、今後さらに研究を進める余地があるだろう。本書はまた、ホセ・カサノヴァ『近代世界の公共宗教』やチャールズ・テイラー『世俗の時代』など、世俗化論を再考するための重要な先行研究を網羅し、確かな理論的視座を提示している。編者の二人がフランスの地域研究や宗教思想の専門家であることから、本書には、日本ではまだ邦訳がない現代フランス宗教学の魅力を紹介するという一面もある。本書の意義として最後にもうひとつ、これまで宗教学においても正面から論じられてこなかったカトリックという「近代知の他者」に向きあっているということを挙げておきたい。この他者の物語は、私たち自身の現在そして未来にも何らかの示唆を与えてくれるはずだ。
(紹介文執筆者: 人文社会系研究科・文学部 准教授 渡辺 優 / 2024)
本の目次
西洋における宗教と世俗の変容――カトリック的伝統の再構成[伊達聖伸・渡辺 優]
一、カサノヴァ『近代世界の公共宗教』の議論を踏まえつつ超え出ていくために
二、カトリシズムの歴史的変化――一九六〇年代を一つの分水嶺とみなして
三、カトリシズムの地理的多様性――ヨーロッパ、北米、南米
四、国際政治とグローバル化――「普遍教会」はどこへ向かうか
各 論
〈第I部 世俗の知とカトリックの知の交錯〉
第1章 ジャン・セギーとフランスの戦後宗教社会学[田中浩喜]
はじめに――ジャン・セギーとは何者か
一、対象を拡大する――セクトと修道会
二、理論を輸入する――ウェーバーとトレルチ
三、概念を洗練させる――「ユートピア」の宗教社会学
四、観点を逆転させる――「メタファー宗教」と「宗教的近代」
おわりに――荒野を流浪する
第2章 ケベックにおける宗教学の誕生――フランス宗教社会学との交流を背景として[伊達聖伸]
はじめに
一、フランスにおける宗教学の誕生とカトリック的宗教社会学の盛衰
二、ケベックにおける宗教研究の刷新
三、UQAMにおける「宗教学」(religiologie)の誕生
四、ケベックにおける宗教研究の多様性――モントリオール、ケベック市、シェーブルック
五、一九七〇年代以降のケベック宗教社会学――アンリ・デロッシュの受容をめぐって
おわりに――神学部が閉鎖されるなかでの宗教研究
第3章 イタリアのカトリック的伝統における宗教史学――ペッタッツォーニの「信教の自由」論を中心に[江川純一]
はじめに ペッタッツォーニの転回――同時代イタリアへの批判的視点
一、国際宗教史学会議ローマ大会(一九五五年)をめぐって
二、講演「イタリアにおける教会と宗教生活」(一九五七年)
三、講演「イタリアにおける信教の自由のために」(一九五八年)
四、ペッタッツォーニ以後
おわりに
〈第II部 カサノヴァ「公共宗教」論の見直し、その限界と可能性〉
第4章 ポーランドの政教関係から見た公共宗教論の現在地――民主化運動のレガシーの行きつくところ[加藤久子]
はじめに
一、「民主化の第三の波」におけるカトリック教会
二、カトリック保守派による政治活動
三、人工妊娠中絶とカトリック教会
おわりに
第5章 現代アルゼンチンにおけるカトリック教会と国民宗教意識[渡部奈々]
はじめに
一、カトリック教会の公共的役割
二、教皇フランシスコと社会教説
三、教会と国民意識のずれ
四、民とはだれか
五、喪失する役割
おわりに
第6章 権威主義体制期ポルトガルにおけるカトリック教会と「準反対派」――フランシスコ・サ・カルネイロの活動を中心として[西脇靖洋]
はじめに
一、権威主義体制期の政教関係
二、「準反対派」とカトリシズム
おわりに
〈第III部 グローバル時代のカトリック、普遍主義のゆくえ〉
第7章 ダニエル・マニックスと脱植民地化、二つの世界大戦、冷戦の中のカトリック教会[小川浩之]
はじめに
一、ナショナリズムと脱植民地化
二、二つの世界大戦
三、冷戦と「第三の道」
おわりに
第8章 カトリック的「世界市民」をつくる――学生・知識人信徒による国際団体「パクス・ロマーナ」の活動をめぐって[渡邊千秋]
はじめに
一、創立――第一次世界大戦前後
二、深化――第二次世界大戦期
三、拡大――第二次世界大戦後
四、頂点――第二ヴァチカン公会議
五、分断――公会議後の世界
おわりに
第9章 イエズス会士セルトーと危機の時代の教会論――「第三の人」(一九六六年)をめぐって[渡辺 優]
はじめに
一、「第三の人」とセルトー
二、労働者たちの祈り――「奇妙な移動教会」
三、場所を持つこと
四、ボカン修道院とセルトー――「人間の経験の大海」に臨む場所
おわりに
関連情報
https://www.keisoshobo.co.jp/search/s18886.html
書籍紹介・書評:
あとがきたちよみ (勁草書房編集部ウェブサイト けいそうビブリオフィル 2024年1月31日)
https://keisobiblio.com/2024/01/31/atogakitachiyomi_catholiquetekidentounosaikousei/
島薗進 評 (『宗教研究』98巻2号p.209-221 2024年9月10日)
https://doi.org/10.20716/rsjars.98.2_209
イベント:
「西洋における宗教と世俗の変容」オンライン合評会
第1回『カトリック的伝統の再構成』 (2024年5月17日)
第2回『イスラームの定着と葛藤』 (2024年6月2日)
第3回『世俗の新展開と「人間」の変貌』 (2024年7月19日)



 書籍検索
書籍検索