自然に学び、持続可能な社会をつくる 環境問題に取り組むための教育と社会活動

毎年4月22日は、地球環境への意識を高め、将来の世代のために環境を守る行動の重要性を確認する「アースデイ」です。地球環境への負荷を軽減するために何をすべきか、自然からの学びをどう活かすかについて、東京大学大学院農学生命科学研究科の五十嵐圭日子教授に聞きました。

地球環境への負荷を軽減するために
── 持続可能な社会の実現を阻む最大の要因は何ですか?
現代の人間社会の仕組みが、自然環境に過大な負荷をかけています。エネルギーや食物、素材原料として私たちが自然から取り出すものの量と、自然に還すものの量との間でバランスがとれていないのです。どんな新技術が開発されたとしても、この循環による均衡が保たれない限り、長期的な持続可能性は実現できません。
アース・オーバーシュート・デーと呼ばれる日のことをご存知ですか。地球が再生産できる生物資源の総量を、人間がすべて使い切ってしまうタイミングを、1年のうちの日付になぞらえて示すものです。1月1日から使い始めてその日を過ぎると、私たちは未来から資源を"借りて"消費していることになります。私が生まれた1970年代、人類は1年間でおよそ地球1個分の資源を消費していました。辛うじてオーバーシュートはしていなかったと言えます。しかし、昨年(2022年)は7月28日にアース・オーバーシュート・デーを迎えました。しかも地球上のすべての人々が日本に住む私たちと同じレベルの生活を送っていたなら、5月6日にはアース・オーバーシュート・デーを迎えることになります。つまり、今の私たちの生活スタイルをそのまま続けるなら、1年間に地球約2.9個分の資源が必要になるのです。アース・オーバーシュート・デーの日付は、年々早まっています。
── 何が過大な負荷となっているのでしょう?
私たち人間とバイオマス、つまり地球の表面上に存在する有機物との関わり方が主な原因の一つです。バイオマスとは、生きている、もしくは直前まで生きていた動植物に由来する再生可能な有機物です。人が口にする食物、衣服に用いる綿や羊毛、家を建てるための木材などがその例です。
人が木を燃やしたり食料を摂取したりしてこれらの物質を消費すると、主に二酸化炭素の形で炭素が発生します。この炭素は、植物によって吸収され、地球環境に還元されます。これを「炭素循環」と呼びます。地球環境を維持するためには、この循環が十分に機能することが必要です。
ところが、毎日の食料品からプラスチック製品に至るまで、私たちは作ったモノを大量に廃棄し、浪費しています。その結果、食品のように本来炭素循環によって地球に戻すことができるものが、その循環に乗ることがなくなっています。流通している商品の扱い方が、環境に負荷を与える原因となっているわけです。リサイクルが可能であれば再利用する、そうでないものは炭素を地球に還元できるように、循環サイクルの改善が必要です。
また、石油や天然ガスなどの化石資源は、通常の炭素循環には含まれません。厳密には、化石資源ももとは動植物ですが、数億年かかって形成されたため、「長い間地下に隔離されていた炭素」とでも言いうるものなのです。これをエネルギーとして利用するために燃やすと、膨大な時間の中で貯蔵されていた大量の二酸化炭素が大気中に放出され、自然がこれを有機物に戻す速度が追いつかないわけです。
未来に向けた教育と社会活動
── 地球環境への負荷を軽減するため、私たちにできることは何でしょうか?
実際のところ、個人レベルでできることは限られています。例えばプラスチックの購入や廃棄を避けることはほとんど不可能です。家庭の定番であるお米を考えてみてください。かつてお米は稲わらから作られた俵に入れて売られていました。のちに、麻袋をそのつど生産者のところに持っていき、米を買うようになりました。ところが、今では、ポリ袋に入った米が販売され、この袋は生産者に返却されることもなく、自然に還ることもありません。袋は捨てられ、また新しい袋に入った米を購入しなければなりません。米がポリ袋で販売されている限り、プラスチック廃棄による環境負荷を個人の努力で削減させることは難しいでしょう。
つまり、これは企業や産業界、政府レベルにおいて大規模かつ組織的なシステムの変革が求められている課題なのです。そのような巨大な存在と向き合うことになると、私たちは一人の人間としてあまりにも無力であると絶望してしまいそうです。しかし、その絶望こそが変革を促すエネルギーにもなるのです。問題とその解決のためになすべきことに気付くのが第一歩です。そして、できるだけ多くの人々にそのことを知ってもらうために、教育と社会活動が欠かせません。

── どのような教育や社会活動を実践していらっしゃるのでしょう?
東京大学の取り組みとして、私を含め3名の教員で、2017年にワン・アース・ガーディアンズ(One Earth Guardians)育成プログラム を立ち上げました。アース・オーバーシュート・デーの背後にある考え方と同じく、地球環境への負荷についての意識を高め、地球1個分相当の資源での生活を実現するためのイノベーションについて考えることを目的としています。このプログラムに参加する学生は、講義を受けるだけでなく、プロジェクトを遂行し、企業や政府機関の人々と関わりながら持続可能性に関する問題を明らかにしその解決策を導き出すためのトレーニングを受けます。プログラム修了後は、その経験を将来の研究やキャリアに活かすことができます。
を立ち上げました。アース・オーバーシュート・デーの背後にある考え方と同じく、地球環境への負荷についての意識を高め、地球1個分相当の資源での生活を実現するためのイノベーションについて考えることを目的としています。このプログラムに参加する学生は、講義を受けるだけでなく、プロジェクトを遂行し、企業や政府機関の人々と関わりながら持続可能性に関する問題を明らかにしその解決策を導き出すためのトレーニングを受けます。プログラム修了後は、その経験を将来の研究やキャリアに活かすことができます。
社会活動としては、「クライメート・リアリティ・プロジェクト(Climate Reality Project) 」に関わっています。このプロジェクトは、気候変動について人々の意識を高め、その対策について正確な情報を発信するために、さまざまな分野のボランティア人材を養成しています。これまでに世界で約45,000人、日本では800人以上のクライメート・リアリティ・リーダーが生まれました。リーダーになると、多様な背景を持つ人々が所属する大きなグループの一員として、気候変動問題について意見を交わし知見を共有することができます。このプロジェクトに参加してから、気候変動問題についての私の意識は変わりました。この問題についての議論が世界でどのように行われているのかを、根拠を持って定量的に理解していますので、それに基づいて、日本で、そして大学で、私たちは気候変動にどう取り組むべきかをより真剣に考えるようになったのです。
」に関わっています。このプロジェクトは、気候変動について人々の意識を高め、その対策について正確な情報を発信するために、さまざまな分野のボランティア人材を養成しています。これまでに世界で約45,000人、日本では800人以上のクライメート・リアリティ・リーダーが生まれました。リーダーになると、多様な背景を持つ人々が所属する大きなグループの一員として、気候変動問題について意見を交わし知見を共有することができます。このプロジェクトに参加してから、気候変動問題についての私の意識は変わりました。この問題についての議論が世界でどのように行われているのかを、根拠を持って定量的に理解していますので、それに基づいて、日本で、そして大学で、私たちは気候変動にどう取り組むべきかをより真剣に考えるようになったのです。
他には、映画『せかいのおきく』の監修も行っています。この映画を制作しているYOIHIプロジェクト は、映画製作者と科学者が連携し、気候変動についての意識を高める物語を創り映画の形で広く伝えて行こうとする活動です。『せかいのおきく』という映画は、江戸時代を舞台に「循環型バイオエコノミー」ともいえる生き方を紹介し、2023年の社会に生きる私たちがどうすれば再びその生き方を実現できるのかを考えさせます。それは、何かを買い、使い、捨てる、という現代の直線的(リニア)な経済に替わって、再利用、リサイクル、修繕などによって資源を循環させ続ける方法を見つけ出すということです。
は、映画製作者と科学者が連携し、気候変動についての意識を高める物語を創り映画の形で広く伝えて行こうとする活動です。『せかいのおきく』という映画は、江戸時代を舞台に「循環型バイオエコノミー」ともいえる生き方を紹介し、2023年の社会に生きる私たちがどうすれば再びその生き方を実現できるのかを考えさせます。それは、何かを買い、使い、捨てる、という現代の直線的(リニア)な経済に替わって、再利用、リサイクル、修繕などによって資源を循環させ続ける方法を見つけ出すということです。
このような活動は、異なった形をとってさまざまな場で展開されています。気候変動について正確な事実を知るだけでなく、地球環境への負荷を軽減するためには現状とは異なる暮らしかたがあり得るのだということを理解しなければなりません。
自然界から学べること
── 持続可能なライフスタイルにつながるものとして、どのような自然現象に注目していらっしゃいますか?
私の専門は「キノコ」です。菌類であるキノコは、木から必要な栄養分を吸収する、すなわち、外部から有機物を取り込むことによって生きており、最小限のエネルギーで新しい物質を作り出すという驚くべき特徴を持っています。独自の消化酵素を使い、エネルギーをまったく使わずに、木という材料を利用しているのです。
私たちはプラスチックを作るときに非常に多くのエネルギーを使い、廃棄するために燃やす際にもまたエネルギーを用います。リサイクルしようとしてもエネルギーが必要です。プラスチックに限らず、現代社会における生活では、あらゆる場面でエネルギーを消費しています。
一方、自然界では、ごくわずかなエネルギー消費で物質を作ったり、壊したりすることができています。例えば、ツガサルノコシカケ(学名:Fomitopsis pinicola)の子実体が成熟して胞子を放出するとき、子実体はプラスチックのように硬くなります。プラスチックを作るには200℃を超える高温の状態が必要ですが、キノコは自然な森林の温度の中でも、プラスチックのような固さの物質を作り出すことができるのです。自然環境におけるエネルギーや資源の使われ方の仕組みがごく一部でも分かれば、人間の日常生活に応用し実現できることは多いはずです。

── これまで人間は自然界とどう関わり何を学んできたのでしょう。また、現在の研究の状況を教えてください。
品種改良に注目すると、私たちがこれまで自然界から学んできたことの一端が分かるでしょう。品種改良とは、ある生物に備わっていてほしい遺伝的性質を特定し、それを持つ個体を繁殖させ、子孫が必ずその特定の性質を持つようにする過程のことです。動物を家畜化したり、本来は食べられなかった、あるいは栄養価が低かったイチゴ、ジャガイモ、トウモロコシなどを食料として摂取できるようにするためなど、理由は様々ですが、人類は何千年にもわたって品種改良を実践してきました。自然をつぶさに観察し、自分たちにとって有益なものを生み出そうとしてきたのです。
近年、よく話題になるゲノム編集は、人類がこれまで実践してきた品種改良の延長線上にあると言えるでしょう。もともとある遺伝子のパターンに変化を加えるという論理は同じだからです。しかし、実は、私が大学院学生だった1990年代後半以後、ゲノムをめぐる研究の状況は劇的に変化しています。遺伝子をはじめとするDNA情報、つまりゲノムそのものに関する知識が得られるようになったからです。以前は、ある生物が特定の条件下でどのような反応を示すかを観察によって把握することはできても、反応の背景にある遺伝子レベルの原因までは知られていませんでした。ゲノムは簡単に「読める」ものではありません。それが容易に解読できるようになって、あらゆることが変わりました。ゲノムにアクセスできなかった頃と比べると、COVID-19のような新種のウイルスも、はるかに容易に扱えるようになりました。
しかし、これから懸念されることもあります。例えば、とても筋肉量が多い魚や肉を作り出すなど、将来的に人類がゲノム編集をどこまで利用していくのかについては、議論をする必要があると考えています。品種改良の延長線上にあるゲノム編集とは異なり、本来持っていなかった遺伝子を人為的に加える遺伝子組み換えについても慎重な検討が必要です。生命科学は非常に大きな転機を迎えています。生物の働きについてより詳細な知見が得られ、人間の生活にも影響する多くの可能性が解明されてきています。とはいえ、自然界の種について、分かっていないことはまだたくさんあります。私たちを取り巻く自然界がどのようにして成り立ち何を必要としているのかを理解することによってはじめて、私たちは自然環境との均衡のなかで生きていくことができるのです。
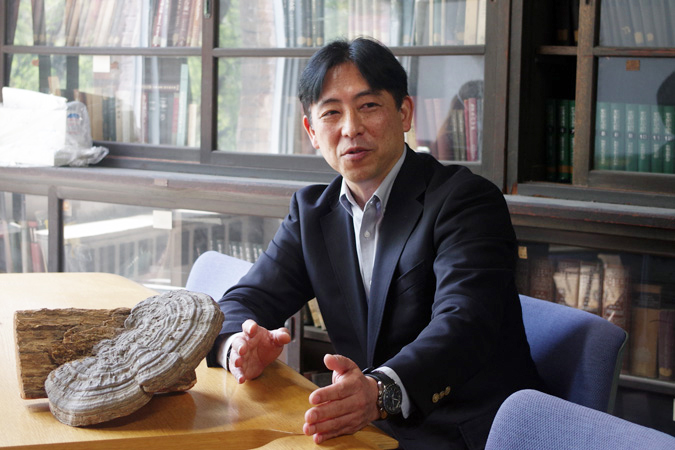
五十嵐 圭日子
大学院農学生命科学研究科教授
東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了。博士(農学)。米国ジョージア大学訪問研究員、日本学術振興会特別研究員、スウェーデンウプサラ大学博士研究員を経て、2002年に帰国後、東京大学大学院農学生命科学研究科助手、2007年より同助教、2009年より同准教授、2021年より現職。2016年よりフィンランドVTT技術研究センター客員教授。著者・共著者として数百本以上の論文を執筆。植物や菌類からの物質・エネルギー生産研究の第一人者。
本記事は、Education and outreach to create a sustainable society: Perspectives from the natural world(取材日:2023年4月4日、公開日:2023年4月21日)をもとに、日本語版を作成しました。
取材:ハナ・ダールバーグ=ドッド、寺田悠紀





