科学の進展で生じた不安の緩和は対話が鍵に 「科学と人の心」をテーマに東京フォーラム2021を開催


2021年12月2、3日に開催された東京フォーラム2021の「統括セッション」では、若手研究者6名が各セッションの内容を報告し、人類の共通課題について意見交換を行った。藤井輝夫東京大学総長(中央)、八木信行農学生命科学研究科教授(右)も登壇し、NHK国際放送局の山本美希エグゼクティブアナウンサーが司会を務めた
近年の目覚ましい科学の進歩で人間の生活は飛躍的に便利になった一方、人や情報の越境による外界との接触の増大など、その負の側面は多くの人々を不安に陥れています。2021年12月2日(木)、3日(金)の2日間にわたってオンランで開催された「東京フォーラム2021」(東京大学と、韓国の学術振興財団Chey Institute for Advanced Studies(CIAS)の共催)は、世界各国から40人以上の識者が参加し、「科学と人の心」をテーマに、近年生じた新たな心の不安についてどう対応すべきか、活発な議論が交わされました。約110か国・地域から8000人以上の登録視聴者があり、まさに世界をつなぐ会議となりました。

藤井輝夫・東京大学総長は開会の挨拶で、「近年の科学の発展は目覚しく、人間の生活はより便利で効率的になりました。しかし、皮肉なことに科学進展の結果、不安が増大している面もあります」と今回のテーマについて口火を切り、「我々が今日直面する課題の多くは『対話』が鍵になると確信しています」と述べました。
また、藤井総長は自身が2021年秋に公表した、目指すべき理念や方向性をめぐる基本方針「UTokyo Compass」に触れ、「(基本方針は)『対話』を最重要課題にしています。大学が育てる『問いを立てる力』は、対話の始まりに不可欠です」と語りました。
さらに、「問題に共に向かいあい、対話を通じて関わり合うことで、ともに見る、ともに感じる、ともに考えることを基盤とする理解が形成され、信頼が醸成されます。対話がもたらすのは、議することで推し進められる、多声の協奏です。そのように多様性が創造する未来を描くには、不公正や差別の理不尽、さまざまな社会的弱者の存在に対する鋭敏な感性を持ち、課題と真摯に向きあう主体的な姿勢が要請されます」と続けました。
テーマの背景には、デジタル・デバイドや、人や情報の越境による外界との接触の増大、人工知能(AI)の急激な進展、福島第一原子力発電所事故など、人々の心に不安が生じさせるような現象や科学への信頼を揺るがす事故があります。不安は排他的ナショナリズムを燃えたぎらせる燃料になります。科学は人類にあまねく共有されるどころか、再び国家間の争いの道具と化しました。会議では、「科学を振興しながら、それに伴う不安をいかに説明し、対処していくか」「世界中の人々を一つにするために、いかに科学を進展させるか」などが話し合われました。

基調講演では、イェール大学イェール・カレッジ長のマーヴィン・チョン教授から、脳内の思考を読み取る技術「マインド・リーディング」の研究が紹介されました。チョン教授がAIや磁気共鳴機能画像法(fMRI)を使用して行った研究は、うつ病やアルツハイマー病など精神疾患や神経系の疾患の治療に応用できます。画期的な技術ですが、メンタル・プライバシー(心に思っていることについてのプライバシー)や、偏見、バイアスを生じさせる可能性などの問題が生じ得ます。
藤井総長は、チョン教授との対話で、この技術をいかに共生社会の構築に役立たせることができるのかと問いました。チョン教授は、「脳撮像やAIの発展で応用できる重要な点は、世界をさらに共生社会にすることです」と応じ、例えば、大学の入学資格審査などに応用可能としました。現在の審査は、すでに恵まれた境遇にある者に有利な方法を採用しているといい、「これらの技術を活用し、入学資格審査の公平を保つことが期待されるし、社会的弱者や障害者に機会を与えることもできます」と答えました。
チョン教授のほか、世界的な建築家、隈研吾・東京大学特別教授も基調講演を行い、コンクリートや鋼鉄に代わり木材や自然の素材を利用した、持続可能な建築への同教授の取り組みを紹介しました。
イノベーションの意図しない結果と向き合う
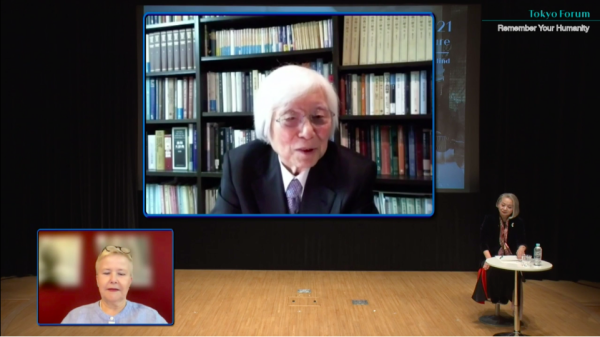
科学分野の功績の負の部分に向き合う取り組みは、今までもなされてきました。全ての核兵器および大量破壊兵器の根絶を訴える科学者によるパグウォッシュ会議が有名な例です。1995年にノーベル平和賞を受賞した同会議は、バートランド・ラッセルとアルベルト・アインシュタインが1955年に公表したラッセル・アインシュタイン宣言の呼びかけを受け、1957年に第1回が開催されました。同宣言は、「あなたが人間であること、それだけを心に留めて、他のことは忘れてください」と呼びかけ、世界の指導者たちに核兵器を放棄することを求めています。
第1日目の「サイエンスとヒューマニティ」と題したハイレベルトークセッションでは、2015年に長崎で開かれた第61回パグウォッシュ会議の開催に尽力した吉川弘之・元東大総長が、科学者の人間性と社会的責任について見解を披露しました。
ラッセル・アインシュタイン宣言は、原子力エネルギーの解放に物理学者は責任を負うと指摘している点は意義深いものです。しかし、物理学以外のすべての分野もふくめて「科学知識を使うことの責任」が長い間「蔑ろ」にされてきたと、吉川元総長は指摘しました。1999年にハンガリー・ブダペストで開催された世界科学会議で採択された「科学と科学的知識の利用に関する世界宣言」において、科学的知識の応用についてようやく焦点が当てられたといいます。
その状況を踏まえ、吉川元総長は「科学的知識を使ってモノを作ることをデザインと言いますが、これまでデザインにはあまり焦点があてられてこなかった。個人的にデザインを研究するうちに、『デザインは、自然科学だけではない』と気がつきました。人間の行動や幸福に直結する社会のデザインが大切です。だからこそ、自然科学者が人文・社会科学者と対話を持つことが重要になるのです」と、分野を超えた対話の重要性を説きました。

ウィーン大学のウルリケ・フェルト教授は、同セッションで欧州連合(EU)が採用する「責任ある研究・イノベーション(RRI)」の枠組みについて説明し、「RRIは、社会的諸アクター(関係者)とイノベーターがお互いに関与し合う、より透明でインタラクティブなプロセスと定義できます。目的は、倫理的に受容でき、かつ持続可能なイノベーションをもたらすことにあります」と述べました。つまり、科学がもたらし得る負の社会的影響を最小限に抑えるため、社会的諸アクター(研究者、市民、為政者、ビジネス界、第三セクター)が協働し、イノベーションの価値と方向性を決定することがRRIの主眼になります。フェルト教授はまた、市民参加も重要だと強調し、「一般の人々の参加とは、人々の懸念や価値、ビジョンを研究開発やイノベーションのプロセスに組み込むことです」と続けました。
それでは、ビジネス界は、科学の発展によって生じた世界の懸念を払拭するための取り組みについて、どう感じているのでしょうか。この点で示唆を与えてくれたのは、CIASを設立した韓国SKグループのチェ・テウォン会長です。チェ会長は開会の挨拶で、環境危機に立ち向かう企業の取り組みについて触れ、「民間セクターは重要な役割を担います。正しいインセンティブがあれば、企業は技術的知識、財務の専門性を使い、グリーンテクノロジーを採用できるのです。企業はそれぞれの分野を超えて協働し、(排出量削減に向けて)転換する道筋を歩む支援ができるよう迅速に適応できるのです」と語りました。
自然と調和して生きること
2日目の分野横断型ディスカッションでは、「強調的な行動に向けた信頼感の構築」をテーマに、人類社会の現状を中心に活発な議論が行われました。
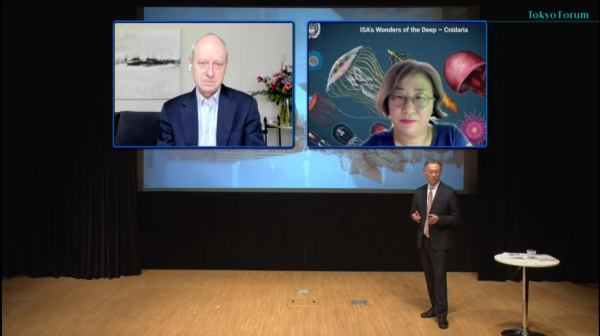
米ハーバード大学のマイケル・サンデル教授は、「過去数十年において、グローバル化がもたらした所得と富の不平等により、人生の勝者と敗者の格差が広がりました」と述べた上で、「勝者は自身の成功は努力の賜物、敗者については当然の運命」だとする傾向を嘆きました。
「人生において幸運が持つ役割は大きいし、自身の才能は他が与えてくれた贈り物なのです。この認識を持つことこそが我々を謙虚にさせ、社会がコモン・グッド(共通善)、つまり自然との調和を追求することを可能とするのです」とも述べ、人々にもっと謙虚になるよう訴えました。
東大の八木信行教授はサンデル教授に同調し、「人々が食料を得ることができるのは、自身の才能や努力ではなく、自然生態系が人類の食料生産に寄与しているからです。謙虚さは、『自然と調和して生きること』と『科学技術の進展』との間に存在するある種の緊張を和らげる鍵となります」と指摘しました。では、人類が自然界に対して、慈しみや敬意、畏敬の念を持つのが難しくなってきている今、どのように対応していくべきなのでしょうか。
同セッションで、「国際公共財(グローバル・コモンズ)へ人類が協働して正しい対応をできるかどうかが鍵になる」と答えたのが、国際海底機構(ISA)のジヒョン・リー環境管理・鉱物資源事務局ディレクターです。「人類は、協力して鉱物資源の探査や将来の開発を規制し、国際海底の環境を保全するためのルールや規則、手順など作ってきました。まだ始まってさえもいない海底鉱物資源の採掘について規制しようと長年検討、尽力してきました。このような人類の活動は類を見ません」と語りました。なお、国連海洋法条約では、深海底とそこに眠る資源を、「人類の共同の財産」と定義しています。
多種多様の課題に挑む
同じく2日目に開かれた4つのパネルディスカッションでは、科学と人の心をめぐる様々な課題について話し合われました。「信頼されるAIと寛容な社会の構築に向けて」と題されたセッションでは、新型コロナ感染症ワクチンの迅速な開発促進などAIの正の側面と、先進国と発展途上国の間の格差拡大など負の側面の両方が語られました。「脳とその復元力:社会や自然と調和する私たちの心の健康について」と題したセッションでは、社会関係資本や社会とのつながりが、人々のレジリエンス(苦境からの復元力)を高める役割を果たすことや、心を科学的に理解し訓練することでメンタルヘルスを維持する方法などが語られました。
続いて行われた「科学技術と人間性」と題したセッションでは、集中型AIは監視や専制政治を助長するリスクがあるが、パーソナルAIは集中型AIを置き換えて人権や民主主義を促進する可能性がある点を中心として、「個人情報とAI」を中心に議論がなされました。また、「科学技術の進展がもたらす、国際関係への不安」と題されたセッションでは、米中の軍事対立や、両国の宇宙開発競争が議論されました。
会議最後のまとめセッションでは、各国から6人の新進気鋭の若手学者らが登場。米イェール大学のディラン・ジー助教授は、学術分野を超えて相乗効果を生み出すことや様々な分野から知識を持ち寄ることの重要性を、この会議を通して再認識したと感想を述べました。「私は心理学者としての視点でこの会議について考えましたが、我々が直面する世界の課題に取り組むには、共通した価値を考慮することや人類の協力は重要だと感じました」
続いて、藤井総長は、「自然との調和」「透明性」「信頼醸成」など、会議を通して印象に残ったキーワードを披露しました。「社会の格差解消や、孤立した人々に新たなつながりや交流をもたらすには対話しかありません。長年にわたり培われた信頼によって、我々は様々なステークホルダーと対話を深め、理解を高め、世界公共に寄与すべく協働できるのです」と会議を結びました。
東京フォーラムは、「Shaping the Future(未来を形作る)」を包括的なテーマとして2019年から2028年までの10年間にわたり開催される予定です。社会が複雑に絡み合った課題に直面する中、世界と人類の未来を形作る最良の提案を大学の枠組みを超えて議論するのが目的です。また、同会議は人をはぐくみ、卓越した学知と責任ある研究、および様々なつながりを生み出す大学の役割の具現化の一つでもあります。なお、2021年4月に現職に就任した藤井総長は、任期6年すべてで東京フォーラムを開催します。
地球環境危機の回避には更なる世界的な取り組みが必要
12月2日に開催されたパネルディスカッションでは、世界的に著名な地球環境問題の専門家が、「科学と共感に基づくグローバル・コモンズの責任ある管理」をテーマにオンラインで議論を交わし、加速化した経済発展がもたらした現在の地球環境危機を回避するためには、世界全体の一層の取り組みが急務だと改めて訴えました。
同セッションは、「不可逆的な地球環境の壊滅を回避するための猶予は10年しかない」と厳粛な警告を発した「東京フォーラムオンライン2020」のフォローアップという位置づけで開催されました。
ポール・ポルマン元ユニリーバCEO(バリューチェーンにおける気候変動への取り組みを支援する団体「IMAGINE」主宰)は、「グラスゴーの会議の成果は、政治レベルでは予想をおそらく大きく上回り、科学的レベルでは期待にはほど遠いなど、功罪相半ばでしたが、明るい兆しもあります」と、COP26の結果に一定の評価を与えました。氏は、今回のCOPで改めて、産業革命前からの気温上昇を1.5℃に抑えることが国際的な目標として確認された点を歓迎し、来年のCOPまでに各国が削減目標をさらに深堀りすることに合意したことを高く評価しました。またCOPでは脱炭素化を加速するため企業と政策主体との協働イニシアティブが多く立ち上がったことを受け、東大グローバル・コモンズ・センター(CGC)が日本そしてアジアのビジネス・リーダーと協働して世界課題に貢献することへの期待を述べました。

ポツダム気候影響研究所(PIK)のヨハン・ロックストロム所長は、同研究所が東大グローバル・コモンズ・センター(CGC)と共同で行っている、地球環境システムの保全に向けた経済システム転換の効果について現時点での成果を紹介しました。CGCでは、グローバル・コモンズを守るためには、「エネルギー」「土地利用」「都市」「産業」分野でのシステム転換が必要と考えていますが、分析結果は、4つの分野で現在国のレベルであるいは産業のレベルで想定されているシステム転換がすべて実行されたとしても、グローバル・コモンズが不可逆な壊滅状況に陥るのを防ぐには不十分だというものでした。
また、アニルッダ・ダスグプタ世界資源研究所(WRI)代表は、「気候分野のシステム転換の現状を評価する報告書」の成果を紹介しました。この研究では、温暖化を抑制するために必要な40のシステム転換を選択しその進展度合いを評価しました。結果は、全般的にシステム転換が進んでいることは確認できましたが、その速度が遅く、40指標うち、適切な速度と規模で正しい方向に進んでいる指標は皆無であり、システム転換を大きく加速させる必要性が強調されました。
一方、米コロンビア大学のジェフリー・サックス教授は、CGCと国連SDSN(持続可能な開発ソリューションネットワーク)、米イェール大学が同日に共同発表した、グローバル・コモンズ・スチュワードシップ(GCS)指標の2021版レポートを紹介しました。GCS指標は、各国がどれだけ地球環境に負荷を与えてきたかまたどの程度改善したかを測るものです。「高所得国や上位中所得国に現在の地球環境危機を引き起こした責任があり、それによって下位中所得国や低所得国が貧困や環境負荷に苦しんでいる」と、GCS指標で明らかになった点を指摘しました。
CGCのディレクターで、同セッションのモデレーターを務めた石井菜穂子・東京大学理事も、貿易による効果を勘案すると、日本などの高所得国は、低所得国で生産された工業品や食料品の輸入を通じて、温暖化ガスの排出や土壌劣化、生物多様性喪失などグローバル・コモンズの棄損に大きな責任があり、この問題を解決するには、先進国と発展途上国がバリューチェーンを通じて協働する必要があると応じました。
ベラ・ソンウェ国連事務次長兼国連アフリカ経済委員会事務総長は、ビジネス・リーダーの果たすべき役割を高く評価し、国家ベースの既存の枠組みを超えた新しい機関を設立し、発展途上国の環境問題をグローバルに協議するよう提案しました。サックス教授も、先進国と新興国の20か国・地域からなるG20にアフリカ連合を加えたG21を設立してこの問題を議論することを提唱しました。
全体として、世界はグローバル・コモンズを守るための有効なガバナンス構造をいまだもっていないこと、特に先進国側がいかに責任を果たしていくかの議論が必要であることが明らかとなりました。






