小さな建築プロジェクトから大きな未来を描く 途上国のコミュニティと共に発想する持続可能な社会


コロンビア北西部の港湾都市トゥルボで、川沿いの湿地帯に建てられた住居
持続可能な地球環境の構築のために、建築家ができることは何なのか?
新領域創成科学研究科の岡部明子教授は、アジアや南米などの途上国の建物や公共空間に介入する「スーパーミクロ」なプロジェクトの実践を通じて、「スーパーマクロ」な影響をもたらす政策について研究してきました。一貫しているのは、政府の都市計画の範囲外で自然発生的に発展してきたスラムなどの「インフォーマル・コミュニティ」を否定することなく、彼らが自力でより良い生活を求められるような住環境作りを促進し、持続可能な社会を構想するアプローチです。
東京出身の岡部先生の原点は、家族の仕事の都合で暮らしたメキシコでの幼少期の体験。8歳から10歳まで通ったメキシコ・シティの公立小学校には、義務教育を修了せずに一度小学校を退学したあと戻ってきた現地の大人も多く在籍していました。そこで、日本の歴史より先にメキシコの歴史や地理について学んだといいます。
「日本が島国であることも知らないような時期に勉強したのがメキシコの建国の歴史でした。大雑把にいうとメキシコ先住民の人たちがいて、そこにスペイン人が征服しにやって来て、それから独立して、というような民主化の歴史。ところが日本に帰ってきて、中学校や高校で世界史を学ぶと、南米の歴史は教科書で半ページほどしか触れられていない。世界は視点を変えるとまったく違って見えてくるんだということを体感して、本当にショックを受けました」。
それ以降、「事実」とされていることを疑う癖がついたと話す岡部先生は、東京大学に進学し、工学部建築学科を卒業すると世界的建築家である磯崎新さんの事務所に就職します。得意のスペイン語を生かしてバルセロナの磯崎オフィスで1992年のオリンピックに向けたプロジェクトに関わるなど、ヨーロッパで実務と研究を続け、2004年、千葉大学工学部デザイン工学科建築学コース助教授に就任。2009年、ある会合で出会った千葉県館山市の旅館の女将に紹介され、館山市の海沿いの「塩見」という集落の古民家の修繕に学生と共に関わることになりました。
「衰退」するコミュニティから得た気づき
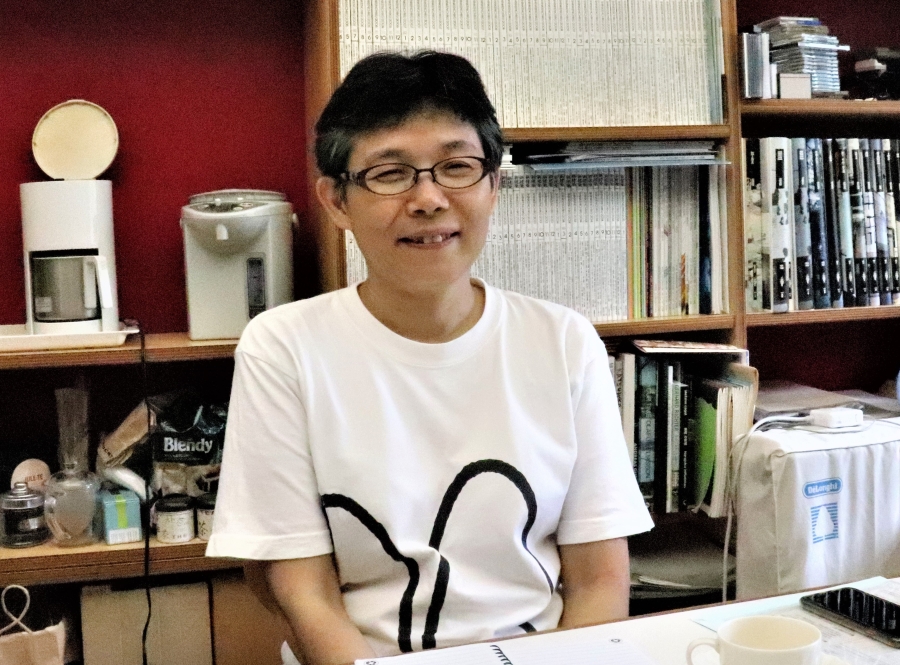
新領域創成科学研究科の岡部明子教授
塩見は海沿いの50軒ほどからなる、1000年以上前からの記録が残る伝統的な集落。気候も温暖で、海の幸に恵まれ古くから半農半漁の集落として栄えてきました。戦後は房総半島の海水浴ブームで民宿や別荘が増えた時期もあり、高齢化に対応しながらコミュニティとして機能し、維持されてきました。研究室のメンバーは当初、「衰退した地方のコミュニティ再生のお手伝いをする」つもりでしたが、結果的には自分たちがコミュニティについて学ぶ機会になったと振り返ります。
「今でも毎月1回、全世帯から一人ずつ代表が神社の集会所に集まって会合をしているんです。そういうところに学生を連れていくと、ちゃんと挨拶をしなさいよ、とか、ゴミはこうしなさい、とか、地元の高齢者の方に教えていただくことがしばしばありました」。
研究室が行ったのは茅葺きの民家の改修。屋根の葺き替えは集落の皆で助け合って行う行事でしたが、茅を葺ける人がいなくなり放置されていました。先生は県外の若い職人さんの協力を得て、学生とともに毎年5分の1ずつ葺き替えていきました。
「ゴンジロウ」という愛称で呼ばれるこの家屋のプロジェクトは先生が2015年に東大に移ってからも続けられ、他大学も含めた学生の合宿や、地域住民の交流の場として現在も活用されています。材料の茅の確保から古い茅の始末に至るまですべて自分たちで行った結果、茅葺民家が景観を守るだけでなく里山の生態系の循環やコミュニティの維持に貢献してきたこと、また人間は最終的に「必要」があることで助け合って暮らしていけるという「当たり前のこと」に気付かされたと話します。

千葉県館山市の民家「ゴンジロウ」の屋根で葺き替えをする学生たち

改修後のゴンジロウで行われた流しそうめん
一方、2009年頃からインドネシアのジャカルタ市内にあるチキニという人口密集地域での共同トイレの改善や子どもたちの遊び場作りなどにも関わって来ました。
研究室の学生は、インフォーマル・エリアとも呼ばれるスラム地区で小さなプロジェクトに数多く関わりますが、「先進国日本にあるいろんな技術や知見をうまく提供すれば彼らの生活改善に貢献できるはず」という使命感を帯びた思い込みは、現地でたくましく生きている人たちと生活するうちに打ち砕かれることが多いといいます。

ジャカルタの人口超密集地区チキニに立ち並ぶ「インフォーマル」な住居
「現地の人たちは、私たちより毎日を豊かに、その日その日を大切に生きている。それに比べて学生は、在学中から就活のことを考え、キャリアプランがどうのこうの、って今日を生きていない。まちづくりは大きなテーマなんですが、学生たちは、自分たちがいかに郊外の核家族で育ってきてコミュニティというものを知らなかったかを思い知らされるわけです。また、現地では建物を作ることが多いのですが、建築を学んでいても実はリアルに建築物がどうできてくるのかは知らなかったりします。逆に現地に住んでいる人たちは自分の家を自分で建てられる。現地の人と一緒に何かを作っていくうちに、建築とは何かという本質を考え直すきっかけになることがあります」。

両川厚輝さんが学部生時代、寝泊りしながら改修したエクアドル・キトの廃屋
廃材だけで建物をリサイクル

両川厚輝さん
研究室に所属する両川厚輝さん(修士課程2年)も、学部生時代から南米に何度も足を運んで来ました。最初に訪れたのが、エクアドルの首都キト。2016年、現地の建築事務所のスタッフと一緒に歴史的市街地の一角で廃墟化した建物をすべて廃材でリサイクルするという実験に取り組みました。先住民のケチュア人の伝統である、誰かが家を建てる時に近隣住民も工事に参加するという文化に倣い、住民や地元の大学生を呼んで共同で建物を改修し、同年10月にキトで開かれた国連人間居住会議(ハビタット3)のサイドイベントの一つとして発表しました。
「廃材ガラスを切って、屋根の上に並べて天窓を付けてみるとか、リサイクルのアイデアをひたすら試しました」と話す両川さん。半年近く、ドアもついていない廃屋を工事しながらそこで寝泊まりしましたが、キトは標高が高いので暑すぎず、蚊もいなくて快適だったと飄々と振り返ります。「僕は毎日工事の記録を絵に描いてフェイスブックに上げたり展示したりして。そういうことを都市全体でやっていけば、もっと持続可能でより良い住宅を自分たちの手で作って、物理的にもゴミを減らすことができるというモデルを示せました」。
両川さんはその後、2016年4月のエクアドル地震で地震・津波の被害を受けたチャマンガという漁村を数度にわたって訪れ、地元住民74人に震災前後の暮らしの変化について聞き取り調査を行いました。震災後、政府が漁師の内陸の復興住宅への移転を進めたものの、海沿いにとどまった人が内陸に移住した漁師たちの仕事道具の保管場所を提供するなど、地元住民が自らの力で生活再建しようとしていることを明らかにし、住民同士のネットワークを復興支援にも繋げるべきという提言を卒業論文でまとめました。

2016年4月のエクアドル地震で被災したチャマンガ沿岸地区。漁師は海のすぐそばで生活していた

震災後にチャマンガの内陸部に整備された復興住宅(左側)
途上国から新しいパラダイムを
研究室ではさらに、コロンビアやアルゼンチンでの活動を進めています。コロンビアではエアフィット大学の研究者と共同で、トゥルボというマングローブの生い茂る川沿いの湿地帯にあるコミュニティを調査中です。この地域は麻薬がらみの紛争地帯で治安が悪いため開発が進まず、川が唯一のインフラ。植民地時代に黒人奴隷として南米に送り込まれた人たちの子孫が、紛争でジャングルから追われて出てきて、河口にある都市の湿地帯に定住しています。
「彼らは流木を集めて道を作り、住宅を建てています。雨が降ると水量が増えて道も大きく浮きます。一見すると彼らに良い住宅を建ててあげるのが解決策だと思えるかもしれませんが、住宅を与えるだけでは、仕事もなく何をしていいかわからず、結局麻薬取引に巻き込まれていったりしてしまう」と岡部先生。「彼らが必死になって良い暮らしを求めて生活している、そのパワーに逆行しないよう、それをサポートするようなフォーマルな介入の仕方は何なのか、ということを考えていきたい」。

岡部研が調査を進めるコロンビア北西部トゥルボのインフォーマル・コミュニティ。住民自身が流木を集めて架けた道が貴重なインフラになっている
岡部先生は、心の「故郷」でもあるラテンアメリカから、持続可能な地球を構築するためのモデルを提示したいと考えています。経済成長による低所得者層へのトリクル・ダウン効果を期待し開発一辺倒になりがちなアジア諸国と異なり、南米の政府や大学は、従来型の開発が結果的に自国民の経済格差を増幅したことを認識し、インフォーマル・コミュニティで生活する住民らのパワーを生かした政策作りに関心を持っています。そのような現地のカウンターパートとの協働によって、持続可能な社会に向けた新しいパラダイムを切り開きたい、と熱く語ります。
「国連の推進する持続可能な開発目標(SDGs)とそれ以前のミレニアム開発目標(MDGs) との大きな違いは、MDGsでは先進国がモデルで、技術移転などを通じて途上国はそれにキャッチアップするという目標があったけれども、そこに持続可能な地球の将来は見えなかった。私たちがコミュニティからいろんなことを学んでいるように、途上国には先進国が忘れてしまったたくましさやいろんな知恵がある。それらの知恵と先進国が持っている技術を組み合わせて、まったく新しい方向性を打ち出していかなきゃならない、というのがSDGsだと思うんですよ。それが何なのかはまだはっきりとはわからないけれども、途上国から発想できるような、そういう取り組みが必要だと思っています」。
取材・文:小竹朝子
写真提供:岡部明子研究室






