 極圏、砂漠、火山島に無人島、
極圏、砂漠、火山島に無人島、
5640mの高山から5780mの深海まで
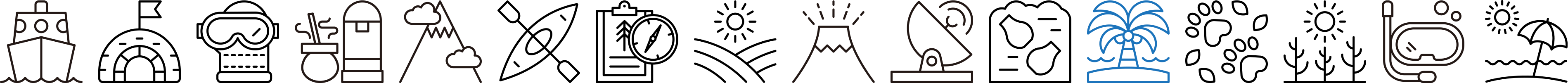
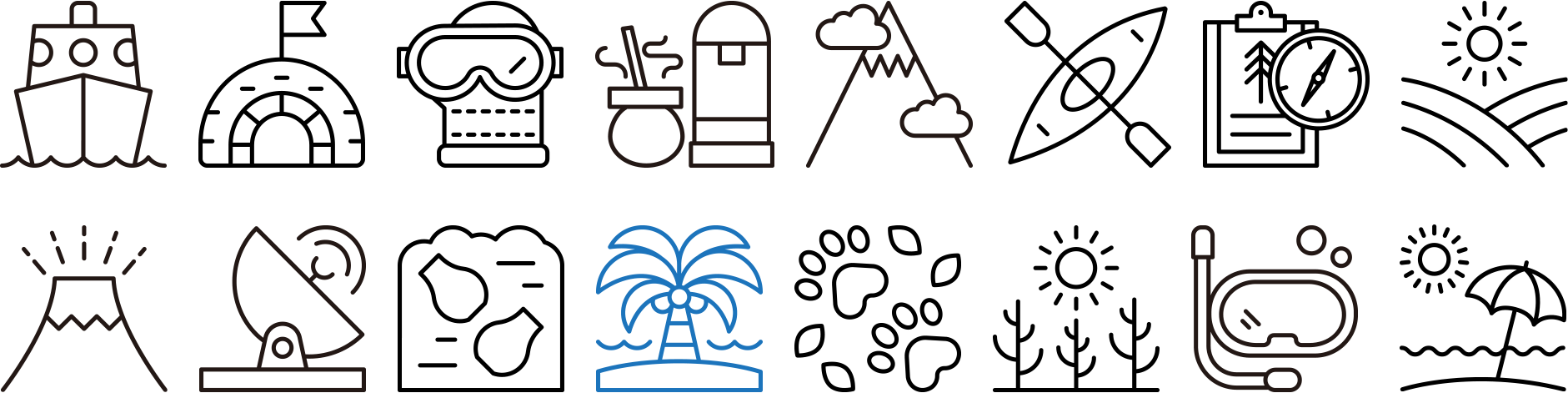
鹿児島県奄美大島に、東京大学が保有する日本最南端の研究施設「奄美医科学研究施設」 があります。
があります。
奄美の温暖な気候を生かして、南米原産のサルの繁殖や、熱帯熱マラリア研究が行われています。
2015年から駐在する獣医師の横田先生にこの施設での取り組みを紹介してもらいました。
動物生命学  南西諸島
南西諸島
日本最南端の東大施設で小型霊長類の繁殖に取り組む
横田伸一
YOKOTA Shin-ichi
医科学研究所 助教


リスザルを繁殖する国内唯一の研究施設
私は2015年から奄美に駐在しています。全国に48ある東京大学の施設のなかで、日本最南端に位置する研究拠点です。もともとはハブの採毒所として1902年に開設しました。現在日本で使われているハブの抗毒素血清は、私の先輩方が100年以上前ここで搾り取った毒を基に研究を重ねて作られたものです。
ハブもいますが、現在は主に南米原産の新世界ザルであるリスザルの繁殖とヨザルの飼育をしています。熱帯雨林に住む体重約1kgの小型霊長類です。私はこの小型霊長類を実験に使うためのリソース研究を行っています。様々な病気の動物モデルとして、創薬やワクチン開発研究などに使いやすいような情報を整備するのが目的です。そのためにサルのゲノム配列や生理的パラメーターといった情報を調べたり、整理したりしています。
ただ課題として、リスザルとヨザルの頭数が減ってきているという現状があります。国内の主要な霊長類研究施設がこの2種類のサルを輸入し繁殖を試みてきましたが、上手くいきませんでした。今では当施設が研究機関としては国内で唯一これらのサルを維持している施設です。繁殖が成功しているのは奄美の温暖な亜熱帯海洋性気候のおかげかもしれません。現在はワシントン条約で輸入規制されているため繁殖していくしかありません。もしも全滅させてしまったら、日本の貴重なリソースを一つ消してしまうことになります。日々胃が痛い思いです。ここは国際共同利用・共同研究拠点でもあるので、国内外の様々な機関の研究者も利用します。そのためにもよりよい繁殖方法を見つけ、頭数を増やすことも私たちの重要な仕事であり使命です。
例えば最近は、微量な尿で判定可能な新世界ザル用の妊娠検査薬の開発研究に協力しました。早期に妊娠が分かればその分早めに隔離するなどの対応が取れます。また、遊び道具を設置したり、餌を探して取るような仕組みを作ったりするなど様々なアメニティを準備してストレスがたまらないような環境づくりにも注力しています。


亜熱帯の気候を生かした研究
リスザルは世界三大感染症の一つであるマラリアの研究に極めて貴重な動物です。マラリアの治療薬はありますが、効き目が良い安価なワクチンはいまだありません。そのワクチンを開発するための、リスザルのマラリアモデル作りにも取り組んでいます。
2023年6月には新研究棟が完成しました。病原体を封じ込めながら、媒介蚊を使った感染実験が可能な施設です。この施設を使って、ジカ熱やデング熱などマラリア以外の蚊が媒介する熱帯病の研究にもいずれは取り組みたいと思っています。蚊は湿度の高い環境を好むため、奄美だと上手くいくかもしれません。地球温暖化が進むなかで、今後新興感染症やすでに根絶された感染症が再び発生する可能性があります。その時には、亜熱帯にあるこの東大が保有する日本最南端施設の研究で貢献したいと考えています。








