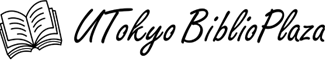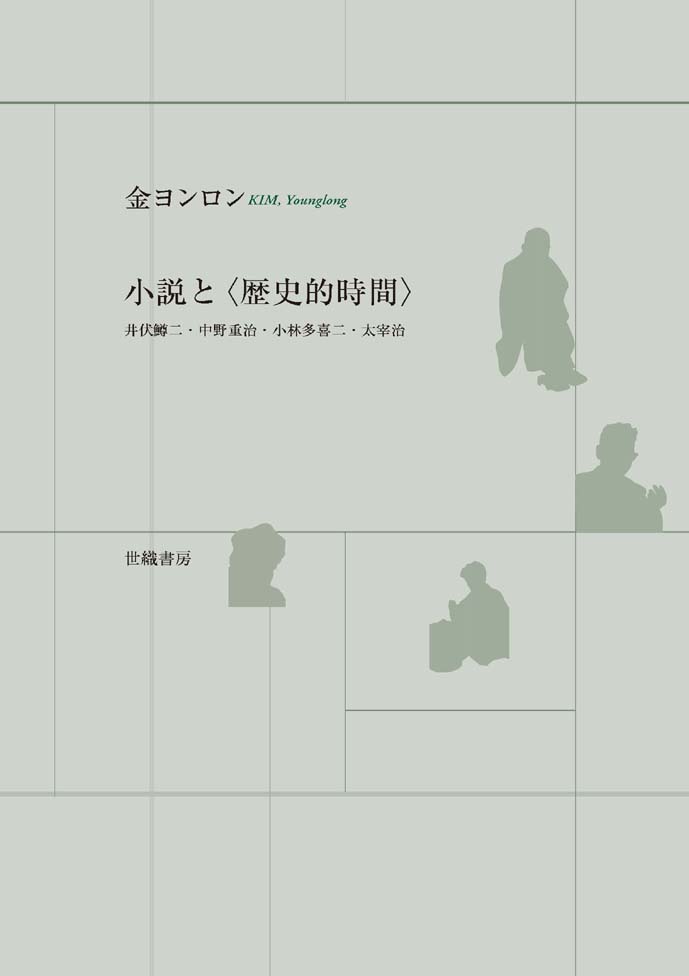
書籍名
小説と〈歴史的時間〉 井伏鱒二・中野重治・小林多喜二・太宰治
判型など
320ページ、A5判、上製
言語
日本語
発行年月日
2018年2月
ISBN コード
978-4-902163-96-4
出版社
世織書房
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
本書は、近代日本の小説の表現方法から〈歴史的時間〉を見出す試みである。
序章では、「カルチュラル・スタディーズ」、「ポスト・コロニアリズム」、「ニュー・ヒストリシズム」など方法論の行き詰まりがいわれている現状の検討を行う。これらの方法論は、当初の問題意識が薄れたまま、小説を同時代の資料とともに読むという方法としてのみ定着したと指摘されている。本書では、この問題を打開するため、近代日本の小説に刻まれた様々な時間 (物語内容の時間、物語言説の時間、初出時、改稿の時間、再収録の時間、再読の時間など) を手掛かりに、テクストを媒介に想像される同時代の (作者と読者の) 時間とそれを読む現在の時間との交差を記述できる、新たな概念として <歴史的時間> を提示する。読書とは、この <歴史的時間> の獲得でしかないと捉えるのである。
このような問題意識に基づいて本文では、1925年前後から1945年前後までの約20年の間に発表された近代日本の小説を読み、<歴史的時間> という概念を導入した実践を行う。
第一部では、戦時体制が形成されつつあった日本で書かれた井伏鱒二の小説を主な対象にする。井伏文学の初期に該当するこの時期、代表作である「山椒魚」をはじめ、数多くの小説が発表されており、研究史では、この時期すでに後の井伏文学へつながるような文体が成立したと評価されている。そうしたなかで井伏文学を特徴づける時間は、<循環的時間> として捉えられ、それが半世紀以上の創作の時間を経てもなお変わらぬ、作者の資質として発見された。それに対して、ここでは、井伏文学における <循環的時間> から召還される <歴史的時間> を浮き彫りにするため、治安維持法が成立 (1925年) してから「満州事変」が勃発 (1931年) するまでの間に書かれた小説を読み直す。
第二部では、いわゆる「十五年戦争」の最中に書かれた小説を対象にする。戦時中、書くことに対する厳しい制約のなかで、作者は読者の積極的参与を頼りにすることで創作をつづけることができた。直接に書くことのできなかった部分を、読まれる形で提示するために工夫された小説の方法は、それを小説の空所として発見し、補填していく読者の創作の過程によって発揮される。ここでは、多くの伏字や削除箇所で知られている小林多喜二の『党生活者』をはじめ、自己検閲という意味において同じく伏字的である一連の小説テクストを読み、小説の空所をめぐって露わになる <歴史的時間> を考察する。
第三部では、敗戦直後の日本で書かれた太宰治の小説を中心に分析する。敗戦を契機に、戦時中の過去を切り捨て、現在を戦後という未来へ直結しようとする時間に対する認識が顕著になる。過去を忘却するよう促すこの <断絶的時間> は、その過去がいつでも「思い出」となって呼び戻されることを強く予感させる。この時期、読者に <連続的時間> を喚起するように駆使された様々な表現方法を太宰治の小説テクストから読み取ることで、<断絶的時間> に対抗し得る <歴史的時間> を模索する。
以上のように約20年間の小説テクストを読むことで、本論文では、帝国主義戦争の準備としての治安維持法体制の成立前後、数度の改正を通して拡張していく法体制と戦争の深化、戦争が終わり、治安維持法が廃止され、象徴天皇制が確立した敗戦直後までの <歴史的時間> を召喚することになる。
(紹介文執筆者: 金ヨンロン / 2020年4月10日)
本の目次
小説、時間、歴史
第I部
<歴史的時間> を召喚する <循環的時間>
第1章
小説が書き直される間
―井伏鱒二「幽閉」(1923) から
「山椒魚」(1930) への改稿問題を中心に―
第2章
「私」を拘束する時間
―井伏鱒二「谷間」(1929) を中心に―
第3章
持続可能な抵抗が模索される時間
―小林多喜二「蟹工船」(1929) と
井伏鱒二「炭鉱地帯病院――その訪問記」(1929) を中心に―
第4章
アレゴリーを読む時間
―井伏鱒二「洪水前後」(1932) を中心に―
第II部
小説の空所と <歴史的時間>
第5章
××を書く、読む時間
―小林多喜二『党生活者』(1933)―
第6章
小説の書けぬ時間
―中野重治「小説の書けぬ小説家」(1936) を中心に―
第7章
疑惑を生み出す再読の時間
―太宰治『新ハムレツト』(1941) 論―
第8章
占領地を流れる時間
―井伏鱒二「花の町」(1942) を中心に―
第III部
<断絶的時間> に対抗する <連続的時間>
第9章
<断絶> と <連続> のせめぎ合い
―太宰治『パンドラの匣』(1945~1946) 論―
第10章
語ることが「嘘」になる時間
―太宰治「嘘」(1946) 論―
第11章
いま、「少しもわからない」小説
―太宰治「女神」(1947) を中心に―
第12章
革命の可能性が問われる時間
―太宰治『冬の花火』(1946) から『斜陽』(1947) へ
終 章
<歴史的時間> の獲得としての読書
関連情報
第93回 叙述態研究会【金ヨンロン『小説と <歴史的時間>――井伏鱒二・中野重治・小林多喜二・太宰治』(世織書房)・書評会】 (国立オリンピック記念青少年総合センター 2018年5月11日)
http://kimspo2006.blogspot.com/2018/04/blog-post.html
書評:
岡村知子 評 [書評] (『昭和文学研究』79集 pp.146-148 2019年9月)
竹内栄美子 評 [書評] (『日本近代文学』100集 pp.115-118 2019 年5月)
宗像和重 評 [書評] (『日本文学』68巻4号 pp.84-85 2019年4月)
金子明雄 評 [書評] (『社会文学』49号 pp.179-181 2019年2月)
http://ajsl.web.fc2.com/kikan-shi41.html
島村輝 評 「気鋭の研究者による、野心的な試みの成果:新たな理論構制の提出と実践」 (『図書新聞』3351号 p.5 2018年5月19日)
http://toshoshimbun.jp/books_newspaper/shinbun_list.php?shinbunno=3351