
書籍名
公判外供述の証拠使用と証人審問権の役割
判型など
472ページ、A5判、上製
言語
日本語
発行年月日
2022年4月
ISBN コード
978-4-641-13956-5
出版社
有斐閣
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
近時、直接主義・口頭主義が強調されつつ、2016年の刑事訴訟法等の改正にあたっては取調べ及び供述調書への過度の依存から脱却すべきであるとの理念が示され、また、判例・実務においては伝聞例外規定の解釈・運用の明確化・厳格化という動きが見て取れる。さらに最近では、いわゆる司法面接に関連して「被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則を新設すること」が立法課題として位置付けられるなど、公判外供述の活用の新たな可能性が模索されている。
しかし、公判外供述の証拠使用の場面全体を視野に入れた理論的な研究は、わが国で近時必ずしも十分になされているとは言い難く、特に、憲法37条2項前段の証人審問権に関する議論は、個別の伝聞例外規定に関する違憲論等を除いては、それが有意に論じられることはほとんどなくなっており、長らく停滞状態にあったことが指摘できる。
他方で、諸外国に目を向ければ、この分野に関して、母法たるアメリカにおいて2004年に大きな判例変更があり、また欧州人権裁判所において近時判例が蓄積し、その影響下で欧州各国において充実した議論がなされているところ、我が国においてこうした諸外国の動向を踏まえた議論は未だ不十分であると言わざるを得ない。
そこで本書は、アメリカ・欧州における議論の最新動向を参照して、公判外供述の証拠使用の場面における証人審問権の役割について、国内法システムの差異を超えた普遍性を持った知見の抽出を行い、従前の議論の停滞状況を打破し得る証人審問権に関する新たな理論的視座を提供することを試みている。
具体的には、これまで必ずしも明確に認識されていなかった、供述証拠の信頼性それ自体の確保という目的と信頼性の十分な評価の可能性の確保という目的との区別を描き出し、証人審問権の中心的な趣旨を後者に見出すことで、従来の議論と異なる議論を展開する。すなわち、供述証拠の信頼性それ自体が一定程度確保されていることによって例外的に公判外供述の証拠使用を正当化する伝聞例外の理論とは異なり、証人審問権は、供述証拠の信頼性を事実認定者が十分確実に評価することが可能かという点に関心を持つものであって、それゆえに、公判外供述が許容されるためには、その信頼性をより確実に評価することを可能にする要素が十分に存することが必要であるという規律を導く。
以上のような本書の試みが十分に成功しているかについては、読者の評価に委ねるほかないが、今後のわが国における議論の進展に何ほどか寄与するところがあれば幸いである。
(紹介文執筆者: 大谷 祐毅 / 2022年8月29日)
本の目次
第1章 わが国における問題状況
第2章 憲法37条2項及び刑事訴訟法320条以下の制定過程
第3章 アメリカにおける議論
第4章 欧州における議論
第5章 わが国における公判外供述の証拠使用と証人審問権の機能
終章――結びに代えて
関連情報
第2回東京大学而立賞受賞 (東京大学 2021年)
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/research/systems-data/n03_kankojosei.html
関連論文:
公判における事後的な反対尋問と証人審問権の保障――アメリカ法を参考に (『法学』84巻1号 p. 1-42 2020年)
https://tohoku.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=130700&item_no=1&page_id=33&block_id=46
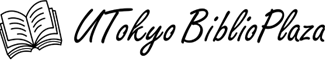



 eBook
eBook