
書籍名
戦国期日本の対明関係 遣明船と大名・禅僧・商人
判型など
308ページ、A5判
言語
日本語
発行年月日
2022年2月22日
ISBN コード
9784642029742
出版社
吉川弘文館
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
日本と中国とのあいだでは、今日にいたるまでのさまざまな年代において、そのときどきの情勢に応じた関係が築かれてきました。明代中国は、基本的には明皇帝へ朝貢してくる諸国の君長からの使節しか受け入れていませんでしたので、貿易を望む室町幕府の将軍は日本国王を名乗って、朝貢使節としての体裁を整えた船、すなわち遣明船を派遣していました。高校の教科書などに出てくる勘合貿易は、これによっておこなわれたものです。
室町・戦国時代の遣明船派遣の歴史を概観すると、おおよそ以下の通りです。15世紀初頭、足利義満 (室町幕府第3代将軍) によって開始された遣明船の派遣は、義持 (同第4代) の時代に一時的に中止したものの、義教 (同第6代) の時代に再開しました。その経営は守護大名や寺社などの有力者に委ねられていましたが、15世紀半ば以降、経営権をめぐるあらそいは激化していきました。そのなかでとりわけ有力だったのが、畿内・四国地方に勢力を有していた細川氏 (細川京兆家) と、中国・九州地方の大内氏で、両氏の抗争は1523年の寧波の乱 (寧波争貢事件) と呼ばれる事件を引き起こしました。そして乱後には2度、大内氏の独占経営する遣明船が派遣され、明側に受け入れられましたが、国内外情勢の変化により、これを最後に日本国王名義で派遣された遣明船は途絶しました。
この遣明船に関し研究をすすめていくと、特に戦国時代について、課題がふたつあることに気づきました。ひとつは、寧波の乱に至るまでを細川・大内両氏抗争時代、乱後を大内氏独占時代とも呼ぶような、通説的な理解の当否の検証です。もうひとつは、遣明船による外交・貿易と、16世紀半ばの豊後の大友氏による使節派遣や、南蛮貿易や朱印船貿易などそれ以後のものとの、連続性ないし断絶性の検討です。
これらふたつの課題について、論証の過程とそれにより導き出された結論を示したのが本書です。内容は下記の目次の通りですが、特に第1部第2・3章では、これまで存在こそ認知されていたものの、遣明船派遣史上における位置づけが明らかでなかった、史料上に「堺渡唐船」あるいは「新貢之三大船」と記される船の実態を解明し、それによって大内氏独占時代と呼ばれていた時期にも抗争が継続していたことを明らかにしました。また、第2部では大友氏の使節や、大徳寺派や妙心寺派の禅僧、堺や京都の商人の分析を通じて、ともすれば中世と近世とで叙述が分割され、別個のものとして扱われがちであった、遣明船とそれ以後の外交・貿易との連続性/断絶性について、実証的に追究しました。
本書は、学術論文をもとにしているため、専門外の方にとっては難解な部分もあると思います。それでも、本書を手にとってくれた読者にとって、連綿とつづく日本と中国との関係史の一端を理解する手がかりになれば幸いです。
(紹介文執筆者: 岡本 真 / 2022年8月26日)
本の目次
一 日明関係史研究のあゆみ
二 課題と本書の構成
第一部 戦国期遣明船の経営者・派遣主体
第一章 寧波の乱以前の遣明船と細川氏
はじめに
一 応仁度船
二 文明八年度船・同十五年度船
三 明応度船
四 永正度船
五 大永度船
おわりに
第二章 「堺渡唐船」考
はじめに
一 関係諸勢力の立場
二 搭乗者と派遣目的
三 歴史的位置
おわりに
第三章 種子島「新貢之三大船」考
はじめに
一 船団構成と渡航時期
二 派遣主体にかかわる従来説
三 一号船・二号船の派遣主体
おわりに
第四章 天文年間の遣明船と大内氏の国内活動
はじめに
一 室町幕府への働きかけ
二 足利義晴の位置づけ
三 人材の取り込み・囲い込み
おわりに
第二部 遣明船からの連続と変容
第一章 弘治年間の遣明使節の歴史的位置
はじめに
一 弘治三年渡航の徳陽
二 弘治三・四年渡航の善妙・龍喜
おわりに
第二章 「山隣派」と遣明船
はじめに
一 大徳寺派と遣明船
二 妙心寺派と遣明船
おわりに
第三章 堺商人日比屋と十六世紀半ばの対外貿易
はじめに
一 日比屋と対外貿易
二 了珪とその親族
三 日比屋の活動にみる遣明船貿易と来航船貿易の連続性
おわりに
第四章 戦国期の京都商人と対外貿易
はじめに
一 銭一族
二 五井一族
三 角倉吉田一族
おわりに
終章 結論と展望
一 本書の結論
二 成果と今後の展望
あとがき
索引
関連情報
第2回東京大学而立賞受賞 (東京大学 2021年)
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/research/systems-data/n03_kankojosei.html
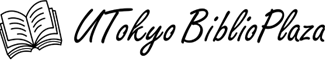



 eBook
eBook