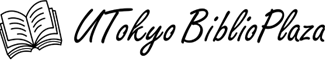書籍名
芸術する人びとをつくる 美大生の社会学
判型など
256ページ、A5判
言語
日本語
発行年月日
2022年3月30日
ISBN コード
9784771035867
出版社
晃洋書房
出版社URL
学内図書館貸出状況(OPAC)
英語版ページ指定
人は社会によってつくられ、社会をつくっていきます。
本書は、芸術の道を志す人びとが社会の中で芸術家としてつくられる過程の解明を目指したものです。多様なジャンルで構成される芸術分野の中でも、美術分野に焦点を当て丁寧に議論を進めました。芸術家になるための条件として個性や天賦の才がしばしば強調されますが、著名な芸術家の多くは現在、専門教育機関から輩出されています。そこで、本書では、美術作家の養成を目的に掲げる美術系大学・学部 [=美大] に注目しました。そして、そこで学ぶ学生 [=美大生] の子ども時代から大学卒業までの人生を手がかかりに、社会学的な視点から、芸術家はどうつくられるかという問いへの回答を試みました。
本書のオリジナリティは、美大生の視点を重視することで、高等教育の研究と芸術・文化生産の研究を架橋したところにあります。
まず、これまでの高等教育の研究では、芸術・美術分野の学校や学生は周縁的な位置づけがなされ、研究対象として十分に扱われてきませんでした。その理由としては、大学教育の中で芸術を専門的に学ぶ学生が少数であること、実技が重視される分野であり、学力的な序列の内部で捉えにくいことなどが挙げられます。
もちろん、近年は大学教育を考える上で、専攻分野の違いを加味した理論や分析の必要性が認識されていますが、それでも大学教育の中で芸術・美術は「例外」のままとなっています。しかし、本書で示したように、美大生になることは、子ども時代からのディスポジション (性向) 形成あるいは学校・クラス集団内での社会的ポジションの結果として可能になっています。また、美大への進学ないし受験対策のための美術系予備校の利用には、出身地域や家庭の諸資源による差、つまり機会の不平等がある可能性も見出されました。それゆえ、芸術・美術は教育の中で例外的な分野ではなく、他分野と共通した課題を有していること、芸術の道を志すか否かの選択は教育機会の構造に制約されていることを、本書では示すことができたと考えています。
つぎに、芸術社会学や芸術・文化生産の研究でも、芸術家の教育・訓練は主要なテーマとして取り組まれていません。日本では、芸術家の労働やキャリア形成について、その現状や課題を明らかにした調査研究がいくつか生み出されていますが、かれらの芸術実践や芸術界への参入方法に美大といった教育機関が与える影響については、知見の積み重ねが浅い状況にあります。
そうした中で、本書は、美術系予備校と美大による美術作家の二段階養成システムの現状を描き出し、実技重視の教育体制ゆえに生じる課題を指摘しました。さらに、学生たちがその中で抱く感情の束も同時に掬い取ることができました。詳しくは本書をご覧ください。
最後に、本書を読む上で、そこに登場する美大生たちを「ありえたかもしれない自分」の姿として見ていただきたいと思っています。そして、本書で示した様々な数値や語りを材料として、ご自身の経験や考え方との共通点や差異を探ってみてください。そうした読み方をしていただけると、筆者としては大変嬉しく思います。
(紹介文執筆者: 喜始 照宣 / 2022年8月8日)
本の目次
序 章 美大生の社会学に向けて
第1章 美術系大学の学生の子ども時代
第2章 美術系高校・大学への進路選択
第3章 美術系予備校・画塾を通じた文化獲得
第4章 美術系予備校・画塾が学生の大学生活に与える影響
第5章 大学生活を通じた表現行為の追求と「大学」の意味
第6章 美術系大学の学生の大学生活満足度
第7章 美術系大学からの卒業後進路選択
終 章 美大生の社会学から日本の芸術家養成を考える
あとがき
初出一覧 / 参考文献 / 巻末資料 / 索引
関連情報
第2回東京大学而立賞受賞 (東京大学 2021年)
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/research/systems-data/n03_kankojosei.html
関連論文:
美術系大学からの卒業後進路選択 ―― 作家志望に着目して (『高等教育研究』18巻 p. 191-211 2015年)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaher/18/0/18_191/_article/-char/ja/