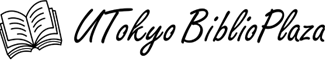いかにして善悪の知識はえられるのか。林檎が我々の神経系に作用して生じるという、巧妙な説明を捨てるとともに、哲学者たちは様々に答えてきた。曰く、それは自明である。曰く、それは直観による。曰く、それは生得的である。曰く、それは常識である。曰く……。
本書はまず、もぐら叩きをする。すなわち、これらの答えのそれぞれの誤りを指摘し、そもそも我々が善悪について何かしら知ることは不可能であることを示さんとするものである。
なぜ、この道徳の認識可能性についての問いが重要なのか。道徳とは我々自身の生を導くのであり、そのような意味で「よき生」について教えてくれるがゆえに重要であるのだ。これはひとつの答えではあろう。たしかに内省的で有閑な人々にとっては、「よき生」の中心性は疑うべくもない。我々とてこの問いの価値を否定する積りはない。
だがこの描像は、受肉せる道徳の姿をほとんど歪めて捉えている。道徳はしばしば、ひめやかな思いにとどまらず、他者への道徳的介入というかたちで現れる。そして、善行を褒め称える道徳的賞賛は印象的であるにせよ、これは例外である。(そして「この」例外はすべてを証明しない。) むしろ、他者の行為を制御するための道徳的非難こそが、道徳が我々の社会において果たしている主たる役回りであろう。
こうして、道徳的知識の可能性が問題になるのは、道徳的非難や処罰に代表される、道徳的信念に基づく他者への介入という事情があるからにほかならない。仮に我々が善悪について知ることができないとすれば、こうした介入はいささかも正当でないからである。ちょうど雨が降ると知らないのに矢鱈とひとに傘をもたせたがるかのようである。
もぐらを叩き終えたあと、我々が突き当たるのは、既存の道徳的実践をどうすべきなのかという新たな問いである。本書の結論は条件的で、多義的である。「少なくとも現行の方式においては」我々の道徳的実践には深刻な問題がある。とは言え、仮に一定のタイプの道徳的実践が我々にとって有益であるというならば、適切に調整された内容の道徳をある種のフィクションとして再導入することもありえよう。とはいえ、そのように道徳が有益であるとは限らない。そのとき我々には道徳を廃絶する選択肢すら開かれる。そのとき我々は何によって自らを導くのか。美であれ法であれ、我々は好きに選ぶことができよう。
(紹介文執筆者: 野上 志学 / 2025年1月27日)
本の目次
序 章 道徳懐疑論にむけて
1 道徳懐疑論の簡潔な分類
2 モラリズムと道徳の権威
3 倫理の自律性と道徳認識論
4 以降の見取り図
第1章 知識の実践性と注文の多い道徳
1 知識の実践性と可謬主義
2 知識の実践性と認識的確率の閾値
3 注文の多い道徳と外界存在
4 結論
第2章 直観主義と自明性――直観主義の諸問題 (1)
1 穏健な基礎づけ主義,あるいは直観の必要性
2 Rossと Audiの道徳的直観主義
3 自明性に訴える理論の問題
4 小括
第3章 「現れ」としての直観――直観主義の諸問題 (2)
1 「現れ」とは何か
2 現れ一般および道徳的直観の存在についての疑義
3 現れの信頼性についての疑義
4 外界懐疑論の回避
5 結論
第4章 常識道徳の退位
1 常識と証言の正規プロセス
2 常識論法の基本モデル――証言の一致に関するベイズ認識論
3 追跡仮定とその問題
4 共通原因による条件付き独立性仮定の破れ
5 同調による条件付き独立性仮定の破れ
6 「普遍的同意」の不在
7 非自然主義と常識論法
8 結論――常識道徳の退位
第5章 フィクションによるユートピアか廃絶か
1 保存主義と虚構主義と廃絶論
2 廃絶論者による道徳批判
3 選択的虚構主義
4 選択的虚構主義による「道徳」
5 結論――フィクションによるユートピアか廃絶か
補遺1 可謬主義的命題認識論理の近傍意味論
補遺2 頂点一致性条件の問題と序列不変性条件
補遺3 閾値の導出
補遺4 確率と因果モデルとその拡張
文献表
あとがき
人名索引
事項索引
関連情報
第3回東京大学而立賞受賞 (東京大学 2022年)
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/research/systems-data/n03_kankojosei.html
書評:
蝶名林亮 (創価大学文学部准教授) 評 (『図書新聞』 2023年12月2日号)
https://www.fujisan.co.jp/product/1281687685/b/2456397/
書籍紹介:
あとがきたちよみ (けいそうビブリオフィル|勁草書房編集部ウェブサイト 2023年3月22日)
https://keisobiblio.com/2023/03/22/atogakitachiyomi_doutokuchishiki/